【読書記録】心理的安全性の作り方(著者:石井 遼介)|自分が「行動」することの効果
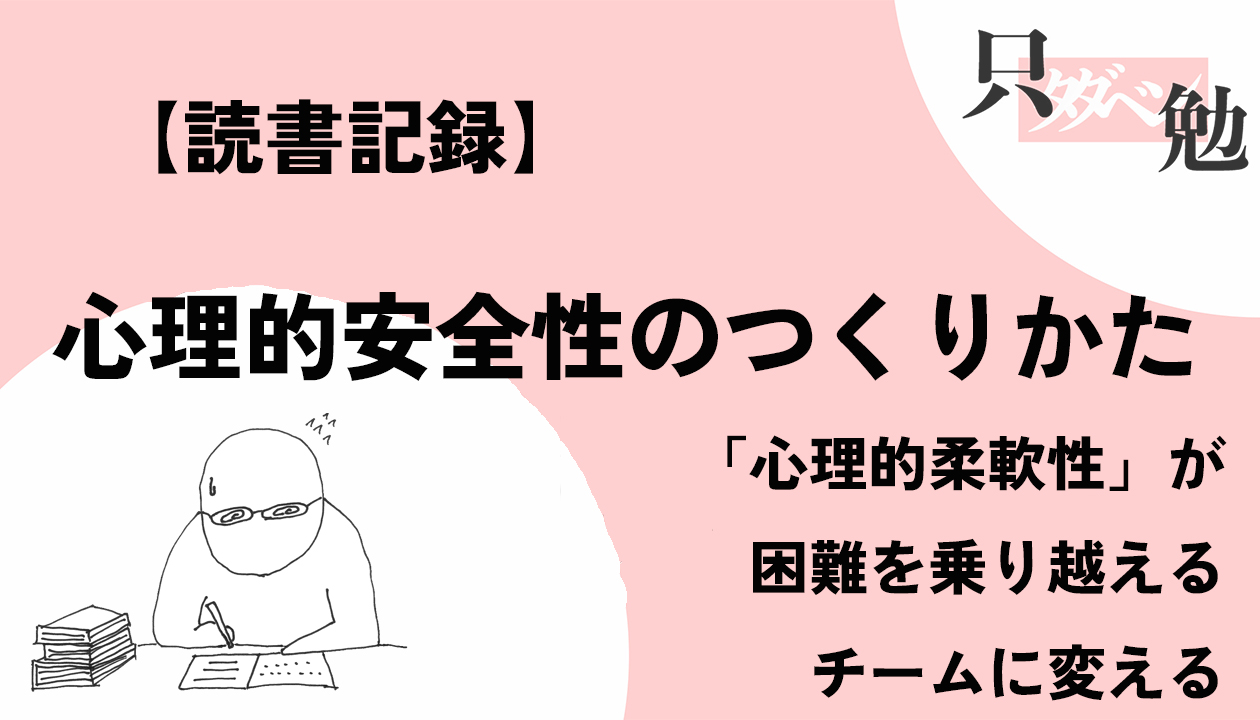
働きやすい環境を作ったり、社内の雰囲気を変えたいとか。
仕事だけではなく、人が集まるところを居心地の良い状態に整えたいと、大体の人は思うと思います。
人のことはどうでも良いと思っている人でも、自分自身が居心地の良さを感じる場所に身を置くでしょう。
チームや組織のリーダーに当たる立場にいる人は、良いと思える環境や雰囲気を作るために行動したり促したりするものです。
しかし、部下とはいえ自分と違う人間に行動を促したり、行動を変えるということはなかなか難しく、思い通りにいかないことがほとんどです。
それぞれで経験や価値観、習慣も異なる人が集まって一つの事を追い求めるので。
それをまとめるのでも一苦労という感じかもしれません。
しかし、多様性が尊重され、様々な価値が生まれ続ける今において、個々が持っている経験や価値観はとても大切なもので、チームや組織としては活用しない手はありません。
そのような時代において、チームや組織としてしなやかに成長を続けるにはどうすれば良いのか?
その答えが今回の本で語られている、心理的安全性にあります。
理想とするチームや組織の形
この本の副題に「困難を乗り越えるチーム」に変えるとあります。
なので、全体的にはビジネス環境寄りなものとはなりますが。
対人関係と捉えれば、この本の内容は普段の生活にも当てはめることができるものです。
理想とするチームや組織の形についても述べられていますが、いつでも誰でも、立場にかかわらず、成果に向けて活発に議論を交わし、ともに成長していけるような雰囲気のあるものではないでしょうか?
そのような活気を感じる事ができ、実際に自分の意見や考えが採用されたり反映されれば。
働きがいを感じたり、貢献できる喜びにより、より自分の成長を目指すことができると思います。
そのような環境が「心理的安全性が確保されている」状態とされています。
「心理的安全性」とは、このように組織やチーム全体の成果に向けた、率直な意見、素朴な疑問、そして違和感の指摘が、いつでも、誰もが気兼ねなく言えることです。
はじめに P.3
日本の組織では、①話しやすさ、②助け合い、③挑戦、④新奇歓迎の4つの因子があるとき、心理的安全性が感じられる
第1章チームの心理的安全性 P.49
何でもかんでも自分の好きに言ったり行動できるわけではなく、「組織やチーム全体の成果」を元に、そのような行動をメンバーが取ることができる状態。
ということが、ポイントになってきます。
つまり、基準はチームや組織の誰かの価値基準ではなく、組織やチームが目指す目標や成果ということになります。
その時の判断材料として持っておくべきものが、「心理的柔軟性」と呼ばれる発せられた言葉や行動にしなやかに対応するための、行動基準です。
心理的柔軟性とはこの「状況・立場・文脈」に応じて、取っている行動をより役に立つように切り替えられるしなやかさのことです。
第2章リーダーシップとしての心理的柔軟性 P.92
心理的柔軟性の3要素
①必要な困難に直面し、変えられないものを受け入れる
②大切なことへ向かい、変えられるものに取り組む
③それら変えられないものと、変えられるものをマインドフルに見分ける第2章リーダーシップとしての心理的柔軟性 P.96
現実に起こる様々な問題に対し、しなやかに対処できるようになりたいというのは、誰でも思うことでしょう。
しかし、しなやかに対処するには、ある意味では自分の軸をぶらさないことが大切です。
組織やチームにおいては、それが成果や目標という「大切なこと」となります。
その結果、取り組み行動すべきものが明確になり、そこに集中することで成果を得ることができます。
本書から引用した「心理的安全性の4つの因子」は、まさにここで集中すべき行動を表しています。
この「4つの因子」の行動をしなやかに増やすために行うのが、行動分析です。
行動分析
「きっかけ→行動→みかえり」フレームワーク
心理的安全性の4つの因子<中略>はそれぞれ「行動」の集積です。
<中略>
これらの望ましい行動を増やし、望ましくない行動を減らす
第3章 行動分析で作る心理的安全性 P.156~157
個人的にこの第3章で扱われる行動分析が、非常にためになりました。
「きっかけ→行動→みかえり」フレームワークの構造は、非常にわかりやすいものです。
「きっかけ」があった時に、「みかえり」を求めて、人は「行動」します。
本書の中では、エアコンのオン/オフなどのわかりやすい例を上げて説明してくれています。
そして自分の「みかえり」による「行動」が「きっかけ」となり、相手が「みかえり」を求めて「行動」するという流れになるわけです。
つまり、起点でも中間でも、自分の「行動」により相手に「行動」を促すことになっているということです。
一つ前に読んだ、「人望が集まる人の考え方」にも通じる内容で、それが要素分解され頭で整理されたような感覚になりました。
相手は自分の鏡で、自分が相手に望んだ振る舞いを相手が返してくる。
そのロジックが分かったような感覚です。
・・・で、本章について書き続けると、まとまりがなくなる上にいつまでも書いてしまいそうな気もするので。
有効性が確認されているこの手法は、本書を実際に読んで確認していただければと!
「行動分析」は・・・<中略>・・・応用行動分析(ABA)や、認知行動療法など、主に心理学や精神医学の文脈で活用されている、100年近くの時の試練を経て、有効性が確認されている行動変容手法です。
第3章 行動分析で作る心理的安全性 P.155
自分の行動を変える
インターネットの発達により、人間関係は広がりを見せると共に、より複雑になっています。
そのため、対人関係や本書で取り扱われている組織やチームという人間の集団が抱える問題も、複雑になっています。
人間関係の不安や相談というのも、これもインターネットの発達によるところが大きいですが、様々なところでできるようになっています。
それらの回答に関する答えとして良く聞くのが、「相手が変わることを期待するより、自分が変わる方が早い」というものです。
今は様々な人間関係を作りやすいこともあり、そこまである特定のグループに所属することにこだわる必要はありませんが。
だから、瞬間というか一時的というか。そのような対応として、語られているような気もします。
しかし、実際には一時的では済まない場合もあるわけです。
その時に自分をどのように変えるのかというと、本書で繰り返し描かれているように。
相手の言動が自分の求める「みかえり」となるように、自分の「行動」を変えるということです。
本書も、まずは個人として感覚をつかめるような構成となっているので。
自分を振り返りながら読み進め、自分の「行動」を変えて見たくなる本でした。
まぁ、ちょうど自分自身が関わる人との立ち振舞に悩んでいたこともあるので、刺さったというのもありますけどね。

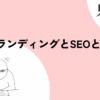

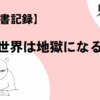
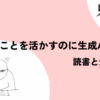
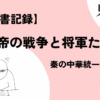
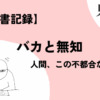
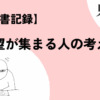

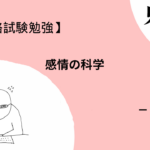
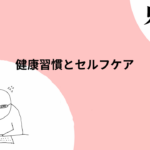
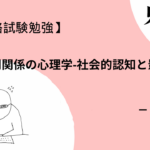


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません