【読書記録】上級国民/下級国民(著者:橘玲)|リベラル化で引き起こされるマジョリティの分断
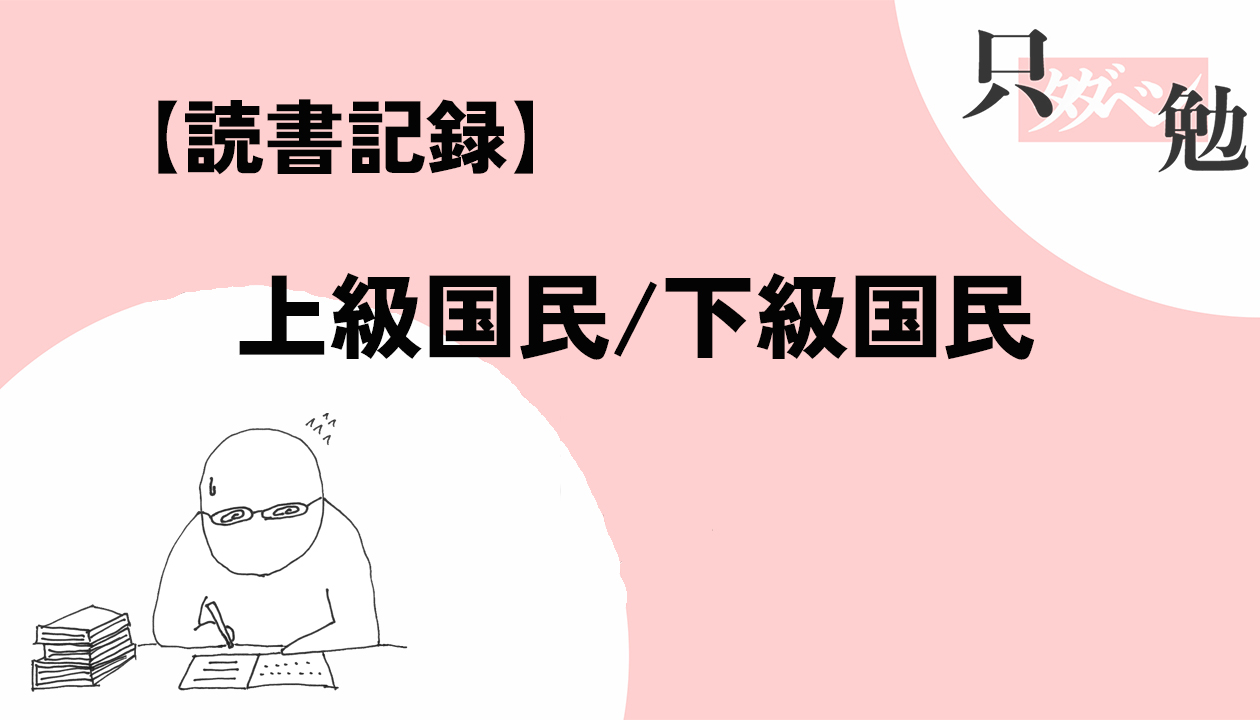
2025年に入ってから、色々と重なってしまい。
落ち着いてきたので、積読に手を伸ばし始めました。
と言いつつ、読書記録の記事が2回続いてるんですけどねw
今回は橘玲さんの「上級国民/下級国民」です。
前に2冊読んだので
タイトルは元々知っていましたが、タイトルのセンセーショナルさから読むのがなんとなく怖く。
遠ざけていた本でした。
とはいえ、実はこの本の続編に当たる「無理ゲー社会」と「世界はなぜ地獄になるのか」を先に読んでました。
記事にもさせていただいてます。
で、この2冊の中でも「上級国民/下級国民」について触れられていたなかで。
どうにも理解しにくいところが何箇所かあったのも事実で。
今回読んでみることにしたのです。
というのも、「言ってはいけない」「もっと言ってはいけない」「バカと無知」も3部作のような扱いですが。
逆から読んでいって、自分の理解が深まったという経験があるからです。
「言ってはいけない」の3部作のような、進化人類学のような話かと思って読み始めたものの、より社会よりな内容で、ここ10年以内(この記事を書いているのは2025年です。)から最近でも起きていることについて扱われているので。
1作目となる今作を読めば、より内容を理解できると思ったのです。
日本で起きた労働市場の分断
今作のタイトルとなっている「上級国民」と「下級国民」は、一時期ネットで良く見かけたワードです。
正直、あんまり良い印象で使われていなかったので、見かけても「またか」程度で流してました。
その見かけるきっかけもネットだったので、あんまり期待しないで読み始めたというのが、正直なスタートです。
が。
これは単なる特権階級を揶揄するような言葉ではなく、労働市場の変化によって誕生してしまった「下級国民」という分断の結果であるということに驚きました。
たまたま、この前に読んでいたのが「ほんとうの日本経済」だったので、労働市場のことについて考えてみたばかりでタイムリーではありました。
が、一時期ニュースになっていた「日本型雇用の崩壊」などは、実質的には起きておらず。
それを維持するために、若者の雇用機会を破壊し。
また、最低賃金の上昇により、未経験の若者が正規雇用されにくい状態が作られてきたと。
まぁ・・・その理由もなんとなく想像がついてしまいますが、票の塊である「団塊の世代」を護るためでしょう。
そうは本書の中では書かれてはいませんが、中高年が既得権益にしがみついているという表現があります。
まぁ、これが票に直結するわけではありませんが、日本国民の中でも大きな塊となっている年代を保護することに繋がりますからね。
その背後で若者たちは開かない正社員の椅子を獲得することができず。
獲得できないことを、「努力が足りない」などの若者自身に問題があるという方向に持ってかれてしまっていたのです。
そのため、ひきこもりやニートが生まれ、結果的に労働生産性の低下につながっているんだろうなと。
その方々が労働市場から退場する時代となり。
令和は、その人たちの年金を護る時代になると本書では書かれています。
その結果予想される日本の状態は・・・本書を読んでみてください。
労働市場の分断によって起きた格差
職の安定により変わってくるものは、賃金です。
最低賃金の上昇は、一見嬉しいことに聞こえますが、企業の利益を圧迫することに繋がります。
そうなると、企業側としては何ができるのかわからない若者よりも、経験のある中高年を優遇するようになる。
それが、労働市場で若者に起きたことです。
しかしそれは若者の間にも影響が出ていて、それが「学歴による格差」です。
これも単純で、少しでも優秀そうな若者を採用するのに、見るものが「学歴」ということですかね。
本書でも度々出てきますが、今は「知能社会」「知識社会」なので、学歴が高い方が優秀そうな気がするということです。
学歴により、若者、特に男性の幸福度に差が出ているという調査結果を、本書では示しています。
学歴が職の安定に繋がるのであれば、当然差が出るのが収入です。
収入の差で、「持っている者」と「持っていない者」という分断が起きていると本書では続きます。
そしてこの格差が、性愛の格差にもつながっていると。
女性が安心して子どもを育てられる状態を臨むとすると。
やはり相手に求めるのは、それ相応の収入であると。
なので、自由恋愛の現代日本では、「持っている」若者に女性が集中し、「持っていない」若者は対象にすら入れてもらえないと。
男性内での格差につながっているとしています。
それは日本だけでなく、海外でも起きていて、「インセル」という名称が使われているそうです。
このように、マジョリティであるはずの男性の中で分断が起き。
それらの人の境遇よりも、他のマイノリティの方が優遇されているという状態になってしまい。
それが、争いや問題の原因となっている。
という、マジョリティ内の分断というのが、本書のテーマとなってきます。
リベラル化の波に乗れるのか
テクノロジーの発達によって、人類は今までにない豊かさを手に入れたとされています。
その結果、家族や共同体と共に生きることに必死になるのではなく。
自分の人生は自由に選択できるという、価値観の相転移が起きたとも。
それにより、「自己実現できる社会」を理想とする、「能力主義」が本質のリベラル化が進むようになりました。
その結果、知識社会化、リベラル化、グローバル化が加速し、それに適応できるかどうかでの格差も生じているとしています。
適応しなければ、拠り所となるアイデンティティが、知識社会、リベラル化、グローバル化とは外れたモノとなってしまい。
それが、生来のマイノリティへの憎悪に繋がり、マジョリティの中での分断につながっているともしています。
それを回避するためには、テクノロジーを作る側になるか、テクノロジーを利用して評判を手に入いれるかになると。
少し強引なまとめになってしまいましたが、グローバル化が進み、一部の勝者とその他大勢の社会が進む中で、どのような選択をすると良いか?という判断材料が投げかけられています。
現代の問題のベースが理解できた気がする
と、最後まで読んでの感想は、「だから、残り2冊を書いたのかな?」です。
この本はどちらかというと、何かを最後に後押しするというよりも。
近代以降で起きたことで、どのような変化が社会に起きたかを説明することに注力されている気がします。
小学館新書から発行されているからか、文章自体もどちらかというと読みやすく、理解しやすい内容でもあります。
しかし、すこし消化不良というか・・・物足りない感を感じました。
が、「無理ゲー社会」でPART2の若者の分断について扱い。
「世界はなぜ地獄になるのか」でPART3の世界的な分断について扱われていると考えると。
ある意味本書は、問題の原因と背景を把握することに努める本なんだなという印象です。
扱っている内容の割には、サクサク読める本でもあります。
社会の流れを把握するなら
個人的には、「あぁそうか。」と納得できてしまう部分も多く。
知らず知らずのうちに、この本で描かれている社会の流れを体感していたんだなと思いました。
「テクノロジーの発達により知識社会が終焉を迎える」というような文章もありましたがー。
昨今の生成AIの進化とAIエージェントの実用化などを考えると。
本書が発行された2019年からの6年間で、急激な変化の真っ最中であることを実感します。
この先、どのようなポジションで歩んでいくのか。
しっかりと考えたいと思います。

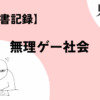
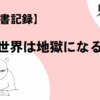
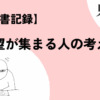
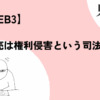
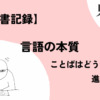
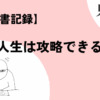
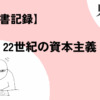
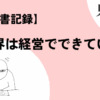
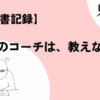

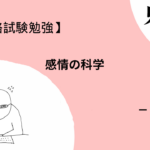
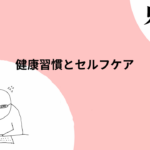
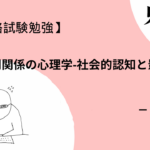


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません