【読書記録】ほんとうの日本経済(著者:坂本貴志)」|データから紐解く日本の今とこれから
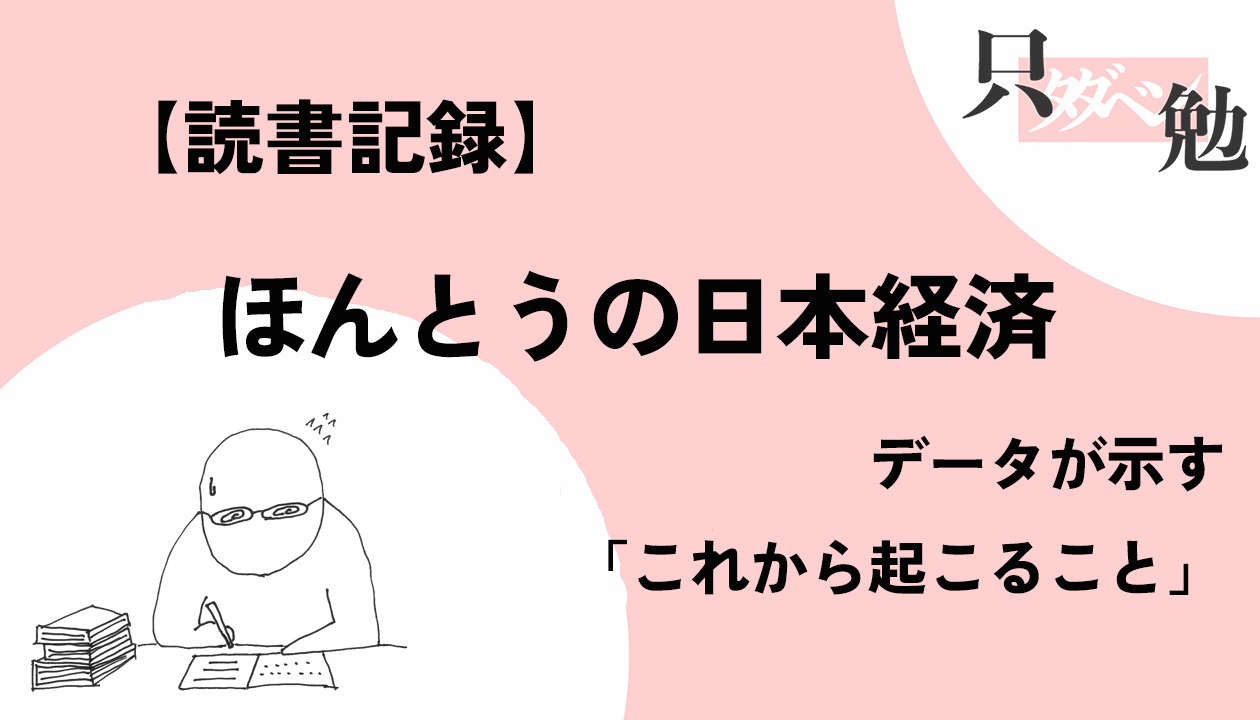
2025年の年始に買ってから、かなり遅いペースで読み進めることになった「ほんとうの日本経済」です。
ちょうど、勤め先の業務の方向性が変わるタイミングに本屋で出会ったこともあり。
少しじっくり読みたいなと思って手に取ったんですがー。
流石に3ヶ月はかかりすぎですかねw
データ活用のための分析
データドリブンという言葉が使われるようになって久しいですが。
本書の著者である坂本貴志さんは、紹介文を読むとエコノミストでありアナリストの方であるとのこと。
「経済財政白書」の執筆を努めたり、著者も統計に基づくものが多く、日頃からデータの高度な扱いをしている方なのかなぁと。
自分は無知なので、存じ上げませんでしたが。
そんな方が、この本の副題にあるように、これから日本に起こることをデータを元に予測しているのが本書です。
そして、文章を読む限りだと、労働市場に関するデータ分析を主に行っているようで、普通の生活を送っている自分のような人間にも納得感のあるデータが並んでいます。
で、本書を選んだ理由が2つあり。
1つは、日本経済の方向性・・・というか、どうなると考えられるかを自分の肌感覚だけではなく、実際にデータではどう言っているのかを知りたかったということです。
自分の勤め先の業務の方向性が変わることになっていたと書きましたが、その中で話し合われていることと、これから起こり得る変化が同じ方を向いているかを確認したいという感じですかね。
これについては、先にも書きましたが、かなり納得感があるというか。
労働市場を元にした分析からの著書ということもあり、一般消費者目線で感じることができる変化とその背景にあるデータを示してくれているので。
かなり納得感を持って読み進めることができました。
こちらはどちらかと言うと、本の内容に関する興味といった感じです。
2つ目は、ちょうどDS検定の受験を考えていた頃だったので。
データ分析と、その流れについて興味があったというのがあります。
どちらかと言うと、普段の仕事でもデータを扱って考えたり、提案したりはしていますが。
自分の思考回路だけで実施することが多く。
「こういった考え方や思考の流れで良いのか?」という疑問があったため、一度データが多めに示されていて、予測的な本で確認してみたかったという感じです。
で。
この本はそこまでセンセーショナルなタイトルではないですが、見る人によってはかなり興味を惹かれるものだとも思います。
そのためか、Youtubeや他のブログなどで度々紹介されているのを見かけました。
なので、1つ目のこの本の内容についてはあんまり触れなくても良いかなぁと。
2つ目のデータ分析の流れの部分で、色々と思ったことを書いて行こうかと思います。
1次データの中でも
まず、この本を読み始めて思ったのは、実際の現場レベルで起きている事例紹介が多いということです。
自分の偏見もあるかもしれませんが、こういった内容を扱う本の場合。
データを示すことや、実際に起きていることよりも、著者自身の体感や体験をベースに、「だからこうだ!」という感じで書かれているような印象があります。
その現場にいて、知識を持っている方が書いているので、それが間違いだとは思いません。
しかし、どうしても押し付けに感じてしまうというか。
「ふーん」という感じで読み流してしまうことが多いです。
しかし、実際の現場で最前線で対策に取り組んでいる方々のインタビューを交えながらの事例紹介なので、「そうなんだ!」と興味深く読むことができました。
データの分析から何かしらのインサイトを得る場合、1次データの重要性は分かっているつもりでしたが。
実際に現場で起きていることについては、その取材した方の言葉が多くなるよりも、実際にインタビューを受けた方の言葉が多い方が、納得感が違います。
データ分析のために、「必要に応じて現地取材を〜」というようなことはDS検定の学習で学びましたが。
それを実践してくれているような印象で、非常に面白く、しかも施策の背景まで細かく考えることができました。
何らかの目的のために情報を自分から収集するのが1次データですが。
その中でも、強力なのが現地調査だなと、改めて実感しました。
データ分析の流れでの文章構成
納得感があるなぁと思ったのが、実際のデータ分析の流れで文章が構成されているように感じたことです。
仮説の立案とその裏付け→データ分析による仮説検証、という流れが現在と予測の両方で行われています。
最初は、実例から近年起きている経済構造の変化を見出し、そこで起きていることを裏付けるデータから、10個の変化を導き出し。
結果、実際の日本経済の構造の変化を引き起こしていることが、データからも読み取れることが示されています。
そして、その変化を実感している企業の実例から、どのような取り組みを行っているかを紹介し。
そのような取り組みに至る理由を裏付けるデータから、8つの未来予測を行っています。
さらに現在起きている変化と未来予測から、この先に考えなければならない論点を7つあげ、本書を締めくくっています。
最初に実例を知れた上で、自分たち読者がなんとなく感じていることをデータで示してくれるので。
「やっぱりそうなんだ!」という感覚を得ることができますね。
データから示唆を得て、それを元に読者を納得させるという、データ・アナリティクスの妙技を体感できた気分です。
しかも、考えを羅列されるだけではなく(僕はこう思う・・・だらけのような)、数値も見れるので、あんまり良く感じない内容のものでも、そこまで悲観的な感じにならないのが面白いところです。
良いところもあれば悪いところもあるというような、当たり前のことに対する納得感が違うなぁと。
温度差?データ量の差?
ただ、少し気になってしまったのは、たまに扱い方の差を感じる部分があったことです。
温度差・・・というのは著者の方の興味に寄りすぎるので、データ量の差かな?と思いましたが。
もしかしたら、今回扱っているのが労働市場の人口減少により起きている変化とこれから起きる変化なので。
その切り口だけからだと、正確な分析ができないため、あえてフワッとさせているのかな?とか思いました。
そこまで書いたら、流石に新書じゃ無理になるのかもしれないですけどね。
じっくりだけど早めに読みたい本
この本を読み終えて、まず思ったのは、対象読者が現在働ける人全員に対するものだなぁと。
なので、手に取られやすい、新書の形での発行になったのかな?とか。
ステークホルダーの見極めと言う感じですかね?
そこまで考えたのかなぁとか、勝手に思いましたw
で、この記事を読んで誰がこの本を読みたくなるんだ・・・と書きながら思っていますが。
内容は本当に興味深いです。
人口減少によって、個人、企業、国がどのような影響を受けるのか。
そして、どのようなことを考え、行動した方が良いのか。
企業や国に何を期待し、選べば良いのか。
そんなことをじっくりと考えさせられる本です。
ですが、すでに起きている変化について扱っているので。
読むなら早めに内容を把握して、気になるところを再度じっくり読みたいですね。

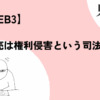

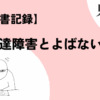
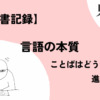

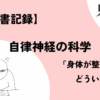
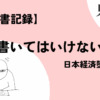




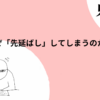

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません