【読書記録】ゼロからわかる量子コンピューター(著者:小林雅一)|最先端技術の捉え方
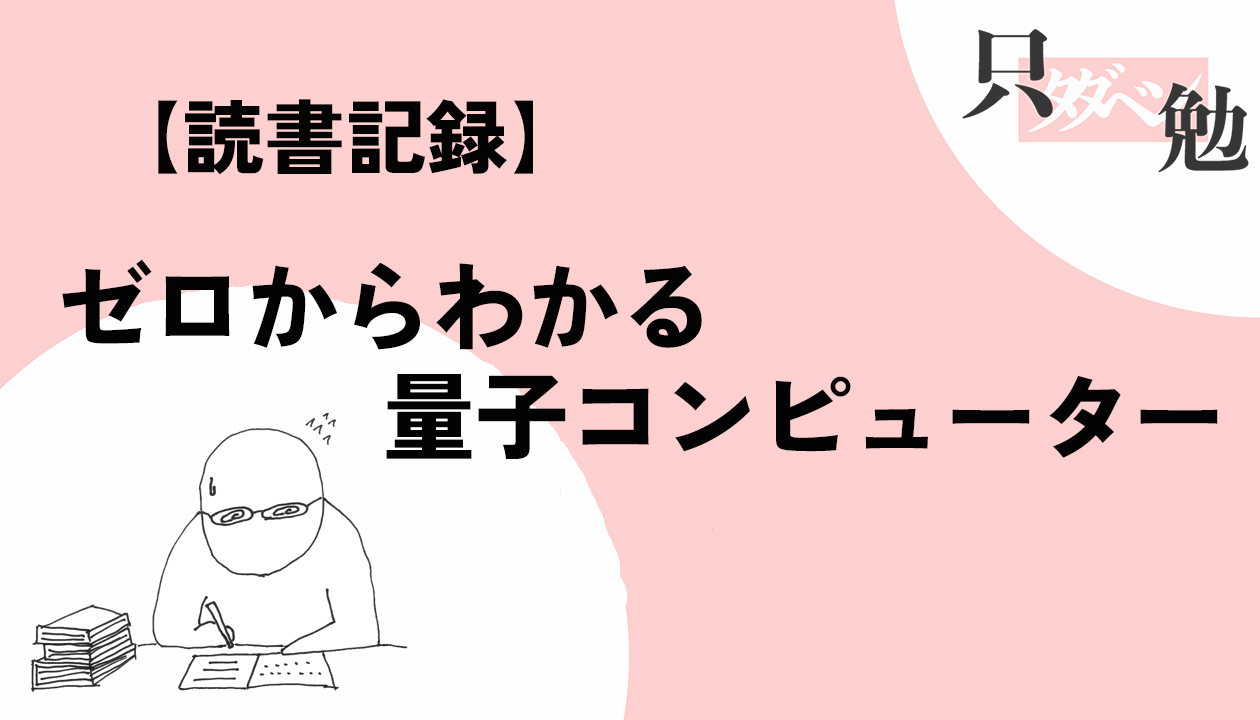
10年以上前でしょうか。
ビットコインの第1期ブームが終わった頃にブロックチェーンをしり、WEB3の情報を定期的に仕入れるようになりました。
ブロックチェーンの特徴の一つに、高度な暗号技術を使用することでのセキュリティの保証があります。
資産を扱うブロックチェーンなので、とても大切な部分ではありますが。
その暗号技術を膨大な計算量で破ることができると言われていたのが、量子コンピューターです。
なので、どんなものか知らないとなぁと思いつつ日々が過ぎ。
ついに本を読むことにしました。
これまでの勉強が活きた
量子コンピューターの歴史と仕組みについて説明し、活用が期待される分野への取り組みも紹介されています。
出版が2022年6月なので、3〜4年前の内容なのかもしれませんが。
量子コンピューターや使われている量子力学についての知識が無くても、分かりやすく読むことができる本です。
数式の説明などの数学的な解説は外せはしないものの、極力簡単に書かれていてしかも短いので「ふーん。そうなんだ。」というように読み進められます。
高校でも大学でも、化学で挫折し物理を避けてきた自分でも思ったよりもサクサクと読み進めることができました。
これまでに行ってきた、情報技術者試験やG検定などの勉強によって、そこら辺の知識を得ていたこともあり。
頭の中で想像しながら読めたので、面白かったですねー。
開発競争
この本によると、量子コンピューターの理論が提唱されたのが1980〜90年代とのことで。
機械学習やAIについての理論と同時期なので、登場する研究者も一度聞いたような名前が多かったです。
この時期は様々な科学的な発見がされ、革新が続いたイメージもあるので、かなり熱狂した時代だったのかなぁと。
今と同じような状況を感じました。
そこから研究が進み、IBMやGoogleといった莫大な資金を持つビックテックも開発に参入し。
2013年頃から試験機が登場していたようです。
国家間の争いも情報戦が主流になったことから、暗号を短時間で看破できる量子コンピューターは国家の命運を分ける技術とも言えます。
そのため、アメリカや中国といった開発の先を行く国々はもちろん、追従する各国も量子コンピューターの研究開発に資金を投入するように。
多額の資金をつぎ込まれる技術であれば、国家競争に勝てるであろうと見込まれ、メディアも取り上げているという状況のようです。
その結果、可能性や理想が先行するようなブームが起きているのでは?
というのが、この本で語られている大まかな量子コンピューターの開発の流れです。
量子コンピューターが、そのような計算能力を持つ理由については。
一般的なコンピューターは、1ビットで0か1のどちらかの状態を取って計算を処理します。
量子コンピューターでは、1量子ビットで0と1の両方の状態を取ることができ。
「ビーフは肉でもあると同時に野菜でもある」と主張するようなもの・・・
第2章 現実離れした「量子コンピューター」の仕組み P.79
という、感覚的にもつかみにくい状態を実現する技術なのです。
これにより実現される、複数の状態が同時並列的に次の状態に推移する「量子並列性」により、莫大な計算能力を持つとのこと。
しかし、量子現象が起こる環境も整えるための設備を用意するのも大変そうですし。
制御できる量子量も限られている状況みたいです。
なので、日々研究開発が進んでいるわけです。
この本を読むだけでも、SF映画などで表現されているような事が実現できるんじゃないかと。
未来が楽しみになってきます。
ただ、途中で書いた通り、夢を見るだけではなく。
現実も見ないとなぁとも思いました。
最先端技術を知るときの心構え
最後の章となる第3章「量子コンピューターは世界をどう変えるのか」の最後のトピックが、「最先端技術よりも優先すべきこと」となっています。
この章の中で、量子コンピューターの活用が期待される業界が紹介され、期待感にあふれる内容となりますが。
途中から、先に書いた開発競争について触れられ少し不安になったところで、最後のトピックです。
そこで書かれていた言葉で現実に引き戻された気がしましたが。
・・・超高度技術を適切に管理し、平和的に使いこなせるほどの倫理水準に現在の人類は到達したと言えるだろうか?
<中略>
もちろん量子技術は核兵器や生物兵器、あるいはミサイルのような軍事技術ではないが、使い方次第では、それらに勝るとも劣らない破壊的な結果をもたらすデュアル・ユース(民生・軍事両用)技術であろう。
第3章 量子コンピューターは世界をどう変えるのか P.199〜200
この引用文の前後で、AIが軍事利用されていることについて触れられています。
AIは便利で楽しいもので、仕事の形や産業の仕組みなども変えている最先端技術です。
冒頭で書いた通り、AIの初期的な理論が提唱されたのも量子コンピューターと同時期であり。
同じ用に量子コンピューターが軍事利用される可能性があります。
これも先程書きましたが、量子コンピューターの計算能力があれば、現状の暗号技術で守られているもののほとんどが破られてしまいますし。
情報戦でリードできるかどうかにも関わってきます。
残念ながら、技術革新と戦争は切っても切れないところがあるのも事実です。
手放しで喜ぶだけでなく、平和利用がメインとなるように、利用する側も監視しなければならないと同時に。
引用文の中にあるように、「倫理水準」を高める努力はしなければならないと、気を引き締めました。
初期理論が提供された頃は、様々な発見により熱狂した時代だと思います。
実現できるかどうかはおいといて、未来への希望にあふれる夢のある状態だったのでしょう。
それから約30年経ち。
試験機とはいえ使える可能性が高まると、どのように利用するかで現実的になってきているのかもしれません。
また、コロナ禍が落ち着いたことで、前向きになる気持ちにもなっているのかもしれません。
少し現実的になってきた夢や希望が優先され、考える方が良いことは、置いとかれているような気もします。
もちろん、研究者や開発者の方は考えてると思いますし、対策を立ててるとも思いますが。
その恩恵を受ける自分たちも自分たちで、考えることが大事なのではないかと思います。
とにかく楽しみ
新書なので、一気に読める厚さではありますが。
量子技術や量子力学の凄さに触れることができました。
ド文系の自分でも、十分に楽しめて、ワクワクしながら読み進める日々でした。
と、ちょうど読み終わった頃に。
Web3関連のニュースサイトでもあるCoin Desk Japaの記事で、Googleが新しい量子コンピューターチップを開発したとの記事が投稿されてました。
この記事の中でもイーサリアムの創業者のヴィタリック・ブテリン氏も言ってますし、この本の中でも書かれていますが。
「耐量子暗号」の開発も急務となってきました。
最先端技術は、様々なところに影響を与えるものです。

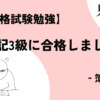

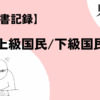
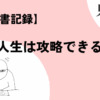
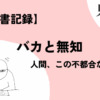
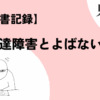
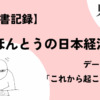

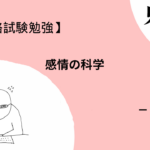
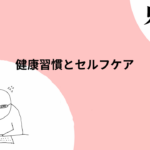
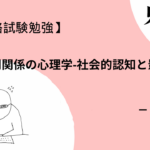


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません