AIを使わないことがリスク?じゃあ、私はこう使ってます

「AIを使いましょう!」と発信しながら、自分がどのように使っているかをちゃんと書いてませんでした。
なので、私ぽんぞうのAIの使い方について自己開示してみようかなと。
今回は記事タイトルもAIに任せたんですがー。
ちょっと恥ずかしさを感じるタイトルにw
AIの作成した文章の方が受け入れやすいというデータもあるようですし。
このタイトルをそのまま使って書き進めることにしました。
- 1. AIを使っている場面
- 1.1. ブログ記事の下書き:ChatGPT、Gemini
- 1.2. 会議メモや議事録の要約:Copilot、NotionAI
- 1.3. 情報整理や複数ソースの比較:notebookLM
- 1.4. WEB検索前提の情報整理:Bing、ChromeのAIモード
- 1.5. 論点整理・構造化:ChatGPT、Copilot
- 1.6. 事業計画のアウトライン作成:ChatGPT、Gemini、Copilot
- 1.7. 資料のアウトライン作成:イルシル、Canva
- 1.8. 挿絵や画像の生成:stable diffusion
- 1.9. プログラム作成:Cursor、Github Copilot
- 1.10. 番外編:ローカルLLM:Ollama
- 2. 私なりのルール
- 3. 不安要素としては
- 4. 「AIを使う=生成する」ではない
- 5. 自分の考え方や価値観をサポートする存在
AIを使っている場面
AIと言っても、主に生成AIを利用しています。
物体認識や音声認識など使ってみたいAIは多々あるんですが。
頭の中での作業が多いため、基本的にはテキストベースの生成AIですね。
ざっと用途と使用する生成AIやツールと、どんな使い方をしているかについて書きます。
ブログ記事の下書き:ChatGPT、Gemini
このブログを含め、運営しているブログの下書きは最近生成AIにまかせてしまってます。
いくつかテキスト生成AIを使ってみて、文章作成のお供はこの2つのどちらかにしてます。
Geminiの方が比較的緩い内容で、ChatGPTの方が知識の網羅率が高いという印象です。
ブログの内容によって使い分けています。
あ、下書きと言っても記事の構造を作る程度です。
私はどうしても書いていると、色んな方向に飛んでしまうことが多いので。
文章の流れの道標を生成AIに用意してもらう感じです。
会議メモや議事録の要約:Copilot、NotionAI
仕事で使っているのがWindowsなので、会議使用だとCopilotの利用が多いです。
スマホやパソコンで録音し、文字起こしをした物をCopilotに要約させています。
緊急のときはNotionAIで音声を拾いつつササッと要約。
結構高性能で、NotionAIの一本にしたいくらいですが。
まぁ。社内事情と言うやつですw
情報整理や複数ソースの比較:notebookLM
notebookLMにAIが搭載されて、初めて使ったときは感動しました。
ソースを限定するだけで、生成AIの信頼性がこんなにあがるのか!と。
内容の共通点や相違点の抽出から、論点整理や構造化、実行プラン案の作成など。
参考にしたいものがはっきりしている場合に使用しています。
手書きメモなどのスマホで撮影したものをPDF化して、ソースに使えるのも便利。
今では学習ツールとして欠かせないものでもありますかね。
読書のお供にもしています。
WEB検索前提の情報整理:Bing、ChromeのAIモード
チャットベースでも検索はしてもらえますが。
検索=ブラウザ起動が身についてしまっているので、ブラウザの機能を使う方が違和感なく使えますね。
AIモードはまだ恐る恐るという感じなので、メインはBingですが。
まだ検索してURLを溜め込む➾notebookLMに流し込む。
という感じでの使用の方が多いです。
検索した時に読む時間を取れない場合などはですが。
論点整理・構造化:ChatGPT、Copilot
小難しいことをするのは、ChatGPTかCopilotが良いという印象です。
自分の頭の中で論点が定まらないことについて投げてみると。
整理はもちろん、違う論点も提示してくれます。
ただ、普通に利用すると私の意見に沿ったものしか出力されず、モヤモヤとするので。
背理系プロンプトエンジニアリングを実践しています。
ここまでが考えの整理や構造化で使っているものですね。
事業計画のアウトライン作成:ChatGPT、Gemini、Copilot
事業計画や作業計画などを1から作ることが多いんですが。
ざっと目的や目標、条件などを入力してまずはGeminiに概要を作らせます。
出力された概要をチェックして、抜けや漏れを調整しながら第1段階終了。
第2段階で、ChatGPTやCopilotにできた概要をチェックさせて、内容をブラッシュアップしてます。
私基準で80%納得のいく程度になったら、GeminiかCopilotでスケジュールを作成。
できたスケジュールをGoogleカレンダーやNotionカレンダーに落とし込み実行する。
という感じです。
GeminiかCopilotは、仕事かプライベートかで使い分けているだけです。
なので、第2段階ではChatGPTを使うことの方が多いですかね。
ChatGPTのスケジュールは・・・私にとっては少しタイトというか、細かいので。
システムプロンプトとかでいじれば良いんでしょうけどねぇ。
自分がAIエージェントになった気分で計画を立ててますw
資料のアウトライン作成:イルシル、Canva
資料を作成するときは、生成AIサービスを利用しています。
このブログでも紹介したことのある「イルシル」はスライドのアウトラインとして。
試しに使ってから、なんとなくの構想でビジュアルが作れるので良いなと。
Canvaはデザインやレイアウトにこだわる時のイメージ創りに。
便利なサービスが増えています。
挿絵や画像の生成:stable diffusion
画像生成AIはstable diffusionを利用しています。
仕事で利用しているPCはメディア作成に特化していないため、GPU非搭載なので・・・
個人的に利用している感じですね。
このブログでは画像をあまり挿入せずに運用していますが。
HP作成やLP作成、紙媒体の挿絵の作成などで利用しています。
プログラム作成:Cursor、Github Copilot
プログラミングのお供はClaudeにしてます。
GPTやGeminiも悪くはないんですが、Claudeの方が効率が高いかなと。
最近はプログラムを書く頻度も減ってしまっているので、使うときはほぼエージェントを利用しますが。
ファイルに反映させる前に、動作やコードを提案させて、もろもろ確認の上という感じ。
番外編:ローカルLLM:Ollama
ここ最近の壁打ち相手にローカルLLMを使用しています。
DockerでOllamaを起動させて、対話を楽しんでいます。
まぁ会社の情報を扱っていると、社内イントラで使える生成AIがあると便利だなと思ったり。
そこら辺の実験も兼ねてです。
私なりのルール
と、以上のような感じで生成AIを使い分けています。
基本的には生成AIが出力したものをそのまま使うことはしません。
自分の考えや頭の中の整理に使ったり、道筋を作るために使って一緒に考えるような感じです。
「脳の拡張」というイメージですかね。
考えの道筋をAIに頼り、起点や着地点などを自分で考え選択する。
そんな感じです。
画像生成AIも利用に当たっては多少加工したり。サイズとか。
なので、私のAIを使うルールはざっとこんな感じです。
テーマや目的を決めてからAIを使う
なんとなくAIを使おうと思ったときは、自分の頭や時間に余力があるとみなし、まずは自分で考えます。
過去になんとなくで使い始めて、思うような出力にならずイライラした経験があるからなんですが。
ぼんやりでも大まかでも方向性を決めることで、AIとどのようなやり取りをするかを決めることができ。
AIの提案に対して、どのようなものなら受け入れ、無視するかの基準を決めることもできます。
そして、「なぜAIを使うのか?」を決めることで、以下の流れがスムーズになります。
AIの役割を指定する
上記が決まると、AIにどんな視点で出力して欲しいか決まります。
例えば、ブロガーや業種専門のコンサル、マーケター、SEなど。
AIの利用目的=自分が相談したい人、ということです。
知識レベルで言えば、最難関の司法試験に合格できるレベルとも言われているので。
システムプロンプトとして、役割を設定することで、AIの出力を安定させることにもつながります。
出力をそのまま使わない
高性能になっても、LLMは相変わらずハルシネーションを起こします。
こればっかりは、私達人間の役に立つように設計されているためしょうがないのかもしれませんが。
正確性のためにも出力はそのまま使わないようにしています。
また、AIが生成するものは教科書のようなものだとも思っているので。
少しは人間くさい、下手な文章の方が面白がってもらえるんじゃないかなぁと。
そんな希望を抱いていますw
画像生成AIはそのまま使うことはありますかね。
著作権を侵害してないかは確認しますが。
どこまでAIを使うか?を決める
出力をそのまま使わないにもつながりますが、AIに任せるのはどこまでかは明確にしておきます。
例えば、ブログ記事の下書きは骨組みまで、などです。
対話をしていると、AIは次々とプロセスを提案してくれます。
それに乗るのは楽ですが、自分の考えや想いとは別の方向に出力が向かいやすいです。
しかも、全く同じ物を生成するのは苦手(そのように設定されている)なので、微妙に変わる出力にイライラしたこともあります。
なので、AIの提案を受け入れるのはどこまでで、どこから無視するかの境界線を決めておくと。
自分が考えた通りの流れで進められるかなと。
個人的には、工程の60~70%程度までがちょうど良い印象です。
ブログ記事で言えば、情報の整理・論点整理・必要な知識の補完・アウトラインの作成、ここまでAIを使えれば十分かなと。
これで、実際のブログ作業時間は3~4日かかっていたのが1日で投稿までいけます。
作業計画の場合は、作業のリスト・工程の見積もり・大まかなスケジュール、ここまでをAIと行い。
実際のスケジュールや作業の割り振りは自分で決めるという感じです。
仕事でやってみたところ、報告前にざっとシミュレーションをする余裕もでき、報告の精度が前よりも上がったみたいで、計画から実行までの時間が短縮されたように感じます。
タイパもそうですが、やはり頭の余力の差が大きいなと思う今日このごろです。
不安要素としては
AIを使うことで、1日の作業時間の流れが変わったのは事実です。
以前よりもAIを利用している部分の作業の効率は変わりました。
なので、帰宅時間が一定になったり、ブログを書いたり勉強をするために深夜まで起きていることも少なくなりましたね。
これを生活の様々なところで活かせば、やりたいと思っていることをどんどん実行できるんじゃないかと。
そんな期待感があります。
しかし、たまに「あんまり考えなくなったかなぁ?」と不安になることがあります。
行っている作業の前後関係や、作業のつながりを見失う・・・というか忘れる感覚があります。
数学の難問を解けるようになるには、ある程度の国語力が必要で、社会ニュースに触れて多角的な視点を捉える力も磨く必要がある、というのに近い感覚でしょうか。
なので、定期的に目標や目的を再確認するという時間を取るようにはしています。
そのような時間をじっくり取れるのも、生成AIを利用している効果ではあるとは思いますが。
AIの利活用を進めると、書いたり話したりという、アナログの効果や大切さを実感する不思議です。
「何のためにAIを使うのか?」という問いは、ここらへんのズレを調整し目標に向かうとともに、自分の行動を決定するためのものでもあるんだなと。
書いていて気が付きました。
「AIを使う=生成する」ではない
生成AIの進化は凄まじく、下手に人間が作るよりもクオリティの高いものが生成できるのは事実です。
しかし、この「生成する」ということが、AI導入を妨げているのではないかとおもうのです。
物体認識や音声認識など、AIが導入されていて利活用できる領域は増えていますが。
生成AIのインパクトが強く、「AIを使う=何かを作らせる」というような感覚になっているのではないかと。
その結果、AIに作らせるよりも経験のある自分自身が作った方が早いという思考になるのかなと。
また、自分が行っている仕事の流れの中で、AIに何を「作らせれば」良いのかわからないと。
ニュースにもたまに取り上げられるようなハルシネーション。
「AIは嘘をつく」のようなことを言われれば、「作ってもらったもの」に対する不信感しかのこりません。
「AIを使う=生成する」という観点だと、こうなるのもしょうがないかとは思います。
しかし、AI利用において大切なのは、出力=生成されたものをどのように扱うかです。
生成AIではないAIの出力は、加工や分析のために利用されます。
つまり、生成AIであっても出力されたものの扱い方を考えることが、AIの利活用であると考えます。
現時点での生成AIは、確率の高い単語を予測する超高確率計算機でしかありません。
「生成されたもの」をどのように扱うか、どのような視点で受け取るか。
これが、AI社会を活きる私達に必要な心構えでしょう。
そうすれば、AIが何をできて(何をできるようになって)、何が変わって、目標や目的の達成にどのような良い影響があるのかを把握し、そのために私達人間にしかできない事が見えてくるわけです。
この感覚を持てるかどうかが、「AIを使わないリスク」になると、私は考えています。
自分の考え方や価値観をサポートする存在
人間関係の構築スキルにアサーションがあります。
相手も自分も大切にする自己表現とは、自分の行動の結果起こる相手の反応を受け入れ、対処することだとされています。
AIとの向き合い方はこれに近いものを感じていて。
私達が入力したプロンプトに応じて、その回答の正解として一番確率の高い単語群をAIが返しているわけです。
つまり、自分の考えや思いといったものをテキストにしたものを、AIが計算して返しています。
その出力に対して責任を持つのが、私達の役割です。
AIは私達が考えたことや価値観として持っているものを、膨大な学習データを元に支え補強するツールであるとも言えるでしょう。
AIの利活用=自分が考えていること。
AIは私達人間の脳を拡張するツールなのです。
・・・という意識で、今日もAIと戯れている私です。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
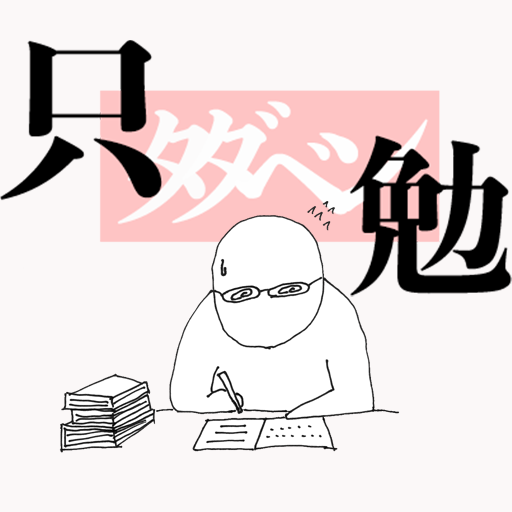
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!
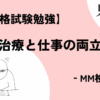
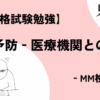
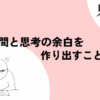
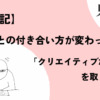
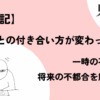
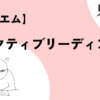


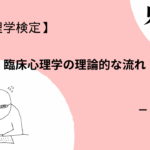
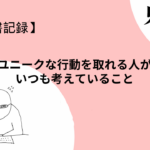
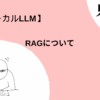
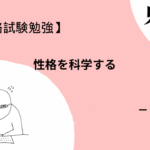
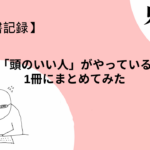
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません