EAPと外部資源の活用|メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)
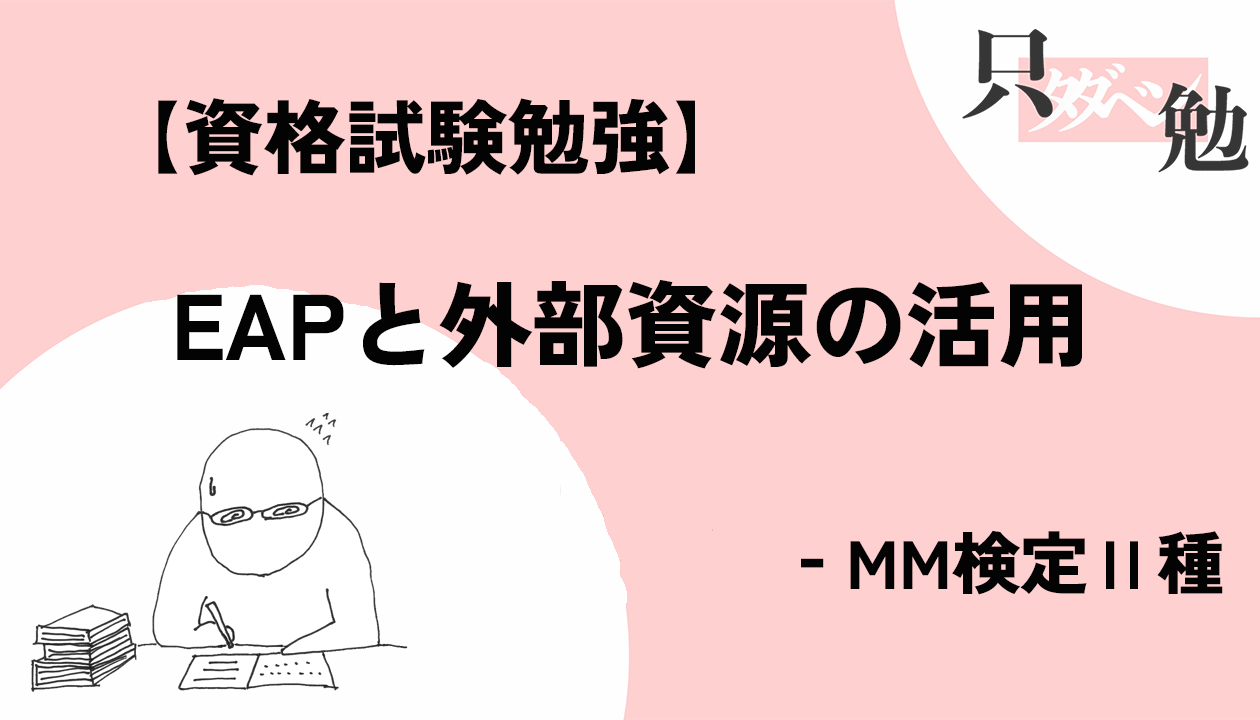
職場で部下のメンタルヘルス不調の早期発見と初期対応は、管理監督者や人事労務スタッフの役割です。
また、適切な機関へつなぎ、メンタルヘルス不調の改善につなげることも大切な役割です。
このような従業員を助ける仕組みとして、EAP(Employee Assistance Program:従業員支援プログラム)というものがあります。
メンタルヘルス問題の複雑化に伴い、職場だけでは解決できない問題が増え。
専門家の助けを得て、適切な支援を行うことが組織の生産性を維持し、持続可能性を高めるために必要です。
EAPとは
米国において、アルコール依存症のケアを行う活動から始まったのが、EAPという機関です。
1989年にEAP協会が設立され、日本にもその支部として一般社団法人国際EAP協会日本支部があります。
従業員の個人的な問題となる、
・健康問題
・結婚・家族問題
・経済問題
・アルコール・ドラッグ中毒
・法的問題
・対人関係
・心理的問題
といったものを解決する、専門性の高い手段を提供します。
このような個人的な問題が企業の生産性に関わり、経営上の問題と認識されていることから。
組織に対しても、ニーズに合わせた継続的・システム的な支援の提供を目的としています。
従業員にとっては、ストレスの軽減、問題の早期解決、安心して働ける環境の確保につながり。
組織にとっては、休職率や離職率の低下、生産性の維持、ハラスメントやコンプライアンスといった問題の予防にもつながります。
管理監督者は、組織の生産性を保つという視点だけではなく、部下を専門家につなぐ仕組みとして理解しておくことが重要です。
公式テキストに上げられているEAPの機能と役割は以下の通りです。
・労働者の心の健康問題に関する評価
・組織に対する職業性ストレスの評価・コンサルテーション
・労働者の抱える問題に対する適切な医療機関や相談機関への紹介とフォロー
・管理監督者や人事労務管理スタッフへの問題対処方法やEAPの適切な利用に関するコンサルテーション
・従業員やその家族、管理監督者、人事労務管理スタッフに対するメンタルヘルス教育、EAP利用方法の教育
・短期的カウンセリング
・健康問題を生じる可能性がある聴きへの介入
・EAP機関と連携する事業場内メンタルヘルス担当者の育成
・事業場内産業保健スタッフへのメンタルヘルス対策の教育
・EAPサービスの効果評価公式テキストP.272
EAPの種類
EAPには「内部EAP」と「外部EAP」があります。
EAP機関とはいえ、あくまで従業員支援のためのサービスなので。
企業内に配置している産業医・保健師・カウンセラーといった専門家によって提供するものが、内部EAP。
企業外の専門機関によって提供されるものが、外部EAPです。
内部EAPは組織文化や従業員の情報を把握しやすいので、連携がスムーズなのがメリットです。
しかし、自身の健康情報を知られたくないと考えている従業員にとっては、利用に抵抗感が出てしまいます。
また、すべての問題に対応できる人員を配置することは難しいので、対応できる領域が限られてしまう場合もあります。
外部EAPであれば、社外機関となるため提携先によって様々な対応を取れるようになりますし。
従業員も上司などに健康上をを知られ、人事や処遇に影響が出るかもしれないという、不安を抱かずに利用することもできます。
しかし、あくまで組織外であるため、組織の状況や社内文化、業界情報について理解してもらうのに時間がかかる可能性もあります。
内部EAPにも外部EAPにもメリットとデメリットは存在しますが。
守秘義務の観点も踏まえると、外部EAPの活用が推奨されているようです。
外部資源
EAPだけでなく、組織の産業保健活動を支える外部資源は多くあります。
一部は「メンタルヘルスを支える公的機関や相談窓口」で紹介したとおりですが。
専門家という観点であれば、精神科や心療内科を備える医療機関や。
公認心理師や臨床心理士といったカウンセラーの、カウンセリングや心理療法の利用。
こういった機関の利用を進めることも、部下の健康を守るためには必要です。
また、職場環境については産業保健センターの支援を受けることもできますし。
ハラスメントや労働問題に対し、法的に対処するとともに予防できるのが、弁護士や社会保険労務士への相談です。
休職者に対する復職支援等は地域障害者職業センターも利用できます。
これらの機関は、管理監督者が負う必要のない責任を専門的に扱う機関なので、管理監督者がメンタルヘルス対策を進める助けとなります。
そのような専門家の助言やサービスを受けることで、部下に対して示すサポートも専門的なものにすることができ。
提供された情報を活用した従業員の健康に寄与することもあるでしょう。
利活用を推進する
従業員の健康への投資は、企業の生産性を高めるものとして周知の事実となっています。
しかし、本人からすると、問題を抱えていても利用の必要を感じていないかもしれません。
また、問題を解決したいと願っていても、どこに相談すれば良いのかわからないということもありえます。
なので、管理監督者が部下との信頼関係を築くとともに、普段の状況を把握し。
相談を受け受ける中で、「安心して相談できる専門家がいる」というように利用を推奨することができます。
普段から利用できる外部EAP機関や外部窓口の存在をポスターで掲示することで周知したり。
産業医と連携して、外部資源の情報を共有し、適切な窓口を案内できるよう、組織的に備えておくことも必要です。
事業主も外部資源との連携をコストではなく、従業員の健康を守ることで組織の活性化に繋げるための投資ととらえ。
環境を整えるとともに、利用を推奨する姿勢も必要でしょう。
このように、組織全体として従業員の健康を守る意識を高めることができます。
EAPや外部資源を有効活用
管理監督者は責任感の強い人がその立場に就くことが多く。
自分の部下の問題として抱え込んでしまう傾向があります。
しかし、専門的なことの判断を間違えると大きな問題になりますし、そのような判断をする必要もありません。
様々な機関と連携して、部下自身やチームの環境を良好に保つ姿勢をみせることが、今後の管理監督者に求められる姿でもあります。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
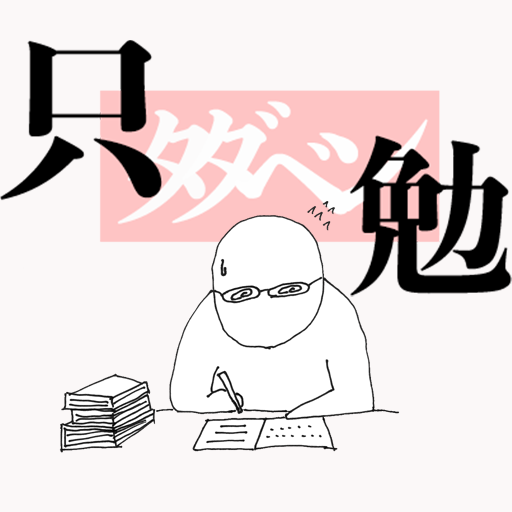
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!

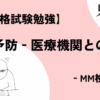

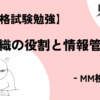

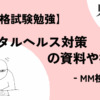

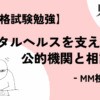

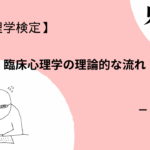
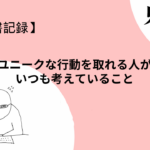
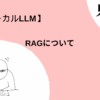
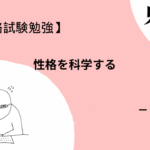
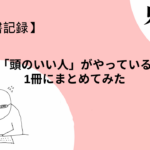
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません