フィジカルAIと日本と私達
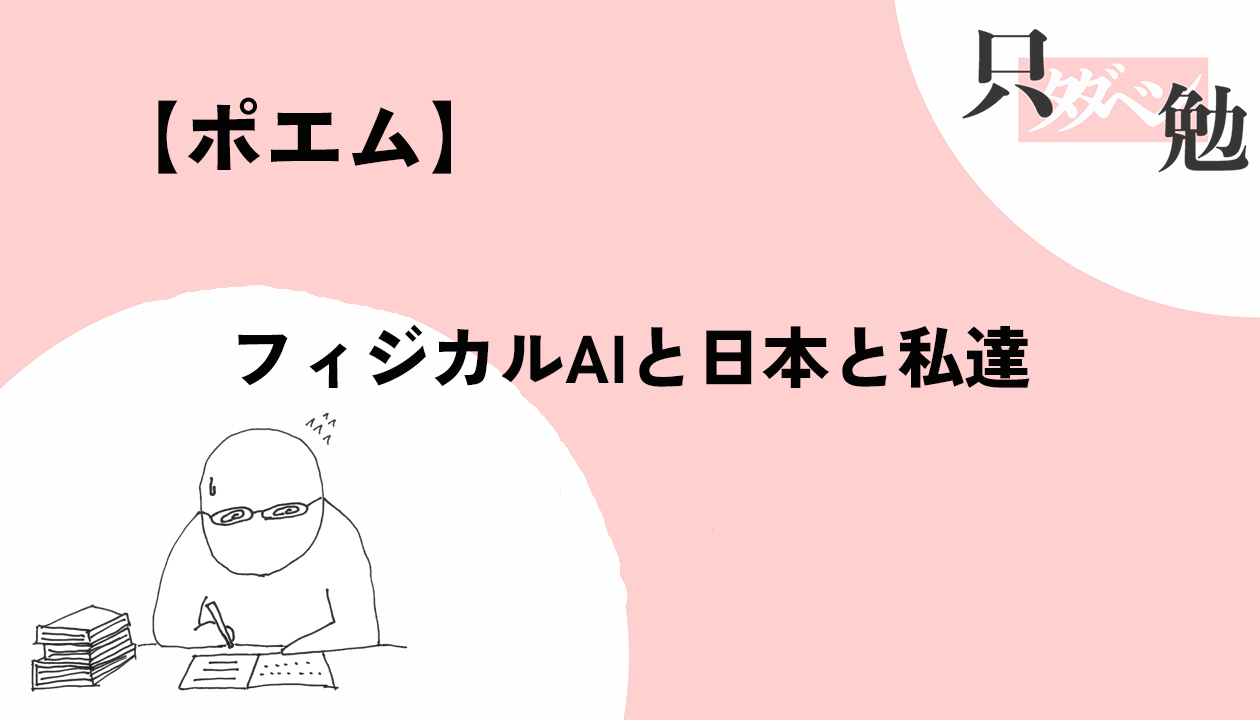
フィジカルAIとはどういうものかについてざっくりと書きました。
これが、今後の日本のAI戦略の中心になると考えられます。
「AIを使わない」という選択肢はないとも言われるようになっている中で。
どのような戦略を日本政府が考えているか。
それがどのように私達に関係してくるのか。
少し考えてみたいと思います。
参考:内閣府・人工知能基本計画「AIを使わないことが最大のリスク」日本が挑む反転攻勢の国家戦略‐innovatopia
日本はAIを創り使う流れ
2025年9月にAI推進法が施行されました。
様々なところで言われていますが、日本の生成AI利用率は先進国の中では低水準です。
個人レベルで利用されているものの、業務レベルでの活用には壁が存在している現状です。
しかし、政府としての行動は「広島AIプロセス」や「AI推進法」の施行など中心的なものがあります。
つまり日本政府としても、AIを活用した国家のあり方を目指しているとも言えます。
「AI推進法」での目標は、「世界で最もAIを開発・活用しやすい国」となることとされています。
2019年に内閣府が公表した「人間中心のAI社会原則」の内容も含め。
・人間中心
・アジャイル
・内外一体
という3つの原則を実現するために。
・AIを使う
・AIを創る
・AIの信頼性を高める
・AIと協働する
という基本方針が示されました。
「AIを使わないことが最大のリスク」という言葉をいろんなところで聞くようになりましたが。
AIの「開発」には「使うこと」が欠かせません。
日本語の習得難易度は世界トップクラスであるように、LLMに学習させる難易度が高いのも事実です。
そのため、私達日本人が利活用することでしか、日本のAIは改善のサイクルを回すことが難しいでしょう。
AIによる機械翻訳によって、あまり違和感のない日本語が生成されるようにはなりましたが。
細かなニュアンスや、文脈の理解という意味ではまだ足りないと感じることがあるのも現状です。
また、AIはあくまで予測する確率計算機で、現実を理解しているわけではありません。
しかしAIが与える影響はかなり大きく、事業自体を変えてしまっているかもしれません。
ここらへんについては、別記事で書いているのでこれくらいに。
AIを安心・信頼の元に使うには、ガバナンスの構築も必要です。
個人での使い方はそれぞれに任されているので、個人の利用が進んでいる要因でもあるかもしれませんね。
そのようにして初めて、効果のあるAIとの協働が実現するのです。
このような状況を企業が実現するとともに、AIの社会実装をすすめ。
それを国としてフォローしていくというのが、大まかな戦略です。
とはいえ。
大幅に出遅れている状態といのは事実で。
「使う」という発想自体もない人もいるでしょう。
AIがサービスに組み込まれているもので、特に自分が操作せずに楽しむぐらいでしょうか。
この状況を打破し、理念や国としての枠組みだけでなく、本当にリーダーシップを取る可能性を秘めている技術が「フィジカルAI」です。
フィジカルAIでの日本の強み
フィジカルAIは、現実世界に作用する能力を持つAI技術です。
詳しくは冒頭でリンクを貼った別記事をお読み頂ければと。
現在の生成AIのモデルであるLLMは、文字のつながりから次に来る単語を予測し出力しています。
なので、現実世界の事や物理法則を理解しているわけではなく。
現実世界に作用させるためには、現実世界の「理解」と物理法則に則った「制御」が必要となります。
LLMでの「予測」に「理解」と「制御」を加える技術が、フィジカルAIであると言え。
「制御」するためには身体が必要です。
そこで日本のロボティクス技術が活かされるわけです。
そのために必要な、精密機械の製造や目や耳の代わりとなるセンサー技術など。
日本が誇る技術力というものが、フィジカルAIとの親和性が高いのです。
それに加えて、「AI推進法」です。
あくまで人を中心に据えるという方向性は、現実に作用することになるフィジカルAIの導入においての指針となりますし。
「AIと協働」する方法を提示する、倫理や社会実装にもフィットする考え方です。
現時点でのLLMの利用・開発で出遅れているとしても、その次の現実世界で稼働するフィジカルAIの分野で一気に並べる可能性を秘めています。
AI開発者もLLMの限界に気付き、次の段階であるフィジカルAIへの開発に動いているのも事実です。
参考:LLMの“次に来るAI”? NVIDIAが推進する「フィジカルAI」とは何か、識者に聞いた‐ITMediaAI+
参考:OpenAI、AGI競争でロボティクス研究を加速‐WIRED
だからこそ私たちは、AIを利活用し、AIとどのように働くかを今からでも体験しておくことで。
AIがどのようなことができて、できないかを知る。
➾フィジカルAIの登場でどのようなことができるようになるかを知る。
自分の業務において、どのようなことが重要かを知る。
➾自分の携わっている仕事内容を理解し、本当に時間を割くべきことを見出す。
「AIを使わないことがリスク」なのであれば、今からでも使うようにしてみるのが良いでしょう。
そうは言ってもハードルがある
各AI利活用や開発の最前線にいる方々も、どんな小さなことでも良いから、AIを使うことを勧めています。
この記事を書いている時点でも、生成AIが出力するものの性能はどんどん上がっていますし。
エージェントAIやMCPサーバーなど、生成AIのできることがどんどん増えています。
そのため、自分が今まで行ってきた仕事がなくなるという不安や、手が空いたら何をしたら良いかわからないという状態もあり得るかもしれません。
また、生成AIを利用する場合、未だにハルシネーションの問題はあります。
だいぶ少なくなったので気を抜いていたのが私ですが、つい最近ハルシネーションが起きて気を引き締め直しました。
このような事があると、正直「自分でやった方が早い」という思考になってしまい。
使用頻度が減ってしまうのも事実ですね。
これは、ミスが許されない仕事で考えると、厄介な問題とも言えます。
情報漏えい対策という意味も含めて、ローカルLLMにも注目は集まっているみたいではあります。
他にも色々なハードルはありますが、結果AIが使われているサービスは使うけど、自ら進んでは・・・という感じになるのも頷けます。
しかし、今はそのような情報が大切なのです。
AIで仕事が一つなくなった
➾こういう使い方をしたら、こんな仕事をAIに任せられるようになった
こんな内容でAIとやり取りしていたら、ハルシネーションが起きた
➾内容やプロンプトをこう工夫すればハルシネーションを防げるかも?
というように、AIの出力や利活用の結果だけでなく、その過程が重要なのです。
それを同じ目標で働く職場の仲間と共有できたら、AIとの協働に近づくと思いませんか?
そのような姿勢が企業と職場で働く人に求められていると、私は考えています。
一人ひとりが活躍できる世界へ
AIに関する記事を書く時に毎回つづってしまいますがー。
私は、生成AIを人間の脳の拡張と考えています。
思考することの限界を拡張し、選択や判断といったリソースを消費するものにより力を割くために、AIの推論能力を活かすというように。
フィジカルAIが現実のものとなった時、それは身体の拡張になるかもしれません。
「猫の手も借りたい」と忙しい時に思うのが、フィジカルAIによって可能になるかもしれませんね。
⋯肉球がついてるかはわかりませんが。
そのためには、私達一人一人がAIを活用しそれを共有することが、まず必要になります。
SNSの発展やコロナ禍を経て、共有の意識はだいぶ根付いたように感じます。
共有することで、相手も知ることができるとともに、自分の中での理解を深めることができます。
この逆もあります。
日本らしい、信頼と共創によるAI利活用の文化形成を身近な職場などから始めることが。
今後の社会の発展に繋がるでしょう。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
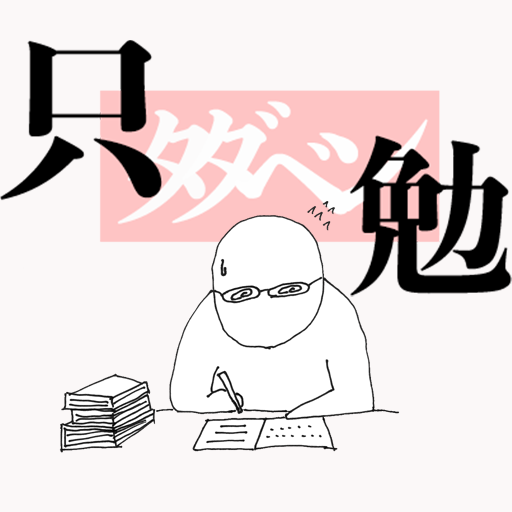
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!
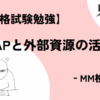

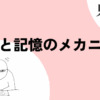

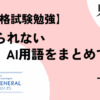
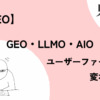
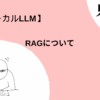

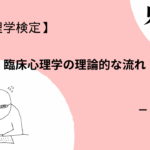
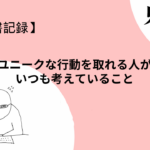
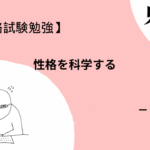
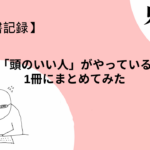
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません