自律神経の科学 「身体が整う」とはどういうことか (著者: 鈴木 郁子)|健康が生活習慣に帰結する理由
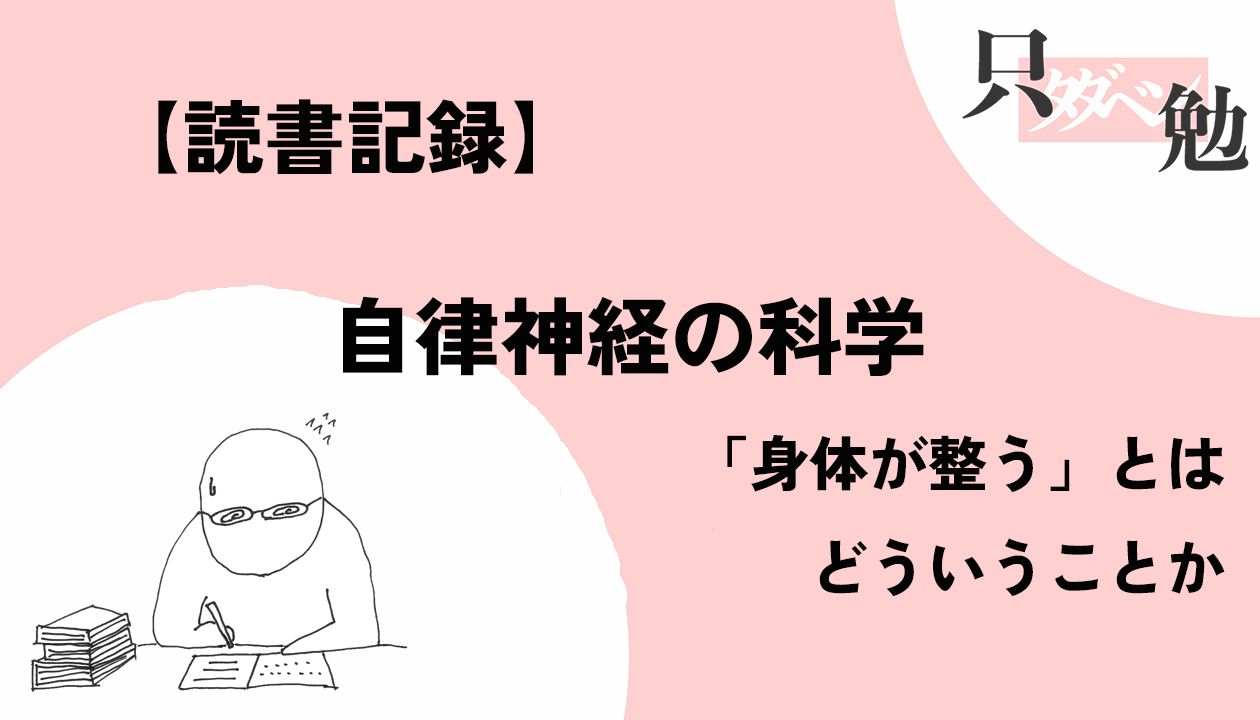
少し体調が悪いなぁと思う時に気になるキーワードの一つに、「自律神経」があると思います。
メディアで健康が扱われるときにも、自律神経がテーマになることは多い印象です。
自分で選んでいるとはいえ、今まで読んできた本にも関係するテーマなのではないかと。
ふと気になったので、今回読んでみることに。
・・・前回読んでいたのが東洋医学についての本だったので、その流れでなんですけどね。
自律神経系
正直、自律神経というものの存在は知っているものの、良くわからない神経という印象をこの本を読む前は持っていました。
良くわからないけど、整えると気分や体調が良くなるという感じです。
まさに副題の「「身体が整う」とはどういうことか」という状態だったわけです。
本書は、著者が実際の講義の内容から自律神経とその働きについて説明し。
その知識を元に、どのように生活を送れば、ストレスフルな現代を健康的に生きられるかを提案しています。
自律神経系には、内臓求心性繊維、交感神経と副交感神経、腸管神経系の3種類があり。
意識して動かすことのできない平滑筋(内蔵の筋肉)に接続されています。
そのため、身体の状態に合わせて自律的に適切な状態に調節してくれるため、自律神経と呼ばれているそうです。
自律神経がさまざまな臓器とつながり、外部環境に応じて全身の働きを調整し、身体の内部環境を守っている
第7章 自律神経から考える「心身を整える方法」P.210
このような調整を24時間行ってくれているので、私達は変化を感じつつも生活を送ることができているのです。
二重支配と拮抗支配
自律神経系がどのように内蔵と脳につながり、私達の心や身体に影響しているかを、日常的な反応を元にわかりやすく説明してくれているのが本書です。
細かい引用はしませんが、臓器につながっているため自律神経の症状は多岐にわたります。
冒頭に書いた、「なんとなく調子が悪い」という状態に自律神経が関係する理由も納得です。
その調子の悪い原因となりうるのが、自律神経のバランスが崩れること。
よく<交感神経と副交感神経のバランスが大切>とか<自律神経が乱れる>という表現を耳にします。これは、交感神経もしくは副交感神経の電気活動のバランスが崩れて、臓器が正常に働かなくなっている状態を指しています。
第1章 自律神経とはなにか P.53
なぜバランスが必要なのかというと、先程書いた外部環境の変化による24時間体制での微調整に対応するため、交感神経と副交感神経で臓器に対するアクションが変わるからとされています。
交感神経と副交感神経のどちらで機能が促されるかは、器官によって異なります。<中略>概して循環器系は交感神経によって機能が促され、消化器官系や泌尿器系は副交感神経によって機能が促されます。
第1章 自律神経とはなにか P.50
この交感神経と副交感神経がつながっている状態を二重支配といい、相反する活動を促す状態を拮抗支配といいます。
この支配によって、私達の身体が正常に保たれているわけですが。
心身の不調にはこのバランスの乱れが関係していて、現代の生活は乱れやすい状況が多いということです。
健康を維持する8つの方法
どのように自律神経を整えるかについて、本書の内容を元にどのような生活を送れば良いかを提案してくれています。
項目を参照して抜き出すと。
①自分の意思で自律神経を調節する
②ストレスを緩和し、交感神経の過度な活動を休める
③運動によって交感神経の調節機能を活性化する
④夜はしっかりと睡眠を取り副交感神経の活動を高め、交感神経の活動を休める
⑤腸管神経系の活動を高め、内蔵求心性繊維の活動にも気を配る
⑥生活の工夫を共有する
⑦脳への負担を減らし、自律神経を休める
⑧超資本主義社会に無理に合わせない
という感じです。
それぞれの項目について触れると、本書の内容全てに触れないといけなくなるのでざっくりと似しますが。
①〜⑥については、良いと言われている生活習慣を送る事が大切です。
知的で文化的な生活を送ることができる人間も、結局は地球の自然環境の中で生きる一種の動物です。
その自然環境や身体のリズムから逃れることはできません。
生活習慣病などの現代病の原因は、現代の生活リズムにより、そのリズムに則った生き方を送ることになり、自律神経のバランスが崩れやすくなっているとされています。
①の「自分の意志」というのは、まさに生活習慣を自分から改善するということです。
自律神経は各器官につながっているので、生活習慣の影響をモロに受けるわけです。
なので、良く眠り、運動し、身体に良いものを食べるという生活習慣が、心にも身体にも良いということなのです。
薬の影響についても書かれていて、薬のいらない治療法としても生活習慣の改善が勧められていました。
しかし、良い生活習慣を難しくしているのが、⑦と⑧だと言わざるを得ません。
脳の警報と自律神経系
現代人の精神や心に起きている事について書かれた本で、よく見かけるのが「脳の警報がなりっぱなし」というような表現です。
⑦の脳の負担は、現代の情報化社会により絶えず情報を処理し続けることができてしまう、常に交感神経が興奮している状態になっていたり。
情報を取得するためのデバイスが、人間の身体に近づいた結果、情報を見る目の副交感神経が過活動状態になっているともされています。
また⑧によって人間や地球に大切なものよりも、利益が優先されやすい社会の動向となっているためストレスをためやすい環境でもあります。
ストレスとは外部刺激なので、⑦では直接的に、⑧では間接的にそのような刺激を受けているとも考えられます。
ストレスに対する瞬時の対応として、自律神経系が働きます。
交感神経‐副腎髄質系の動きにより、闘争または逃走の反応が生まれ。
副交感神経の働きにより、ストレスをやり過ごす反応が生まれます。
本書では「火事場の馬鹿力はどうやって生まれる?」という項目からこれらの反応について解説されています。
しかし、「火事場の馬鹿力」は持続できるものではありません。
また、やり過ごすのにも限界があります。
長期間続くようになれば、副腎皮質ホルモンが分泌されストレスに耐える身体となります。
が、このストレスに耐える状態というのが、闘争または逃走の状態です。
戦うにしても逃げるにしても、すぐに動き出すための準備が必要です。
ここから先は本書に含まれていない内容も含みます。
副腎皮質ホルモンが分泌されると、血糖値が上がります。
エネルギーを補給するために胃の消化が保護よりも優先されます。
動いてる最中に排泄は必要ないため、抑制されます。
眠ると危険なため、不眠の症状も出ます。
このように、現代病と言われる症状が揃うわけです。
情報化社会で超資本主義社会を活きる私達は、常に押し寄せる情報や周囲の評価、利益の獲得競争にさらされていると言えるかもしれません。
その結果、ストレス状態を常に感じることになり、自律神経系は常に過活動状態になっていると言えます。
自律神経系は脳ともつながっているため、脳が警報を発し続けているということなんだなと。
今まで読んできた本がつながった気がしました。
そして、それを休める状態が少ないというのも異常な事態であることも分かります。
働き方改革や多様性・個の尊重などにより、一時期よりは自分らしい過ごし方をできるようになったかもしれませんが。
自分から敢えて⑦である押し寄せる情報から距離を取り、⑧での利益ではなく本当に大切にしたいものを追求することを行わなければ。
自律神経のバランスを取ることが難しい時代とも言えるなと、思いました。
自分に影響を及ぼせるのは自分
すべてと言ったら広すぎるかもしれませんが。
現代の悩みとされるものの解決策として、生活習慣の改善が上げられています。
その理由が、ただ単に健康のためではなく。
自律神経など普段気にしていないであろう部分を癒やし。
人間が持つ本来の能力を発揮するためなんだなと。
そんなことを思いました。
もちろん、日常を送るのはそんなに難しいことではありませんし。
自分一人で完結するわけではありません。
それでも、まずは自分を「整える」ことで悩みや問題が減り、余裕を持てるようになるでしょう。
それが、現代社会を自分らしく活きる一歩なのかなと。
そんなことを考えました。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
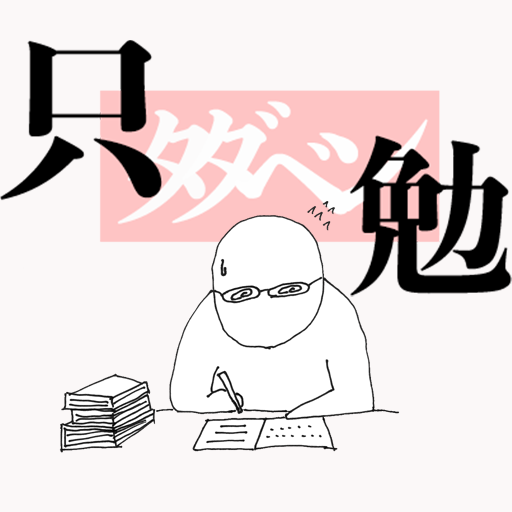
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!

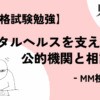
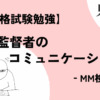
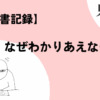
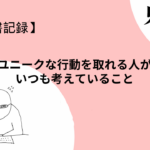
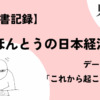
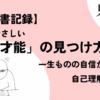
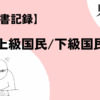

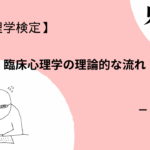
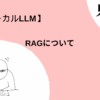
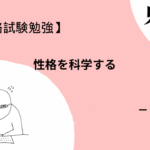
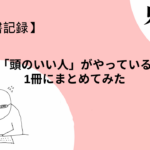
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません