管理監督者のコミュニケーション力|メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)
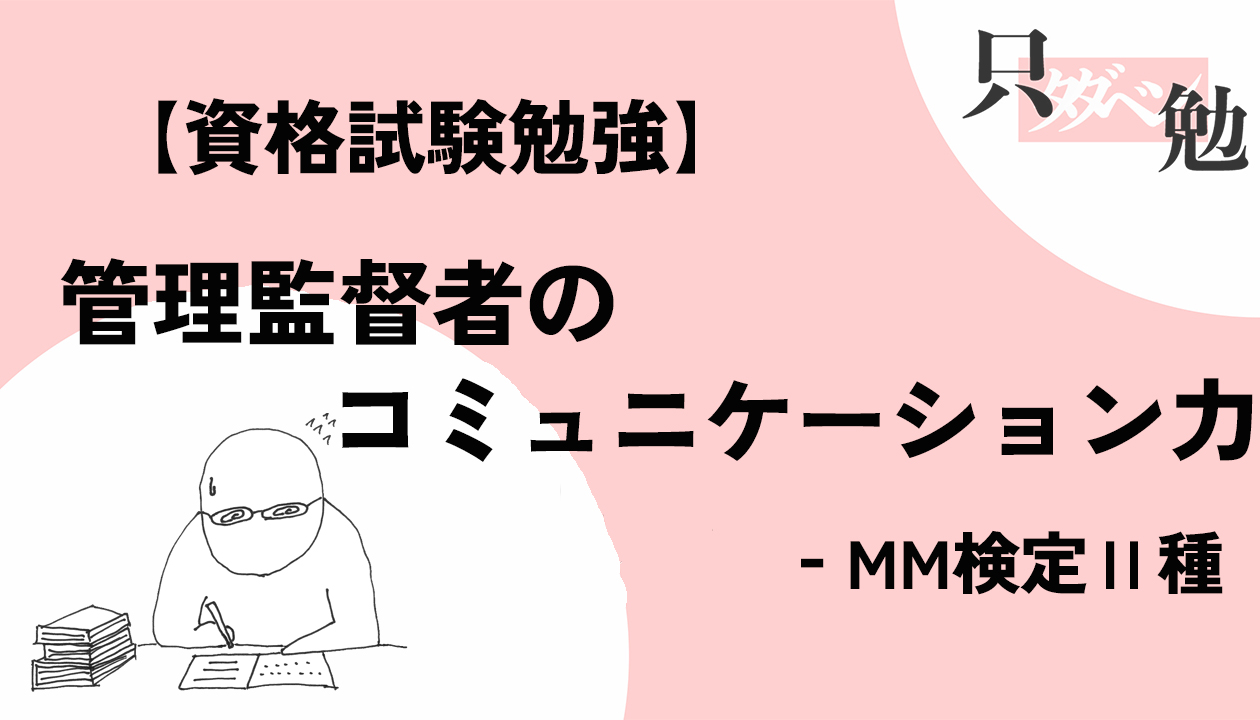
管理監督者は職場環境を作りストレス対策を行い、ストレス要因を減らすことが求められます。
「働き方と心の健康:過重労働・ハラスメント・テレワークなどの職場環境について」の記事で扱いましたが。
職場のストレス要因の上位に「人間関係」があります。
上下関係やハラスメントなど、人間関係の問題になるものは多くありますが。
人間関係の基本はコミュニケーションです。
そして、仕事を行う上で避けては通れない道であると共に。
良好なコミュニケーションを取ることができれば、ストレスを緩和するソーシャル・サポートの基盤にもなります。
なので、管理監督者が知っておきたいコミュニケーション技術について、メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種の公式テキストの内容を元にまとめます。
コミュニケーションとは
コミュニケーションは双方向の行為です。
基本的にはメッセージの「送り手」「媒体」「受け手」によって成り立ちます。
送り手がメッセージを送る媒体を選び、受け手に送ります。
受け手は受け取ったメッセージを媒体を利用し、送り手にかえします。
業務上の指示や報告を考えると、この流れはわかりやすいかもしれません。
このやり取りに問題が発生することで、コミュニケーションに問題が発生します。
送り手の場合は、送りたいメッセージを発信することができない状態。
受け手は、相手のメッセージを受信することができない状態。
これは物理的にも、精神的にも起こり得るため「状態」とさせていただきました。
コミュニケーションの機会が得られないまたは阻害されると、深刻な悩みに発展してしまう場合もあります。
そうなるのを防ぐと同時に、不調のサインや性格傾向を把握したり、適切な相談行動を引き出すきっかけにもなります。
なので、ストレス要因を防ぐと共に、重症化する前に行動を促すことができるのも、コミュニケーションの力なのです。
アサーティブコミュニケーション
職場での人間関係において、一方通行であることはストレス要因になりえます。
しかし、仕事においては注意や指導が必要となる場合もあります。
その方法を間違えると、パワハラなどの問題となるため、多くの上司の悩みとなっているのも事実です。
そこで、まずはコミュニケーションの姿勢として「アサーション」を知りましょう。
アサーションは、相手も自分も大切にする自己表現方法です。
相手の意見や気持ちを尊重しつつ、自分の意見や要求を率直かつ誠実に伝え、お互いを尊重した解決策を共に検討します。
例えば、報告書の期限を守れない部下に対して「いつも遅い」と指導するのではなく。
「何か期限を守れない要因があるのではないか?」と過程に注目し。
「何か困っていることはない?」といった問いかけにより、問題を把握し。
原因を取り除いたり、何らかの協力を行うことで解決を目指します。
アサーションでは自己表現を「攻撃的」「非主張的」にまず分け、場面において自分がどのような行動を選択するかを把握し。
「アサーティブ」な対応はどれかを検討することから始まります。
コミュニケーションは相手があってのものなので、アサーティブな対応というのは自己表現に対する相手の反応に責任を取ることが重要です。
そのような誠実な態度は、部下との信頼関係を保つ助けとなるでしょう。
また、相手の反応への責任を取るということは、自分の行動の責任を取ることでもあります。
自分が取れる範囲の責任を取るために、自分らしいアサーティブな対応を見つけることも重要です。
部下のみならず、上司や取引先など多くの相手に対してはたらきかけを行うのが仕事です。
それぞれに対し、誠実で責任のある行動を取ることは、信頼関係の構築につながります。
このブログでも「アサーション入門」という本のレビューで扱っていますので、興味のある方は読んでみてください。
傾聴とマイクロ技法
信頼関係を維持する手法がアサーションですが。
その前に信頼関係を築かなければ、コミュニケーションは始まりません。
信頼関係を築くために必要なスキルは、相手の話を良く聴くことです。
私達は、自分の話をちゃんと聞いてくれる人に好意を抱くのではないでしょうか?
それを実践できるスキルが「傾聴」です。
傾聴は、自分の考えを一旦置いておき、相手の感じていることをそのまま受け取る聴く姿勢です。
管理監督者は「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中で、「日常的に労働者からの自発的な相談に対応するように務める必要がある」としています。
対応することで、その内容を正確に把握し、解決に必要な資材・人財の有効活用につなげ、解決につなげることができます。
この「正確に把握」するためには、相手の状況や感じていることを受け取らなければなりません。
聞き手である管理監督者からすれば問題のない出来事や状況も、相談した部下にとっては大きな問題なのです。
しかも、問題として抱えているということは、それを相談するまで悩み苦み。
どうにもならなくなっていることが現れたとも言えます。
話しにくいことを話しているのに、受け止めてもらえない、理解しようとしてもらえないと感じさせてしまえば、信頼関係を築くことはできません。
逆に、受け止めてもらえる、理解してもらえるということを実感できれば、信頼を置いてもらうことができ積極的に話してくれるようになり。
より詳細に問題を把握することができ、それが職場環境の改善へとつながり。
相談してきた部下だけでなく、職場全体の問題解決につながります。
このような効果もあるので、傾聴はぜひ身につけたいものです。
傾聴を実践する際に活用したいのが、カウンセリングにおけるコミュニケーションに関する諸原理や諸技法を検討し抽出した「マイクロ技法」です。
マイクロ技法に上げられている、
・関わり行動(視線の位置、言語追跡、身体言語、声の質)
・質問技法(開かれた質問、閉ざされた質問)
・クライエント観察技法
・はげまし、言い換え、要約
・感情の反映
は信頼関係を作るために不可欠なものとされています。
部下自身と部下が話してくれたことに関心があることを示す事ができる方法です。
つまり、部下の話を聴くには、まずは部下に対して興心を持ち大切に思う気持ちを持つことがスタートです。
部下に気をかけ、声掛けを行い。
話されることを傾聴することが、コミュニケーションの土台を築くことになります。
ジョハリの窓
自己を捉える方法として「ジョハリの窓」というものがありますが。
情報を軸に、上司と部下の関係性を把握する方法として見ることができます。
横軸に「自分が知っている」「自分が知らない」、縦軸に「他人が知っている」「他人が知らない」をとった4面のマトリクスで分類します。
「自分が知っている」と「他人が知っている」の両者がしっている領域を「開放領域」といいます。
「自分が知らない」けど「他人が知っている」は「盲点領域」。
「自分が知っている」けど「他人が知らない」は「隠蔽領域」。
「自分が知らない」し「他人も知らない」は「未知領域」。
このように分けます。
すべてをお互いが知っていて、気軽に指摘し会える「開放領域」での関係性が望ましいといえますが。
現実的にはなかなかできることではないでしょう。
ほとんどの情報は「盲点領域」か「隠蔽領域」に入るかもしれません。
「盲点領域」は、部下のことを良く観察しないと気づくことができないかもしれません。
コミュニケーションにより「開放領域」へ移行し得るのは「隠蔽領域」です。
何らかの理由で上司には伝えづらく感じている情報がこの領域に入るため、信頼関係を築き自己開示を促すことができるでしょう。
自己開示を促すことにおいて覚えて起きたいのは「返報性の法則」です。
人は他社から受けた好意や行動に行動に対して、同じものを返さなければならないという心理が働くという法則です。
自分が接して欲しいように相手に接するということは、この法則に当てはまります。
上司からコミュニケーションをとり、自己開示を行うことで。
部下に自己開示を促すことになり、より部下の事を把握する助けとなります。
これについては、「人望が集まる人の考え方」という本が参考になるかもしれません。
2つのコミュニケーション
ここまではコミュニケーションの効果について書いて来ましたが。
コミュニケーションは機能の側面もあります。
日常的に行われるコミュニケーションのほとんどは、「道具的コミュニケーション」です。
道具的コミュニケーションは、効率性が重視される情報伝達の機能をもつものです。
「何かをして欲しい」という気持ちの元で行い、仕事であれば指示・報告・連絡・相談といった情報伝達で使われます。
日常生活においても、「醤油を取って欲しい」といった形で利用しています。
このように、何かしらの効果を期待するコミュニケーションですが、期待せず話すこと自体で満足できるコミュニケーションもあります。
それが「自己充足的コミュニケーション」です。
雑談や趣味の話、ランチしながらのリラックスした会話は、何かしらの効果を期待して行うのではなく。
共に過ごす人と話すことを目的としているでしょう。
どちらかというと、コミュニケーションという言葉のイメージはこちらだと思いますが。
人間関係の維持・構築・向上・緊張解消という、対人関係を調整する事ができ。
信頼感と心理的安全性の土台を築くコミュニケーションです。
仕事の関係となると、上司も部下もお互いに業務を抱えているため道具的コミュニケーションが増えてしまうかもしれませんが。
意図的に自己充足的コミュニケーションの時間を作り、接することで部下の本音を引き出しやすい関係を築くことができるでしょう。
言語的コミュニケーション
コミュニケーションの基本で「媒体」を選ぶと書きましたが。
その媒体は言語を何で表すかという違いでしかありません。
対面の会話だけでなく、電話やメール、手紙など文字も言語的コミュニケーションです。
言葉は受け手によって様々な意味を持つため、送り手の伝えたいことが伝わらなければ誤解を生みトラブルが発生していまいます。
特に対面でないと、自分の外面的な部分に対する意識(公的自己意識)よりも、内面的な意識(私的自己意識)が強くなるため。
自分の正確や感情に正直に行動しやすくなるため、トラブルになりやすい上に、相手を正確に把握できないものになる可能性があります。
自分がどう見られるか?を意識する必要がなければ、自分が考えていることや主張に意識を割く割合が増えるのは当然でしょう。
その結果、攻撃的な気持ちになったり、被害的な気持ちになりやすくもなります。
道具的なコミュニケーションは、テキストを元に行うことも多いので要注意ですね。
しかし対面となると、話す言葉などの言語情報の重要性が少し下がり。
顔の表情などの視覚情報や声のトーンなどの聴覚情報を元に、言語情報を受取るようになります。
言語以外でのコミュニケーションを、「非言語的コミュニケーション」といい。
・動作行動:表情やジェスチャーなど
・接触行動:なでる、叩くなど
・身体特徴:体格、匂いなど身体的特徴
・準言語:話し方、声の質
・空間行動:相手との空間での位置関係
・人工物:服装や装飾品
・環境要因:建物やインテリア、環境音など
という要素があります。
これらの要素と話すことが一致していると、安心感や親近感につながり。
言語でのメッセージがより伝わりやすくなるでしょう。
言葉だけではなく、伝え方や伝える場所も大切です。
コミュニケーションはストレス予防になる
途中書いた通り、コミュニケーションを取ることで、ストレスの早期発見や予防につながるだけでなく。
ストレス要因に気付き除去することができると共に、ストレス要因を生まない環境作りにもつながります。
しかし、コミュニケーションによる信頼関係の構築は、一朝一夕で達成できるものではありません。
日々の積み重ねにより築くことができ、関係性や職場環境の改善はそれからです。
ここに書いた一つ一つを実践したり取り入れ、継続することが職場全体の健康と生産性向上につながります。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
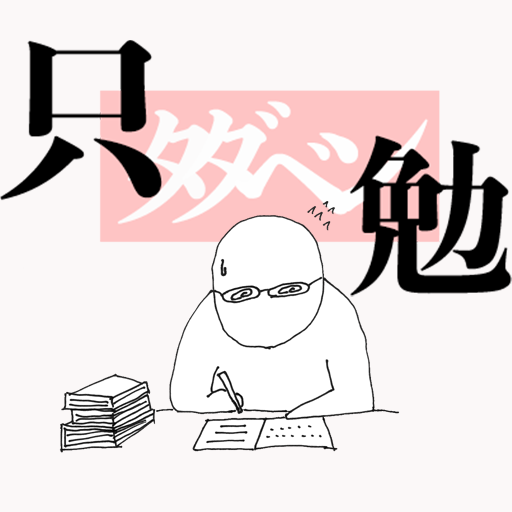
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!


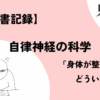
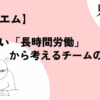
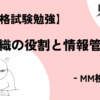
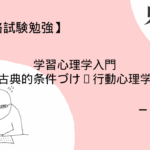

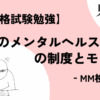
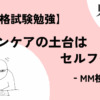

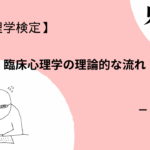
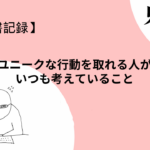
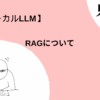
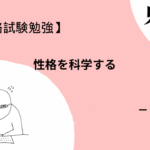
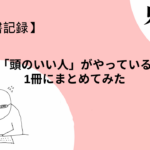
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません