組織の役割と情報管理|メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)
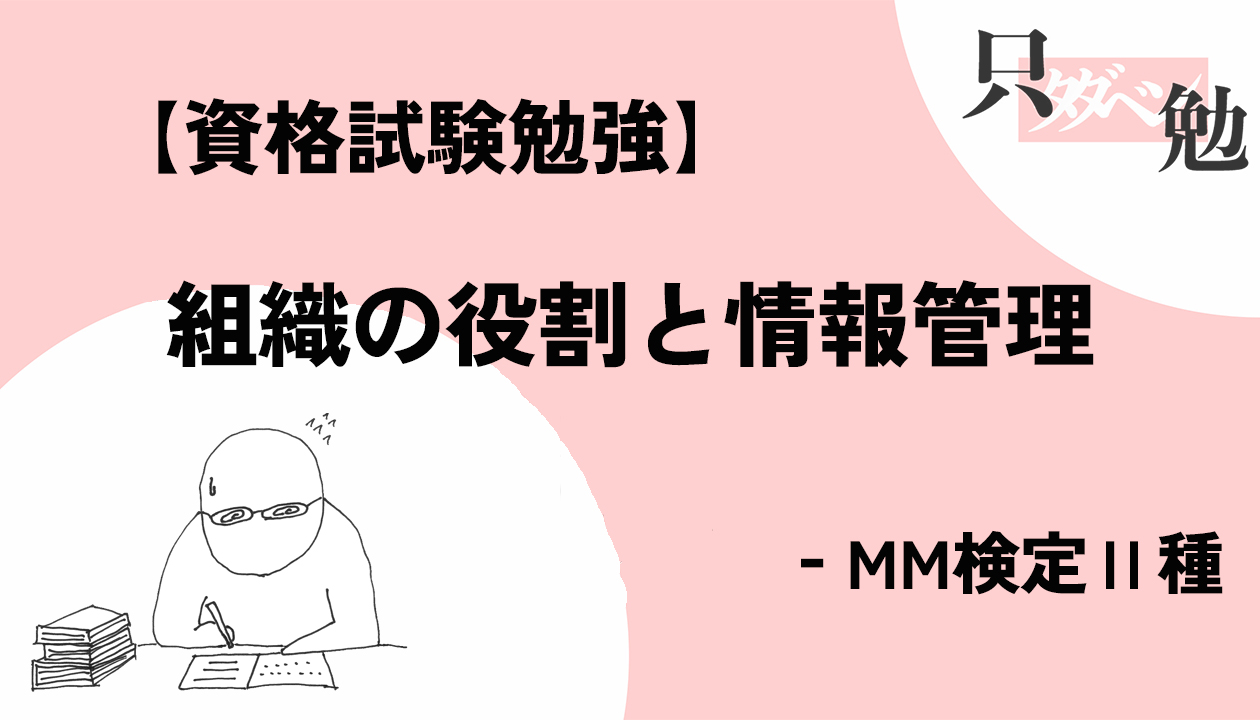
メンタルヘルス対策において、管理監督者は部下の状態を観察することが大切です。
しかし、管理監督者だけで対応したり、最終的に部下任せになるようでは対策になりません。
これまでのメンタルヘルスケア・マネジメント検定試験Ⅱ種の記事でも書いてきましたが。
生産性の低下や負荷の増大など、組織においても経営課題として捉えるべき問題でもあります。
もちろん、メンタルヘルス不調になり苦しい思いをするのは本人ですが。
メンタルヘルス対策を推進する立場である管理監督者は、個人のケアに気を配るとともに、職場全体の環境管理にも対策を施します。
この記事では、管理上の役割や情報管理について触れていきます。
管理監督者の基本的役割
厚生労働省が提示している「労働者の心の健康の保持増進のための指針」において。
・職場環境等の改善
・個々の労働者に対する相談対応
この両面から、ラインによるケアを推進することが求められています。
日頃から部下を観察し、業務遂行状況や遅刻・欠勤といった行動面の変化に注意を払うとともに。
その変化の原因となり得る、チームの業務量や人間関係など職場環境の把握にも務めます。
とはいえ、ストレスの受け止め方や考え方とそれによる健康問題は、個人差が大きいものです。
部下の状態を把握しつつ、部下の話を積極的に耳を傾け、個々の特徴や健康状況の把握に務めることも大切です。
それにより、部下が抱える仕事上の悩みや不安を理解し、適切なサポートを行うことにつながります。
その時に大切な姿勢が、相手を否定せずに受け止めつつ状況を理解する、傾聴です。
管理監督者は以上のように早期発見・早期対処に務めますが、自分だけで対処するには限界があります。
事業場内外の産業保健スタッフに対応を相談したり、メンタルヘルス不調を抱える部下へ専門家への相談や受信を促すのも大切な役割です。
以上がラインケアにおいて、管理監督者が果たせる役割を簡単にまとめたものです。
この役割を果たすために知っておくべきことが以下の通りです。
◯職場環境
・物理的な職場環境(作業環境、作業方法等)
・職場環境を広く捉えた労働時間
・仕事の量と質
・職場の人間関係
・職場の組織および人事労務管理体制
・職場の文化や風土
◯求められる知識
・人事労務
・組織論
・ストレスマネジメント
・リーダーシップによる人間関係調整能力
◯求められる姿勢
・権限のある日とや組織から助言、協力を求める姿勢
・積極的傾聴
・教育研修を積極的に受ける
労働者個人の状況だけでなく、組織の制度や方針なども理解しておくことが、ラインケアによるメンタルヘルス対策に必要です。
これらすべてを一度で解決するのは難しいですし、社会の状況も変化していき組織のあり方も変わっていきます。
継続的にこれらの対策を行っていくことが、ラインケアの基本なのです。
部下の状況を把握する視点
部下の状況を把握するの助けとなる視点を、WHO(世界保健機関)が提示しています。
健康問題に起因したパフォーマンスの損失を表す、アブセンティーズムとプレゼンティーズムという視点です。
◯アブセンティーズム
健康問題によって仕事を欠勤している状態。
欠勤・休職・遅刻などで職場に不在となり、勤怠管理上にも現れる把握しやすい視点です。
◯プレゼンティーズム
欠勤には至らないが、健康問題が理由で業務遂行能力・生産性が低下している状態。
出勤しているので勤怠管理上に現れない上に、アレルギーや片頭痛、生活習慣などでも低下するため、普段の観察が重要です。
問題となるのがプレゼンティーズムの視点です。
調査によると、プレゼンティーズムによる生産性の低下によるコストは、医療費によるコストを上回っているとのことです。
この健康関連コストへの対策として、健康経営が提唱されているのです。
プレゼンティーズムは放置すると、アブセンティーズムへと移行し。
実質的に他の労働者への負担も増えることになり、健康問題リスクを抱え続ける悪循環にもつながってしまいます。
なので、管理監督者もこの視点を活かし、取り組んで行きましょう。
プライバシーの配慮
企業はメンタルヘルス対策だけではなく、健康診断など健康増進の施策を実施します。
そのようにして発生する従業員の健康情報は、個人情報保護法において機微な個人情報に当たるとされ。
要配慮個人情報という、厳格に保護するべきものです。
個人情報の取扱いは信頼関係に直結しますし、間違うと法的問題に発生するものでもあり、慎重に行うべきものです。
特にメンタルヘルスに関する情報は、客観的にはわかりにくく、誤解や偏見が起こりやすものでもあります。
そのため、プライバシーを保護することが企業に求められるとともに、取扱いにおいても従業員本人の意志を尊重することが必要です。
原則である、必要最小限の情報を本人の同意を得て収集することはもちろん、適切な個人情報保護体制を整備し運用していきます。
法令・指針を遵守した体制を構築し、自主的に高いレベルの個人情報マネジメント・システムを確立・運用している証として、一般財団法人日本情報経済社会推進協会が認定するプライバシーマーク制度も利用できます。
そのような体制を構築することで、従業員が安心してメンタルヘルスケアに取り組めるとともに。
産業保健スタッフなどへの相談もスムーズになり、心の健康問題の早期発見にもつながります。
このプライバシー保護に係るのは、事業主と管理監督者、事業場内産業保健スタッフ等です。
◯事業場内産業保健スタッフ等
・産業医等
・衛生管理者等
・保健師等
・人事労務管理スタッフ等
・心の健康づくり専門スタッフ等
・同僚労働者
同僚労働者は、職場内で何かしらの対策を講じる場合、協力や理解が必要ですし。
管理監督者が部下の状態を把握するうえで、同僚の変化として情報を得る協力者でもあります。
つまり、プライバシーの保護は企業で働く全従業員が守るべきルールでもあるのです。
もちろん、個人情報を収集できる範囲は限定的なものなので、関係者が知る範囲も取り扱う範囲により徹底して限定されます。
守秘義務
プライバシーの配慮は、機微な健康情報をどのように扱うべきかですが。
知り得た健康情報を、他に漏らしてはならないという法律によって規定されている原則が守秘義務です。
プライバシーの配慮で上げた個人情報を知り得る関係者に対し。
医師は刑法、保健師や看護師は保健師助産師看護師法、健康診断の事務担当者は労働安全衛生法でそれぞれ罰則規定が規定されています。
これ以外は、民法により損害賠償責任を追求される可能性があります。
厚生労働省は「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのための事業者が講ずべき措置に関する指示」において。
①労働者が不利益な取扱いを受けるという不安を抱くことなく、安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにすること。
②事業者が必要な情報を収録して労働者の健康確保措置を十全に行えるようにすること。
と定めていて、従業員の健康を確保するために、事業者が健康情報を取得することを認めています。
そのため、事業者は守秘義務を厳守するために、衛生委員会などで協議し、「事業者における健康情報等の取扱規定を策定するための手引」を参照しながら、健康情報等に関する取扱規定を策定し。
健康情報を取り扱うものや、その権限・範囲を定めます。
取扱規定の中で、法令上守秘義務を課されていない関係者に守秘義務を課すことを規定することが望ましいともされています。
そのように企業における個人情報の取扱い者を規定し、掲示なイントラなどを利用し広く周知するものとします。
このようにして、従業員の健康情報を保護し適正に取り扱うわけですが。
事業活動を行う上で、顧客や同僚の安全と健康の確保も同時に求められます。
企業は従業員の健康情報の保護が求められると共に、従業員や顧客の安全配慮義務も追っているのです。
人命は何よりも尊いものとされているので、それが侵されるような状態は許されません。
そのため、安全配慮義務と健康情報のバランスを取ることも、企業には求められます。
抵触する場合には、本人に説明したうえで健康情報の保護と、他者の安全配慮義務のバランスの取れる対応に協力してもらえるようにします。
協力が得られない場合、事業者自身でこのバランスを考慮し、必要最小限の情報を、必要最小限の関係者に提供し対応を決定します。
このような厳格な管理の一環として、健康情報は事業場内にいる医療職が一元管理し、必要に応じた加工をしたうえで提供することが望ましいとされています。
医療職であれば正しい知識を持っているので、偏見や誤解が生じにくいですし。
刑法で守秘義務が課されているので、安全な管理を実現しやすいからです。
また、他の業務にも言えることではありますが、事業者は情報漏えいの防止にも対策が必要です。
物理的・技術的・人的・組織的に対策するため、教育や研修の機会を設け。
メールのご送信の防止やファイルの共有方法、使用する通信回線の安全性に係る情報などを共有します。
こちらも、円滑な産業保健活動とのバランスを考える必要がある要素です。
徹底して守秘義務を守ることによって、事業場内の環境改善につながるとともに、事業場外においても信用性につながることになるのです。
持続的に取り組むために
冒頭でも書きましたが、メンタルヘルスケアに係る対策は組織全体として持続的に取り組まなければなりません。
社会や技術の変化に合わせた適切な対応も必要です。
国では健康優良銘柄の選定、世界基準の労働安全衛生マネジメントシステムの策定など、従業員の健康に投資する、健康経営の取り組みを助ける制度が用意されています。
このようなものを利用して企業での取り組み方を決めるのもそうですが、現場でラインケアを実践する管理監督者に対し、適切な情報提供や組織の制度を伝えるために、研修を行うことも重要です。
管理監督者自身に求められる対応も増えるため、教育の機会や知識の提供の機会を用意することは重要な企業としての取り組みです。
メンタルヘルス対策においても、経営者層が方向性を決定し。
管理者層は、経営者層が示した方向性を監督者層に伝え実行してもらうとともに、実行する現場の意見の経営者層に伝え、反映させます。
監督者層は上層部の示した方向性を現場で実行するといった、マネジメントの流れは有効です。
さらに、マネジメントのあらゆる場所で利用されるPDCAサイクルを利用することで、持続的な改善を行うこともできます。
労働安全マネジメントシステムはPDCAサイクルを規格化したものなので、メンタルヘルス対策の体制をつくる時に参考にしましょう。
ラインケアの役割を担う管理監督者は、経営者層と現場をつなぐ役割とも言えます。
メンタルヘルス対策における会社の方針を従業員に伝えるとともに。
教育研修や相談窓口、産業保健スタッフとの連携といった、組織の仕組みを機能させるとともに。
現場の状況から職場改善につながる状況について、経営者層に伝えマネジメントに反映できるように協力します。
これらを継続的に実施することで、職場環境の改善を実現し、メンタルヘルス対策が実現されていきます。
従業員の健康への投資
事業者や管理監督者がラインケアで行う取り組みについてまとめました。
全ては、従業員の健康への投資です。
策定した健康問題の対策を、どのように行うとともに安心して利用してもらうか。
そして、継続的に改善していくか。
時間がかかることでもありますが、取り組むことで高い生産性を維持し、魅力的な組織風土を築くことにつながります。
管理監督者に求められることが多いため、事業主が行う管理監督者へのメンタルヘルス対策を忘れてはなりません。
このように、事業主と管理監督者が協力し合うことで、円滑なメンタルヘルス対策を実施できます。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
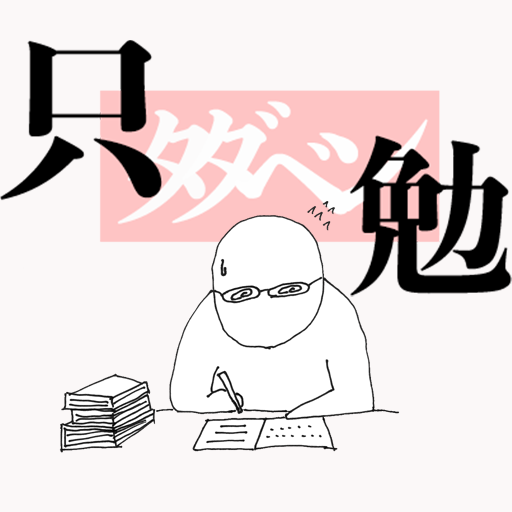
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!

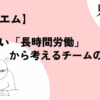
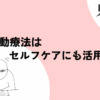
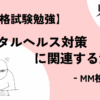

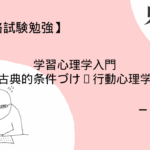
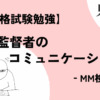
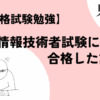

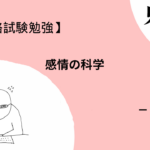
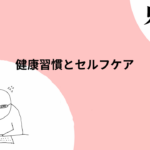
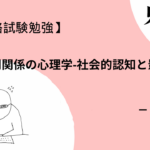


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません