認知行動療法はセルフケアやチームケアにも活用したい!
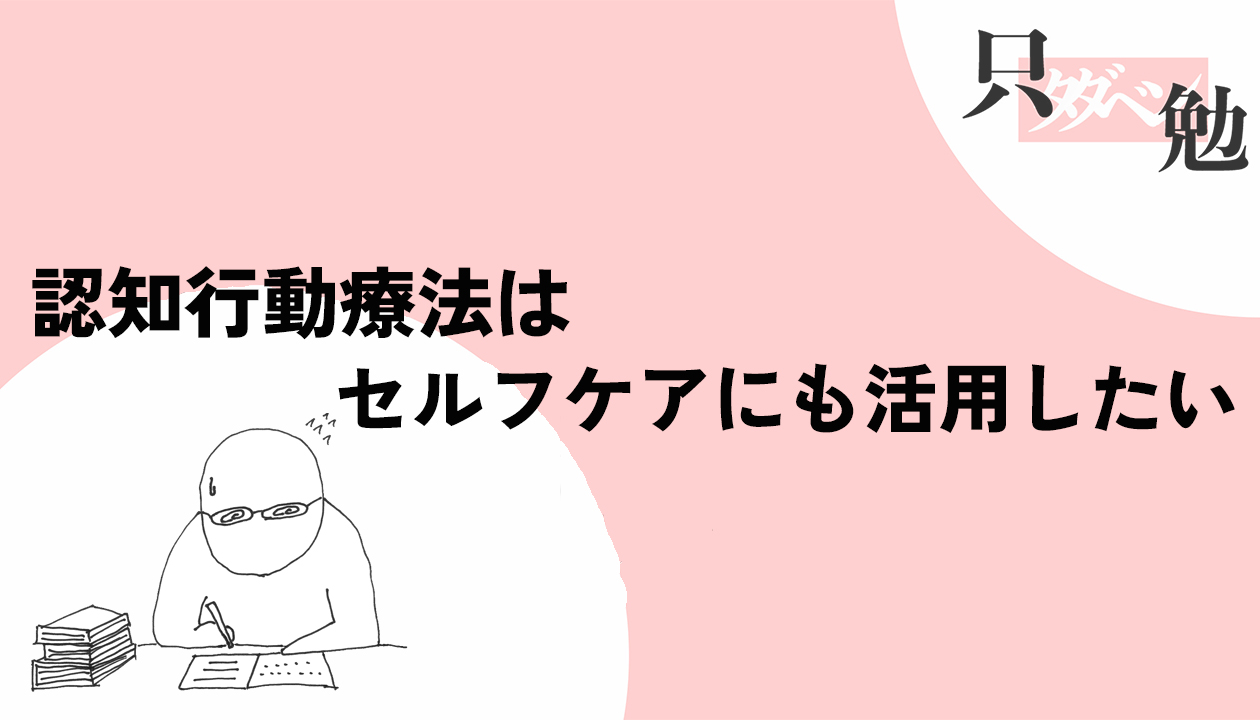
※この投稿はプロモーションを含みます。
個人的な範囲ですが。
今年の夏に心理的安全性と同じくらい耳や目にした言葉が、認知行動療法です。
効果が高い心理療法で、世界的に効果の高い療法として採用されていますが。
コーチングやチームビルディングにおいても導入されている考え方で、職場環境作りや自己啓発にも活用できるものです。
これも、認知行動療法が特定の療法を表すのではなく総称だからかもしれませんね。
しかし考え方を知ることで。
職場で働く人の、AIなど新しい技術の導入に関する抵抗感を軽減したり。
パフォーマンス低下のサインを感じ取り、その解決法を考える助けにもなります。
そんな認知行動療法について、簡単にまとめて行きます。
認知行動療法とは?
今回の記事を書くにあたり、少し疑問に思ったのが。
注目されている様々な領域に適用されているにもかかわらず、認知行動療法という言葉があまり広まらなかったのはなぜか?ということです。
正直、まとめながら普段私自身が取り組んでいることや、心がけてきたことが心理学的に解説されている印象を受け。
それが、先ほどかいたようなチームビルディングやコーチング、心理的安全性や自己啓発といった言葉に変わっているのかと。
経験に基づくコトで表していくと、論理的な思考をする療法でもある分、同じような提案に落ち着くのかもしれませんね。
もしかしたら、「心理療法の一つ」というのに抵抗感があるのかなぁとか。
記事に関係ないことも考えてしまいました。
ただ、それだけ色々な自己啓発や考え方の技術の根底に活用されている考え方でもあります。
さて。
認知行動療法は英語で「Cognitive Behavioral Therapy」と呼ばれるので、頭文字を取って「CBT」とも呼ばれます。
Cognitionが認知で、Behaviorが行動で、療法なのでTherapyです。
療法の説明としては、認知と行動の両面から働きかけることでセルフコントロール力を高め。
ストレスや抑うつ、不安といった症状や問題の改善を促す心理療法の技法の総称です。
なので、認知療法と行動療法の手法を活用するものですが。
論理情動行動療法の基礎理論であるABC理論について触れておきます。
この理論は、人間の悩みとなる感情や行動を、「結果」として生じるものとし、「C」とします。
その感情や行動が起こる発端は「出来事」にあり、これを「A」とし。
「出来事」をどう受け止めるかというその人の「受け止め方」を「B」として。
AをBとして受け止めるから、Cとなる。という理論です。
最近の自己啓発系の内容にも通じますが、A・B・Cの中で自分自身で選ぶことができるのはBとCです。
認知行動療法は、この自分自身で選べる=変えられることに焦点をあて。
どのような受け止め方ができるか、どのような行動をとればよくなるか。
心がけたり、行動に移しやすいものに気づくことができる療法なので、効果が高い療法とされています。
ビジネスのように言うと、出来事と受け止め方による結果について、PDCAサイクルを回すようなイメージですかね。
これが認知行動療法の考え方になりますが、基本モデルを知ることでより扱いやすくなります。
認知行動療法の基本モデル
認知行動療法では、人間の悩みが起こる過程を、
・その人が置かれている環境や状況といった出来事
から考えます。これを環境要因といいます。
そこから、
・その出来事をどのように受け止めたか➾認知(思考)
・どのような感情が起こったか➾気分・感情(情動)
・どのような行動をしたか➾行動
・どのような生理反応が起きたか➾身体反応
というものを調べて行きます。これを個人的要因といいます。
出来事はもちろん、自然に湧いてくる気分や感情、冷や汗をかくなどの身体反応をコントロールすることは難しいです。
しかし、受け止め方である認知や、感情の反応である行動を変える、自分で選択することはできます。
この環境要因と個人的要因の相互作用に注目することで、悩みに対する実践的な対処を考える。
どのような受け止め方をするか、どのような対処行動を取るか、を選ぶことができるのです。
特に、受け止め方の部分で言うと、個人的要因の悪循環に陥る「認知のゆがみ」があります。
この「認知のゆがみ」を修正し、行動パターンを変えることが、悩みに対する実践的な対処です。
つまり、感情は思考と行動の結果と捉え、感情をコントロールするのではなく、感情を生み出す思考に気づくことが大切です。
まずは、自分の認知や考え方の「クセ」を知るようしましょう。
心の使い方をメンテナンスする
なので、自分の認知や考え方の「クセ」を知る事ができるワークを利用します。
実際に書き出すことで、自分の「クセ」を客観的に評価できます。
・思考記録表
感情が起こった時の状態、考えたこと、そのように考えた理由、といったものを書き出します。
その考えた理由に対して反論を考え、別の考え方や見方を見出します。
感情が起こった時と、別の見方をした時の気分を%で表し、どのような変化が起こったかを数値で把握します。
・不安階層表
感情が動いた出来事をカードなどの紙に書き出し、どの程度不安かを%などで数値化します。
この数値が不安の程度を表すので、数値の小さい(比較的克服しやすい)ものから、考え方を変える方法や対処法を考えていきます。
このように、段階的に自分の悩みの種と向き合う方法です。
・活動記録表
自分の生活習慣を振り返り、悩みの解決となる行動課題を発見する方法です。
一日の活動時間(起きている時間)を2~3時間に大まかに分け、仕事や食事などの活動を記録します。
そうすることで、見直すべき習慣や取り組める課題を見つけ出すことができます。
こういったワークをする時の注意は、無意識で行っている自分の考えや判断を知ることになるので。
続けるのが苦痛になる場合もあります。
その時は中断し、時間をおいて取り組むようにしましょう。
これを元に自分の考え方や行動の内容を選ぶ訓練となり、同じような出来事が起きても結果を変えられるようになります。
また、出来事によっては緊張や不安を伴う場合もあります。
そのようなときには、リラクセーション法の実行も有効です。
・呼吸法
・斬新的筋弛緩法
・自律訓練法
といったもので、肉体の緊張や不安を軽減し冷静さを取り戻すことができます。
簡単なやり方は、「ラインケアの土台はセルフケア」という記事で書いたので、よろしければ御覧ください。
また、緊張や不安は将来や過去の出来事により起こります。
そういった場合には、マインドフルネスを実践し、「今、ここ」に注意を集中するのも有効です。
認知行動療法は、ワークなどで自分の考え方を客観的に観察し、それに対して別の考え方や行動を選べるように訓練する方法です。
これらを習得することで、出来事や自分に起きた感情の捉えかたを選べるようになり、どのような行動を取るかも選べるようになります。
リラクセーション法などは、出来事に対して行動を起こすことで、自分の認知を見つめ直す方法とも言えます。
チームマネジメントに活かす
チームビルディングやコーチングに活かす事ができると冒頭に書きましたが。
そのような方法を知りたいのは、職場でリーダーの立場にいる管理監督者の方だと思います。
心理的安全性についてまとめた記事でもふれましたが、組織やチームでの心理的安全性に対するリーダーの影響は大きいですし。
リーダーシップのスタイルが与える生産性への影響はかなり大きいものです。
リーダーの立場にいると、どうしても部下を評価する視点となり、結果にフォーカスして判断しがちかもしれません。
それがリーダーにとっての「認知のゆがみ」といえます。
成績など結果を求められる立場でもあるので、ある程度はしょうがないですし。
心理的安全性に基づいても、相応の仕事の難しさは必要です。
しかし、ただ結果に基づいて、できていない=やる気がない、といった判断をしてしまうと。
チームとしての学びにならず、次に繋げることができません。
さらに、その判断をされた部下のパフォーマンスをさらに悪くする可能性もあります。
なので、認知行動療法のモデルを活用し、まずはリーダー自身の考えや行動を客観視し、チームの成果をつながる行動を選べるようにします。
「できていない」ことに対して、なぜできていないのかを知りたいでしょうか?
どうすれば「できた」かを知り、メンバーにフォローをお願いできるでしょうか?
実際に部下へヒアリングを行う場合も、客観的な問いかけを行うことで部下が自分自身を理解することにつながりますし。
さらに、「自分のことをリーダーが理解してくれようとしている」といった、受け入れてもらえる安心感にもつながるでしょう。
そうすれば部下からの信頼を得ると共に。
より緊密なコミュニケーションをとれるようになるかもしれません。
一人ひとりの部下とそのような関係性を作れれば、働きやすく生産性の高いチームとなると思いませんか?
小さいとしてもチームのリーダーの行動は、企業の組織風土を作る元となり、文化となります。
なので、リーダー自身が認知行動療法のモデルを知り、実践することに大きな意味があるのです。
人間の思考と関係を扱う力を高める
内容を知ると、「あれ?これ普段から形は違うけど、意識してるなぁ」ということがあるかもしれないのが認知行動療法です。
心理学を学ばなくても、心理学的に考え、人生に適応されている療法とも言えるかもしれません。
最近、生成AIがどのように使われているかを目にするたびに、悩みのタネとなる対人関係の緩衝材としての利用が増えているようにも感じます。
それで健康に日々を送れるなら良いかもしれません。
しかし、逆に私達人間自身にも、「人の心を扱う力」を養わなければ、信頼を得にくい時代になっているのかもしれませんね。
AIは人間の脳の研究で、心理学はその脳から生じる心についての学問です。
自分の心を客観視し、より良い関係を築くために次の判断を変える一歩として、心理学を利用できるでしょう。
認知行動療法に基づいて作成された、アウェアファイ
自己啓発系の話でよくされることではありますが。
相手が変化するのを待つより、自分が変化する方が効果があります。
自分の人生をより良くするために行動を選んでいきましょう。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
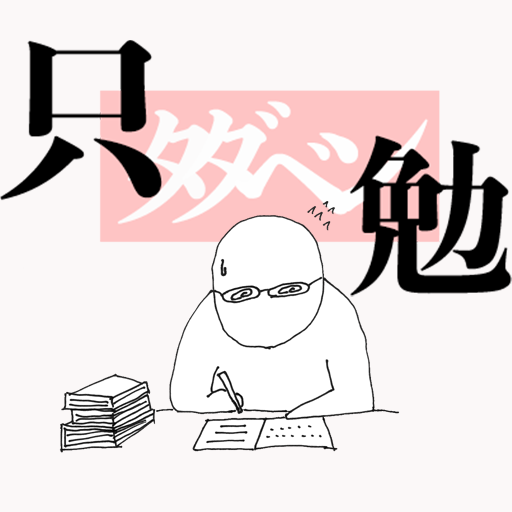
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!
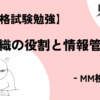
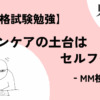
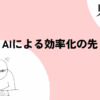
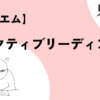
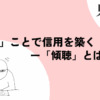
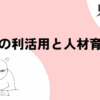
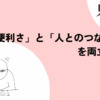

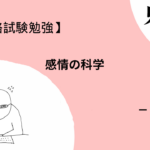
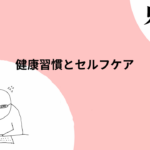
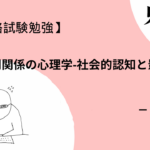


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません