ラインケアの土台はセルフケア|メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)
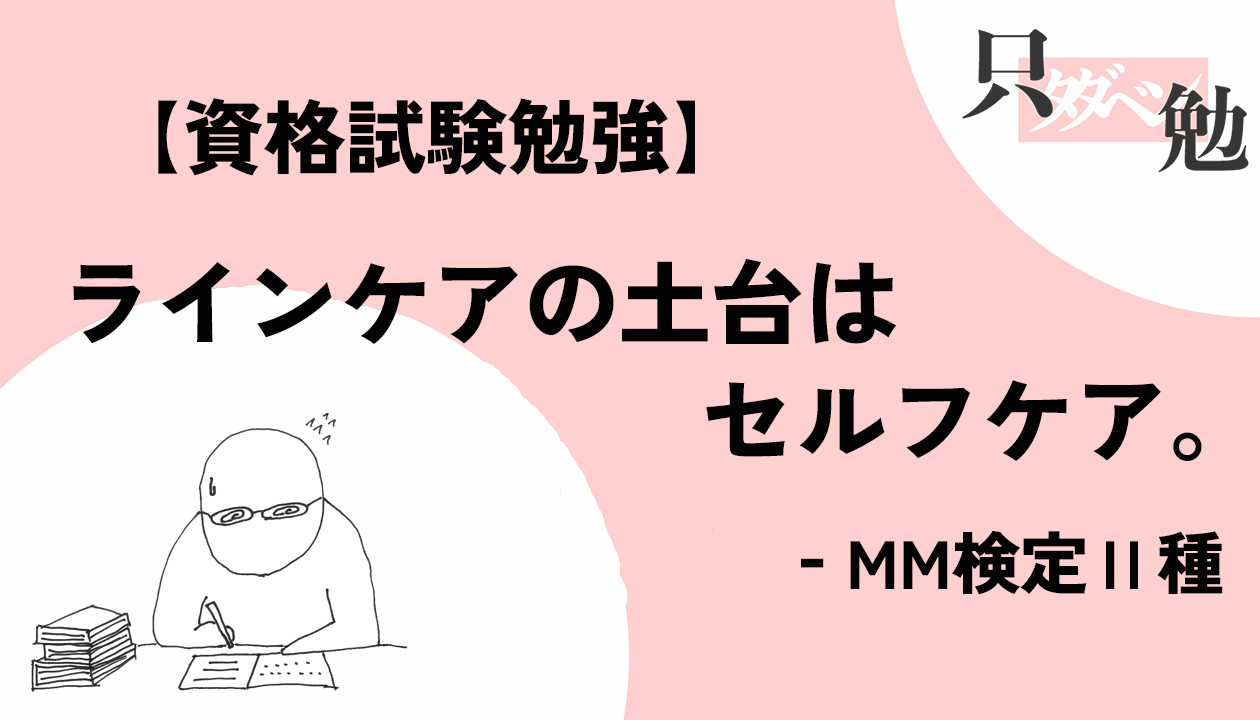
メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)の内容について、まとめているシリーズです。
前回の「ストレスと職場環境」の最後で、ラインケアを行う立場にある管理監督者のストレスについて触れました。
そういった立場にあるため、自身の健康状態にも注意を払わなければなりません。
メンタルヘルスケアの基本は、セルフケアです。
部下の状態を理解し、予防のために適切なアドバスや対応を行うためにも必要な知識です。
日常生活での取り組み
私達の身体を作るのは日常での生活です。
ストレスに立ち向かう大本を作るのは日常生活なのです。
健康習慣
メンタルヘルス不調により、身体に何らかの不調が起きたり、悪化することと。
ストレス要因に明らかな対応が認められる関係を、心身相関といいます。
このストレス要因は、業務に関連したストレスが重要な位置を占めるとされています。
そのため、ストレス要因に対処するために、日常から身体の健康に期を配ることで。
メンタルヘルス不調を防ぐ助けになります。
休養を取る
休養はただ単に休むことではありません。
「休む」ことは、心身の疲労を取り、エネルギーを充電することです。
「養う」ことは、趣味や楽しみなどを通じて、豊かで余裕のある心持ちにすることです。
つまり、身体の疲れを取りつつ、自分の楽しみに触れ心にも栄養を与えることが、休養です。
十分取れていないと、仕事の効率や質を低下させることにもつながります。
読書について、一日のうち数分でも本を読む時間を取らないと、調子が悪くなるという話を聞いたこともあります。
ただ休むだけではなく、楽しみながら身体を休める習慣を持ちたいものです。
睡眠
疲労回復に一番効果があるのは睡眠で、脳を休めることにもつながります。
不足すると、疲労感が残るだけでなく。
作業効率の低下や行動・判断のミスが起きたり、情緒不安定になります。
労働災害や交通事故の背景に睡眠不足があることも多いとのことです。
私自身、ブログを書いたりと勤務時間以外に作業することも多いため、日によって睡眠時間がバラバラとなってしまってますが。
6時間以上取れたときと取れなかったときで、パフォーマンスが明らかに違うことを体感しております。
修正しないとですね。
ただ、睡眠時間よりも質の方が重要ともされていて、以下のポイントがあげられています。
光
これは日光という意味合いですが、眠気ホルモンのメラトニンは朝の光を浴びてから、14〜16時間後に生成されるそうです。
規則正しい起床時間を心がけることで、睡眠時間も維持しやすくなります。
体温
人間は眠りに入る過程で体温が1度低下することで、質の高い深い眠りになるとのことです。
入浴習慣などにより、体温を高めに保つことも。
良い眠りのポイントとなります。
自律神経系
夜は副交感神経や優位となります。
睡眠時だけでなく、その前から明るすぎない静かな環境で過ごすことも、眠る準備として有効です。
寝室環境
明るすぎず、暑ずぎす、うるさくない、暗めの環境を保つようにしましょう。
他にも、リラックスできるようにアロマテラピーの利用や、音楽を流すといった工夫も有効です。
運動
運動をすることで、エンドルフィンなどの脳内伝達物質が分泌され、メンタルヘルス不調の症状が改善されます。
それだけでなく、身体の健康維持や生活習慣病の改善といった身体への効果もあり、心身相関の観点からも重要な行動といえます。
また定期的な運動習慣は熟睡を促進するとも報告されているので。
階段を使ったり、歩くようにするなど、日常習慣の中で身体を動かすように心がけたり。
散歩などの軽い運動を習慣にすることも効果が見込めます。
食事
身体を作るのに大切な要素が食事です。
偏った食事や食事を抜くことが、集中力や気分の波に悪い影響を与えます。
これも私自身経験がありますが。
一時期、運動をあまりしないこともあり、昼食を食べずにいることがありました。
あまり問題ないかと思いそうしたんですが。
明らかに仕事に集中できる時間が減り、無駄な時間を過ごすことが多かった記憶があります。
そんな時に、たまに昼食を取ると集中力が増し、内心驚いていました。
睡眠不足と昼食を抜くことが重なったときは・・・端から見ると最悪だったんだろうなと思います。
また、食事で取れる栄養素はホルモン分泌にも必要なため、心の健康にも影響を及ぼします。
ホルモンの分泌によりタンパク質の代謝が亢進するため、肉類や魚類をとって補いましょう。
また、高ストレスホルモンであるアドレナリンやコルチゾールの生成には、ビタミンCやBが必要です。
ビタミンCが含まれる野菜や果物、ビタミンBが含まれる豚肉・乳製品・レバー納豆といった食物を摂取するようにしましょう。
精神の安定に効果がある栄養素は、マグネシウムやカルシウムです。
カルシウムは小魚や海藻類、乳製品。マグネシウムはナッツ類や大豆などで摂取できます。
ストレス化では食欲が低下し、摂取が難しくなる場合もあるので、普段以上に栄養に気を使うことも大切です。
メタボ対策
ストレス化では食欲が低下・・・と書いたばかりですが、逆に過食の症状が出てしまう場合もあります。
また、現代は生活習慣が乱れやすく、偏食や十分な休養が取れないなどで、メタボリック・シンドローム該当者や予備軍になってしまうかもしれません。
メタボは生活習慣病に罹患する可能性を高め、脳・心臓疾患という重篤な症状に発展してしまう可能性を高めます。
内臓脂肪の蓄積によって病態が進行することになるため、基本的な予防策は健康的な生活習慣を維持することで、肥満を予防・改善することにあります。
これまでに書いてきた健康的な生活習慣作りに取り組むことが必要ですが。
健康診断の結果をバロメーターとして活用したり、保健指導による生活改善や情報提供を活用しましょう。
特に特定健診や特定保健指導は、メタボ視点で実施されるものとなり、脳・心臓循環器疾患の予防にもつながるので。
用意されている制度を有効活用しましょう。
ストレスへの対処力を高める
どんなに身体の健康に気を使ったとしても、ストレスは外部からの刺激として発生します。
そのため、ストレス要因を完全になくすことは難しいと言えます。
ストレスへの対処力を高める方法について、簡単に解説します。
リラクセーション法
心身をリラックスした状態へと導く行動技法です。
手軽に取り組めるため、おすすめされたり、心理療法で取り入れられています。
呼吸法
簡単に言えば深呼吸ですが。
腹式呼吸を行い、呼吸に意識を集中することで心身をリラックスさせます。
やり方は色々とあるみたいですが、メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種の公式テキストに記載の方法だと。
①息を吐く(お腹の動きを感じるために、両手を重ねてお腹の前に当て、少し背中を丸める)
②ゆっくり息を吸う(4拍数えながら)➾お腹が膨らむ
③ゆっくり息を吐く(8拍数えながら)➾お腹がへこむ
④②と③を繰り返す公式テキストP.174
となります。最初は3分間続けることを目指し、徐々に長くしていくことを目指します。
ストレス状態にあると心身は緊張し、呼吸は浅くなり、心拍もあがります。
呼吸法はそれを落ち着かせ、平常時に戻すことで平静を取り戻すきっかけにもなります。
漸進的筋弛緩法
不安や緊張を感じると、身体がこわばります。
そのこわばりをほぐし、心をリラックスさせる方法です。
公式テキストの肩だけ引用しますが。
①肩をすぼめ、約10秒間両肩に力を入れたままにする
②その後、ストンと肩を落とし、脱力する
③リラックスする公式テキストP.175
なんとなく周りがやっていたり、アスリートがやっている姿を見て、無意識で取り組んだことがあるかもしれませんね。
自律訓練法
自己暗示の練習によって不安や緊張を軽減させ、筋肉を弛緩させ自律神経系をの働きのバランスを整えます。
ストレスによる身体症状の治療法として利用される場合は、専門家の指導のもと実施される本格的なものですが。
標準練習の手順はリラクセーション法としても利用されます。
①背景公式(安静練習)⋯「気持ちが落ち着いてる」と暗示する
②第1公式(重感練習)⋯「両手両脚が重たい」と暗示する
③第2公式(温感練習)⋯「両手両脚が温かい」と暗示する
④消去動作⋯両手の開閉運動、両肘の屈伸運動を数回行い、続いて背伸びしながら息を吐いて最後に目を開ける公式テキストP.176
ただし、不安感やイライラ感、不快感を伴う胸痛や頻脈が出る場合は中止しましょう。
特に道具を必要としないため取り組みやすいものがリラクセーション法ですが。
漸進的筋弛緩法と自律訓練法は、実施する環境について考慮することも大切です。
マインドフルネス
「今、ここ」の現実をあるがままに知覚し、感情や思考にとらわれない意識の持ち方を目指すのが、マインドフルネス瞑想です。
世界的な大企業も社員の健康増進や生産性向上のために取り入れている事例もあります。
メンタルヘルス不調の状態では、過去や将来に対して否定的な考えを繰り返す状態にあることが多いです。
そのため、「今」に注意を向けることでそのような思考と距離をとり、自分に起こっている思考や感情を俯瞰するために瞑想し。
冷静に対処し行動できるようにします。
呼吸など特定の対象に集中し、集中力を高めるための集中瞑想。
思考た感覚などの経験が現れては消えていくさまに「気づいている」状態訓練する洞察瞑想の、2つがあります。
洞察瞑想はどんな体験でも穏やかで、落ち着いた心の状態でいる平静さを育むことが目的です。
普段からの取り組みとして推奨する精神科医の方もいますね。
認知行動療法
効果のある心理療法として、世界的に認められているのが、認知行動療法です。
認知と行動の両面からの働きかけによりセルフコントロール力を高め、様々な問題の改善を図る心理療法の総称です。
個人を取り巻く環境であるストレス状況と、認知(思考)・気分(感情)・行動・身体反応の4つの側面からなるストレス反応からストレスを分析します。
行動については、これまでに書いたリラクセーション法やマインドフルネスなどの行動技法を利用します。
そして、認知療法の技法を利用し、自動思考からスキーマを理解することで認知の歪みを修正します。
認知が変われば行動を変えることができるし、行動を変えれば認知も変えることができるとしています。
心理療法以外にも取り入れやすいため、コーチングやアスリートのメンタルトレーニングなどにも利用されています。
コーピング
ストレスへの対処行動をコーピングといい、ストレス反応の発生を抑えたり、ストレス反応の低減が目的となります。
ストレッサーを解決されるべき課題ととらえ、コーピングを課題解決のための行動とらえる、問題解決思考の高い方法でもあります。
問題焦点型のコーピングは、ストレッサー自体を取り除き、直接的に解決するためのコーピングです。
騒音がひどい住環境から引っ越すといった行動です。
情動焦点型のコーピングは、ストレッサーによって引き起こされた気分や感情を変化させるためのコーピングです。
リラクセーション法を実施したり、気晴らしになる行動を行います。
どのコーピングを行うかはストレス発生の過程によって選べます。
刺激の発生:問題焦点型コーピングにより、刺激自体を取り除いたり予防する
認知的評価:認知行動療法の手法を利用し、物事の受け取り方を変える
情動的興奮:怒り・焦燥感・不安などで情緒が不安定なため、リラクセーション法を実施
身体的興奮:ストレス反応が身体に出ている状態で、心身の安定のためにコルチゾールを有酸素運動などによって消費する
管理監督者はこれらのストレス対処方法についての知識を持つだけでなく。
身につけることでQOLの向上につながることを伝えるとともに、継続的な取り組みが必要であることを指導していきます。
ソーシャル・サポートを利用する
ストレス低減に直接的な効果があり、他の対処行動を強める環境要因にソーシャル・サポートがあります。
配偶者や恋人、家族、友人といった周囲の人や、医師や看護師などの専門家があたりますが。
心理社会要因となる職場において、上司や同僚も重要な立場にいるとされています。
職場で行えるサポートは主に4つに分けられます。
①情緒的サポート
「やる気」を起こさせ、情緒的に安定させることを目的としたサポート。
傾聴や励まし、慰めなど、周囲が受容的な態度を示すことで実現。
②情報的サポート
的確な指示や解決法といった情報を与えるサポート。
あらかじめ問題が生じないようにする、予防的な意味合いも含まれるため、会社の上司や先輩だからこそできる重要なもの。
③道具的サポート
問題解決を直接的に勧め、実際に手助けを行うサポート。
一緒に処理に当たったり、増員して負担を軽減したり、機械の導入による効率化など。
④評価的サポート
仕事ぶりや業績などを適切に評価するサポート。
自己評価の高まり、今後について積極的になるなど、心理的に安定する
どのサポートを行うかは、相手が現状でどの程度適応しているかによって選びます。
・適応していると判断できる場合
無理していないか様子を見守る。
過剰適応している場合、一時的には高いパフォーマンスを示すが、長期的には疲弊してまう。
・適応に問題はないが、最近元気がない
ストレスを感じ始めている状態。
情緒的サポートにより受容と傾聴を行うとともに、解決につながる情報的サポートや道具的サポートを実施する。
・適応が悪い
協力なサポートが必要な「燃え尽き」の状態に陥っている可能性があります。
本人が問題に感じていない場合もあるため、適切な措置の必要性や妥当性を理解してもらうための、情報的サポートが必要となります。
また、職務内容によっても必要なサポートが異なります。
生産関連➾評価的サポートにより、仕事ぶりを適切に評価する
事務関連➾道具的サポートで処理の負担を軽減する
営業関連➾情報的サポートを行い、成果の達成を助ける
このように、4つのサポートそれぞれを使い分け、包括的に実施していきましょう。
普段の生活から職場での取り組みまで
このように、日常生活や運動習慣により身体の健康を維持することが心の健康につながります。
そして、職場でのサポートにより、ストレス要因を取り除いたり、ストレス反応を低減したり。
ストレスの対処法を身につけ、セルフケアに努めていきます。
その結果、安定したリーダーシップが実現し、部下へ説得力のある指導を行うことができます。
認知行動療法に関するものは自分の言動を変えるきっかけになりますし。
リラクセーション法を実践することで、その効果を目の当たりにすることができます。
管理監督者がセルフケアの面で見本となることで、部下も効果を観察し取り組みやすくなるでしょう。
また、管理監督者の指導もポイントを抑えたものとなり、一次予防の促進へもつながります。
セルフケアにより、組織全体のメンタルヘルス対策の強化につながるのです。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
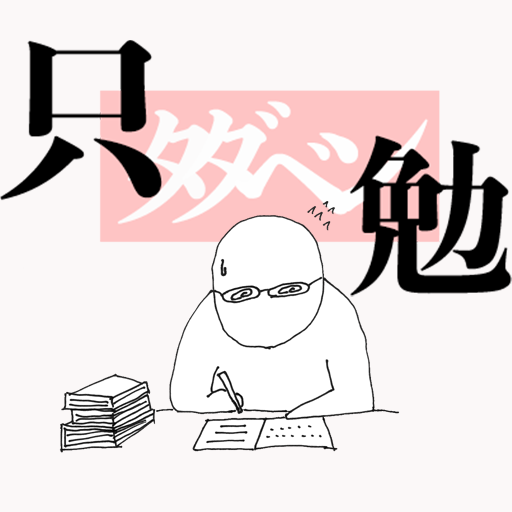
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!


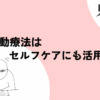
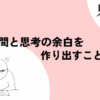
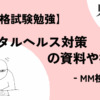
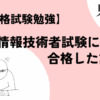
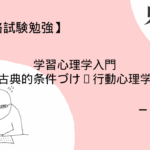
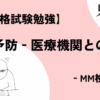
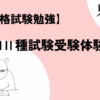




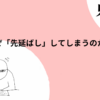

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません