AIで時間と思考の「余白」を作り出すことの意味
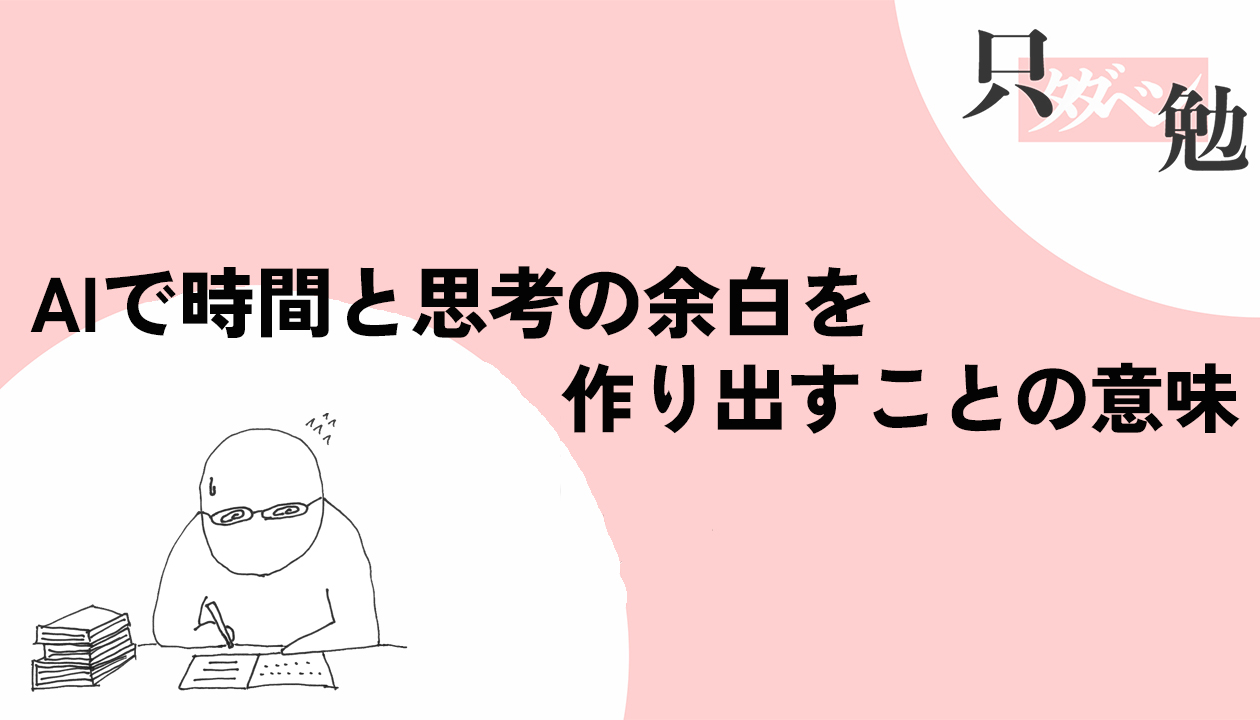
狙ったわけではないんですがー。
先を見据える系の記事の投稿が続きました。
まず、AI利活用の効率化の先にあるものについて。
続いて、それを利用した心理的安全性の構築についてです。
この2つの記事を書くきっかけが今回の記事にありました。
生成AIの利活用によって、私達の脳は拡張され、選択にリソースをより割けるようになります。
単純作業や定例業務といったものは、生成AIに置き換えられるでしょう。
そのため「仕事がなくなるかもしれない」という不安が起こります。
そんなことはない!というのが、上記2つの記事です。
しかし、「空白の時間」が生まれるのは事実です。
今回は、その捉え方について詳しく書いてみます。
落ち着かない時間
特に日本人に多いとされていますが。
私達は、仕事中に手が空くことを恐れます。
暇になりたいとか楽になりたいとかではなく、「なにかしていないと悪い気がする」「サボっているように見える」という、周りの視線が気になってしまうというものです。
そして、自己肯定感につながることですが、作業を行うことで自分の役割に満足しやすいかもしれません。
生成AIを利活用することで「仕事がなくなる」という言葉の背景には、このような思考があると思います。
周りの視線については、大体の方も思ったことがあると思います。
最近は聞かなくなりましたが、「給料ドロボー」という言葉もあったぐらいですし。
後半の方については、AIに限った話ではなく、有望な後輩や同僚に対しても起こり得るものです。
行き過ぎた事例は恐怖体験談などで、自分の「地位」が脅かされるんじゃないかと、犯罪行為に手を染めてしまう例はテレビなどで扱われていますね。
そのように、手が空くことに対する不安は思ったよりも大きいものです。
冒頭で紹介した記事で書いたことですが、生成AIは仕事というよりも「業務」から解放される可能性を秘めています。
そのため、この不安は思った以上に大きな影響があると、私は考えています。
リーダーほど不安かも?
現在活用が進んでいるAIで利用されている、LLM(大規模言語モデル)は私達が扱う言葉によって推論し生成します。
そのため、生成AIの脅威に当たるのは、頭脳労働者階級と言われています。
その立場に当たるのは、意思決定を行うリーダー達です。
現場や経営者にかかわらず、知識や知恵を使って戦略の立案をしたり、企画をしたり。
そのような仕事を行っている人たちほど、「時間が空きやすい」ともいえます。
正直、頭脳労働をある程度行うであろうリーダーの立場にいる人たちには、「仕事がなくなる」という不安を抱いていてほしくないというのが私の本音なんですがー。
私も含め。
現代は自分の仕事を抱えつつ、リーダーとしての仕事を行う「プレイングマネージャー」という状態にある方がほとんどだと思います。
AIによって負荷がなくなるのは、自分の仕事の部分でしょう。
そのため、今までやっていたことをやらなくて良くなり、「時間が空く不安」を抱くようになるかもしれません。
自分の仕事にチームのマネジメントにと、忙しくしていたことが半分なくなるため、仕事ができるという有能感を失い、アイデンティティが揺らいでしまう可能性はあります。
業務の分解や自分のやるべきことが明確であれば、このようになる恐れは低いんですが。
日々の仕事に追われていると、なかなかそうは行かないのも分かります。
なので、AI活用によって生まれる「空白の時間」について考えておくことが、私は大事だと思っています。
「空白」にしないためにはどうするのか?
答えの一つが、冒頭の2記事目の心理的安全性の構築です。
つまり、リーダーとしてのマネジメントの時間にあて。
時間がかかり、ある意味では面倒なことにこそ、時間をかけられるようになる。
そう考えています。
思考の余白が増える
生成AIを業務に活用するためには、利活用前提で組み直さなければならないと、良く言われます。
どの仕事をAIにまかせ、どの仕事を人間がやるのかを決めるためです。
使い方がわからないという方の多くは、AIが生成するモノをみているからで、生成できるコトを見ていないからだと、個人的に思います。
一つの企画書を作り上げるのに、どれくらいの時間がかかるでしょうか?
企画のためのリサーチや情報の整理。
文章や資料の構成。
プレゼンの準備など、時間や手間のかかる作業が多くあります。
今までやっていたことを、思い返してみてください。
使用する資料や情報を判断するだけでよくなるとしたら?
文章も微調整し、伝えたいことに集中できるとしたら?
見栄えの良い構成を、自分の感覚を元に選択できるとしたら?
プレゼンの準備の時間をより多くとれるようになるとしたら?
これが、生成AIを業務に組み込む効果で、生成されたものをそのまま使うということではありません。
もちろん、ハルシネーションの対策という意味合いもありますが。
人間が脳の力を一番消費するのは「選択」だと言われています。
どんなに小さなものでも、「選択」には負荷がかかると。
スティーブ・ジョブスが同じTシャツを何枚も持っていて、着るものを選択しないようにしていたというのは、有名な話・・・だと思います。
他にも、現代の名だたる起業家はどう「選択」のために脳力を残しておくかに敏感な印象です。
つまり、AIの利活用によって増えるのは時間だけではなく。
「思考の余裕」も増えるのです。
・・・そんなことを言いながら、ブログを書くために資料を準備し読み込んで、筋書き書いて下書きして・・・ということを私はまだやってしまいますが。
公開する清書の段階で、すでに頭が疲れていて。
伝えたいことを書き忘れるということが、そのような時には起こっています。
本来は、皆様に読んでもらう清書にこそ細心の注意を払わなければならないんですが。
その頃には余裕がなくなっていた(る)とも言えます。
この「思考の余裕」を取り戻し、「時間の余白」を得ることがAI利活用の一歩ではないでしょうか?
そこから、取り戻した2つを何に注ぐかですが。
私は、AIではできない領域。
対人関係の構築にあると思っています。
何もしないことの利点
「人と向き合おう!」と思っても、なかなかできないものです。
職場にかかわらずですが。
基本的には何かをやっている人に話しかけるのは、勇気がいるものです。
重要なことに取り組んでいて、その手を止めてしまうのではないか。
自分の話題に、手を止めてもらう価値があるのか。
話しかけられたら、邪魔だと思われてしまうのでは?
などなど。考え出すとキリがありません。
温和な空気を持っていて「何でも気軽に話しかけてね!」と言ってくれる上司でも、いざとなると尻込みしてしまったことはありませんか?
・・・私はよくあります。
それだけ、「何かをしている」というのは、コミュニケーションの弊害となっているのです。
もちろん、仕事をするために働いているので、すべてが弊害とは言いません。
しかしAIによって余白が生まれるのであれば、この弊害を最大限取り除くことはできるのではないでしょうか?
あえて「何もしない」という選択によって、話しかけやすい雰囲気を作ったり。
働いているメンバーの様子を観察するなど。
自分ではなくメンバーに目を向ける時間にするのです。
また、コミュニケーションを取るにしても、話すのが苦手なメンバーもいるでしょう。
心理的安全性の記事でも触れましたが、メンバーも不安を乗り越え、勇気を持って発言してくれるのです。
なので、沈黙も関係性をつくる場としてとらえ、待つ姿勢を持つ事ができるようになるのも、この余白によって実現されます。
余白がなければ、待っている間に自分の仕事やチームの予定が気になってしまうでしょうし。
その結果、リーダーの意向でメンバーを納得させるような話し合いになるかもしれません。
それでは心理的安全性の高いチームにはできないでしょう。
「関係性」につなげる
このように、AIによってできる「余白」は「関係性」に使うことができるはずです。
そして、この「関係性」は職場環境を整えることにつながり、メンバーが活き活きと働けるようになり、生産性を向上させるはずです。
今までは「やらないといけないと分かってはいたけど、やれなかった」ことで。
しかも「人間にしかできないこと」というものを「選択」し、取り組める環境の構築。
これが、AI利活用の結果だと考えます。
このようなチームが職場内に増えれば、生成AIの利活用において必要とされている一つである、新たな領域への挑戦にも繋げやすいでしょう。
AI利活用は、使うだけでなく、その先を見据えるのが大事です。
今からその「余白」を作り、利活用の先を見据えるのにAIを活用するのもありですね。
それがメンバーへの率先垂範となり、チーム内でのポジティブなAI利活用にもつながるかもしれません。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
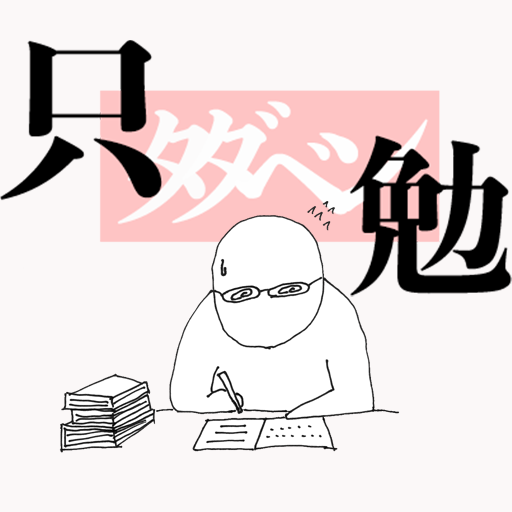
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!
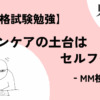
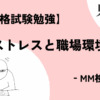

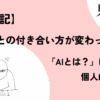


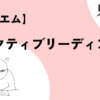



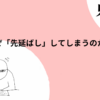

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません