ストレスと職場環境|メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)
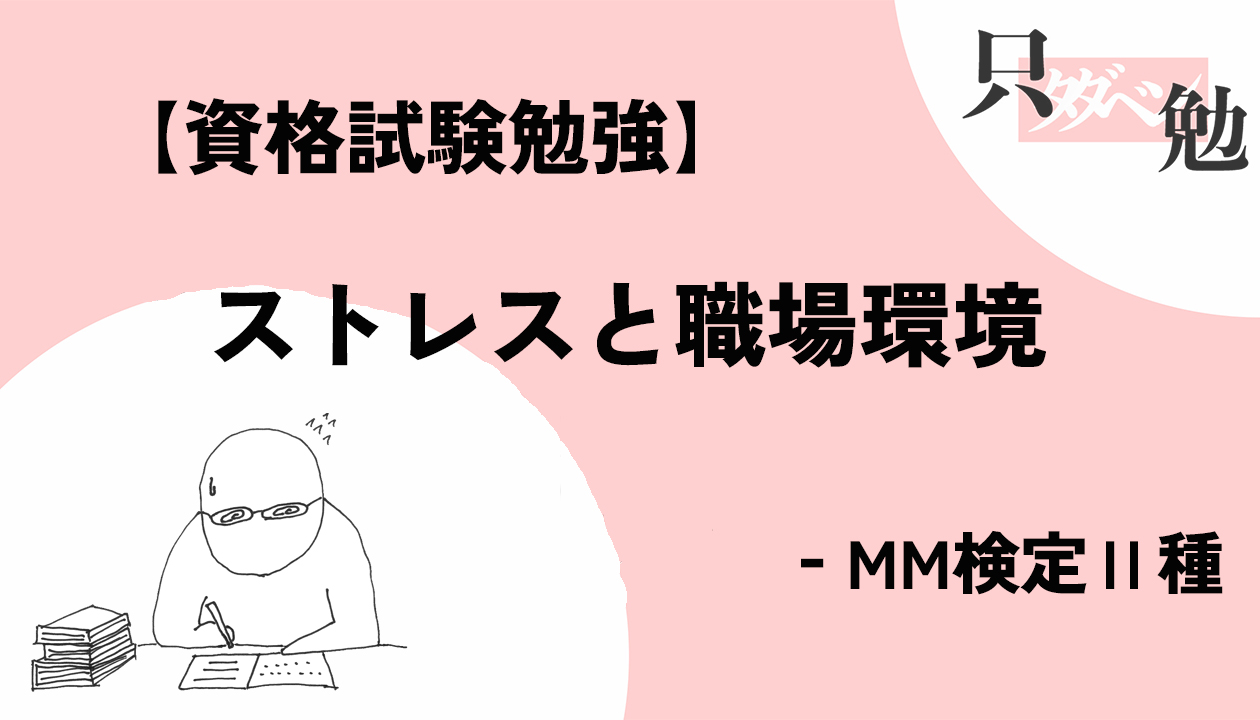
メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)の内容に従って記事を作成しております。
メンタルヘルス対策に活用したい制度や理論について書いてきました。
今回は、メンタルヘルス不調の元となるストレスについてまとめていきます。
メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)において、メンタルヘルス不調を未然に防ぐ一次予防の観点が重視されています。
そのためには、ストレスのメカニズムやサインを把握しておくことが助けになります。
ストレスの基礎
まずは、ストレスの基本を把握していきましょう。
このブログでは特に引用しませんが、公式テキストでは図や表も多く使われていますので。
理解を深めることにつながりますよ。
ストレスとは何か
私達が普段ストレスと言う言葉を使う時。
不快な状態であったり、憂鬱な気分になる要因だったり。
通常ではない、負担となる原因やそれから発生する気分などをストレスと呼んでいます。
細かくわけると、外部の刺激によって起こり、負担になる出来事や要請をストレッサーといいます。
ストレッサーは、ストレスの要因、ストレス負荷、ストレスの原因と呼ばれることもあります。
ストレッサーにより引き起こされる反応を、ストレス反応といいます。
・不安、抑うつ気分などの精神症状
・食欲不振、不眠などの身体症状
・喫煙や飲酒量の増加などの行動の変化
様々な症状がありますが、ストレッサーにより引き起こされる症状や状態はストレス反応です。
人間の身体は、脳によって各機能が制御されているため、ストレッサーからストレス反応までの症状には脳の働きが関係しています。
まず、負担となる出来事に直面すると、記憶を司る海馬から経験などを引き出し、大脳皮質で困難性や苦痛の程度が評価され、ストレスとして認知されます。
認知されたストレスが大脳辺縁系に伝わることで神経細胞が活性化し、神経伝達物質の働きによって感情が起こります。
これらの神経伝達物質の産生や伝達に以上が起きることで、不安や抑うつ気分などの精神症状の原因となります。
また感情が起こることで、神経細胞の興奮が視床下部に伝わり、自律神経系・内分泌系・免疫系でストレス反応が起こります。
自律神経系も感情に関与していますが、交感神経と副交感神経の連動によって、各体の器官の動きを制御しています。
そのため、感情を元にした食欲不振などの消化器症状を引き起こします。
ストレスによって心疾患が引き起こされることは、よく聞きますが。
これは、視床下部が内分泌系の中枢であることが関係しています。
ストレスが続くことで、風邪を引きやすくなったり、帯状疱疹が出ることがありますが。
免疫系のリンパ球やNK細胞の働きが抑えられることが原因です。
これらは、コルチゾールやアドレナリン、ノルアドレナリンという、ストレス状態で産生されるホルモンや神経伝達物質が関係しています。
通常は身体を維持するための生命維持機構ですが、ストレスに直面することでバランスが保たれなくなり、何らかの健康障害が発生することになります。
ストレス反応の3相期
ストレスに直面したあと、心身の不調がでるまでに3つの期間があります。
まず、よく聞くことかもしれませんが、適度なストレスは良い影響もあります。
その理由は、ストレスに反応し対処できるように身体が準備をするからです。
ストレスに対処する闘争、ストレスを避ける逃走、ストレスに耐えるフリーズのどれかを選べる状態になります。
これらの反応が出るのを「警告反応期」といい、ストレス要因が加えられ一時的に弱ってから、それに対処する力を得る時期です。
それから1週間から10日間の期間を「抵抗期」といい、心身の活動が高まり一定の安定を確保できる状態となります。
これらの期間で行う対処行動により、人として成長することにつなげることができますし。
その後同じようなストレスに直面した場合に、効果的な対処をすることもできるようになり。
以前ほど負担に感じなくなります。
しかし、ストレスとなる状況が長期間続くと、ストレスに適応するエネルギーが徐々になくなっていき。
「疲憊期」という時期に突入します。
この時期になると、抵抗力が弱まりストレス反応が発生し、心身に反応が出てしまいます。
これによって、身体面・行動面・心理面に不調をきたすことに。
ストレスの3相という段階があることも知り、観察することによって、適切なフォローを選ぶ助けにもなります。
ストレス要因の種類
ストレッサーとなるものは、日常の至る所に潜んでいます。
ストレスというと、真っ先に浮かぶのが仕事関係だと思います。
立場や責任、自分の能力に良くも悪くも見合わない要求といったものです。
これは仕事に限らず、家庭にも存在します。
良い親でありたい、良い子でいなきゃいけないといった人間関係に係るものもあれば。
親しい人との離別という経験も大きなストレスとなります。
また、自分の欲求が満たされないこともストレスに感じることになるでしょう。
食事や睡眠といった生理的な欲求や、所属することでの安心の欲求など。
マズローの5段階欲求仮説が分かりやすいかもしれません。
職場環境のストレッサー
多様な働き方が認められるようになったとはいえ、仕事には拘束時間がついてきます。
就業時間中は、自分の勝手で職場を離れるわけにはいきません。
そのため、職場環境がストレス要因になりやすいとも言えます。
・物理的な要因:
有害物質、職場レイアウト、作業負荷、作業内容、作業に伴う責任自由度
・職場環境の要因:
労働時間、人事制度、組織風土、会社の将来性、雇用の安定性
・心理・社会的な要因:
職場組織、コミュニケーション、人間関係、意思決定の参画、入手できる情報、仕事のコントロール、同僚・上司の支援、仕事の要求度
主にこのようなものです。
日常生活も職場環境も体験するのは、ひとりの人間です。
そのため、ストレス反応が出てしまった場合、これらのストレス要因が複雑に絡み合っている場合がほとんどです。
職場環境の要因だけを取り除いても、家庭内で何かしらのストレスを抱えている場合、根本的な解決には至らない可能性もあります。
当人を取り巻く様々な環境や状況が、ストレス要因になっていることは忘れないでおきましょう。
管理監督者として把握しておきたいストレスのこと
管理監督者は以上のストレスの基本知識を抑えつつ、部下の健康状態に気を払い不調の早期発見に務めることが求められます。
早期発見に役立てるために。
・ストレス反応の特徴
・ライフステージよるストレスの特徴
これらの知識も役立ちます。
部下の心身の変化
部下に限らずではありますが。
ストレスによって3つの面で変化が起こります。
身体的変化
具合の悪さとして現れるもので、頭痛や胃痛といった直接的なものから。
疲労感や不眠といった症状も身体的変化によって生じます。
症状として現れるものなので、気付きやすいと思われるかもしれませんが。
実際には部下が症状を訴えてくれないと、わかりにくかったり。
見当違いだったりする場合もあります。
また、部下自身が市販薬などで対処し、勤務中は不調が出ないかもしれません。
そのため、日頃から観察することや、コミュニケーションをとるといったアクションが、把握のためにも大切です。
行動的変化
身体的変化よりも把握しやすいのは行動的変化です。
遅刻や欠勤の増加、飲酒や喫煙量の増加、ミスの増加など、本人よりも周囲が把握しやすいものです。
遅刻や欠勤は勤務データにも表れやすいため、定期的にチェックをすることでも把握できます。
身体的変化や次の心理的変化によって起きている可能性もありますが。
行動的変化を確認できたら、ストレス反応を疑い、該当する部下をよく観察するようにしましょう。
心理的変化
ストレスにうまく対処できていない時の反応です。
抑うつ、不安、イライラといったもので、体調は悪いけど対処の仕方が難しい変化でもあります。
本人自身が「自分が性格的に弱いからだ」と考え、内向きになることもあり、身体的変化同様、把握することは難しいです。
自責的なるため、部下から語られる可能性も低いため。
部下が語る事がある場合、積極的に耳を傾け、異変に気付けるようにすることが大切です。
「いつもと違う」に敏感になる
これらの変化は、普段の部下の様子と違うことに気づくことが大切です。
そのため、普段から部下の様子を気にかけ、時系列で変化を捉えるようにしましょう。
ストレスレベルが低い:活気がない
ストレスレベルが中程度:不安感、イライラ、落ち着かない
ストレスレベルが高い:抑うつ感
と言ったように、ストレス反応の遷移を確認することもできますし。
先程書いた「ストレスの3相」を念頭に、部下の状態を気にかけることも把握の助けになるでしょう。
特に、仕事上であれば行動面の変化に気付きやすいとも言えます。
普段の部下の仕事ぶりを把握し、「いつもと違う」ように感じたら、アクションを起こすことを心がけましょう。
ライフサイクルなどによるストレスの特性
年齢を加えることで、立場や役割として求められることが変わります。
各段階に特徴的なストレスがあるので、把握しておくとフォローの助けになるでしょう。
若年労働者
新入社員を含めた若年労働者は、自由度が高く親などの援助があった学生生活から。
上司や同僚と協働して責任のある仕事を求められるようになり。
人間関係や処遇に対する不満がストレスの原因になることもあります。
また、一部では人間的な未成熟さにより、メンタルヘルス不調を抱えやすい人もいます。
そのような人には状況を見ながら、社会人としての教育を施し成長を促すことも考慮する必要もあります。
壮年労働者
ライフサイクルの中で、ストレスを抱えやすいのが壮年世代です。
社会や企業の経験から、第一線での活躍が求められ負担が増えるとともに、長時間労働問題になりやすいことが上げられます。
今では管理職がプレイング・マネージャーであることも多くなり。
経験ある壮年労働者には実務を遂行しつつ、リーダーシップの発揮が求められることになり。
複雑化・高度化した仕事に対し、ストレスを感じる可能性もあります。
また、転職した場合に、経験して来た職場とのギャップに戸惑いや不満を抱いたり。
新たな人間関係による問題なども抱えやすくもあります。
家庭でも役割が増える事によるストレスの発生が見込まれますが、良い関係を家族と築けていれば、緩衝要因となりストレスを緩和してくれます。
中高年労働者
加齢による心身の衰えを感じる年代。
体力や記憶力に加え、新しい環境への適応力も低下するため、新たな取り組み自体がストレスになる場合があります。
その一方で、景観や実績を評価され、指導的な立場に就くことを求められる年齢でもあります。
なので、これまでのキャリア形成や経験などに左右されるとも言えるので。
長期的な視点で仕事の要求を労働者に対して行うことの大切さが分かります。
家庭においては、子供の受検や自律、親の介護といった問題も起こり始めるため、役割分担や協力も一掃求められます。
職場としてストレスに対処する仕組みを整えることが、助けとなる世代とも言えるかもしれません。
高齢労働者
人生100年時代と言われ、シニア世代の活用も進んでいます。
再雇用や定年延長といった制度もありますが、「収入が欲しい」や「老化を防ぐため」といった高齢者特有の悩みもあります。
知識や経験を活かして総合的に判断する「結晶性知能」は80まで上昇を続けますが。
「流動性知能」という、情報を獲得し処理する能力はピークをすぎています。
それに、反射神経機能といった身体能力の低下に加え。
記銘力や想起力といった、記憶に係る能力も低下します。
気持ちや経験など職場にプラスを与える要素と、フォローが必要なマイナスの要素の両方があるため。
職務設計や処遇をしっかりと考えたり。
教育研修を実施することも有効です。
女性労働者特有のストレス
対人関係や雇用の安定性をストレスと感じる割合が男性よりも多いのが、女性労働者です。
職場や家庭でのストレスはもちろん、女性特有の身体の変化によるストレスもあります。
産業保健スタッフと連携して職場環境の改善を行うのはもちろん。
ワーク・ライフ・バランスの実現を目指した体制づくりによって、仕事と家庭の両立をサポートしたり。
ポジティブ・アクションを実施し、機会均等を図るなど。
女性が安心して働ける環境を目指すことで、職場環境全体の改善につながるといえるかもしれません。
非正規雇用者のストレス
非正規雇用者の場合、雇用の安定性という問題よりも、自発性があるかどうかでストレスの個人差が生まれるそうです。
自分から望んで非正規雇用者になった人のストレスレベルは低く。
就職難などの影響で、不本意ながら非正規雇用者になった人は、ストレスを感じやすいそうです。
そのため、現在の就業状況にかかわらず、ポジティブなキャリア感を持てるように支援することも必要です。
管理監督者にもストレスはある
部下の健康を守るために、管理監督者に求められる役割は大きいとはいえ。
管理監督者も人間で、ストレスをかんじます。
部下を適切にサポートするために、セルフケアにより自分自身の健康にも配慮しましょう。
事業者もそのサポート体制を整えることが大切です。
また、産業保健スタッフも管理監督者が相談対応の対象であることと、力になれることを伝えることも大切です。
管理監督者は昇進時にメンタルヘルス不調を発症する場合が多いようです。
・給料の減少
・部下の指導
・責任の増大
・上司と部下の板挟みの立場
という立場によるものや。
・十分な裁量権がない
・働き方改革のしわ寄せによる長時間労働
・リモートワークによる部下への心配、不信感、チームビルディングの難しさ
といった、職場環境によるものがあります。
また、理想的な管理監督者が持つ特性が、ストレスを受けやすい性格であることも理解しておくと良いでしょう。
・真面目
・几帳面
・仕事好き
・他人との円滑な関係に気を使う
管理監督者の立場は、業績面でもメンタルヘルスの面でも重要な立場となります。
日頃から自分自身に注意を払うとともに、呼吸法や漸進的筋弛緩法といったリラクセーション法を実施したり。
マインドフルネスによってストレス発生時の対処法を身に着けておくなど。
進めるだけでなく、自分自身でも実践し、整えて行きましょう。
ストレス理解が職場改善につながる
以上がストレスの基本と、職場におけるストレス要因となり得ることについてです。
ストレス反応が発生するのは部下などの労働者個人ですが。
ストレス要因となるものは、職場環境にあり労働者全員に関係するものです。
そのため、ストレスのメカニズムを理解し、部下を観察することで。
職場環境に潜在するストレス要因を見つけ出すことにつながります。
ストレスチェック制度も、受検するのは労働者個人ですが、集計することで職場のストレス要因を知ることにもつながるので活用していきましょう。
管理監督者となると、企業の中ではチーム単位など小さくなるかもしれませんが。
その小さいところから改善に取り組み、生産性を向上させることで全体に伝播し。
企業の生産性向上と活力につながります。
そのような取り組みが魅力的な組織風土を生み出し、企業自体を変えることにつながるのです。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
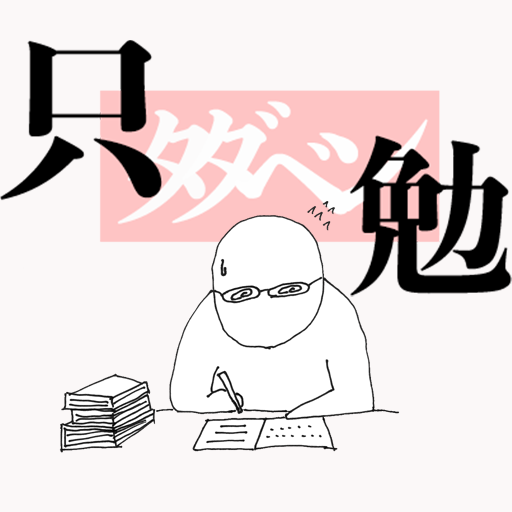
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!


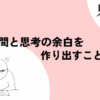
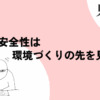
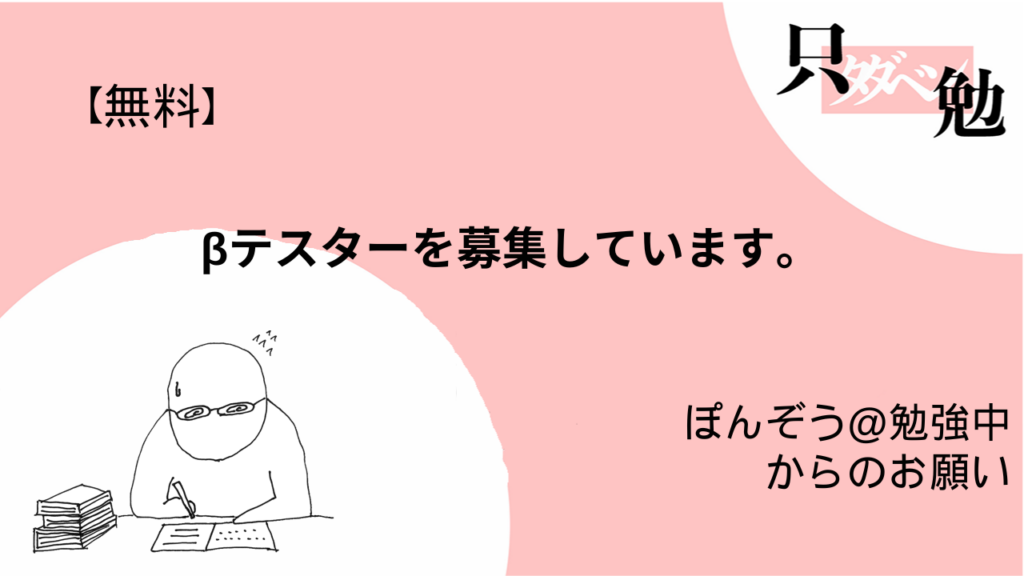

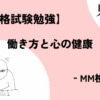
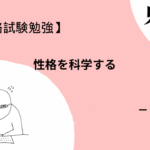
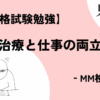
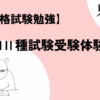

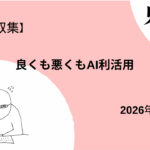
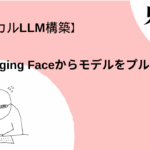
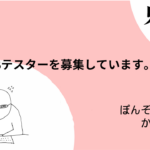
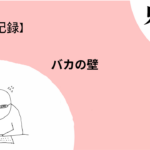
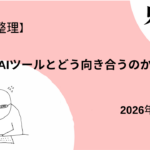
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません