生成AIの回答を変えるプロンプト
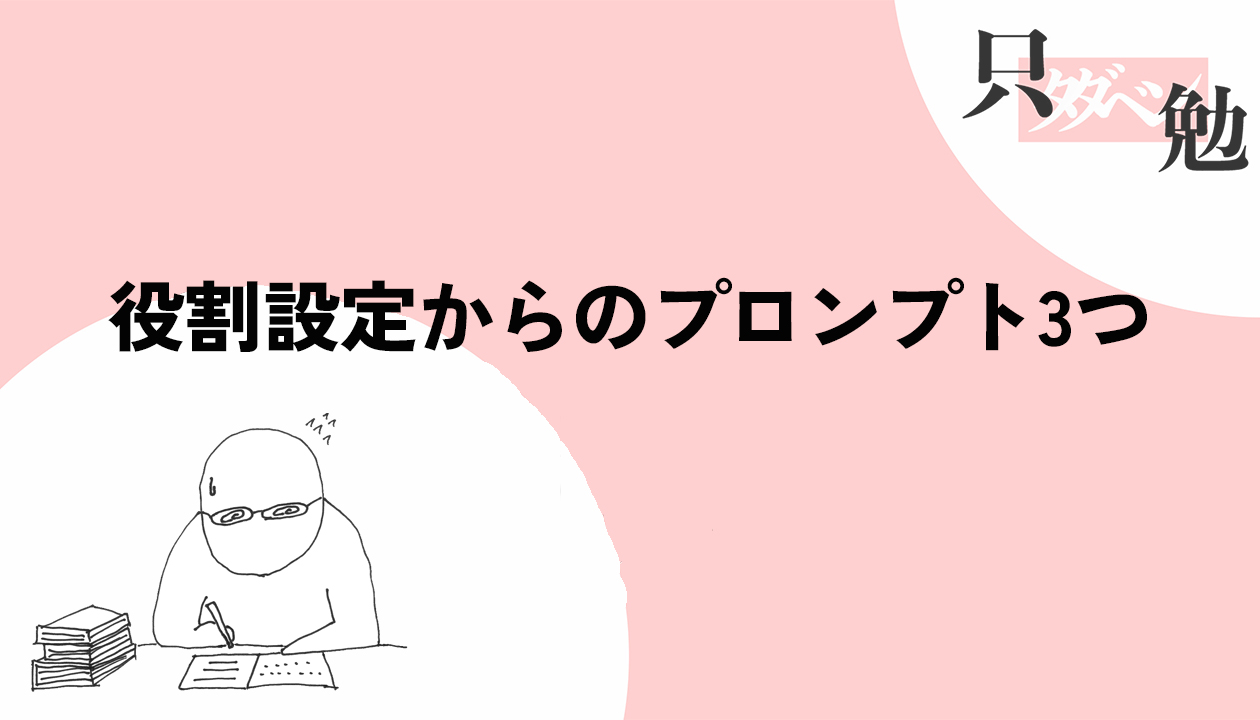
ChatGPTやGemini、Copilotを使わない日がなくなってきた今日このごろです。
私はテキスト生成AIに何かを作り出させるというよりは。
自分の考えを深めたり、計画の作成などで利用しています。
ただ、使っていると代わり映えのしない回答が続いたり、もう一歩踏み込んだ回答がほしいなぁとおもうことが増えてきました。
そんな中、毎週のルーティンであるQiitaの記事巡りをしていたところ。
以下の記事を見つけました。
・「あなたはプロの〇〇です」をもうやめたい、「メタプロンプト」から「コグニティブデザイン」へ
・プロンプトは「お願い」ではなく「コード」。論理式を応用した「公理系」プロンプトエンジニアリング
・AIを「物知り博士」から「知的パートナー」へ。「背理系」プロンプトエンジニアリング
すべて@makotosaekitさんの記事です。
モデルの進化によって、どのようにプロンプトを変えれば良いのか?
正直、生成AIと対話する意味を考え始めてしまっていた私には、ストライクな内容でした。
詳しくはぜひリンク先の記事をお読みいただきたいですが。
生成AIの回答の質を高める方法について、参考にしながら書いていきます。
役割を与える
生成AIが出た頃から、今でも使える手法として「AIに役割を与える」というものがあります。
自分もひたすら使っていましたし、今でも急ぐときは使っています。
よく使うのは。
・あなたは大手企業から信頼を得ているコンサルタントです
・あなたはプロのブロガーです
・あなたは個人事業主向けのキャリアコンサルタントです
といったような感じですかね。
ブログの記事の内容や、作成したい計画の内容に応じて役割を設定しつつ。
少し対象を絞り込むようなプロンプトにしています。
が、冒頭に書いた通りで、少し深堀りをしたいような時に、回答の精度が落ちる・・・というか。
表面的な内容ばかりが帰ってきてしまい、そうじゃないんだよ感が。
こちらの考えが固まっている場合は、あんまり気にしないんですがー。
すこしラフに考えて対話を始めるときは、物足りない回答が出る印象です。
AI自体もユーザーとのやり取りから学習している部分もあるので、利用する人が設定した役割をそれぞれ学習し。
一般的な役割をまとって回答している、ということがあるみたいですね。
それでも、インターネット上の情報を検索して回答してくれるようになってから、少しは良くなった気がします。
なので、方向性が決まっている状態でざっくりと推論してもらったり。
文章の訂正や計画に対する点検にはちょうど良かったりします。
コグニティブ・デザイン
1つ目の記事である、「あなたはプロの〇〇です」をもうやめたい、「メタプロンプト」から「コグニティブデザイン」への内容です。
役割設定の限界について書いてあったのも、この記事です。
で、役割設定から一段階上がるには、「コグニティブデザイン」という設計でプロンプトを作成しよう。
という感じです。
役割設定の場合、「あなたは〇〇です」から始まり、いろいろな制約をズラッとつけてました。
まぁ、この制約を並べる必要がなくなったと感じてから、AIモデルの進化を体感したのが私ですがw
と、「コグニティブデザイン」では、役割ではなく世界観を提示するという感じです。
役割で縛るのではなく、制約で縛るという感じでしょうか。
記事によると5つのプロンプトを作成します。
1,前提:疑うことのない事実、守るべき価値観、条件
2,状況:起きている事実、存在する変数、競合状況
3,目的:具体的なゴール
4,動機:なぜその目的を達成したいのか
5,制約:目的達成のために守るべきルール
という感じですね。
記事で紹介されている例は、これまでのプロンプト通り細かく入力されていますが。
役割ではできた大枠のものを、前提や条件で提示するので、細かくはなりますね。
実際に試してみたところ、ある意味ではAIの思考の枠組みをある程度解放しつつ、一つの目的のために一緒に考えている、という感覚になりました。
役割ではなく世界観を与えることで、ここまで変わるんだなぁと。
公理系プロンプトエンジニアリング
こちらはAIの回答のばらつきを抑え、欲しい回答を生成させるというイメージでしょうか。
2つ目の、プロンプトは「お願い」ではなく「コード」。論理式を応用した「公理系」プロンプトエンジニアリングの内容です。
先に書きますが、このプロンプトを試す機会が今のところないので、試せてはいません。
が、AIは確率計算機で数式や論理式と相性が良いということは理解できるので。
これは強力なんだろうなぁと思います。
また、画像解析や音声解析といった、解析を行うAIの動作と合致してそうな気もします。
1,前提を伝え
2,プロンプト内で使う言葉や操作を定義し
3,データの事象に対する動作をIF文のように書く
という、プログラムを書くようにプロンプトを作成します。
なのでタイトルにも「コード」という言葉が使われているんですね。
現状だとそこまでガチガチに固めたプロンプトを使用する機会が無いので。
生成AIに何らかのデータの整理や解析をお願いすることになったら、使ってみようかなと思います。
このプロンプトをゴリゴリかいて、AIが解析してたらかっこいいんだろうなぁ。
背理系プロンプトエンジニアリング
この3つの記事を読んだあと、よく利用しているのが3つ目の背理系プロンプトエンジニアリングです。
・AIを「物知り博士」から「知的パートナー」へ。「背理系」プロンプトエンジニアリング
背理系フレームワークという思考技術を使って、プロンプトを作り。
AIとの対話により、問題の深堀りをしよう、という感じです。
記事によると、「問題の本質を暴き出し、再定義する」と説明されています。
かなり攻撃的ですがー。
この威力はなかなかでした。
手順としては。
1,目的背理:お願いではなく、状況を伝えて整理させる。
2,構造背理:整理させた状況に対して、異なる視点から問いを投げかける
3,原則背理:対話した内容から、新しいフレームワークを作り出す
詳しくは元記事をぜひ。
威力を感じたのは、目的背理で使用する。
・主体と客体を意識しては「ならない」ものとします
という一文です。これだけで、生成される回答の客観性が高まり、考える余地が広がるという印象。
構造背理も4つほど上げられていますが。
AIとの対話の目的によって使い分けるのが良いと思いますが、私がよく使うのは。
・対立概念の定義と緊張関係の説明
・適合した場合のポジティブな結果とネガティブな結果の例示
といった比較に関わる問いかけですかね。
整理した状況をさらに想定できるものや、異なる視点から比較し、思考を深めるような(つもり)です。
目的背理と構造背理でやり取りを行っていると、かなり長くなるので。
それをまとめる意味で、原則背理を実行しておくと対話がスムーズになる印象。
一旦納得が言った時点でフレームワーク化してもらい。
また疑問が湧いてきたら同様に対話を進める、という感じです。
個人的には、生成AIの使い方を一つ変えることができたと。
実感してしまった方法です。
組み合わせてもOK
とはいえ、日々の出来事におわれていると。
じっくりとプロンプトを考えているわけに行かない場合もあります。
そんな時に私がやっているのは、役割+目的背理です。
コグニティブデザインが良いけど、状況とか細かく説明しているヒマがない
➾役割でざっくり枠を作ってしまえ
同調的なことではなく、事実をズラッと並べてもらって、そこから拾い出したい
➾目的背理で、客観的にリスト化してもらってしまえ
という、ほぼ勢いだけですがw
それでも、帰って来る回答から、深堀りできる論点がみつかり、期待した状態にまで持っていける。
という体感を日々しています。
背理系で作ったフレームワークを使って、公理系で処理してもらうという使い方とか。
少し夢が広がります。
技術の進歩に合わせて
AIの進化の勢いはすごいです。
少し触らないだけでも、受ける印象がだいぶ変わります。
また、AIモデルを開発している各社ごとの特色も出るようになってきた印象です。
そのような良い意味でのばらつきが出てきたからこそ、一定の成果を出しやすいプロンプトを覚えておくとAIを活用しやすくなるのではないでしょうか。
自分の生成AIに対する立ち位置は、このブログでもたびたび書いている通り、「人間の脳の拡張」です。
テキスト生成AIは思考や推論の拡張を行うツールでありパートナーであると考えています。
相手が賢くなるのであれば、こちらも関わり方を変える必要があります。
子供の成長に合わせて、接し方が変わるのと同じですかね。
楽しみながら、AIを活用していきましょう!
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
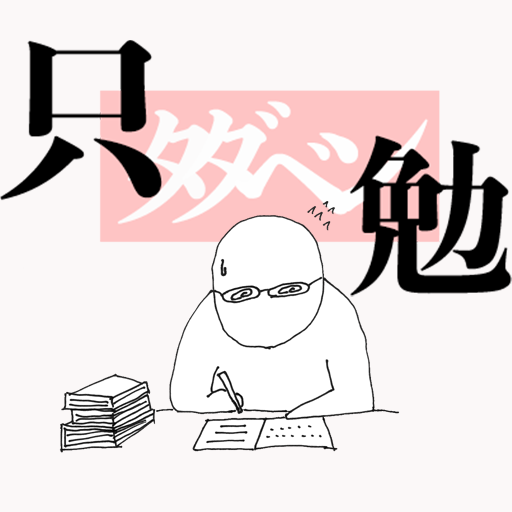
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!
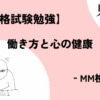

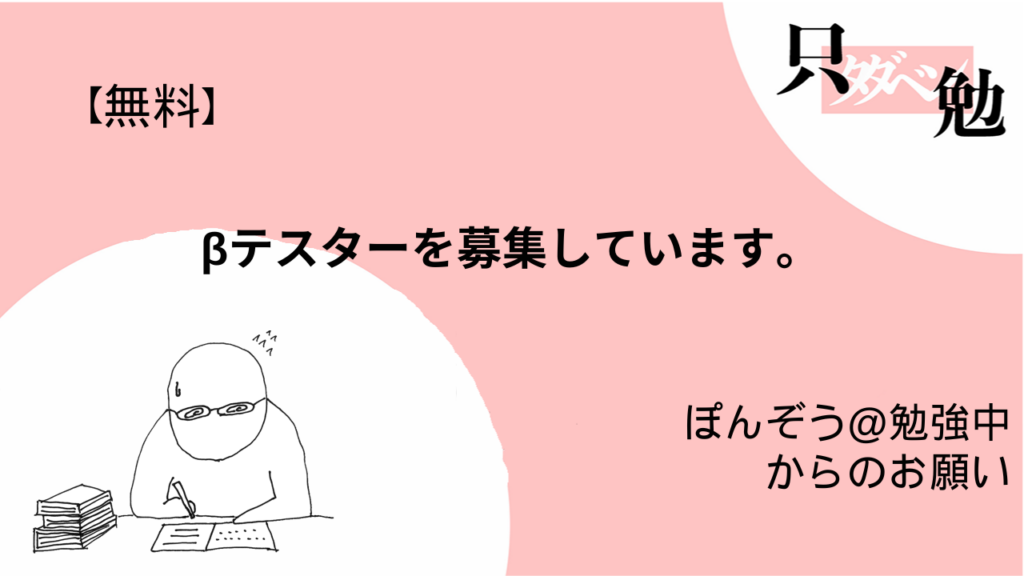

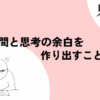
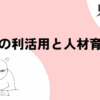

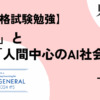

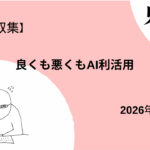
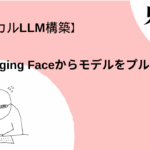
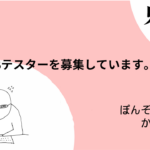
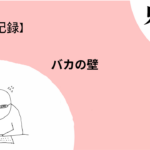
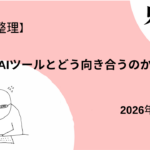
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません