【資格勉強】メンタルヘルス・マネジメント対策に関連する統計資料や指針など関連情報のまとめ|メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種(ラインケアコース)
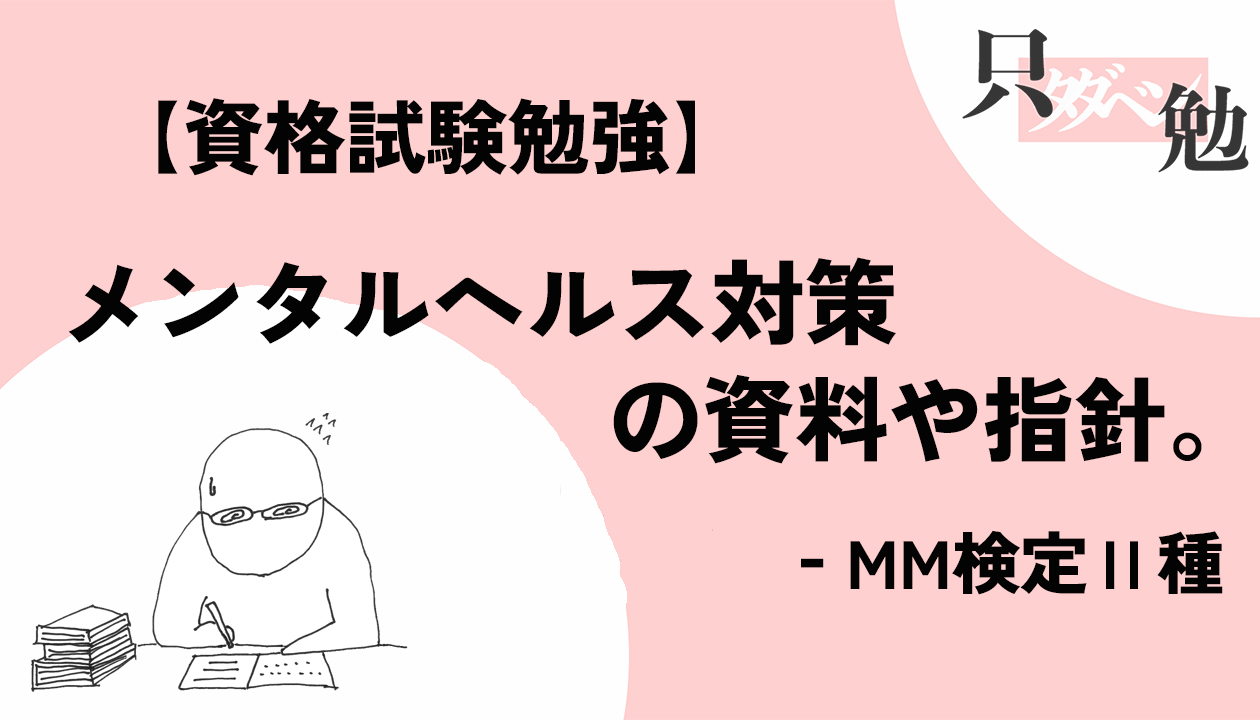
メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種(ラインケアコース)で扱われる日本の法律についてまとめました。
今回は、ガイドライン・統計などテキストで扱われるものを分野ごとに整理してみます。
こちらも試験対策では必須なのでしっかりと把握したいです。
が。
職場環境の整備や、日本の労働環境の現状などを知ることができるので。
資料としても興味深く、これからの働き方について考えることができます。
メンタルヘルスケア・マネジメント検定の受験予定がなくても参考になりますよ。
なお、リンクによってはPDFが開かれる場合もあります。あらかじめご了承ください。
調査・統計・社会動向
公式テキストの第Ⅰ章が、現状を把握するための内容なので。
メンタルヘルスに関する労働者の現状や、対策の状況などを把握するための数値が並びます。
その数値のソースとなるものをまとめます。
労働安全衛生調査:厚生労働省
事業場における安全衛生活動や労働者のストレス状況を把握する統計です。
公式テキストでも最初から最後まで扱われる資料なので、最新版の数値は抑えておきましょう。
社会生活基本調査:総務省
国民の生活時間や行動実態を把握するための、統計法に基づく調査です。
公式テキストでは、メンタルヘルスに関係する睡眠時間の調査結果で参照されています。
国民生活時間調査:NHK文化放送研究所
NHKなので・・・かどうか分かりませんが。
テレビの視聴時間を含む生活時間の調査で、こちらも睡眠時間の調査内容が参照されています。
公開されているサイトでは、15分毎の行動割合を視覚的に表現しているものや。
在宅勤務の割合や週休2日制の定着など、データに基づくコラムも掲載されているので。
情報収集にも良いです。
仕事と生活の調和促進のための行動指針:仕事と生活の調和推進官民トップ会議
ワーク・ライフ・バランス推進のための政府方針を示した指針です。
経済界、労働界、地方自治体、有識者、関係閣僚で構成される団体が作成しました。
コーポレートガバナンス・コード:東京証券取引所
上場企業に求められるガバナンスの基本原則が定められています。
人財や人的資本管理というものが、企業の価値判断基準に含められ重視されています。
それが、ステークホルダーに従業員が含まれていて、メンタルヘルス・マネジメントを経営上の最重要テーマに据えられていることに現れています。
犯罪白書:法務省
精神障害に関する誤解のパートで、一般刑法犯の中で精神障害を持つあるいはその疑いがある人の割合が公式テキストで示されています。
高齢者の生活と意識に関する国際比較調査:内閣府
内閣府による国際比較調査です。
高齢者の生活満足度や健康意識の違いを把握でき、シニア世代の就労意欲やメンタルケアの参考となり、高齢労働者のストレスについての参考資料として引用されています。
労働力調査:総務省
日本の就業者・失業者数や労働参加率を明らかにする基幹統計です。
労働者の分類や働き方の全体像を理解する基礎資料です。
雇用形態によりメンタルヘルスへの影響は異なるため、把握しておくと良いでしょう。
新規学卒者の離職状況:厚生労働省
学卒者の就職後3年間の離職率を示す調査です。
若年層の職場定着やメンタルヘルス課題を考えるうえで重要な資料です。
基本指針・制度
メンタルヘルス・マネジメントを実施するにあたり、参考にすべき指針や利用できる制度についての情報源をまとめます。
義務化されているものや努力義務など、職場環境を整えるために必須の内容です。
労働者のここの健康の保持増進のための指針:厚生労働省
職場における心の健康づくりの基本的方向性を示した指針で、いわゆる「メンタルヘルス指針」です。
メンタルヘルス対策に関する公法的規制の中核と位置づけられています。
労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針:厚生労働省
健康情報やメンタルヘルス情報を扱う際のルールを明確化した指針です。
従業員の健康情報は要配慮個人情報なので、適正な管理が必要です。
ストレスチェック制度:厚生労働省
労働者の心理的負荷を把握するため、事業者に年1回の実施を義務付けた制度です。
労働者自身の気付きを促すとともに、職場環境の改善につなげ、未然に防止することを主な目的として実施されます。
ストレスチェック指針:厚生労働省
正式名称は「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」です。
リンクの「法令」のところにPDF資料があります。
ストレスチェック制度の具体的な実施手順や留意事項を解説しています。
厚生労働省版ストレスチェック実施プログラム:厚生労働省
無料で配布されている、ストレスチェックの受検、ストレスチェックの結果出力、集団分析等が出来るプログラムです。
事業者がストレスチェックを円滑に実施することを目的に配布されています。
職場環境改善のためのヒント集:厚生労働省
ポータルサイト「こころの耳」で掲載されている、メンタルヘルスアクションチェックリストです。
職場のストレス要因を減らすための実践的アイデアが紹介されていて、従業員と共にストレス要因やその改善策について話し合うためのツールとして提供されています。
健康管理・復職支援・両立支援
ワーク・ライフ・バランスの観点での管理・支援に関する資料です。
心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き:厚生労働省
メンタルヘルス不調により休業した労働者の職場復帰に向けた、事業場向けマニュアルです。
段階的な復職プロセスを整理し、支援の流れを明示しています。
治療と職業生活の両立支援ガイドライン:厚生労働省
労働人口の高齢化に伴い、何らかの持病を抱えながら働く人達が増えています。
持病が原因でメンタルヘルス不調につながる場合もあるため、そのような労働者の治療と仕事の両立を支援する事業者向けのガイドラインです。
がん・脳卒中・肝疾患・難病・糖尿病・心疾患が留意事項の対象疾病としてあげられています。
事業場における労働者の健康保持増進のための指針(THP指針):厚生労働省
心身両面から健康づくりを推進する基本的な枠組みを示すガイドラインです。
健康保持増進措置を継続的かつ計画的に進める際の参考となります。
・生活習慣病に対する保健指導、栄養指導、運動指導
・メンタルヘルスケア
・ストレスに対する気付きの援助
・リラクセーションの指導
・良好な職場の雰囲気づくり
以上の推進を目指します。
健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針:厚生労働省
健康診断後に事業者が取るべき対応が整理されています。
就業区分ごとの就業上の措置の内容が記載されています。
健康づくりのための睡眠指針:厚生労働省
次の項目につながるものですが、長時間労働や不規則な勤務により。
睡眠時間の確保や睡眠の質の低下といった状態が起こり、メンタル不調につながることもあります。
睡眠習慣改善のためのアドバイスがまとめられた資料です。
快適な睡眠のポイントや睡眠の質の改善について扱われています。
労働時間・過重労働対策
働く事とメンタルヘルスの関係で必ず問題になるのが、労働時間や過重労働です。
健康に直結する問題でもあるため、労働者自身も把握しておきたい内容です。
労働時間の適正な把握に関する基準:厚生労働省
労働基準監督署による時間管理指導を強化するための内容です。
労働時間を把握する努めは事業者にありますが、その具体的措置を示し遵守を求めています。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン:厚生労働省
使用者が労働時間を適切に管理するための実務ルールについて定めています。
労働時間の考え方についても示されています。
長時間労働者への面接指導マニュアル:厚生労働省
公益財団法人産業医学振興財団のWEBサイトで公表されています。
労働安全衛生法によって、事業者は長時間労働者に医師による面接指導を実施することが定められています。
面接指導を実施する医師に利用が推奨されているマニュアルです。
長時間労働者への面接指導チェックリスト:厚生労働省
面接指導に関する報告書・意見書マニュアルの中に、利用できるチェックリストが含まれています。
面接指導の手順や評価項目が具体的に示されています。
過重労働による健康障害を防止するための措置:厚生労働省
過重労働に対する行政指針を示したものです。
事業者が行うべき対策として、次のものがあげられています。
①時間外・休日労働の削減
②年次有給休暇の取得促進
③労働時間等の設定の改善
④労働者の健康管理に係る措置の徹底
過重労働による健康障害防止のための総合対策:厚生労働省
労働時間の医学的知見を踏まえ、長時間労働による健康リスクを防ぐための包括的な取り組みについて示されています。
適正な時間管理や面接指導等の健康管理などの対策について説明されています。
労災認定・精神障害関連
どんない対策を取っていても、メンタルヘルス不調が起きてしまう場合があります。
もしそうなった時に労災を利用できれば、少しは負担が軽くなります。
メンタルヘルス不調の労災認定についての資料です。
脳血管疾患及び虚血性心疾患の認定基準:厚生労働省
過重労働による、脳・心臓疾患の労災認定基準を示しています。
精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書:厚生労働省
精神障害の認定基準を検討した報告書が公表されています。
長時間労働とうつ病の関係について報告されています。
心理的負荷による精神障害の認定基準:厚生労働省
「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会報告書」を元に策定された、労災補償の判断基準に用いられる公式な基準を示しています。
健康情報・個人情報の取り扱い
途中でも触れましたが、健康情報は要配慮個人情報にあたり、適正な管理が求められています。
そのような健康情報をどのように扱えば良いのかを示しています。
また、事業者は従業員の個人情報を取り扱う立場でもあるので、法令の遵守が求められます。
事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引:厚生労働省
健康情報の管理ルールを職場で作る際に参考となる資料です。
事業者が衛生委員会などで協議の上、策定する際に参照できるものです。
雇用管理に関する個人情報のうち健康情報の取扱い留意事項:個人情報保護委員会
個人情報保護委員会による、健康情報の取扱指針です。
健康情報は、要配慮個人情報に当たるものが多く、当たらないとしても労働者の機微な情報であるとし、適正に取り扱うことが求められています。
プライバシーマーク制度:一般財団法人情報経済推進協会
個人情報を適切に扱う事業者に与えられる認証制度です。
法律への適合はもちろん、自主的に高い保護レベルの個人情報保護マネジメントシステムを確立し、運用していることの証明となります。
労働者はもちろん、取引先などの関係企業の安心にもつながる制度です。
認証制度・取り組み推進
職場環境の改善など、労働者の働きやすい環境作りなど人財への投資を行うことによる生産力の向上が各所に求められています。
それを支える制度や取り組みです。
健康経営優良法人認定制度:経済産業省
経済産業省と日本健康会議が認定する顕彰制度です。
優良な健康経営を実践している大企業や中小企業を認定し、社会的な評価を受けることができる環境を整備することが目的です。
上場企業の場合は「コーポレートガバナンス・コード」による評価がありますが。
「健康経営優良法人」は非上場企業や医療法人等でも受けることができます。
ハラスメント防止
職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が行える対策に対する指針です。
問題となるハラスメントに関しては、厚生労働省の以下のページにまとめられています。
パワーハラスメント防止のための指針:厚生労働省
「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」において、パワーハラスメントの定義や該当する例・しない例を示しています。
事業主に対する措置義務を課しているため、確実に把握しておきましょう。
まとめ
法律を元に事業者やメンタルヘルスに係る人達が行動しやすいように提示されている資料です。
なので、多くなってしまいますが。
企業の方向性に合わせ、自分の部下を守る立場である管理監督者が、メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種の対象なので。
行政の方針について理解し、より良い職場環境につなげたいものです。
この記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
抜けや漏れも大歓迎です!
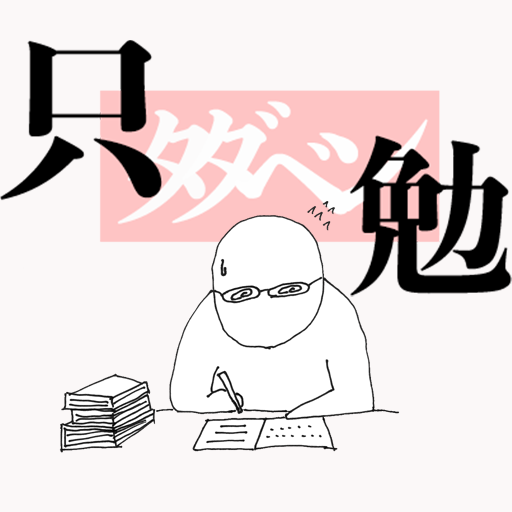
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!
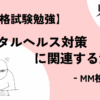

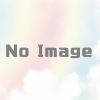




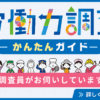
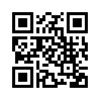
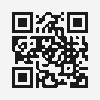
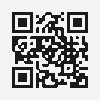
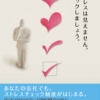
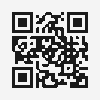


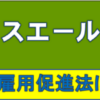
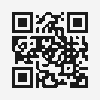
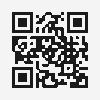
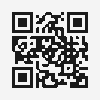
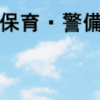
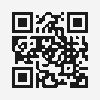
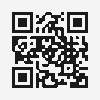
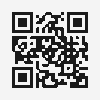




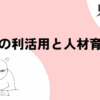
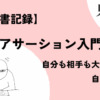
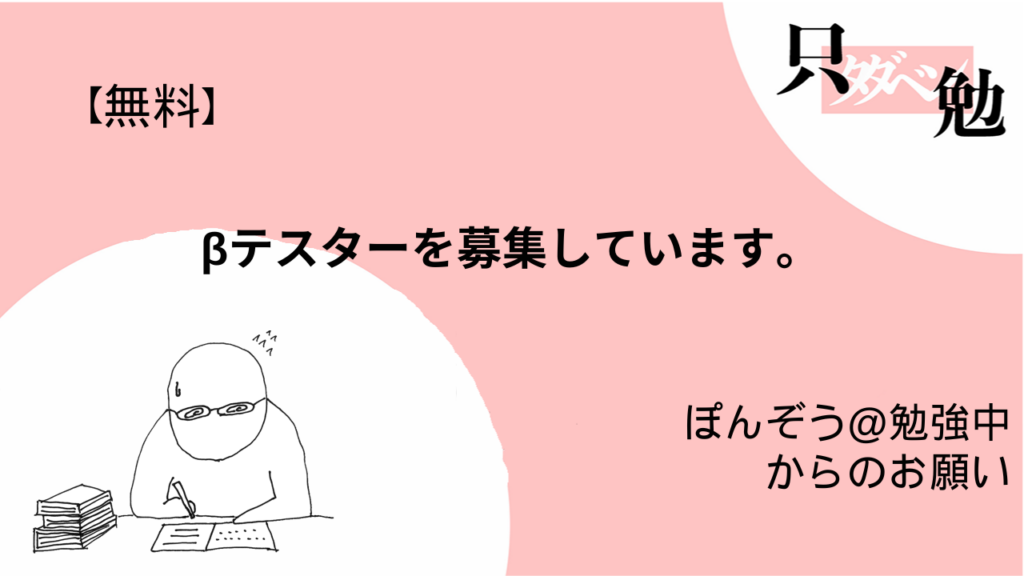
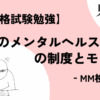
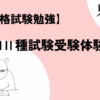
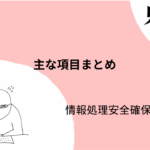
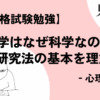
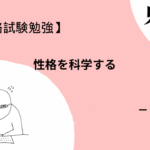

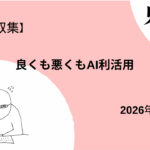
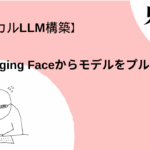
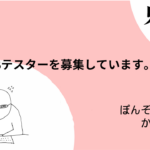
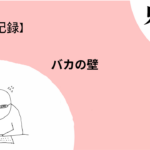
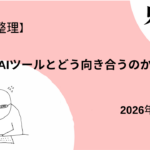
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません