【ポエム】本を読みながら思考力を鍛えるアクティブリーディング
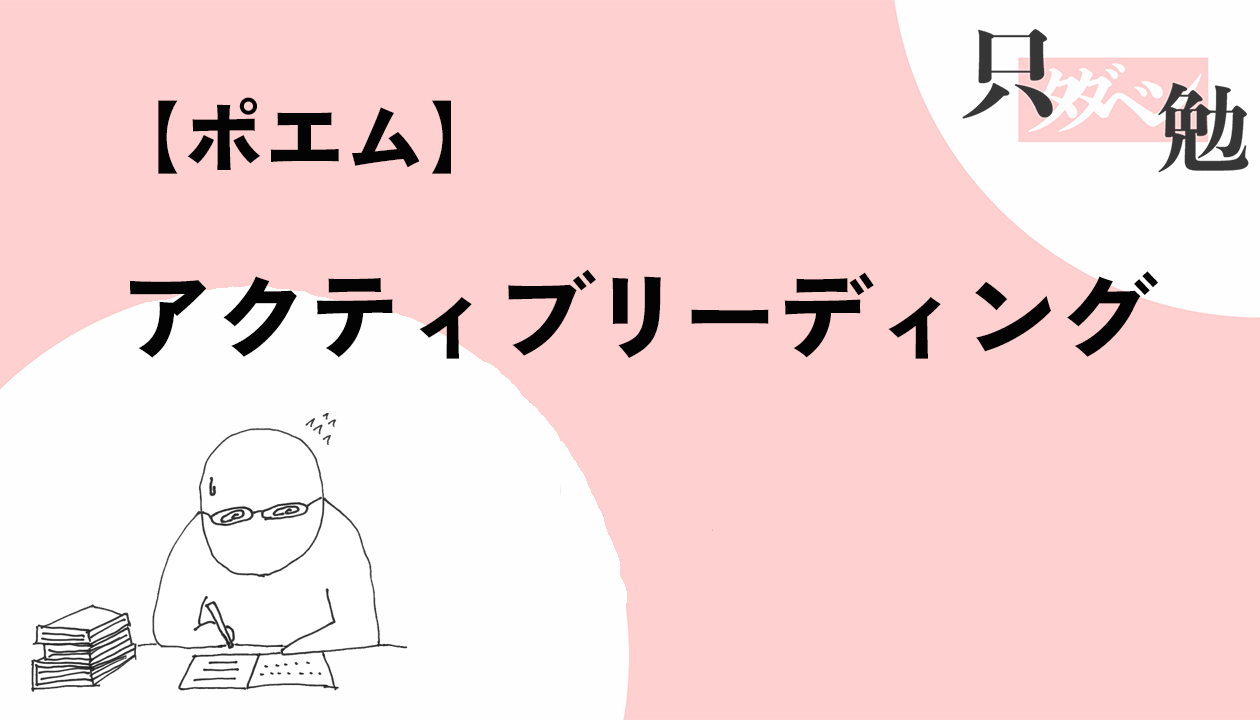
読書に生成AIを活かして、学びを深めることについて書き始めたのが、この一連のポエムです。
学びを深めるという意味では、読書後に使う方法を書いてきました。
読書中だと、分からないことを調べるという使い方ですかね。
しかし、本を読みながらプロンプトを入力するとなると。
少し本から離れて、PCやスマホをいじることになるので。
思考が止まってしまうというか、面倒になることが多いのが私です。
そうすると考えを深めるためにAIを使っているのに。
頭にはAIとのやり取りの方が強く残ってしまったりして、肝心の本の内容が頭に入らないような気がすることも。
そのような状態で読書量を増やしても、あまり印象に残らないものを積むかもしれません。
まぁ、知識として引き出しには入ってるんですけどね。
ただ、スッキリしないし、本を読んだ「だけ」というモヤモヤした状態になるかもしれません。
なので、本を読んでいる段階から、思考力を使い行動につなげる読書法「アクティブリーディング」について。
自分の体験を書いていきます。
「書く」という行動
アクティブリーディングというのは、本を読みながら書いてある内容について。
自分の考えや思ったことを、余白にメモ書きしていく読書法です。
ここで詳しく書かなくても、スタディ・ハッカーさんの記事にあるので、細かくはお任せします。
この記事によると、この読書法を実践しているのが、Microsoftの創業者であるビル・ゲイツ氏とのことです。
読書家であることは知っていましたが。
先進企業の創業者だと、膨大な量の本を読んでいるのかと思っていましたが。
年間50冊。つまり、一ヶ月で約4冊。週に1冊です。
自分がアクティブリーディングを試して見ようと思ったのはここにあって。
このペースは自分の現在の読書ペースとほぼ同じなのです。
無理なく読めて、しかも身につく方法であれば試してみたくなるものですよね。
この本の余白にメモ書きしていくというのが、読書の本質をついてるとも感じます。
読書で良く言われているのは、「著者との対話」という行為であるということです。
とは言え、読むだけになると、対話ではなく一方的に受け取ることだけになります。
対話であれば、ある意味では双方向のコミュニケーションであると。
なので、著者の書いた内容に対して、自分の考えていることや思っていることを書き留めておくというのは、まさに対話の状況を作り出しているとも言えます。
また、どこで見たかは忘れましたがー。
「読書は作者の価値観を受け取る行為である」というのもあります。
「自分はこう考えるけど、著者はこう考えているんだな」と。
自分とは違う考えを受け取る練習ということが言えます。
で、これらの受け取り方は、傾聴やアサーションに繋がっています。
どちらも、「自分はこう考える」という自分がどう思い考えているかを理解し。
それを一旦おいといて、相手の思いや考えを受け取り。
違いを認めつつ、より良い方法や解決策を見出していく。
という感じです。
対話は自分の考えや理解を深める助けにもなるので、読書にも同様の効果が見込めるわけですね。
なので、読書により「著者と対話」するために、自分の考えを直接メモ書きするのは有効なんだろうなと。
思うわけです。
「もったいない」という考え
だがしかし。です。
私は、学生の頃からあまり教科書に線を引いたり、書き込んだりするのが好きではありませんでした。
きれいな状態で使いたいという思いがあったり。
書き込んだものを後で読み直した時に、読む気が失せてしまった経験があるからです。
また、読み直す時に、以前に読んだときとは違う発見があるかもしれない。
そう考えていることもありました。
もう一つ正直に書くと、「売りやすいから」というのもあります。
なので、アクティブリーディングについても効果を感じながらも。
なかなか実践する気になれずにいました。
しかし、読んだ本の内容をブログで書くようになって、色々と困ることが。
内容をまとめて、再び読み直す時にその時に動いた感情や思いを忘れていて、うまく表現できなかったり。
読書メモも要点を書いているのだけなので、なぜ感銘や衝撃を受けたのかを忘れてしまうこともあるんですよね。
やはりアクティブリーディングを実践すべきだ!
・・・と思ったものの。
最後の壁は「売る」ということでしたw
そこで価値を比較してみることに。
本は売ったとしても・・・まぁレア本とかを抜けばですが。
10円とか、高くても500円くらいだと思います。
この金額と、本の内容から本気で何かを学び取り。
自分を変えるきっかけを得ることのプライスレスな価値。
どちらの方が上か?
10円のために、自分がこの本に感じた価値ある部分を捨てるのはもったいない。
というように思い。
書き込む事ができるようになりました。
その結果、記事を書くのもスムーズになりましたし、以前よりもどこに何が書いてあるかを理解できるようになりました。
私はこのように壁を取り払いましたがー。
・ふせんに書き込んで、貼っておく
・消せるように鉛筆やシャープペンを使う
というのでも良いと思います。
目的は、本の余白に書き込むことではありません。
読書中に動いた自分の感情や考えを、分かりやすく残すことです。
「書く」ことの効果
私が「書く」ということに壁を感じていたのは、どちらかというと印象の部分で。
行動に対してはあまり壁を感じていませんでした。
その理由が、これまでの学習経験を通じて、「書く」という行為がないと記憶しにくい特徴があることをわかっていたからです。
「書く」という行為は、自分の思いや考えを表す行為です。
これは「生成効果」というもので、「読む」という受け身の状態よりも、記憶が定着しやすくなるという効果です。
最近はリスキリングなどで「学び方」についての情報を良く見かけますが。
講師の板書をただ写すのではなく、自分の頭の中で整理しながらノートに書く、というのは「生成効果」を促しているのでしょう。
また、自分の思いや考えを文字にすることで、目に見える客観的な情報に変換されます。
つまり、本の該当部分を読んで。
・自分が感じた印象
・自分が考えたこと
・自分が疑問に思ったこと
というものが、可視化されます。
それにより、自分が何を理解していて、何を理解できていないかを把握することができるようになります。
これが「メタ認知」というもので、ただの印象ではなく、思考を深めるきっかけにすることもできます。
余白に書き込んでおくことで、書いたその時には考える時間が取れないとしても。
あとで時間を取り思考を深めることもできます。
このように、「書く」という行為をすることによって、読書中から自分の思考を深め、記憶に刻むことができるのです。
より深い思考でAI読書を実行
AI読書は自分が受けた印象などを元に、本に対する理解を深める手助けになります。
読書中にアクティブリーディングを行い、本の内容に対する自分のポジションや考えを明確にしたうえで、AI読書を実行したらどうなるでしょうか?
自分の思考力を使い、集中して読書を進めることで、内容を脳に定着させることができますし。
読んだときの感情や考えを記録しているので、その時の印象を思い出すこともできます。
その状態で、メモを作成し、AIと対話することで。
より自分が本から学び取ったこと、活かしたいことを明確にできるはずです。
AIは基本的には人間が喜ぶような反応を返します。
自分がAIに相対した状態で、AIの反応の深度もかわると考えて良いでしょう。
つまり、アクティブリーディングで深めた考えをさらに深めるための質問や、思考を広げる視点の提案をしてくれます。
なので、自分自身の思考を深める読書術は、AI活用にもつながるものなのです。
読書中から楽しい時間を
アクティブリーディングの実践により、読書中から自分の思考力を鍛え、有意義な時間を過ごすことができるようになります。
その思考を深める効果が、AIを利用することです。
なので、アクティブリーディングを利用した読書>まとめる>AIの利用、という習慣をオススメします。
自分は、現段階でのAIは「脳の拡張」と捉えているので。
自分の思考力を使いつつ、それを加速または深化させるのにAIを使っていきましょう。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。


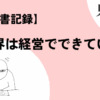
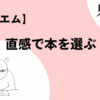

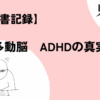
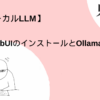
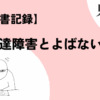
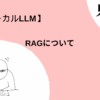

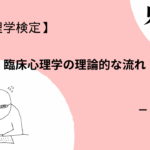
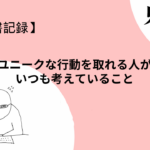
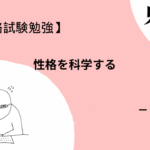
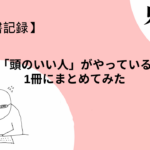
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません