【読書記録】最高のコーチは教えない(著者:吉井理人)|「コーチング」というつなげる技術
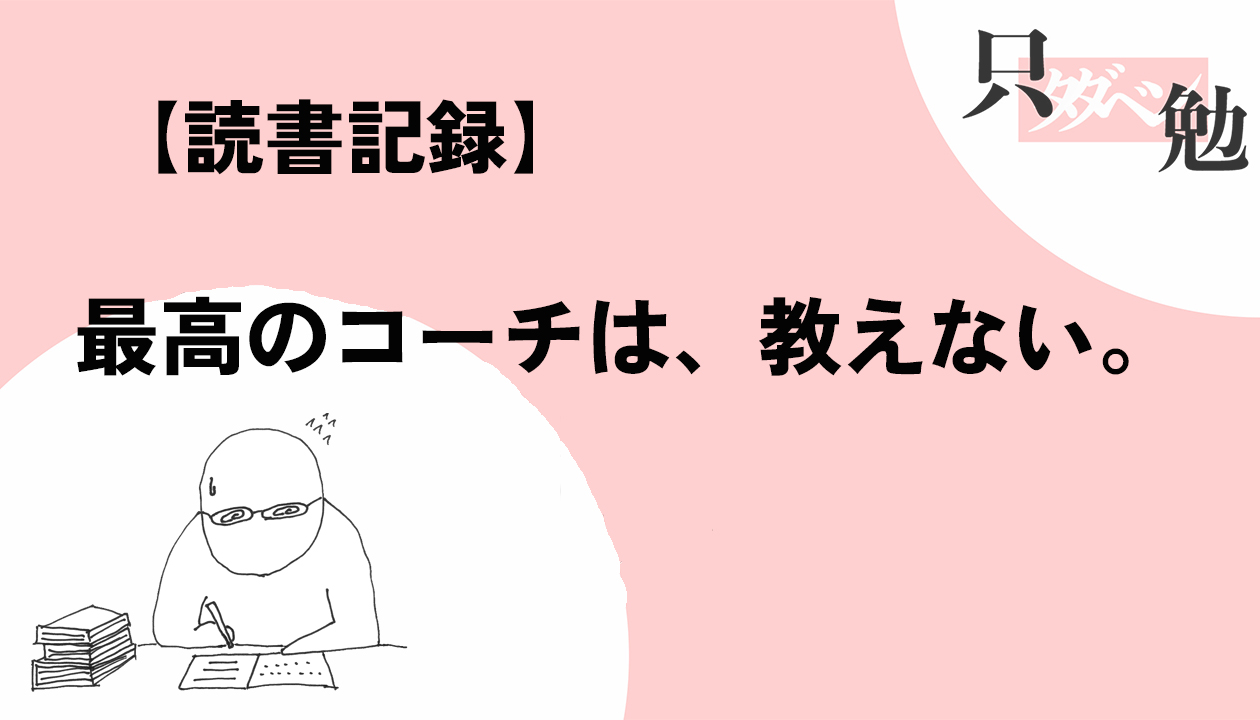
コーチングとは、1対1という関係性の中で、目標達成や自己成長を支援するコミュニケーション技法であると、紹介されることが多いです。
マーケティングの意味合いで流れてくるものを見ると、どう考え方を変えるのか、捉え方を変えるのかといったものが多い印象です。
他者との関係性を構築する技術として学びたいなと思った時に、選択肢にあげていたんですがー。
少し求めているものと違うように感じ、先延ばしにしていたものの、胸に引っかかっているものがありました。
が、「聞き方」について書いた記事で参考にした資料の中心に感じたのが、コーチングの技術だったこともあり。
一度、コーチングについての知識を入れないとなぁと思い始めたころに本棚でみかけたのが、今回の本「最高のコーチは教えない」です。
読み終わった感想は、「コーチングの技術をつなげる技術にするには?」というもの。
組織の中間管理職の立場にいる方には、参考になることが多いのではないでしょうか。
コーチは中間管理職?
バリバリの文系野郎なので、あまり体育会系のノリは分からないんですがー(文系のノリも良く分かってませんけどね)。
コーチというと、教え、導いてくれる人という印象があります。
技術的にも、精神的にも、信念と理論に基づいた指導者というような感じです。
この本の著者である吉井理人さんは、1984年から2007年までプロ野球選手として大リーグでも活躍され。
その後、コーチに転身してから身につけたことを本書で説明しています。
・・・正直、野球の事は良くわからないのですが・・・
美容院の待ち時間でこの本を読んでいたところ、お世話になっている美容師さんも知っていたので。
すごい方なんだと、思います。
で、この本を手にした理由は「最高のコーチは教えない」というタイトルです。
先程書いたのように、「教えない」というスタンスは自分のコーチ像からはかけ離れていたので。
コーチングについて学ぶには、入りやすいかも!・・・と思ったわけです。
私自身が、今まで経験して来た仕事の中で人の教育に当たることが多かったんですがー。
その時に心がけていたことを言語化してもらえてるようで、文章の読みやすさもありスラスラと読めてしまいました。
その中から、「最高のコーチ」の本質は、選手自身が考えて自ら答えを見つけられるようにフォローすることであり。
それとともに、『つなぐ』役割があるということを学べました。
「プロ意識」の拡大
本書を読んでいた時に身の回りに起きていたことで、タイムリーだったのが。
「プロ意識」についての部分でした。
プロ意識とは、自分のパフォーマンスを上げるための思考・行動を、すべての思考・行動に優先させる意識である。
第2章 コーチングの基本理論 P.90
コーチが選手に持てるように助ける意識として、「プロ意識」について説明され、引用のように定義されています。
以降も「プロ意識」について触れる部分では、コーチングの対象である選手にどのように促す事ができるか説明されています。
そして、最後に理想とするコーチ像について書かれている部分に、このような文章がありました。
だから、僕もコーチングのすべてといったノウハウを身につけるのではなく、時代によって、相手によって、そして常に自分も変化することによって、誰かにとって最良のコーチングに近づきたいと願っている。そのプロセスに終わりはない。コーチという職業を続ける限り、プロセスを歩み続けることで一生を終えるような気がする。
おわりに P.265
この部分を読んで感じたのは、吉井理人さんの持っているコーチとしての「プロ意識」でした。
コーチとしての自分のパフォーマンスを最大にすることで、選手のパフォーマンスを最大にできるようにする。
決意のようなものを感じました。
選手であるうちは、自分が最高のパフォーマンスをできるように「思考・行動を優先」させますが。
コーチという立場になれば、自分の感情や態度、言動をコントロールし、コーチとしての最高のパフォーマンスを示しつつ、選手が自分のパフォーマンスを上げる状況を提供するということが目的となってきます。
技術や理論というものを教えることもありますが、メインは「プロ意識」を促すための環境や関係を作ることであるということなのかなと。
自分自身がもつ「プロ意識」により、相手の「プロ意識」も刺激する。
それが、コーチと選手を『つなぐ』役割のように感じます。
これは普段の職場でも言えることで。
自分自身のパフォーマンスはもちろん、誰かの面倒を見る立場であれば、その人が最高のパフォーマンスを発揮できるように状況や関係を整える事が大切だと私自身感じています。
今は人手不足なため、上司に当たる人たちも作業をしつつ、管理・教育を並行しなければならない状況が良くありますが。
上司・部下の関係で、一緒に働く相手とどのように関わるべきなのか。
身近で起きていた出来事と共に、考えさせられた部分です。
言語化と翻訳
もう一つの『つなぐ』役割は、自分を中心とした上司と部下に対するものです。
本書の中にコーチの役割の一つとして「翻訳」があげられています。
監督など組織の上層部の方針や意見を、選手に分かりやすく伝えるという行為のことです。
強いチームや組織は、一つの目標に向かってみんなで向かう姿勢があると言われます。
全員が向かっている目標や成し遂げたいことなどを、自分ごととして捉えている状態、とも言えるでしょうか。
しかし実際には、規模によるとは言え、なかなか浸透しないというのが事実でしょう。
なぜなら、上層部と現場で見ている景色が違うからです。
そのためお互いに理解できず、上層部は「やってくれない」、現場は「理解してくれない」というすれ違いが起きます。
そのため、コーチのような上層部と現場をつなぐ中間管理職の存在が重要になり。
「翻訳」という行動が必要となるのです。
指導者の言っていることが理解できない、ビッグすぎて怖いと毛嫌いするのは、選手にとっても大きな損失になる。手前みそだが、だからこそ僕のような「翻訳者」の存在が非常に重要になる。
<中略>
相手が理解できない言葉で、相手に何かを伝えても意味がない。
第1章 なぜ、コーチが「教えて」はいけないのか P.43~44
現場レベルで部下が考えていることと、マネジメントの立場で上司が考えていることの間に「ずれ」が生じ、上司の無理解に部下が腹を立てる。その齟齬を翻訳して埋めるのがコーチの重要な役割だ。翻訳するときには、直訳ではコーチの存在が意味を持たない。ある程度は腹をくくり「意訳」する覚悟も必要だと思う。
第4章 最高の結果を出すコーチの9つのルール P.236
私自身が感じていることでもありますし、高度情報化社会の現在だからこそ、各所にこのような「翻訳者」の存在が必要であると考えています。
そして、「翻訳」や「意訳」するためには、コーチ自身がその上層部の言う事を自分の言葉で説明できるレベルにまで落とし込む必要もあるでしょう。
ここらへんの理解の技術についても色々ありますが、それはおいといて。
その理解したことを、選手・部下に伝わるように「言語化」しなければなりません。
本書の中では、選手の言語化能力を高めて、思考力を固めるように促すことができる、という文脈で使われていますが。
上層部の言葉を理解して、選手・部下に自分の言葉として伝えることにも「言語化」は必要です。
選手・部下にとっても、直属の上司であるあなたの言葉の方が、たまに見る経営陣の言葉よりも響きやすい。ということはあると思います。
コーチ自身も勉強し続けなければなりませんね。
環境を作る
上の立場の人は、良くも悪くも空気を作ってしまいます。
上下関係が発生するだけで、空気が変わるというか、壁を感じる瞬間もあると思います。
先程書いた、すれ違いの原因にもなってしまうものです。
なので、「教えない」のではなく『伝わりやすい』環境を作るヒントが、この本にはあります。
文章自体が読みやすいですし、参考になりそうなセクションを拾い読みするのでも良いです。
コーチや上司という立場を中心に書いてきましたが。
人と関わったり、何かを成し遂げる場合に、緊張状態というものは起こり得ます。
そのような時でも人と人を『つなげる』ために。
本書の内容は参考になると感じました。


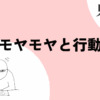
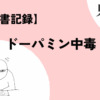

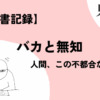
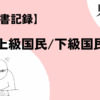
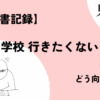

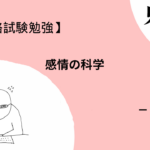
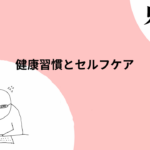
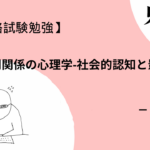


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません