モヤモヤを行動に変えてスッキリ
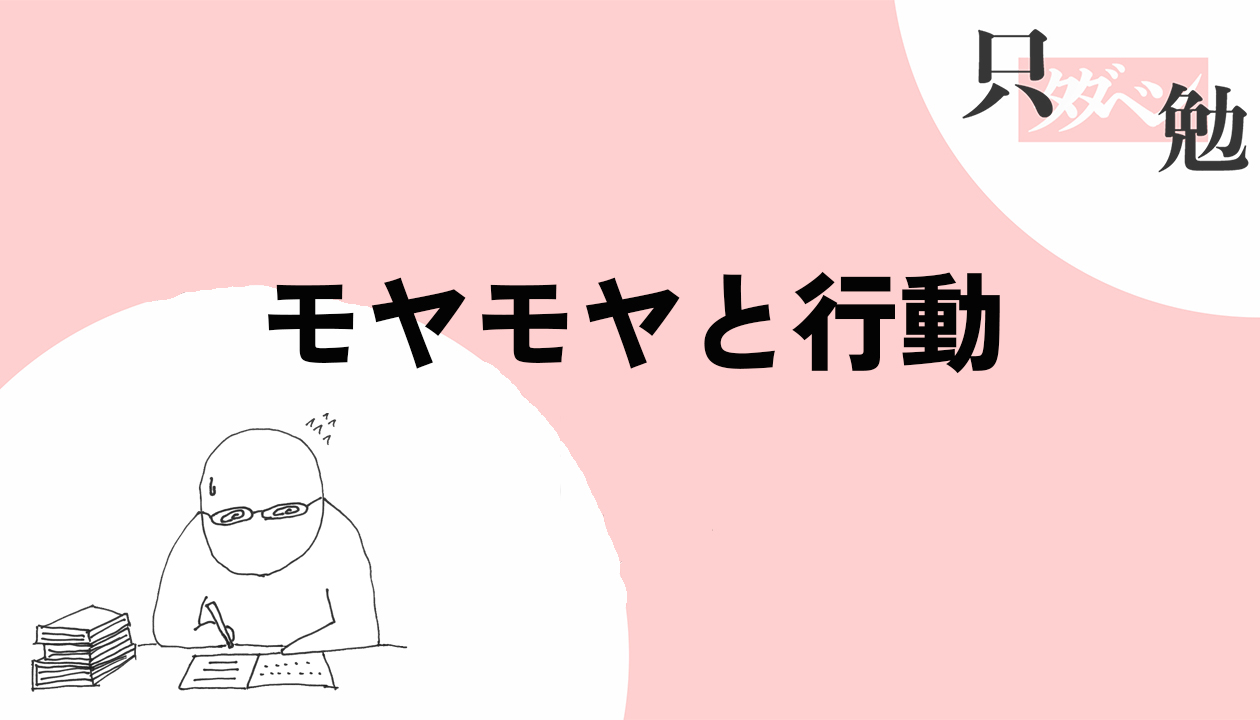
「なんだかモヤモヤする・・・」という経験は誰にでもあると思います。
ある日、会社の同僚が仕事に対する悩みを抱えているものの。
原因がこれと言ってわからずモヤモヤ・・・という感じでした。
社内では重要なポジションについている人のため、パフォーマンスが下がるのはもったいないなぁと思い。
悩みの整理を手伝うことにしました。
と言っても、思いつきのような感じで始まったので、どうなるかなぁと不安でしたが。
終わったらスッキリした顔をしてたので、少しは解消できたかなと。
今回は、会話しながら整理していった内容を紹介してみようと思います。
できるだけ具体的に書くので、お読みいただいた方の参考になれば幸いです。
早速行きます。
ステップ①:悩みのタネをすべて書き出す
まずは、頭の中にある「モヤモヤ」を聞き取り、ホワイトボードに書き出して行きました。
一人の場合には、紙やノートにどんどん書き出してみてください。
どんなに些細なことでも、抽象的でも、自分の「モヤモヤ」を表せていれば良いです。
今回は会話の中なので自分も見ましたが。
「モヤモヤ」を抱えている本人が見るものなので、どんな表現でもOKです。
書くのが苦手でもOK
文字にするのが苦手なら、信用できる人と話してみましょう。悩みを打ち明けることになるので、家族や上司など信頼できる人に頼み、安心できる状態で行いましょう。生成AIとの壁打ちでも良いかもしれません。ただし、会話ではなく「自分の話す内容」に集中してください。
ショックを受けたら無理をしない
文字にすると「モヤモヤ」を視覚的に理解することになります。そのため、ショックを受ける場合があります。自分を楽にするための作業なので、少しでもつらいと感じたら、中断し休憩を取るか後日にしましょう。実際、同僚も顔がこわばり、休憩を取った瞬間がありました。
紙に書くルールを決める
真っ白な紙やノートに自由に書くことが、心理的な壁になる場合もあります。そのような場合は、「A4用紙1枚に収める」「紙に枠を書く」など、あらかじめ制限を設けると書きやすくなります。あくまで、負担にならないようにで実施してください。
ステップ②:書き出したものを分類する
次に、書き出した悩みを2つのグループに分けました。
1:自分ひとりで解決できるもの
2:自分ひとりでは解決できないもの
この時点で明らかになるものは、大体この2つに分類できます。
「1:自分ひとりで解決できるもの」は、自分自身の行動を変えれば解決できるものです。
例えば、「体力がない」の場合は「毎日寝る前に腕立て10回する」などです。
どんな単純な行動が、悩みの解決に繋がるかを考えて実行しましょう。
これで、悩みの一部が解決に向かいます。
「2:自分ひとりでは解決できないもの」は、他者との関係や外部環境に原因があると考えられるものです。
関係する人の行動や協力が必要なもので。
「モヤモヤ」の原因は大体こちらの悩みであることがほとんどです。
ステップ③:割合を設定してみる
私達の悩みのほとんどは対人関係と言われています。
つまり、自分と相手との関わりによって起きるので、「2:自分ひとりでは解決できないもの」という悩みがほとんどです。
こちらに分類した悩みに対して、自分と相手にどの程度原因があるかを考えて設定してみましょう。
関わりによって発生するものなので、視点が違うだけでお互いに何かしらの問題を感じている状態だと言えます。
うまく設定できない場合は、どっちもどっちということで。
「自分50%:相手50%」から考えてみてください。
悩んでいるとどうしても相手のあら探しをしてしまいますが、割合を考えることで相手だけでなく自分にも目を向けることができます。
悩みが起こる状況を想像してみて。
その状況において、自分の言動や態度が関係していそうな割合と、相手の言動や態度が関係していそうな割合や。
その状況の空気の中で、その言動や態度が影響を及ぼす範囲を考えるのも有効です。
例えば、上司の不機嫌な態度で空気が悪くなり、それによって自分の挨拶の声が小さくなり、周囲もピリつく・・・という場合。
「自分20%:相手(上司)80%」というように考えられますかね。
同僚は数字が苦手でしたが・・・「自分50%:相手50%」で納得してました。
ステップ④:自分の問題と相手の問題を書き出す
あげた悩みそれぞれに割合を設定できたら、次は悩み1つずつにある「自分の問題」と「相手の問題」を書き出してみましょう。
その時に、可能であれば「解決後の理想の状態」も具体的に創造してみてください。
「こんな状態なら良いな」という単純なもので良いです。
例えば、「上司との関係」が悩みだという場合。
「上司と良い関係を築きたい」という想いが見えてきます。
そこから、その想いを邪魔している自分の状態・気持ちを追ってみると。
「上司に話しかけるのが怖い」という問題を抱えているとします。
そのように感じてしまう原因が、「上司が怖い雰囲気を出している」であることに気付き。
この2つが解決される、「上司と気軽に相談しあえる関係になる」ことが、解決後の理想の状態して思い描きます。
これをそのまま書き出す感じです。
このままでも「上司に話しかける」という行動に移せそうですが。
上司の怖い雰囲気を感じたままだと、続けることが難しいかもしれません。
理想の状態を叶えるためには、一時的に話せるようになるだけでは足りないでしょう。
また、例にあげたような行動が思いつきやすいものを問題としてあげられるとも限りません。
同僚の場合は、「率直に話し合える状態にしたい」とか、「チームワーク良く連携したい」というものでした。
例も同僚の場合も、思いつく行動が多い上に、行動のハードルが高いものを想像しやすいものであるとも言えます。
そこで、次のステップに進みます。
ステップ⑤:問題を具体化する
自分の行動を変えるには、ストレスなく行動できるレベルまで落とし込むことが大切です。
習慣にできれば、自然な行動として無理なく継続することができ。
時間が必要な問題の解決にも自然に取り組む事ができます。
ステップ④で上げた問題が抽象的であればあるほど、このステップ⑤の手順が行動に移す鍵を握ります。
問題の核心を明らかにし、悩みの原因を突き止めることに繋がります。
先程の「上司に話しかけるのが怖い」の例について、まずは1つ目の質問に答えます。
なぜそれが問題なのか?
「上司に話しかけるのが怖い」と、どのような問題を引き起こすかを具体的に考えます。
自分自身が「上司に話しかけることが怖い」と思っていることで、実際にどんな影響が出ているかです。
例えば、「話しかけたい時に話しかけられず、聞きたい時に聞けていない」という答えとします。
仕事上で内容の確認や、案件の不明点の確認など。
様々な状況で起こり得ることではあります。
現実に起きてしまっている問題・影響を明らかにしましょう。
誰に影響があるのか?
どの程度の割合で、自分と相手に悩みの割合があるかを設定しましたが。
「なぜ問題か?」を考えた次に、割合を元にして、明らかにした現実に起きている問題の結果。
影響を受けている又は影響を受ける可能性がある人が誰かを想像してみます。
これには2つの意味があると思っていて。
まずは、問題の影響の範囲を客観的に知ることができるということです。
「悩んでいる」状態というのは、個人的なものです。
「悩んでいそうだな」と見てて思うことはありますが、実際に悩んでいるかどうかは本人にしかわかりません。
なので、一人でモヤモヤと悩むことになり、自分の思考や感情に集中してしまいやすくなります。
そこで、この問題を放置することで影響がある人をあえて考えてみましょう。
例えば、母親と喧嘩して関係が悪くなってしまい、気まずくなってしまった場合。
同じ空間で過ごす人に、父親や兄弟姉妹がいるでしょう。
その父親や兄弟姉妹にどのような影響があるでしょうか?同じ空間で楽しく過ごせるでしょうか?
「自分には関係ない」と考えられたり、いつもの光景だとしても。
ため息が出るぐらいの気持ちではあるかもしれません。
こう考えると、放置して良い問題ではないことが分かります。
このように影響が出る人を考えることによって、問題の中に自分と相手に加えて第三者の存在がいることに気づけます。
これが2つ目の効果で、問題の解決に繋がる協力者の存在に気づくことができます。
相手に直接行動を起こさなくても、協力者に対して起こす行動を選ぶこともできるわけです。
あなたがモヤモヤし、元気がないというだけで、影響を受ける人もいるのです。
どんな不都合がおきているのか?
これも「悩んでいる」という状態に関係するものですが。
「悩んでいる」ときは、その問題に対して何かしらの行動を起こせていないことがほとんどです。
つまり、自分の思う通りに動けていないから悩みになっているとも言えます。
どんな行動が制限されているかを考えてみましょう。
この時に、一つ前の質問「誰に影響があるのか?」も参考になります。
例えで使っている「上司に話しかけるのが怖い」という問題の影響が、「自分と情報不足で困る可能性のある同僚」だと分かった場合。
聞きたいことが聞きにくかったり、確認してもらいたいけど小さいことだからと判断してしまったり。
手順を間違えてしまい、見積もりよりも時間がかかってしまう。
という状況になるかもしれません。
自分が安心と確信を持って仕事を進めることが制限されていると言え、「仕事の進行が遅れる、小さなミスを見過ごしてしまう」という不都合が生じていると気づくことができます。
「不都合」から考えて、「誰に影響するか」を考えるのでも良いですね。
ステップ⑥:悩みの関連性を見つけ順番を決める
ここまでのステップ③〜⑤は、ステップ②であげた「2:自分ひとりでは解決できないもの」全てに行います。
それぞれで、問題と考えられる状態、問題に影響される人たち、それによって現実で起きている問題、という3つの要素を見つけています。
それらの関係性を考えることで、関連する要素を見つけることができ。
その結果、一つの行動を起こすことで、複数の悩みに対処できる可能性があります。
今回一緒に考えた同僚もそうですし、このステップの流れは個人でやることも多いのですが。
悩んでいることに対して上がってきた複数の問題は、何かしらの関連を持っていることが多いです。
その関連性を見つけたら、整理するためにそれも文字にしてしまいましょう。
例で言うと、起きている不都合として、「挨拶がしにくい」ことや「メンバーが空気を読み合っている」という問題があるとします。
この問題の関係性を考えると。
「挨拶がなくて、その日の機嫌や調子がわかりにくいから、空気を読み合うようになっている」
というものが浮かんできます。
これを少し組み替えて、「空気を読み合ってしまうのは、挨拶がないせいでその日の機嫌や調子がわかりにくいから」と考えると、この悩みで解決を優先すべきなのは「挨拶がない」ということが分かります。
「挨拶があれば、その日の機嫌や調子が伝わりやすくなり、空気を読み合わなくなるかもしれない」という仮説ですね。
このように、取り組む順番を明確にします。
ステップ⑦:単純なレベルまで落とし込む
順番が決まると、大まかな行動が決まって来ているでしょう。
例だと、「挨拶をする」ということになりますが。
これを自然な習慣として身につけるために、単純な行動のレベルまで具体化します。
例えば、「朝、上司のデスクの前を通る時に、『おはようございます」と大きな声で挨拶する」
と言った具合です。
こうすれば、挨拶のタイミングが分かりやすく、続けやすくると思います。
この単純なレベルに行動を落とし込むときのポイントがいくつかあります。
相手の行動に期待しない
考えるのはあくまで「自分の行動」です。相手の行動を期待すると、続けることができなくなったり、新たな悩みになってしまう可能性があります。自分の行動でどのような影響を与えたいかに集中します。人間は基本的には変化が苦手で、相手を変える労力は膨大でしかも効果は見込みにくいです。自分の行動に集中する方が、悩みの解決に近づきます。
解決へのアプローチに集中する
自分の行動を変えることが、解決に繋がります。なので、どうやって行動のハードルを下げ、解決にアプローチするかに集中します。ただし、解決に近づかない行動は選ばないようにしてください。「上司と何でも言い合える関係になりたい」のに、「頻繁に席を立って、注意を向けてもらえるようにする」というのは逆効果です。
優先度が高い一つの問題への行動でも良い
すべての問題に対して行動を決めることが理想ですが、関連性を見つけにくかったり、複雑でわかりにくい場合があります。そのような場合は、自分が求める理想的な状態に近い、優先度の高い問題の行動を一つだけ決定するのでも良いです。一つ変えることができれば、その他の問題を解決につながったり、新しい行動のヒントになることもあります。
自分の行動を変えれば、相手の行動も変わると信じましょう。
急に胡散臭くなりましたがーw
ポイントに書いた通りで、確実に変えられるのは自分の行動です。
相手に配慮した行動を選ぶことも重要ですが、基本的には自分が扱われたいように相手を扱えば、相手はそれを返してくれます。
心理学にある「返報性の法則」や「鏡の法則」が勇気をくれます。
自分の行動によって、相手が同じような行動を返してくれるという心理効果です(ざっくりですが)。
ここらへんは、「人望を集める人の考え方」に詳しく書いてあります。
ステップ⑧:行動を誓う
行動が決まったら、後はやるだけです。
考え終わったら、即移しても良いと思いますが。
急激に変化させたくない場合は、「いつまでに行動するか?」を決めておき、自分自身と約束しましょう
小さな行動を積み重ねる
モヤモヤとした悩みは、これまでに書いてきた通り、人の行動に制限を加えてきます。
動けなかったり、状況を我慢するだけの状態から抜け出すためには、小さなことでも行動を変え積み重ねることです。
この小さな行動が、自分の抱えている悩みや不安の開放へとつながっているので、希望をもって続けることもできるでしょう。
同僚もチームメンバーに良い影響を与えるために、単純な行動をみつけられ、スッキリした顔をしてました。
ぜひ、試してみてください!
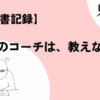
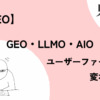
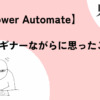
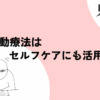
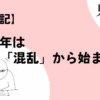
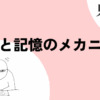


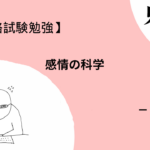
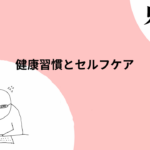
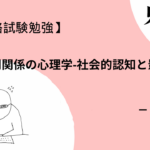


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません