AIを読書のパートナーにしてみる
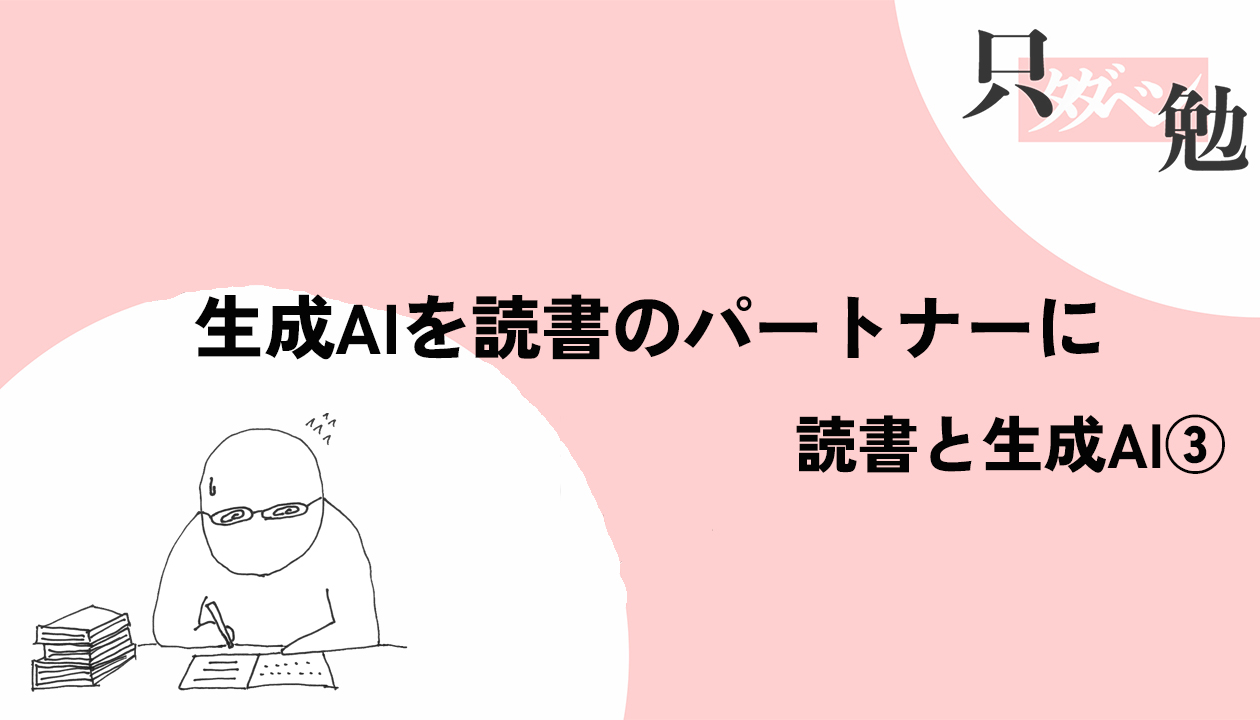
「本を読んでも、読んだだけで終わってしまう・・・」
これはまさに私のことで、アウトプットすることで身につけるようにしたいと思い。
読書記録という形で、記事にしているのが私です。
そんな本から得たものを行動に変えるために、生成AIが活用できるということについて書いたのが前回です。
この記事でも書きましたが、生成AIが得意とする要約や、対話形式で思考を深めるチャット形式のUIなど。
これらを読書「中」にも活かすことで、呼んでいる時から学びを深めることができるのではないか。
そんな、生成AIを読書のパートナーにする事について、書いて行きます。
理解を深めるパートナー
要約とは、文章の要点を簡潔にまとめることです。
生成AIは要約が得意なので、情報の整理も得意です。
それを私達が普段から使用している言葉で表現してくれるので、内容の理解を助けてくれます。
業務の合間に「あれ?これってどういうことだ?」と疑問が浮かんだ時。
ざっくりと概要だけ抑えられれば良い時に、生成AIは便利です。
CopilotやGeminiなどWEBから検索した情報を参照することもできるAIもあるので。
情報の新しさという面でも、心配は減ったなぁと思っています。
この手軽さを読書にも応用してみましょう。
辞書や参考書代わりに
本を呼んでいると、言葉の意味が分からない単語や、理解するのに難しい概念が解説されている場合があります。
そのような時、辞書を引いたり、WEBで検索して概要を把握したりして、理解しながら読書を続けますが。
読書が中断されるストレスもあり、そのまま読み進めてしまう場合もあるかもしれません。
「知ったかぶり読書」は・・・自分もやってしまいますね。
辞書を引いたり、検索したりすれば良いんですがー。
そこに生成AIを使うと、即座に返答があるのはメリットですね。
WEB検索でも十分なこともありますが、ブラウザを開いたり、情報が載っていそうなサイトを選んだり。
意外と本から離れる時間が長くなってしまいます。
生成AIであれば、アプリやウインドウ一つで済むので。
読書の流れは途切れにくいですねぇ。
情報を処理させる
調べても良く分からない概念の部分を、生成AIに説明させるということもできます。
この場合は、電子書籍などの方が楽かもしれませんが。
手入力の場合はポイントのようなところを箇条書きで入力していくのでも、大枠は良いかと。
そうすれば、難しいと思っていた内容と文脈を処理し、解説を生成してくれます。
また、マインドマップの生成をお願いすれば、一時期解説系のyoutubeで使われてたような論点整理の可視化もできますし。
相関図の生成による全体像の把握も視覚的にできるようになります。
画像生成AIを使えば、情景を想像する助けになるかもしれませんね。
視覚情報は文章の理解を助け、深めるものなので。
読書がさらに楽しくなる要素でもあります。
挿絵の多い少ないにかかわらず、視覚情報を用意できるのはとてもありがたいなと。
・・・まったく画像を掲載していない私が思いましたw
理解を深める助け
人間の学習や記憶のプロセスでは、「繰り返し」に大きな効果があり。
それと同じくらい効果が見込めるのが、「小テスト」だそうです。
学生時代はなんで毎週テストをやるのかと思っていましたがー。
社会人になり勉強をしていると、テストが無い分、流すような勉強が増えたような気がしています。
試験などの区切りがあれば別ですが、特に無ければ「読んで終わり」「問いて終わり」のような感じに。
それを防ぐために、生成AIでアクションプランを作りましょう、というのが前回でしたが。
もう少し手前で、「小テスト」を作ってもらうことも効果的です。
電子書籍であれば、そのまま使えますし。
手書きのメモを打ち込んで、内容を生成AIに理解させるのでも良いです。
その情報を元に、クイズを作ってもらえば、楽しめる上に復習にもなるという。
文章読解の訓練にもなりそうですし、メリットが大きい使用方法ではないかと。
文章構造の把握
読みたい本はたくさんありますが、あまり速読が得意ではないのが私です。
まぁ訓練自体してないんですが。
そうすると、各章毎に読み進めるような形になり。
後半を読む頃には前半のことがうろ覚え・・・ということが良くあります。
ふせんを貼ったり、線を引いたり。章ごとにメモを作ったり。
これでなんとかしのいできましたが、本全体の構造や論理構造は抜けてしまうことも。
そこで、生成AIに文章の構造や論理構成を説明させることで、全体の構造と各章の役割を意識しながら読み進めることができます。
読み進める以外にも、自分が理解したことと、文脈の整合性を測るのにも使えるので。
論理的に内容を理解する助けになりますね。
そのままアウトプットに繋がる
で、このように読み進めると。
読み終わった時点で、本全体としても、各章毎にも、よく分かっていると「思える」状態です。
その感動をアウトプットすることで、さらに理解を定着させ、体に染み込ませることができます。
前回の記事の具体的なアクションプランに落とし込んだものも良いと思いますし。
文章構造から、本のポイントを説明するのも良いと思います。
伝えたいことを伝わりやすくするために、生成AIの力を借りることです。
アウトプットを作っている最中でも、生成AIと対話することになるので。
自分自身が本から受けた影響を言語化し、しかもわかりやすい形で提供できます。
・・・といいつつ。
書いている内に、冷静さを自分の気持ちが上回って、全然違うことを書いている事も多々ありますがw
まぁ、それもアウトプットに向けた対話がなければ、自分でも気付けない気持ちかもしれませんしね。
どちらにしろ、本の内容を自分のものにする助けになると言えます。
注意点は忘れずに
毎度のような感じですが。
このように便利だし、希望が膨らむ生成AIですが。
利用する人に良くも悪くも寄り添うので、AI利用時の注意点は変わらずです。
読書中の理解に繋がることでもあるので、特に注意しないと間違った情報を得てしまうかもしれません。
ソースは確認する
なんとなくイメージできるものであれば、自分で判断できますが。
知らなかったことや分からないことについて生成AIに尋ねたら、提示されているソースを確認するようにしましょう。
ハルシネーションの問題は、AIと切っても切れない関係なので。
正確な理解に基づき、読書を楽しむために忘れないようにしましょう。
提示されたソースを参照することで、新たな出会いがあるかもしれませんしね。
プロセスやニュアンスは自分で把握する
生成AIはあくまで文章やメモの要約を出力するに過ぎません。
内容を理解しているわけではないというところでも注意です。
構造や文脈を確かにわかりやすくしてくれますが、著者の考えの流れや微妙なニュアンスを汲み取れない場合もあります。
また、例示されていることからの教訓も、文章中に触れられていなければ飛ばしてしまうかもしれません。
あくまで本を読む私達自身じゃないと、拾えない情報があることは覚えて起きましょう。
読書そのものを楽しむのは、あくまで私達自身です。
自分の考えも持つ
本の内容について生成AIと対話して理解を深める場合。
扱われている内容について、自分の意見を持っておくことも必要です。
生成AIが生成する情報に左右されている状態だと、本ではなく生成AIの出力を理解したことになってしまい。
本来の学びとはズレたものになってしまうかもしれません。
主張とまでは言いませんが、自分が持った感想を元に、生成AIとブラッシュアップしていくというイメージで、使いたいものです。
著作権に注意
入力した本の内容はもちろん、生成AIが出力した情報は他の人の著作物が含まれている可能性があります。
個人的な利用の範囲であれば問題にはなりにくいですが、SNSやブログなどで発信した場合、著作権の侵害になってしまう可能性はあります。
なので、出力の情報をそのまま使うのではなく、自分の言葉に置き換える事も必要です。
せっかくの感動の共有に水をさされたくは無いですからね。
生成AIを有意義なパートナーに
生成AIを読書中に活用してみるとどうなるかを書いて来ました。
書いてる自分自身が、少しワクワクしてくるような効果を感じてしまいます。
生成AIのチャット履歴が残ることも考えると、読書メモとしてそのまま活用することもでき。
振り返るのにも有効なツールと言えます。
・・・と、この記事を書くために準備している時に。
「notebookLM」がぴったりじゃないかと思いました。
さすが「notebook」です。
自分に合ったツールで、生成AIをパートナーにした読書を楽しみましょう。
本に限らず、生成AIを文章理解や内容の味わいが深まったという経験があったら、コメントで教えていただけると嬉しいです!
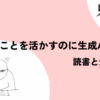
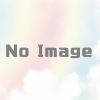
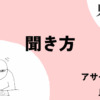
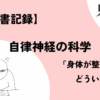
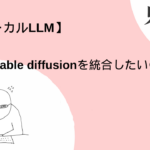
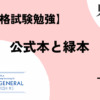
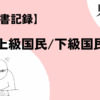
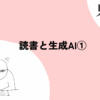




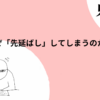

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません