読んだ本を活かすのにAIを活用できる?
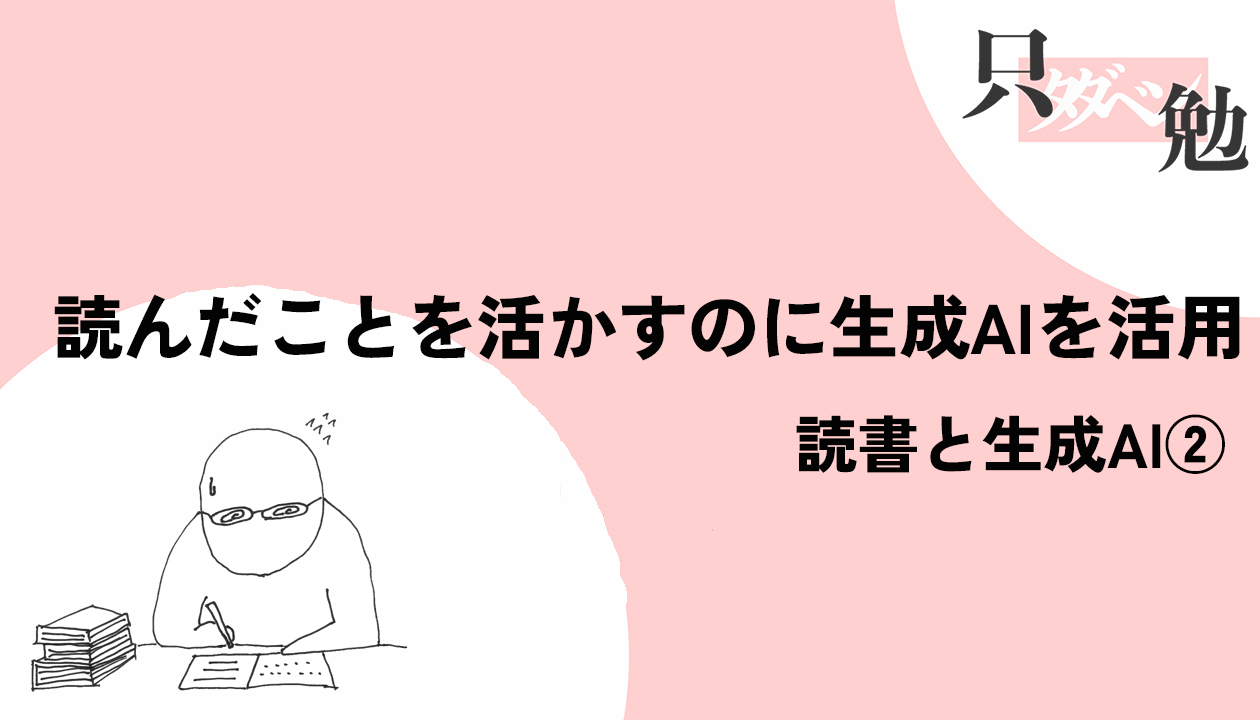
前回の記事では。
生成AIが得意とすることを活用することで、読書をより楽しむことができるのではないか?
ということと。
読書に生成AIを利用する上での注意点について書きました。
今回はもう少し、「活かす」方向で考えていこうと思います。
読書という楽しみの時間をより有意義にする生成AIの利用や。
生成AIとの対話を自分の学びを深めるのに使いたいという方の参考になればと思います。
読書の時間をより有意義に
私達の周りには、楽しむことができるコンテンツが溢れています。
その中で、本という媒体を選ぶ理由は、興味はもちろんあると思いますが。
自分に必要と思える知識を、体系的に得られると考えるからではないでしょうか?
本を買うというコストを払い、さらに内容を読んで理解するという時間のコストも払うわけです。
コストを使うと、サンクコストバイアスという力が働き、かけたコストを回収しようとするのが、私達人間でもあります。
読んだこと自体で満足することもありますけどね。
とはいえ、満足するには「良い本だった!」という感想も持ちたいわけで。
そのような感想を持つということは、知識が増えたことに対する満足感だけではなく、読んだ後に自分の考え方や行動が変わるほどの影響を受けたと感じるんだと思います。
しかし、時が経つと内容をすっかり忘れてしまったり。
結局何も変えられてないと思う事もあるでしょう。
自分も感銘を受けたことを忘れないように、このブログで感想を書き続けているという意味合いもあります。
しかし、読むことが優先になってしまったり。
ポイントを抑えるだけの知識で終わってしまい、知恵に変えられていないと思うことも多々あります。
また、コストをかけている分、何か学びになることが必ずあるんじゃないか?と考えすぎてしまうこともあります。
・・・まぁ、興味や関心があるものを選んでいるので、学びになることはあるんですが。
考えることで力を使い果たし、結局「知識」で終わっているという本もいくつかあります。
Notionなどの便利なメモアプリもあるので、知識を残しやすくはなっていますが。
より実践できるような形で残したいなと思っていた時に読んだのが、前回も紹介したライフハッカージャパンの記事です。
自分だけのワークブックを作る
生成AIを使うことで、文章の要約を効率的に行って理解の助けにすることができますがー。
要約という生成AIが得意とすることを自分の読書メモで行い、自分が感銘を受けた内容の要約を行い。
自分が本を読んで得た経験や考えがまとめられたものを、生成します。
そうして自分の経験や考えを元にできた文章から、自分が活かしたい内容をアクションプランとして生成し。
自分だけのワークブックを作り上げ、本の内容を身に着ける助けにしよう!
・・・というのが、ライフハッカージャパンの記事の、ざっくりとした内容です。
誰かがまとめ上げて考え出したものではなく、自分自身が読んだ事によって影響を受けた部分が元になっているものなので。
本の内容から行動を起こすのに、とても良い手段だと感じました。
実際、自分自身でやろうとすると、メモの内容から本文の内容を思い返すために再度読んだり。
遠い章、例えば、1章と5章の関係を考えるのに、本を行ったり来たりしたりと時間が思ったよりもかかってしまいます。
度々かいてますがー。
そうすると、じっくりと考えたい応用に到達する頃には頭がつかれてしまい。
少し雑に考えることになったり、少し時間が空いてしまい、読んだ後に抱いた熱が少し冷めてしまうこともあります。
そうなると、本を読んで受けたはずの影響の強さが変わってしまい。
思ったようなものではなくなってしまう可能性もゼロではありません。
なので、生成AIが得意とする文章の要約や情報の整理を活用し。
そこから自分にぴったりなアクションプランを提案してもらおう!
ということですね。
自分のメモの要約を見ながら、うろ覚えになってしまったところを補填することで、より正確な知識にも近づけるでしょう。
これはぜひ活用したい!と思い。
読みながら取っているメモを、メモアプリなどでテキスト化するようになりました。
前に読んだ本と重複?
本を選んでいると、同じような内容の本を読んでいるように感じることもあります。
不思議なもので、その時に感じている自分の興味で選んでいるはずなのに、視点が違うだけで内容が近しいものだったということは良くあります。
・・・テーマが違うけど、切り口や観点が似ているという場合もありますかね。
視点やテーマが違う時点で学びはありますがー。
読んでいると「知っている」ということも多く、そこから自分の学びに変える場合、苦しむことになることが多々あります。
・・・私はですがw
同じような考え方や切り口の使い方を学べるという、フレームワークの学びになりやすいんですがー。
実際には、その本の内容を知識として終えておくのか、実際の行動に表す知恵に変えるのかの判断は意外と難しいこともあります。
サンクコストバイアスという言葉を出した通り、かけたお金や時間を回収したいと考えるからです。
・・・貧乏性の私はなおさらですw
それを冷静に判断するときの助けになるのも、やっぱり生成AIです。
自分の考えをまとめるために生成AIへ壁打ちする使い方を、読書にも応用するわけです。
本を読んで学んだことを掘り下げていくとともに、自分にどのように役立つかなどもプロンプトを投げかけながら整理していきます。
AIが登場する以前から、私達人間は他人の会話の中で自分の考えを伝えるとともに。
自分の考えを整理していくという行動をしてきています。
人間同士の会話にはそのような機能があるので、生成AIに対しても同じ効果を期待することができます。
また、もし「近い」と思った本の要約が残っていれば、要約同士をAIに比較させることで、身につけるべき学びがあるかを判断する材料にすることもできます。
生成AIとの対話の結果、知識として持っておくという選択をしたとしても。
他の本からすでに取り入れた内容や考え方に、新たな知識を追加するということになるので。
より強力な知恵として、自分の行動に変換しやすくもなるでしょう。
知識をつなげると言うのも、大事な学びですし。
AIとの対話を行動に変える
自分自身、生成AIの活用を考えた場合に、自分の考えを明確にするとかまとめるという事での利用が多かったのが事実です。
しかし、生成AIが提案やアイデア出しも得意であるという特性も踏まえると。
今回の記事で書いたような、自分の行動を変えるアクションプランを提案させるというのも、一つの方法です。
しかも、自分自身では気づかないようなものが提案される可能性もありますし。
もちろんハルシネーションによる勘違いには気をつけないとなので、提案される内容はよく考えないといけませんけどね。
そのように、自分の考えや行動を変える一助に生成AIを活用するのも、AI利活用の一部です。
読書をより楽しむためのツールとして、生成AIを利用し。
単なる整理やお楽しみの道具から、実用的で実践的な道具へと使い方を変えていきたいものです。
読書に限らず、生成AIを通じて自分の行動を変えた経験や、実際に利用しているという方がいたら、ぜひコメントで教えてもらいたいなと思います。

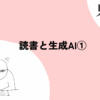

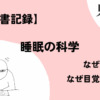
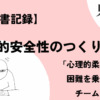
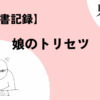




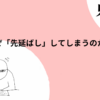

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません