読書の体験を変える生成AI
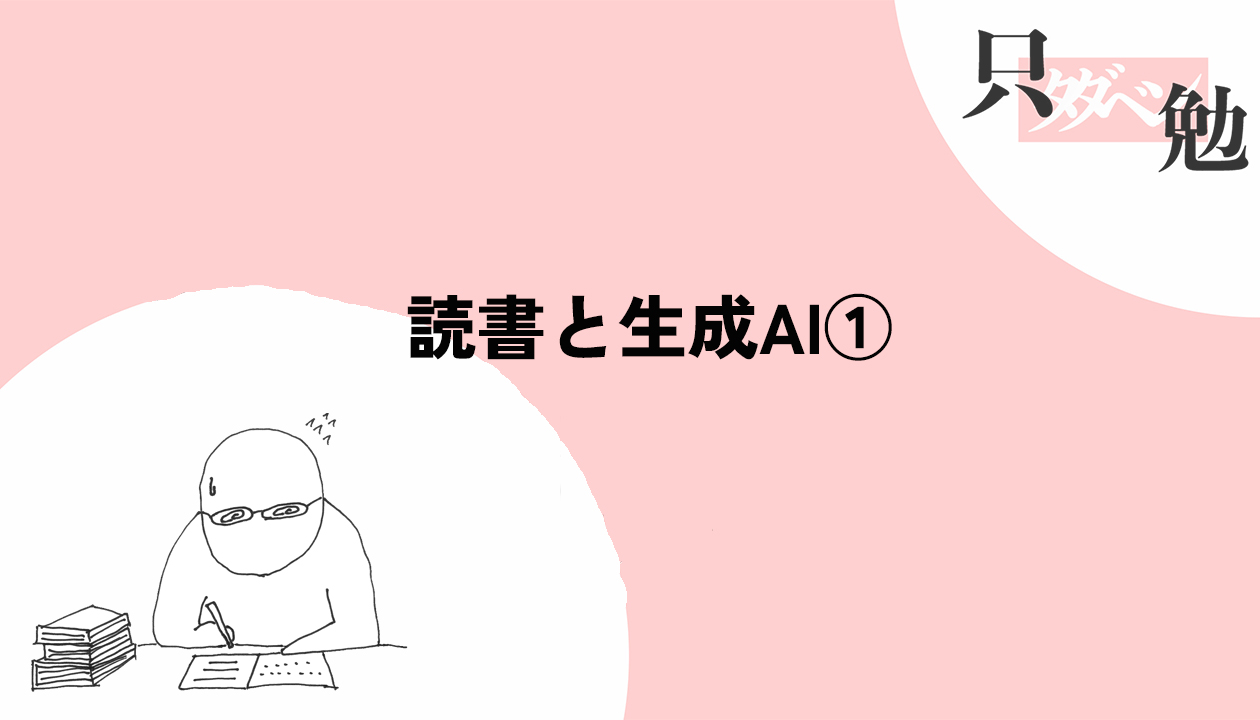
このブログでは「読書記録」というカテゴリーで、私が読んだ本の感想を書いています。
本を読んだり、内容と自分の考えをすり合わせることはとても楽しいのですがー。
一番時間がかかるのは、考えを深めるために、読んだ内容を整理することです。
整理する中で新しい気付きがあるのも事実ですが、メモを取りながら読書をする習慣があるので。
どちらかというと、自分が考えついた論理を再度まとめ直すような意味合いが強いです。
その後から、自分がどう思い考え、活かそうとしているかを考え始めるのでー。
結構時間がかかるというか、作業しているうちに読み終わった後の熱がどっかに行ってしまうこともあります。
・・・なんとも言えない文章になっているときは、大体そんな感じなんですけどね。
どうにかならないかなぁと思っていた時に目に止まったのが。
ライフハッカージャパンのChatGPTを使った読書術についての記事でした。
ChatGPT意外にも、CopilotやGemini、Claudeなど様々な生成AIサービスが生まれているので目移りしてしまいますが。
テキスト生成AIは「要約・再構成」を得意としています。
そこを起点として、読書からより考えを深め、楽しむことができるのではないかと。
これから実践していきたいことを考えてみました。
思ったより長くなってしまったので、これから数記事に分けて書いて行きます。
読書にAIを活用すると?
AIの活用によって生産性がどう上がるかは分野によって異なりますが。
基本的には、効率化や本来時間をかけるべき作業に注意を集中させることができるようになることが、生産性を上げるポイントと言えます。
読書に活用することを考えた場合、本の内容の難解な部分をイメージしやすいように画像生成AIを利用することもできますがー。
今回は考えを深め、学びを得ることを目的としているため、テキスト生成AIに限って考えてみます。
あ、視覚的に捉えられる方が、考えを深める助けになる可能性があるのはごもっともですけどね。
で。
テキスト生成AIが得意とする、「文章作成」「要約・再構成」「対話・シナリオ作成」「創作支援・アイデア出し」「ライティング支援」「構造的なドキュメント作成」といったものをどのように読書に当てはめていくかです。
まず活用したいのは「要約・再構成」ですが。
これについては、本を丸ごと読み込むのではなく、本を読んで得た自分の感想や考えを要約しつつ、論理を整えてもらうことに使えます。
また、得た自分の感想や考えを生成AIにぶつけることで、「対話」を行うことで考えがまとまっていくとともに。
「アイデア出し」の要素で、その考えや意見について、違う視点を提供してくれる事もあります。
それにより、読書による学びの幅を広げることができ、より深い理解を得ることができる。
そう考えます。
また、本を読んでいる中で疑問に思ったことや、感じた違和感のようなもの。
さらに、自分が考えたことの裏付けについて、読書中から生成AIに尋ねることで、分からないことや知らないことを放置せず。
納得感を持って読書を進めることもできます。
読書は著者と読者の対話という側面がありますが、その仲介をしてくれる存在が生成AIであると言えます。
自分の感じたことや印象に残った事をテキストとして整理し。
それを元に生成AIに対し壁打ちを行うことで、本を読んだ内容を自分の血肉にしやすくなるとも言えます。
そうすれば、本の内容に対する自分のポジションを明確にしつつ、本を読んだ後の高揚感がある状態のまま、自分の行動を変えることができるようになるなぁと。
ある意味、忘れやすいからメモを取るという普段のクセが、こんな形でも役に立つとは。
ありがたいことです。
注意点は忘れずに
生成AIを読書に利用する意味を考えていたら、大きなメリットも感じましたがー。
注意点は変わらないということは、覚えておかないとですね。
まず、ハルシネーションの問題はつきまといます。
モデルの進化でだいぶ少なくなったとは思いますが、つい最近こちらが提示したソースを全く無視した回答を生成したことがありました。
notebookLMのような、指定されたソースからの推論に重きを置くようなモデルなら少ないかもしれませんが。
ChatGPTやGeminiといった、汎用的なモデルの場合は特に注意が必要かもしれません。
本の内容ではない意見や、一般的と感じてしまう内容が提示された時に、情報源を精査するクセを付けておく必要があります。
違和感を感じたら、必ずですね。
生成AIの推論のスピードが早いため、考えること自体を委ねてしまうと。
自分の意見のつもりが、生成AIが導き出したものであり。
考えの薄いものになってしまう可能性もあります。
自分もたまにあるんですが、内容をよく理解したつもりが、うまく言語化できなかったり。
その時は、大体生成された内容をそのまま受け取っていて、自分の言葉にできるまで消化できていないことが多いです。
なので、同じ考えを繰り返すことになったり、調べ直すことになり、手間が余計にかかったり。
あくまで人間の脳の拡張であるという意識は、持っていた方が良いでしょう。
生成AIを活用する起点は、あくまでも人間です。
生成AIの利点を活かしつつ学びを深める
「初心に帰る」ということの大切さを実感したのが、今回の読書にAIを活用する一連の記事を計画した時です。
自分が生成AIに興味を強く持ち、G検定の受験やAIに関する知識を増やすきっかけになったのが、松尾教授の「人工知能は脳の研究」であり「人間の脳の拡張」であるという主張を見たことです。
生成AIのできることや、活用事例にばかり目が向き、どのように自分の生活を変えることができるのかということについて。
考えているようで、地に足がついてなかったことを痛感しました。
読書のような個人的な時間に使うことができなければ、業務使用やより大きなことへの導入のひらめきは起こりにくいよなぁと。
本のジャンルによる向き不向きはあるとは言え、読み終わった熱のあるうちに、読書から学びや深い考えを得るという力を使いたい時間に集中しやすくなる利点が間違いなくあります。
もし、すでに読書にAIを活用されていて、メリットを感じておられる方がいらっしゃいましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。
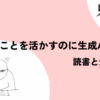
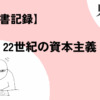
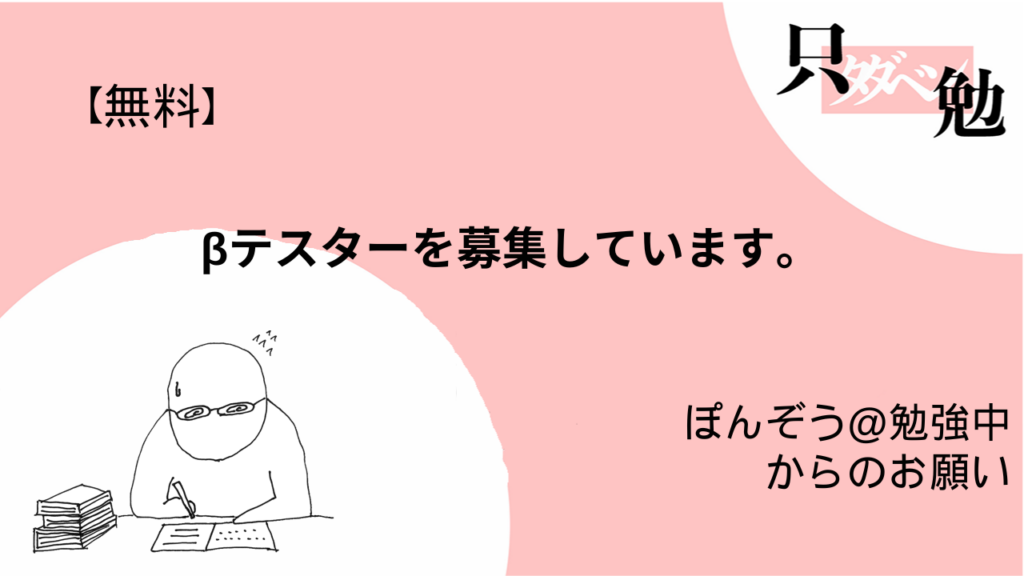
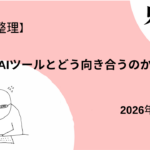
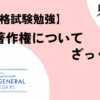

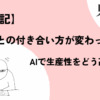


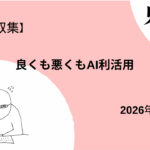
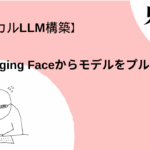
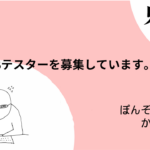
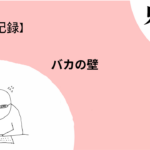
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません