【読書記録】言語の本質(著者:今井むつみ 秋田喜美)|進化し成長する「推論」
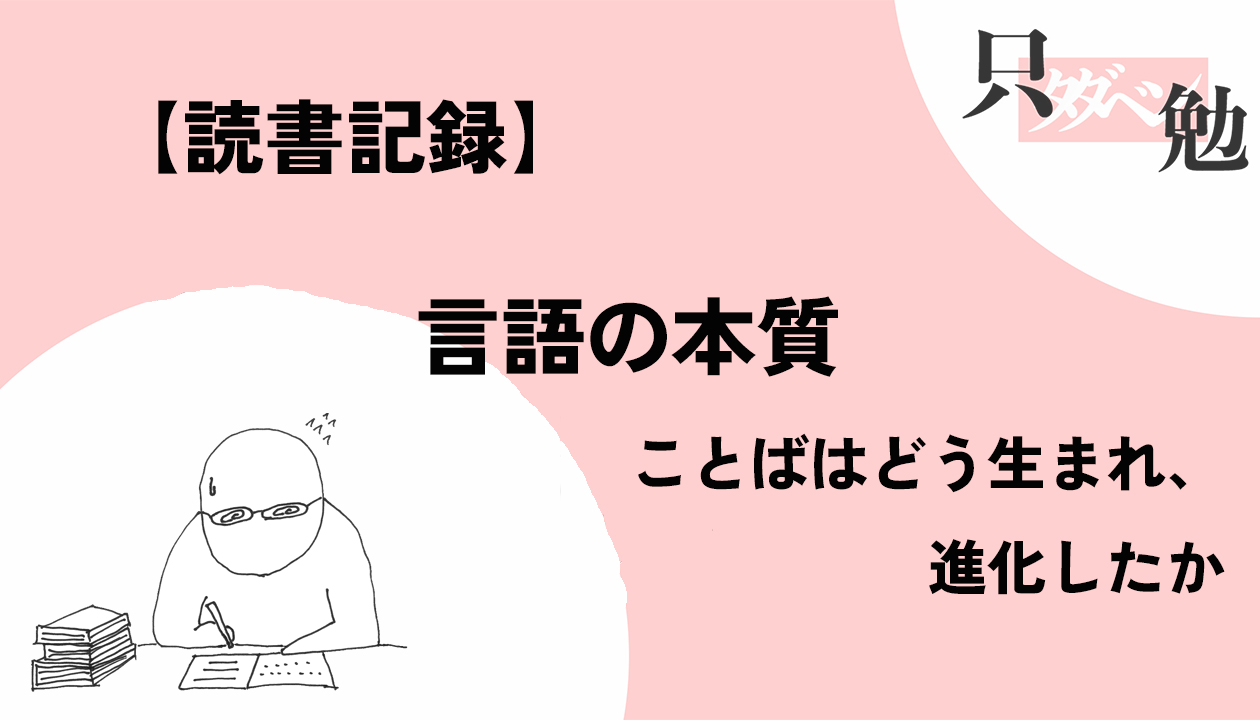
G検定の勉強をしていた頃に、AI用語をまとめていた記事が最近人気のようです。
ChatGPTから生成AIとの付き合いが始まり。
GoogleがTransfomerを開発し、Attention機構が導入されたことで、自然言語処理がスムーズになったということもあり。
ワクワクしながら学習を進めていました。
その仕組みを読みながら思ったのが、たぶん自分たち人間も無意識でこれらの機能のような処理を脳でやっていて、言葉として使っているんだなということでした。
そんな事を考えていたら、「言語ってなんだろう?」というような事を考え始め。
言語論の本を買おうかと思いつつ。何もせずに過ごしていたのが私です。
それから少し経ち。
積読が減ってきたので新たに本を買いに行ったところ、並んでいたのが本書「言語の本質」です。
「これは・・・!?」と思わずにはいられない出会いでした。
オノマトペから始まるヒトが言語を習得するまでの旅
本書は認知科学者の今井むつみさんと言語学者の秋田喜美さんの共著です。
タイトル買いしたようなものなので、あまり著者の方の事は考えていませんでしたが。
心理学関連の本を呼んでいる流れだったので、本書との出会いにも何かを感じてしまいます。
で。
日本人にとっては身近なオノマトペから、複雑な記号体型である言語を習得していくかについて書かれた本です。
「ワンワン」や「さらさら」、「ギザギザ」といったものがオノマトペで、幼少期に多用し大人になっても無意識で使っている言葉でもあります。
オノマトペが表すものは、ヒト・動物の鳴き声・物音などを表す擬音語、様子や動作・手触りを伝える擬態語、感覚・感情を伝える擬情語など、どれも普段から使っているなぁと実感するものです。
そんなオノマトペは、音によるアイコン性を持っていると説明され。
消音と濁音、子音と母音での印象の違いや、使われる場面からマルチモーダルなコミュニケーション手段として成立しているとのこと。
色々なオノマトペが記載されているので、声に出しながら呼んでいると。
内容を体験できるとともに、だんだんと楽しい気分になってくるから不思議です。
外国語のオノマトペも紹介されていて、聞き慣れないものばかりで楽しめましたが。
その言語特有の背景などで、異なっている理由も、オノマトペが音の一部を切り取るアイコン性にあるからだと。
本書でも書かれていますが、オノマトペを使う場面を想像してみると。
普通の言葉では説明しにくい事や、理解してもらうのに多少の専門知識が必要となる時に使うことが多い気がします。
そのような円滑なコミュニケーション手段として利用されているオノマトペを研究していると。
「言語なのか?」という問いに行き着くそうです。
この問に対する答えは、言語ではあるが、一般的に使われる言語を習得するための橋渡しの役目である。
という感じですかね。
言語的な特徴を持ちつつも、音に意味のあるオノマトペから。
音に意味のないことばからなる言語体系を習得する流れとなっているようです。
Cycプロジェクトやニューラルネットワークの話も出てきたり、AIが自然言語を処理する過程を参考にしているのも興味深いものでした。
このように、この世に生まれてから言語を習得するまでの流れが、オノマトペを元に解説されています。
ヒトの武器「推論」
「言語ってなんだろう?」という自分が持っている、漠然とした問いに関する答えとしては。
本書に書かれていることから考えてみるしかないなぁ、という感じなんですがー。
コミュニケーション手段であることと、「推論」という知的能力にあると思いました。
第6章と第7章で推論による言語を習得する過程について解説されていますが。
子どもがよくやってしまう、言葉の意味を取り違えることや、いい間違えが起きる原因というものは、過剰一般化により起きているとのことです。
この過剰一般化は「アブダクション推論」と「帰納推論」によって起こるとのこと。
アブダクション推論は、仮説を立てる推論で「〜ではないか」というもの。
帰納推論は、起きた事象を観察して「〜である」と推敲するもの。
子どもは初めて聞いた言葉と行動やモノなどを結びつけて、それを表す言葉を知り。
その言葉に使われたのと同じような行動やモノに当てはめて使うようになると。
その結果、言葉を理解している大人が思わず微笑んでしまうような間違いをしてしまう。
という流れのようです。
失敗を修正し、知識を再編成することで、新しい推論を行い、成長していく。
これを繰り返すことで、複雑な言語体系を習得していくと。
ざっくりですが、本書では説明されています。
いつの間にか私達は失敗を恐れ、確実な推論、論理的に正しい推論に基づいた行動を取ろうとしてしまいますが。
当たり前に使っていることばの習得では、不確実な推論を繰り返し、間違いを正し続けるという行動を取っていたんですね。
これは、ヒトという種が生き残って行くために必要な能力を、乳児期から訓練しているのではないか?ということが、本書を読み進めていると思えてきます。
論理的に正しい推論は「演繹的推論」で、原因から結果を導き出す方法ですが。
生きている中で、原因がはっきりしている事象というのは、あまり出会わないと思います。
結果として事象が起きているわけで、原因の方を推察するという事態の方が多いはずです。
そして、その事象が起きる原因を学習し、問題解決となる予測を立てられるようになり、安全・安心な状況を増やすことができるわけです。
人間にとってアブダクション推論はもっとも自然な思考なのであり、生存に欠かせない武器である。
<中略>
この推論こそが言語の習得を可能にし、科学の発展を可能にしたのである。
第7章 ヒトと動物を分かつものー推論と思考バイアス P.246
今はすぐに生死に関わる状況というものは少ないですが。
狩猟時代は生死と隣合わせの生活だったでしょう。
その中で、危険に繋がるであろう状況を学習する方法が、アブダクション推論であったと考えられます。
その思考方法を、ヒトのコミュニケーション手段である言語の習得時点から訓練し。
思考した内容を共有したりブラッシュアップさせることで、集団として強くなる。
その結果、ヒトという種が生き残ることができた。
という事を考えるとともに、パスカルの「人間は考える葦である」という言葉が思い出されました。
言語を習得すること事態が思考法を鍛えることであり、その言語を扱えることでさらに思考法を向上させ。
それが自分や周囲の安全を守るための知恵を生み出し、その知恵を持ち合うことで強い種となる。
そんな流れがあるんだろうなと。
これらの推論は、既存の限られた情報から新しい知識を生み出すことができる。<中略>不確かな状況、能力的な成約の下で、限られた情報でも、完全でないにしろそれなりに妥当な問題解決や予測を可能にしている。
また、事例をまとめるルールを作ることで、外界の情報を整理・圧縮することが可能になり、情報処理上の負荷を減らすことができる。現象からその原因を遡及的に推理し、原因を知ることで、新しい事態にも備えることができるのだ。
第7章 ヒトと動物を分かつものー推論と思考バイアス P.244
私達が当たり前に使っている言語を習得する方法と、私達が驚き、恩恵を受けている科学を発展させるための思考法が、実は同じ推論だった。
というのは、ヒトであることを少し誇りに思えるものでした。
進化と成長の行程
まさか、身近な感覚的表現であるオノマトペから「言語の本質」を探る旅で、ヒトの思考について考えることになるとは思っていませんでした。
挑戦や行動という言葉が叫ばれるようになって久しい今の時代ですが。
この言語体系を学び取る推論の過程は、そんな今だからこそ覚えて起きたいものです。
知識を創造する推論には誤りを犯すこと、失敗することは不可避なことである。それを修正することで知識の体系全体を修正し、再編成する。この循環がシステムとしての言語学習にも、科学の発展にも欠かせない。
第6章 子どもの言語習得2ーアブダクション推論篇 P.218
モノを買うのにも、何かをするのにも。
まずはその事について調べるというのが、情報化社会に生きる私達が取る行動です。
それは、他のヒトが経験した成功や失敗を知り、自分の創造通りになるかを検証している行動とも取れます。
自分の中にある知識の体系を修正し、再編成しているとも言えます。
ある意味では、失敗しにくい社会になっていて、ある意味では失敗しないのが当然であるというか。
失敗することに対する過剰な忌避感・・・無駄感というんですかね?
というのがあると思います。
しかし今度は、技術の変化や発達の速度が加速し続け、将来がどのようになるかがわかりにくくなっています。
つまり、失敗したくなくても失敗してしまう状態になっているとも言えるんですがー。
ここまでの流れの通りで、元々ヒトは失敗するようにできているということが分かります。
失敗すると、そこに学びが生まれ。
知識の体系全体を修正し、再編集し。
また失敗し・・・というループを繰り返した結果が、今の自分を形作っているとも言えます。
知識の体系全体を修正し、再編集する過程が学習であると考えられます。
学習というと知識を蓄えるような印象がありますが、心理学的には経験を通して行動が変化していく過程のことを言います。
つまり、挑戦や行動をして失敗しても学習が伴わなければ、進化や成長には繋がらないということです。
正直、数を打つことや、とりあえずやってみる「だけ」になっている方もそれなりにいるなという印象があるので。
失敗と感じた時点で、しっかりと学習するクセを付けたいものです。
また、失敗と学習の流れが多いほど、持っている知識の体系全体の修正と再編集が繰り返されることになり。
より強い知識や経験になることも分かります。
失敗を恐れる必要がないのは、その失敗から学習することで、より知識を強固にしたうえで成長できるからであり。
それを、無意識で体験してきているから、対処するための「推論」や「思考法」は元々身についている。
ということでもあると思います。
まぁ、そこに恥といった感情や優位性といった淘汰の理論が入ってくるので、失敗というものを恐れてしまうんだと思いますけどね。
とはいえ、元々失敗するようにできていると捉えれば。
少しだけ生きるのが楽になるような気もします。
それが、人間としての進化と成長の行程で、元々組み込まれているものなんだと。
言語習得のプロセスを応用したい
と、長々と書いた事が「言語習得」ということで完結にまとめられていたので、引用しておきますw
言語学習とは、推論によって知識を増やしながら、同時に「学習の仕方」自体も学習し、洗練させていく、自律的に成長し続けるプロセスなのである。
第6章 子どもの言語習得2ーアブダクション推論篇 P.204
これは言語習得以外にも応用できるものですし、体験済みなことであるはずなので。
様々な事に応用し、たくさん失敗したいと思います。
・・・アラフォーですがw

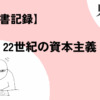

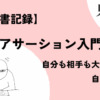
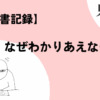
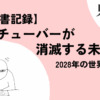
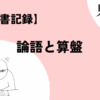
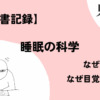




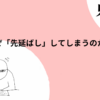

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません