【読書記録】多動脳 ADHDの真実(著者:アンデシュ・ハンセン 訳:久山葉子)|ある意味では「元に戻す」ということ
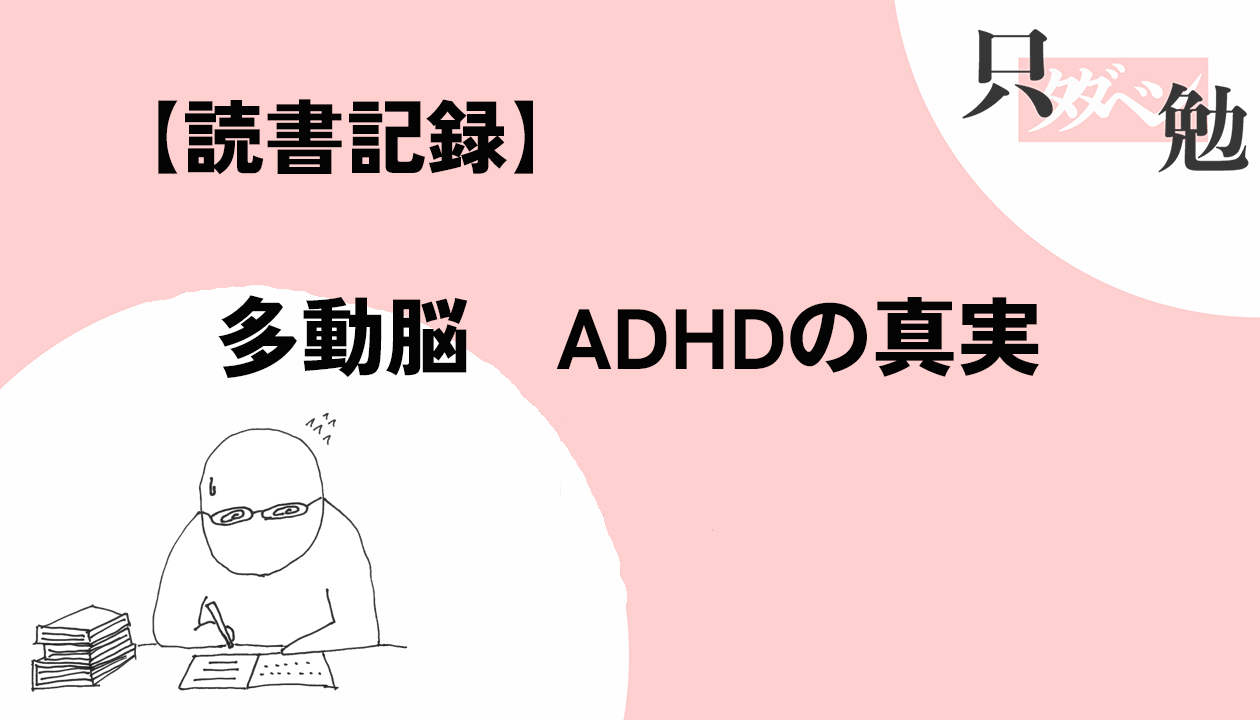
発売が決まってから購入を決めていたのが、今回の本「多動脳 ADHDの真実」です。
「スマホ脳」や「メンタル脳」などベストセラーを書いている著者の方ですがー。
文章も非常に読みやすいんですよね。翻訳者の方の努力も素晴らしいと思います。
スウェーデンの精神科医である著者が、脳の仕組みから依存症や不安、成長過程でおきる心の動きについて書いてきて。
今回はADHDに切り込むということで、非常に楽しみにしていました。
読み終わった感想としては、ある意味ではおおらかさのあった頃に、今の仕組みに合わせて戻る。
ということかと思います。
「誰にでも当てはまる」内容
衝撃を受けるわけではないんですがー。
たぶん、ほとんどの方が思っていたであろうことが、本書の冒頭で述べられています。
誰でも多かれ少なかれADHDの傾向があるからこそこの本をを書きたかったのだ。ADHDの傾向というのはその人独自の工具箱のようなもので、各工具の使い方を学べば人生をうまくやっていけるようになる。
まえがき P.6
ADHDという名前が広がり、発達障害というのもが一般的にも知られるようになり。
チェックリストなどもWEBで少し検索すれば出てきます。
その項目を見ると、自分や周りの人にも当てはまる特徴があるように感じた方も少なくないと思います。
先に進める前に書いておきますが、決してADHDという診断に対して疑問があるわけではありません。
本書でも書かれている通り、深刻な問題や悩みを抱えている方にとっては、診断が出ることで救われることがあることに疑問はないからです。
広がるようになったことで、本書の表現を使えば「グレーゾーン」に当てはまる方々が、深刻に受け取ってしまうようになるとともに。
学校がメインかもしれませんが、周囲の人たちも断定的にADHDという名称を使うようになってしまったのではないかと思うのです。
その結果、「グレーゾーン」でもADHDだと専門家ではない人間の判断で分類されるようになってしまった。
ということになってしまったのではないかなぁと。
なので、ある意味では社会問題として扱われてしまい。
自分もそうなのではないか?という疑問や悩みが生まれやすい状況になったのではないかと。
ですが、そう思うのがある意味では当然であるということが、本書を書いた理由としてあげられています。
つまり、この本に書いてある内容は、誰でも考えたり当てはめたりすることで、自分の生き方や行動を調整することができるものとして読み進めることができます。
ADHDの<強み>と<弱み>
基本的には集中力、多動、衝動という3つの分野で問題が起きている。
第1章 ADHDって何? P.17
本書の構成をざっくりと書いておきますが。
第1章と2章でADHDの特徴や引用した問題が起きる要因について、明らかになってきていることについて述べられています。
第3章と4章で、ADHDの遺伝子が必要とされた歴史的背景・・・というと広すぎますかね。狩猟時代で強みだった理由を、現代のADHDと診断される人たちの特徴から紐解いています。
第5章から7章では、引用した問題を現代の強みに変えるにはどうするか。実際に強みとして活かすことで、世界的に認められた人々を例にあげて説明しています。
第8章と9章はADHDに対する個人的な対策と、社会(学校)でとれる対策について書かれ。
最後の第10章でADHDがなぜ増えたのかについて、書かれています。
なので、問題となりやすい3つの項目。「集中力」「多動」「衝動」について、それをどのように問題となっていて、強みに変えていくのか。
ということが、順を追って説明されています。
著者が精神科医ということもあり、実際の例を元に説明されているので。納得感もあります。
ざっくり書くと。
創造性:様々なことに注意を向けることで、枠にとらわれない自由な発想ができ。それを抑えずに表現し実現することに、抑えられない衝動性と多動が強みとなる。
ハイパーフォーカス:集中力がないのではなく、集中できるものに興味を移せるかどうか。脳が喜ぶようなご褒美を継続的に与得てもらえる対象に対して、過集中できるという強み。
新奇探索傾向:プレッシャーのかかる状況でも、瞬時に様々な要因について検討し、決断を下すことができるのは、一つのことに集中するのが困難という<弱み>があるから。決断を下せるのも、衝動性によるもの。
というような感じです。
良く言われる、短所を長所に言い換えてみるという感じにもなりますが。
まさにその通りで、ADHDにおける問題行動と言われる特徴を、現代で評価されることに対して良い方向、<強み>として変換し活用していく。
個々人によって、傾向や程度が違うのが発達障害なので、個性に合わせて各自の強みを活かせるような仕組みや場を用意できるようにすることが、Win-Winな関係につながるとも思いました。
字数に制限があるでしょうし、本書の内容がすべてではないと思いますが。
本書で書かれている事を個々に当てはめて考え、強みに変えるような思考のクセを付けたいですね。
そして、そのようにしていくことが、神経多様性を認め協力して社会を歩んでいく姿なのだと思います。
今は個人主義の時代だが、人間は元々群れで暮らす動物だ。⋯<中略>⋯群れにおいて絶対的に重要なのが、「全員が同じではないことだ。人間でも他の動物でも。違った特徴を持つ個体が集まっている方が有利なのだ。
<中略>
1990年代にアメリカで「神経多様性」の概念が生まれ、脳の多様性も一つの個性として尊重する考え方から、ADHDや自閉症の見方が変わるきっかけになった。
第10章 ADHDが増加するわけ P.199
障害という強い言葉が使われているからか、どうしても問題に目が行きがちですが。
ADHDは人間の行動の正常なバリエーションである
第1章 ADHDって何?
という視点でいたいものです。
ただ、この視点というのは、誰かを扱う立場にいる人であれば、チームと個人に対して持っておくことで、個人もチームも働きやすい環境づくりになるようなと、思います。
本書はそういう風に読むと、ADHDに限らず人の扱い方を学べるなぁと感じました。
高度知能社会からAI利活用社会への変化
本書を読んでいると、いろんな意味で希望に溢れてくるんですがー。
少し考えて起きたいなと思ったのが、以下の部分です。
150年前は今ほど集中力を求められることもなく、例えば農場や工場で肉体労働をするなど、集中が苦手な人に向いた仕事も多くあった。しかし、現在ではそういう仕事はほとんど消えてしまった。
社会が複雑になり、ますます高い知能が求められるようになり、学校や職場で期待される集中力の基準を下回ってしまう人が増えたのだ。
第10章 ADHDが増加するわけ P.185
技術の発展により、生活がより豊かで便利になる中で。
社会構造が変わってしまうことで、起きる問題というものがあります。
その一つが、ADHDの特徴である「集中できない」というものに起因して、集中して知力を使うことが必要な社会になっているということです。
これは、学歴社会や知能社会という言葉も良く言われるので耳にすることが多い内容かもしれません。
集中よりも行動が重視される職業の数が減り、多くの集中が必要な時代になっているのは事実です。
つまり、学力という意味でも、高い知能や判断力が必要とされる社会で。
集中しなければ、ならない状況と時間が増えているということです。そのままですが。
そのような社会であれば、他の人と少し差があるとそれに悩み。
自分に何か問題があるのではないか?という思考になるような気もします。
そして、それと似たような状況が人間関係にも起き、気軽に効率よくコミュニケーションが取れるようになったものの、そこである意味集中力が無ければ、問題を起こすやり取りにもなりかねない状況ナノではないかと。
そう考えると、すごいストレスフルな状態です。
そこに対して、その知能を差を埋めるであろう技術として、生成AIを始めとするAI技術が発展してきています。
そうなると今後必要となるのは、本書であげられているADHDの<強み>である、創造性や多動性というものだと考えられます。
AIが足りないものや判断材料を提供してくれるのであれば、それをどのように扱い有効利用していくのかが、今必要とされているAIの利活用能力です。
つまり、自分の創造性や衝動を実現するために、どのようにAIを使っていくのか?ということです。
そこに対して、周囲が現実の場としてそれを実現するためのフォローをしていくという、連携が大切でしょう。
AI技術が発展してく中で常々思っているのが、技術発展によりだんだんと人間がやるべきことが泥臭くなっていくなぁということ。
技術が発展行くとともに、生活が便利になる中で。
ある意味では犠牲にして来た、社会的動物である人間としての生き方に立ち返っていくという。
「面倒」と思っていたであろうことに、目を向ける時が来ているんだと思います。
それを、様々な発想を持つ人とともに、楽しんでいけるような環境をつくれたら良いなと思います。
予測の難しい現代だからこそ
今の時代、未踏の地を開拓するということは、ほぼありませんが。
しかし、先がどうなるか分からないという意味では、将来という未踏の地を開拓していかなければなりません。
予測が難しく、将来に対して不安を抱くと、今も不安になってしまいます。
そのような状態を楽しむことができるというのが、ADHDの<強み>に隠されていると思い。
衝動的に素直に表現してくれるので、場が明るくなるという影響を与えやすいのも、この<強み>だとも思います。
本書でもそうですし、他の本でも書かれていますが。
進化の過程で淘汰されず、今まで残ってるというのは、それが問題のある遺伝子ではなく有用な遺伝子だからです。
また、<強み>や<弱み>という観点で言えば、ADHDやその傾向を持っている方にかかわらず、私達全員が持っているものです。
その<弱み>を補い合い、<強み>を活かし合う、そんな社会やチームワークのある組織、さらには家族となれれば。
変化が早く大きい現代を楽しめるようになると感じました。


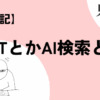
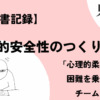
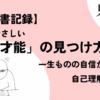
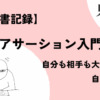
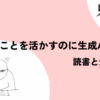
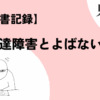

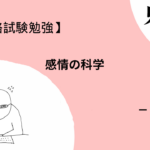
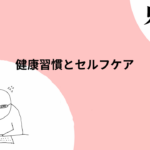
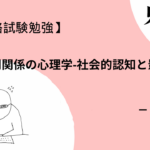


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません