NFTのスタンプラリー記事と最近のSEO情報で思ったこと
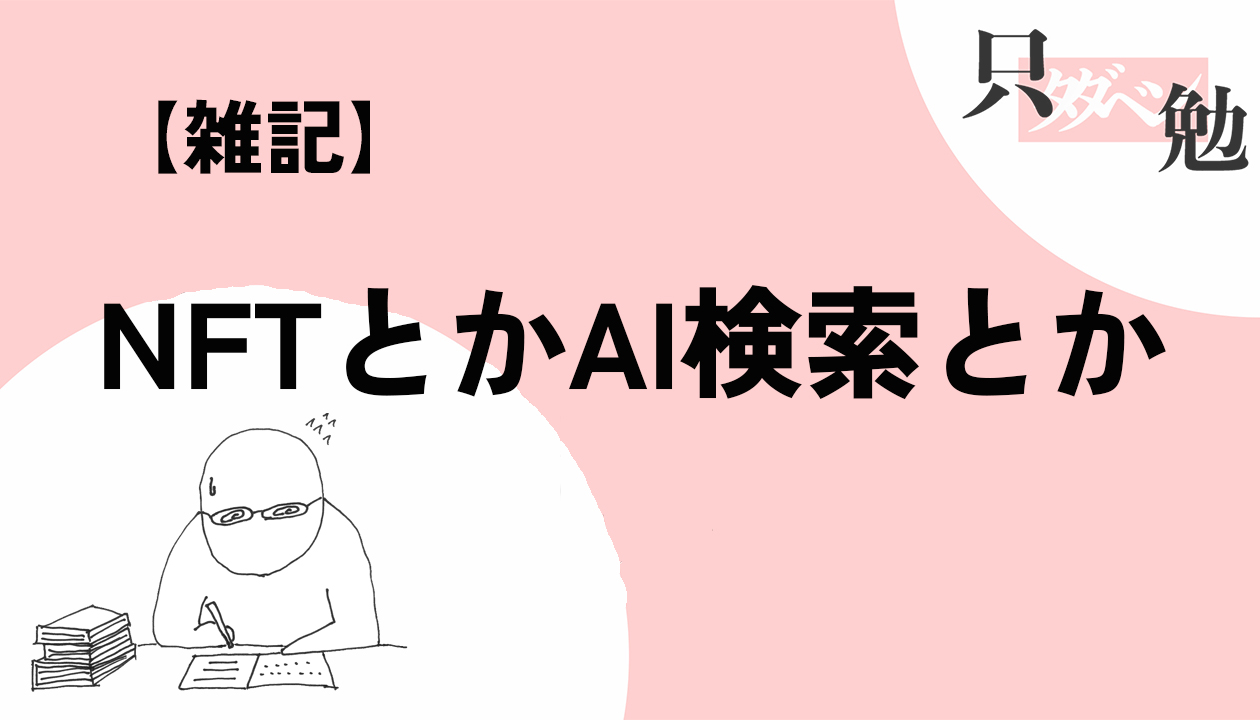
日々状況というものは変化するもので。
だんだんと体が忙しい状況になってきているような気がします。
考えながら動かないとなぁと、日々いろんな情報を取り入れているおじさんです。
今回はポエムのような感じで、軽めに「サイエンスかながわ スタンプラリー」についてのCoinDesk JAPANの記事と、ここ数回の「国内&海外SEO情報ウォッチ」を読んで思った事を書いていきます。
SBTの実現が近づいてきたのかな?
まずは、「サイエンスかながわ スタンプラリー」の内容から。
2年目の開催となるそうですが、神奈川県内の科学館・企業・大学が子ども向けのイベントを開催し、参加することでNFTがもらえる、デジタルスタンプラリーとのことです。
対象施設が6倍に増えたそうで、大阪万博開催によるイノベーションへの注目が増えたこともあるんでしょうか。
こういった情報で個人的に気になるのは、NFTの配布方法とその効果。
NFTを3個集めると、特別イベントに参加できるそうで、受け取る媒体はLINEだそうです。
WEB3関連の課題として挙げられるのが、どうやって普及させるかで。
スポーツやコンサートのチケットなどでの利用は見聞きしてきましたが、一般的な注目度が高い公的なイベントだとどうなのかな?と思ってました。
そんな中、大阪万博でもNFTが発行され。会場に訪れたことを証明する手段として利用できたり。
興味深く情報を集めてましたが、行く機会を作れなそうで・・・w
専用ウォレットが用意されていたり、特別なイベント感もあって良いんですがー。
普及と考えると、アプリが増えるのはどうなのかなと思うところもあるわけです。
そんなNFTが地方自治体のイベントでも導入されるようになり、手軽にNFTを入手できる機会になるなと。
NFTなどの暗号資産は、価値をデジタル上で表現する手段として利用されていますが、今回の場合に表現される価値は「体験」ですね。
暗号資産は忌避感が強い人も多いと思われるので、LINEなどの馴染のあるアプリで入手できるようなのが、やはり普及にはかかせないよなぁと思います。
画像という形で保存もできるでしょうし、個人の体験を発信し共感することに価値のある今なので。
その裏付けが、改ざん耐性のあるブロックチェーン上でなされるのは良いですね。
こうなってくると、個人の体験を証明する手段として「決定版Web3」で紹介されていた、SBT(ソウル・バウンド・トークン)の実現も近いような気もします。
SBTは個人の履歴書のようなトークンで、これまでの体験や経験、能力などを証明する手段となるトークンです。
ただまぁ、ここらへんはブロックチェーン毎の連携やウォレット間の連携など。
色々な問題もあるので、今後どのように統合できるかですかねぇ。
競争確保はしょうがないにしても、色んなサービスが増えて来てしまっている感もありますし。
ここらへんはウォレット開発でどのようにブリッジしていくかですかね。
課題はあんまり変わってないような気もします。
が、少なくとも2〜3年前よりはワクワクするWeb3業界になってきたと感じます。
AIが与えるSEOへの影響
自分自身もAIに興味もあるし、今後の展開に目が離せない毎日です。
AI開発やAIサービス開発に一層の力を入れているのが検索大手のGoogleやMicrosoftだと思います。
インターネット上の情報を集め続けていて、情報が集まるところとしての信頼もあるので、その情報の提供や検索性を高めるという意味で、AI技術ほど開発者と利用者双方のメリットに繋がるものはないですよね。
自分の仕事柄、SEO絡みの情報を定期的に仕入れているので、このブログでもたまに取り上げています。こんな感じで。
AIの性能も格段に良くなり、油断はできないものの、ハルシネーションなどの影響もかなり減ってきたように思います。
検索クエリから信頼性の高い複数のページの内容を要約してくれる、GoogleのAI Overviewなどは本当に便利です。
ただ、ここらへんが便利になり、信頼性が増すほど、WEBサイトへのアクセスには影響が出るのではないか?ということが度々指摘されています。
Google側は、逆にソースへのアクセスが向上すると「AIモード」の発表時に言ってましたがー。
どうでしょうかね?
とは思うものの、少し騒ぎ過ぎな気もしなくもないのが、個人的な意見です。
WEB検索を利用する場合の「密度」がどの程度かは個人差があると思います。
レポートを作成する学生や、研究者、裏付けを探すビジネスパーソンなどは、「密度」が高いので、ソースまで確認する流れになると思います。
しかし、大半は気軽に知りたいという「密度」が低いものだと思うんですよね。
仕事でもなく興味が湧いて検索した場合、その内容をざっくりと知れれば良いので、AI Overviewで満足するときもあるのが私です。
もちろん、ハルシネーションの心配は消えてはいないので、概要程度に済ませるようにはしてます。
少しでも疑問に思ったら、ソースを流し読みする程度です。
または、欲しい製品や商品を探すとかでしょうか。
その場合、必要なWEBページは商品ページかLPでしょう。
AIモードの展開を考えると、商品ページの方が今後は必要そうですが。
なので知識提供型のサイトは厳しくなるという論調ですねぇ。その通りだとは思いますが。
AI Overviewなどの要約機能が便利になればなるほど、少し前まで有効だった言い回しやキャラクターによる、受取やすさの違いというものはほぼ無くなるでしょう。
「あなただから、受け取ってくれる人がいる」という状況が生まれにくくなります。
ゼロではないですが、コストをかける価値は・・・なんとも。
Googleで言えば、すでにE-E-A-Tを勝ち得ているWEBサイトに厳しい戦いを挑むようなものだとも言えます。
そのように、知りたいことをAIが答えてくれてしまうということは、求められる情報が変わるということにもなります。
ここで、NFTの部分と繋がりますが、体験や経験といった独自の情報です。
知識部分で戦うのはテーマによる難しさがありますが、体験や経験からくる情報は人それぞれです。
同じような情報が集まれば、それを好意的に捉えるのが、ここらへんの情報ですね。
レビューで☆の数が多い投稿が多ければ、その商品を好意的に捉える流れです。
これは、レビューサイトだけではなく、SNSの発展に寄るものが大きいとも思えます。
ユーザー生成コンテンツ(UGC)というものですが、特定の専門的な誰かが持つ情報と同じくらい、個人が体験・経験した情報の重要度が上がっているわけです。
じゃあ、そのような情報を求めている人たちがどこにいるかというと、やはりSNSですね。
なので、これからは現実的な範囲で、発信するチャンネルを多くしておくことが重要だとも言えます。
一つの体験を、テキスト、動画、音声、絵など、形を変えたりしながら、様々な媒体で使用するという感じでしょうか。
そして、それを共有してもらうという感じです。
その先に、より詳細な情報としてWEBページを用意しておくという、基本的な流れは変わらないでしょうけども。
なので、検索からの流入というよりも、チャンネルからの流入というのに注力する方が良いでしょうし。
既存のWEBページは、テクニカルSEO寄りの対策を強くし、ボットが情報を収集しやすいようにしておきつつ、コンバージョンにつながる設計にしておくという感じでしょうか。
結局はユーザー視点を忘れないこと
と、AI技術が発達することで、しょうがないことではあるんですが・・・少し騒ぎ過ぎ感を感じているおじさんが私です。
弱小ブログであるこのブログにも、AIボットが来ている履歴が残っているので。
この流れに逆らったところで、無駄な戦いになるなと。
とはいえ、WEBページに訪れてくれた人にとって、必要なページを作成しておくことは変わらず大切です。
商品ページだけ羅列されててAIから高評価を得たとしても、実際に判断するのは人間なので。
信用度を測る要素として、他のコンテンツの必要性は変わりません。
じゃあ体験や経験をガンガン発信しよう!と手当たり次第に投稿するのも・・・微妙です。
できるなら良いですが、手間やコストがかかります。
そこら辺もAIに・・・と考えて、よくチェックもせずに投稿すれば、低品質コンテンツとしてペナルティを受けることは目に見えています。
なので、どこに対象となるユーザーがいるかを絞り込みその媒体に情報を入れていくという、マーケティングスキルの方が個人レベルでもより大切になってきているんでしょうね。
あとは、客観的に顧客の動きを捉えることでしょうか。
便利なもので話題になるものであれば、多くの人が利用するのは当然です。
そこにこちらの思うような、今までの行動を願うよりはこちらの行動を変える方が、顧客にとって意味のある情報を提供できるんじゃないかなとか。
ユーザー視点というものは、常に念頭に置いて行動しないとなと。
今日もブログしか書いてないおじさんは思うのでしたw
本質は変わらないということです
ということで、興味の対象が変わったとしても、本質は変わりません。
SEOの本質はユーザーに取って価値のある情報があることを、検索エンジンに知らせることで。
ユーザーが求めている情報じゃなければ、思ったような結果は得られません。
それが、経験や体験というより生の情報を求める流れがより強くなっただけです。
その裏付けとなるものを、NFTといったWEB3の技術で証明することができるようになってきています。
誰が情報を発信するかに加え、情報の正確性もより個人に求められるようになったと考えれば、是非活用したいですね。
・・・画像をほとんど使ってない当ブログなどはなおさら嬉しいw
今後も色々な情報が出てくるとは思いますが。
本質や本来の目的を見失わないようにしたいものです。


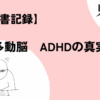
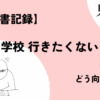
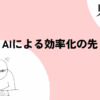
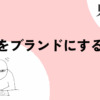
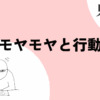

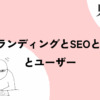

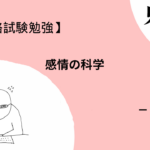
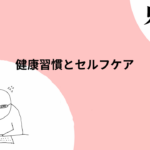
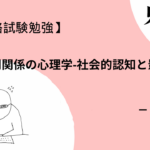


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません