【読書記録】境界性パーソナリティ障害(著者:岡田尊司)|備えて起きたい資質
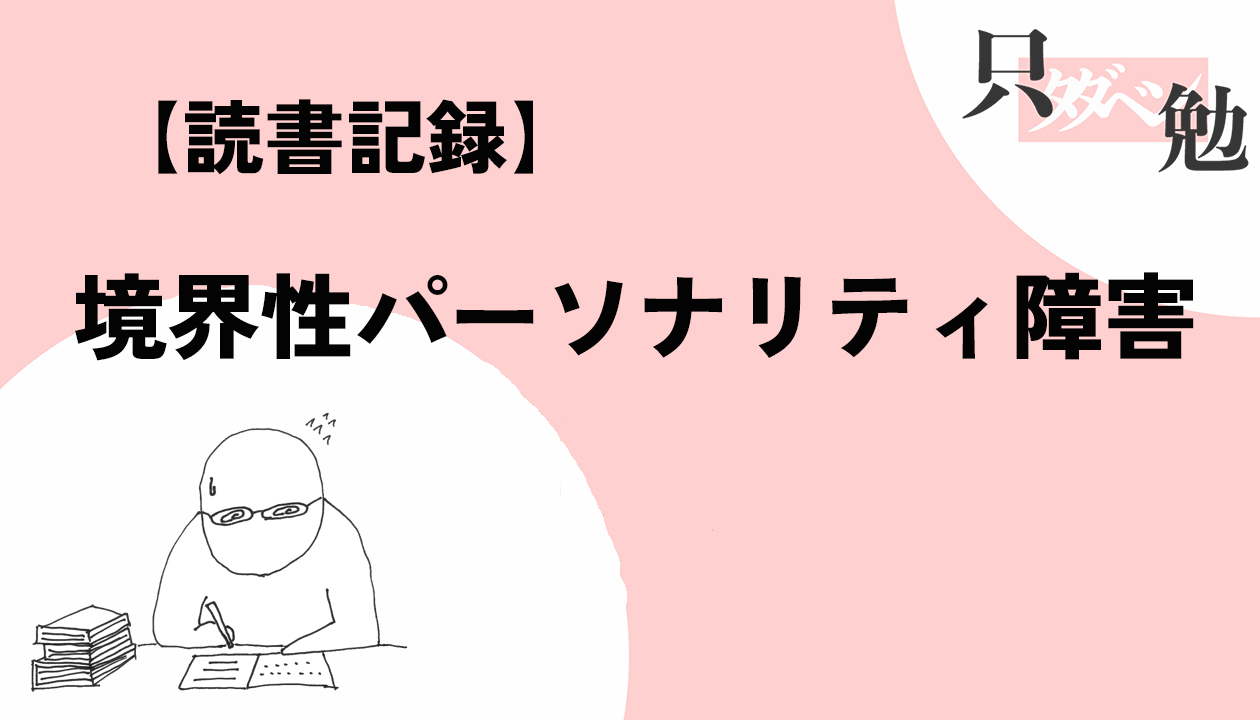
「ドーパミン中毒」の読書記録の中では触れませんでしたが。
私達が過剰摂取することに対処する方法を教えてくれるのが、依存症の人たちである。
という事が書いてあり、頭の中に残っていました。
だからというわけではないんですが、名称は知っているけど内容を知らない事を扱っている本も手に取るようになり。
今回もそんな興味をきっかけとして手にした「境界性パーソナリティ障害」です。
一つ前に読んだ「発達障害とよばないで」の著者である岡田尊司さんの本です。
読み進めれば読み進めるほど、自分の資質について考えさせられてしまいました。
境界性パーソナリティ障害とは?
境界性パーソナリティ障害とは。
・・・と、本を読み終えた今でも一言で説明するのが難しく感じる問いです。
周囲を振り回すような極端な言動から始まり、問題行動にまで発展してしまう、精神の病。
というのが大まかな説明だとは思いますが、それだけでは収まらないよなぁ。
とも読みながら思ったので、少し説明が難しいなと思うのです。
ただ、本書を読み進める内に内容がつながり始める切っ掛けになった境界性パーソナリティ障害の説明が。
境界性パーソナリティ障害は、自己を確立する過程の障害という側面を持ち、⋯
第8章 障害性パーソナリティ障害からの回復 P.230
というものでした。他にも、「自己形成に関わる成長の障害」という説明もあります。
診断基準や著者の臨床経験から、境界性パーソナリティ障害に悩むクライエントの特徴や共通する内容を導き出した結果の言葉だと思いますが。
自己を確立する過程、社会で生きるために認められる自己への移行が、何らかの原因でうまくいかないというふうに考えることで、納得できた感じです。
つまり、アイデンティティに関わる問題であると。
パーソナリティとアイデンティティ
少し言葉の意味を把握しておくことにします。
まず、「パーソナリティ」。
心理学においてのパーソナリティは人格や性格を指し、後天的に形成され、環境や成長において獲得されるものであるとされています。
「アイデンティティ」の心理学的な定義は、状況が変わっても本質的に同じ人間である感覚となりますが。
一般的な、自己を他と区別し、他社から認められるもの。という定義の方が分かりやすいかもしれません。
アイデンティティが形成される過程は成長段階に応じて発生しますが。
パーソナリティを形成することで、自分の人格や考え方というものが出来上がり、それと社会の関係においてアイデンティティが形成される。
社会の中で、他者と自己を分けるものがアイデンティティで、それを支えるベースがパーソナリティであると考えられます。
生まれてから、パーソナリティの元となるのは親の考え方や価値観で、それを元にアイデンティティを形成していきます。
そして、その親から与えられたパーソナリティでは社会に適合できないことに気付き、衝突や失敗を繰り返しながらパーソナリティを作り変え。
自分独自のアイデンティティを形成していくのが、思春期にあたるそうです。
そのアイデンティティの移行がうまく行えず、問題を抱えてしまう状態が境界性パーソナリティ障害であるということです。
その状態がが神経症のものでも、精神病のものでもなく、それでも両方の要素を兼ね備えているので、「境界性」というパーソナリティ障害という言い方にもなると。
読んでいて、その原因となり得る状況や、きっかけとなる出来事というものは、誰にでも起こり得るし。
その人の持っているパーソナリティによっては、程度の差はあれどだれもが多少は持つ考え方でもあるなと。
その意味で、本書にある通り、誰でもなる可能性があるというのに納得できました。
社会の変化
パーソナリティに支えられたアイデンティティは、先程も書いた通りで形成には社会の存在が欠かせません。
この社会というのは、人間関係によって構築されているものです。
本書の第四章「境界性パーソナリティ障害急増の理由」で扱われていますが、社会、人間関係の変化が、アイデンティティの移行がうまくできなくなっている理由とされています。
まずは、「社会体験の貧弱化」と説明されています。
核家族化が進むことで、親と子の密度が濃くなり、親のパーソナリティの影響が強くなると。
今は多世帯が一つの家で住むことが減りました。
・・・という自分も、別に多世帯家族だったわけではないんですが。
それでも、親戚付き合いは今はだいぶ減っているように感じます。
そうなると触れ合う人の数が自然と減り。
色んな考え方や価値観を知る機会が自然と減って行くように思います。
そうなると、多様な価値観を受け入れるというよりは、一つの価値観が強くなり。
偏ったアイデンティティが形成されやすくなるでしょう。
それが社会に受け入れられなかったとしたら、そりゃ本書で述べられているような症状や行動が出るよなとも思うわけです。
そして、受け入れてくれる社会自体が、「自己愛性と非共感性」の社会になってしまっており。
社会として自己のアイデンティティを受け入れてくれる土壌自体が減っており、自分が存在することの安心感が脅かされているとも。
ある意味では教育と現実のギャップのようなものもあると思いますが、個性や個人を重視する教育により育ってきたのに、社会に出たら相手も個性や個人を重視しているわけです。
それにより受容ではなく摩擦が起きるのは当然だと思います。
また、社会としては円滑な運営のために、個性や個人よりも社会に合わせることを求めてくるわけです。
このような摩擦の中で、パーソナリティを形成し、社会の中で生きるためのアイデンティティを見出して行くわけですが。
その中で、自分のことを受け入れたり認めてくれる場所がなければ、この形成は非常に難しいとも思います。
「支える人」から見える人の在り方
そのように、境界性パーソナリティ障害を抱えてしまった人は、過去の出来事と今の出来事が繋がらず。
その結果、良いという評価を得ていたアイデンティティと、悪い行動になってしまったアイデンティティの間で、苦悩を続ける。
という状態になってしまうそうです。
そのような人たちの回復は、家族や専門家などの周囲の「支える人」の存在が不可欠であると。
そのためには、まずは受け入れることです。
自己愛性と非共感性の強い社会というのは、要するに他者に関心がなく認められにくい社会ということです。
問題行動を起こす原因の一つに、そのような「認証」の問題があるそうです。
なので、気持ちや行動なども含めて、その人自身を受け入れることが大事。
もちろん無条件にすべてというわけではないですが。
命の危機やルールに外れた行動も受け止めるのは、いろんな意味で危険ですし。
次に、安心感を与えるということ。
繰り返し、変わらぬ態度と適度な距離感で受け入れ続け、気持ちを認めることで、抱えている不安を払拭することができると。
この2つの信頼関係の土台を築くことで、自分自身と正確に向き合う力を与え、回復に向かっていくと。
この支え方や回復の過程の章の読みながら思ったのは、信頼できる人になるということかと。
「自分のことを受け止めてくれて、安心できる人」ということになりますからね。
家族はもちろんですが、友人にそのような人がいたら、問題を抱えていなくても、かなり助けになります。
それに、全員が全員にと言うわけではなくても、一部でも自分と関わる人には、そのような人になりたいとも思うのではないでしょうか。
なので、この支える人に求められる資質の部分は、対人関係の基本とも言えることをしっかりと説明してくれている印象です。
受け止めて欲しいのであれば、相手のことをまず受け止める。
信頼してほしいのであれば、相手のことを信頼する。
自分が扱われたいように、まず相手を扱うという原則に従い。
自分自身をそのような人間にしたいなと思いました。
今だからこそ備えたい資質
問題を抱えるようになり、診断率が上がったとか。
人口減少や核家族化により、問題が表面化しやすくなったとか。
境界性パーソナリティ障害が増えた理由は色々とあると思いますが。
個人的には、社会環境が希薄になったことが大きいんじゃないかなと思っています。
パーソナリティが後天的に形成されるものであれば、もともとの影響が大きいとしても、自分の事を受け止めてくれて、安心感を与えてくれる人との関わりのもとで、自然な移行ができると思いますし、これまではそうだったんだと思います。
そこには、今の自分が望むものが手元に届きやすい、選択の時代であることも関係しているような気がします。
人とかかわらなくても、自分にとって耳障りの良いものが手に入りやすい反面。
対話などで可能になる、自分と向き合いパーソナリティとして形成していく時間が取りにくい状態であるとも。
社会が便利で快適になると、逆に生きづらくなる人が増える悪循環に陥っているのかなとか。
いろんな研究の調査で、それが明らかになっているとは言え。
受け皿をどうするのか?という社会的な問題にどうしても考えが行ってしまいますね。
まずは、自分一人からでも。
そのような資質を備えた人間になれるように、努力しようと。
それが、結果的には自分の人生の充実にもつながるよなぁと。
そんな意外な教訓を得ることができました。

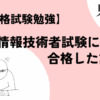

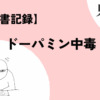
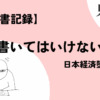

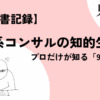
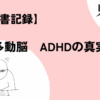




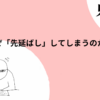
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません