【読書記録】発達障害とよばないで(著者:岡田尊司)|愛着の形成は対人関係を構築するのにも役立つじゃないか
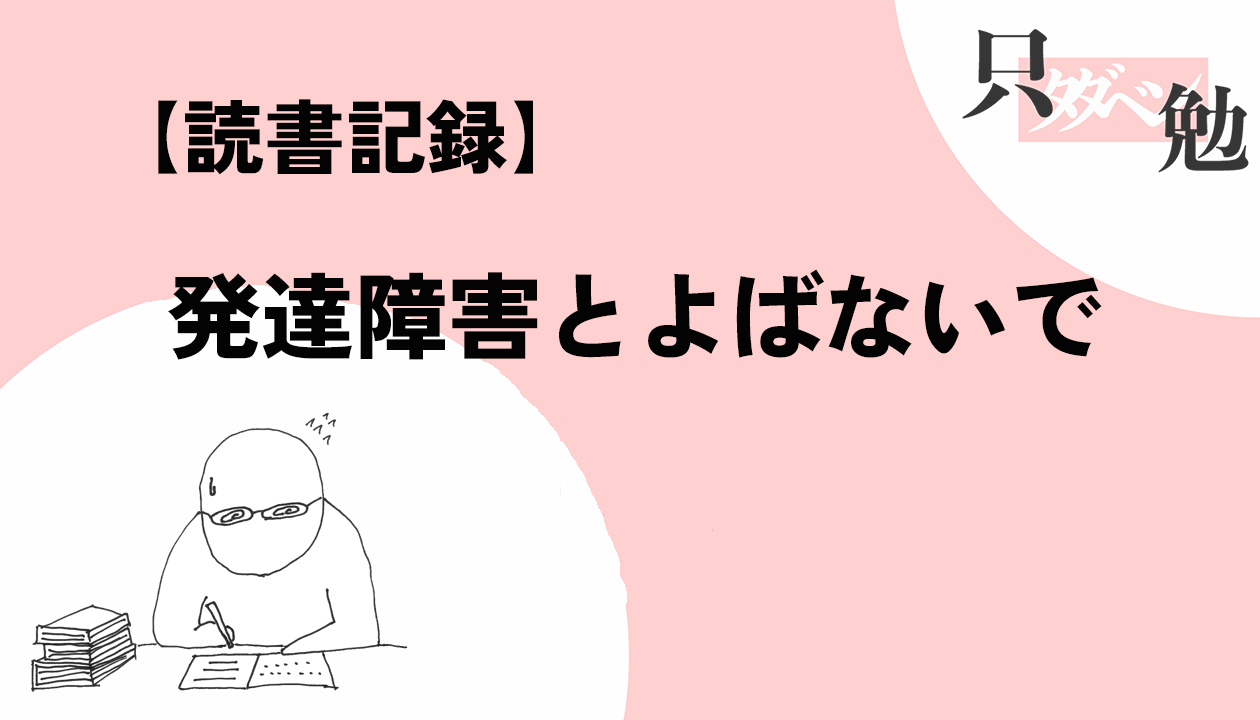
最近呼んでいる本は、心理・精神的なものに寄っています。
そもそも、脳の働きや遺伝の事に興味が湧いたのがきっかけなんですが。
脳と心は密接な関係がある・・・というか、心に作用する臓器が脳なので。
この流れになるのも必然だったのかなぁと思います。
そんな中、読みたい本の前に読んでおきたい本を読み進めることにし。
今回の「発達障害と呼ばないで」を読むことにしました。
第二の遺伝子である愛着
自分の手元にある版は、2017年発行の第12版で。
8年前というと、発達障害という言葉がものすごい勢いで飛び交っていた記憶があります。
その診断例が急増している理由から始まり。
愛着障害という概念を提唱している本というのが、ざっくりとした本の内容です。ざっくりしすぎてますがw
本のタイトルの意味は2種類あることが本書から読み取れます。
①神経発達障害や脳機能障害という生物学的基盤に基づく障害と、愛着形成過程における環境要因に基づく愛着障害を区別する必要がある
②発達障害でも愛着障害でも、そのような診断を下すことに対する弊害が大きい
だから、「発達障害と呼ばないで」というお願いのようなタイトルなんだなと、腑に落ちました。
特に②の要因を深く扱われていますが。
発達障害は脳機能の障害なので、遺伝との兼ね合いが指摘されているものの。
遺伝率は体重の遺伝率に近く、環境が影響する余地が意外に大きいと指摘されています。
もちろん、遺伝要因などの生物学的要因も重要なことに変わりはない。環境要因だけでは起きないからだ。両方の要因が重なった時に、問題が生じやすくなる。
<中略>
大事なのは、誰のせいかということではなく、どうすれば、危険を減らし、また生じた問題を改善できるかということである。
<中略>
環境要因に注意を注ぎ、それを好ましいものにしていくことで、「発達障害」といえども、状態を大幅に改善するチャンスがあるということだ。
第一章「発達障害」急増の謎に迫る P.58~59
この「環境要因」として大きな影響をおよぼすのが、養育環境であり、愛着が形成される環境であるということです。
そして、愛着は情緒的、認知的、行動的発達の土台になるもので、不安定だと影響が出てしまい。
愛着の形成期である幼少期の育て方により、将来の行動を支配する「第二の遺伝子」のような働きをしてしまうとのことです。
愛着が不安定な場合に起こす問題行動が愛着障害ですが、発達障害の子どもと似たものとなるそうです。
これも発達障害が急増している理由の一つとのこと。
そして、愛着障害が見えてくるということは、環境要因が社会レベルでの変化を起こしていることを示唆しているとも。
そのために、発達障害・愛着障害の捉え方を変え、「強み」として捉えることの大切さについて書かれています。
この本の出版から時間が経った今では、多様性が叫ばれるようになり。
表だって問題になることはなく、社会的にも個性として受け入れるような雰囲気になったとは思います。
少しずつ社会は変わっているんだろうなとも思いつつ。
しかし、個人レベルで考えると意識の差や関係者であるかどうかというような。
なんとなくの肌感覚としては、前向きというよりは「しょうがない」という後ろ向きな印象です。
だから、当事者やその家族でない限り、「我慢する」というような判断になっているような感じですかね。
どう接してよいかわからないし、困るなら避ける・・・というような。
そこで、取り入れる事ができる関わり方が、愛着を形成する関わり方なんだなと。
どのように「受け入れるか」を周囲も考え、実践することが大切なんだと。
人との関わり方にも通じる
正直、本書の後半・・・より多いかもしれません。
子育て本のような印象で読み進めていました。
「愛着形成の臨界期が1歳半まで」であるということも書いてあるとおり、幼少期に養護者がどのように関わるかが重要なので、しょうがないはしょうがないんですが。
少し腑に落ちないというか、何を学ぼうか?・・・と考えました。
愛着障害というものを知ることができたこと自体が学びではあるんですが。
実際に自分の行動を変えるという意味では、まだ落とし込めていないなと。
なので、本の内容を思い返しながら日々を過ごし。
まためくってみたりして気がついたのが。
愛着形成のための関わり方が、そのままチームや組織での関わり方に活かせるなと。
もちろん、仕事上でそのような「特性」を持った人と働くことになることはあり。
労働人口の減少などの状況も考えると、お互いにストレスなく働くためにという意味合いにも使えますが。
どちらかというと、関わり方が複雑になり、ある意味では人間関係を築きにくくなっている今、愛着を形成するような、心と心のつながりを作るような関わり方が求められているんじゃないかと。
それが、正しく相手を受け入れること、相手が求めているこちら側の反応になるのではないかと。
そう思ったわけです。
そのためには相手に関心があること、関心を持っていることを示すのが大切で。
相手の気持ちや欲求を感じ取る感受性と、相手の反応や助けに答える応答性を高めることが大切であると本書では説明されています。
感受性と応答性を高めるのに効果的なものが、リフレクティブ・ファンクションを高めること。
もともと相手の気持ちを推し量り、共感するのが上手な人では感受性が高いが、苦手な人では子どもの気持ちを読み取れないということが起きる。相手の気持ちを理解する能力が弱い人では、自分を顧みる能力も低い傾向がみられる。両者は結びついた能力であり、リフレクティブ・ファンクション(reflective function)と呼ばれる。
第八章 安定した愛着こそ子どもを伸ばす P.253
引用部分は感受性についての説明の一部です。
相手の気持ちを理解する能力は、表面的な行動ではなく、そこに至るプロセスを重視し、本当の理解や共感による、相手を受け止め、肯定し、気持ちを共有することを繰り返すことで育む事ができる。
そして、そのような共感、傾聴の態度を取れているか、自分自身を振り返ることで、より相手の気持ちを理解する能力を高めることができる。
というように、この後の説明に続きます。
自分自身の振返りについて言えば、応答性を高めることにも応用できますね。
この時に重要なのが、できなかった自分を責めるのではなく、できなかったことの理由などの問題を考え繰り返さないようにすることです。
そうすることで、相手に関心を持っていることがより伝わりやすくなり、より良い関係を築けるなぁと思いました。
また、そのようにして、子どもに安心感を与え、関心を持っていることを示し、成長を促してくれる存在となることを「安全基地となる」と説明されていますが。
これはそのまま、信用・信頼される人間になると考えられ、特に上司の立場にある人が心がけられること何じゃないかなと。
別の本ですが、「心理的安全性の作り方」がふと思い起こされた瞬間でもあります。
家族もチームであると捉えれば、職場での人間関係にも適用できるはずです。
まずは、安心感を守ること。
居場所を感じるというのはもちろん、希望や未来を信じることができ、主体性が守られる状態を守ります。
まずはこの土台がしっかりしていなければ、安心して働いたり、何かの行動をすることができません。
今は社会の変化も早いので、社会に流されて毎回方向性が変わるようでは、安心感にはつながりません。
そして、その社会の変化の速さから、結果を求めてもそれが確実であるとは限りません。
昨日まで正解だったものが、今日は不正解かもしれませんし、その逆もありえます。
なので、プロセスに目を向け、結果以外の良いところを見つけ。
積み重ねるようにする方が、経験を積むという意味では重要です。
そして、一緒に苦しみを乗り越え、助け合う関係性を、リフレクティブ・ファンクションを使って築くことも重要です。
分業の時代が進み、専門性が高まったことで相手が何をしているのか良くわからないという状態があるかもしれません。
お互いにやること、できることに忙しく、主張が強くなってしまう可能性もあります。
だれも損はしたくないので、コストがかかることであればなおさらでしょう。
だからこそ、相手を理解するための行動とその行動をより良くして行く活動が、重要でもあるのです。
ざっくりと職場でとはなりますが、このように対人関係にも当てはめられるものです。
信用・信頼される人間になりたいのであれば、心がけた方が良い内容ですね。
効率化されるからこそ時間を使うポイント
自己啓発書ではなく、社会現象についての本なので何かを学び取る必要はないかもしれませんがー。
仕事もプライベートも便利になり、効率化されているからこそ、考えたいポイントです。
時間に余裕ができたことで、その隙間を何かしらの消費に使いがちですが。
人間関係という、効率化できないし、人間じゃないと取り組めないことに時間をかけるべきだと思います。
今後、AIなどの情報技術やロボットなどの機械技術も進展し、より生活が効率的になるかもしれません。
その時に考えたいのは、昔の大家族の時代にできていた愛着対象が近くにいる状態を、現代の核家族・共働きの状態でも作れるようにすることなのかなとか。
・・・意外と壮大な結論の感想文になってしまったかも。


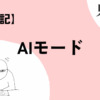
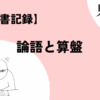
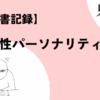
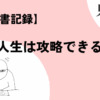
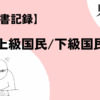
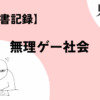

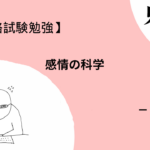
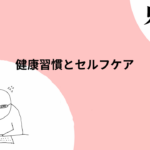
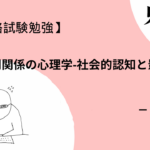


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません