AIでウェブ検索体験を再構築する「AIモード」
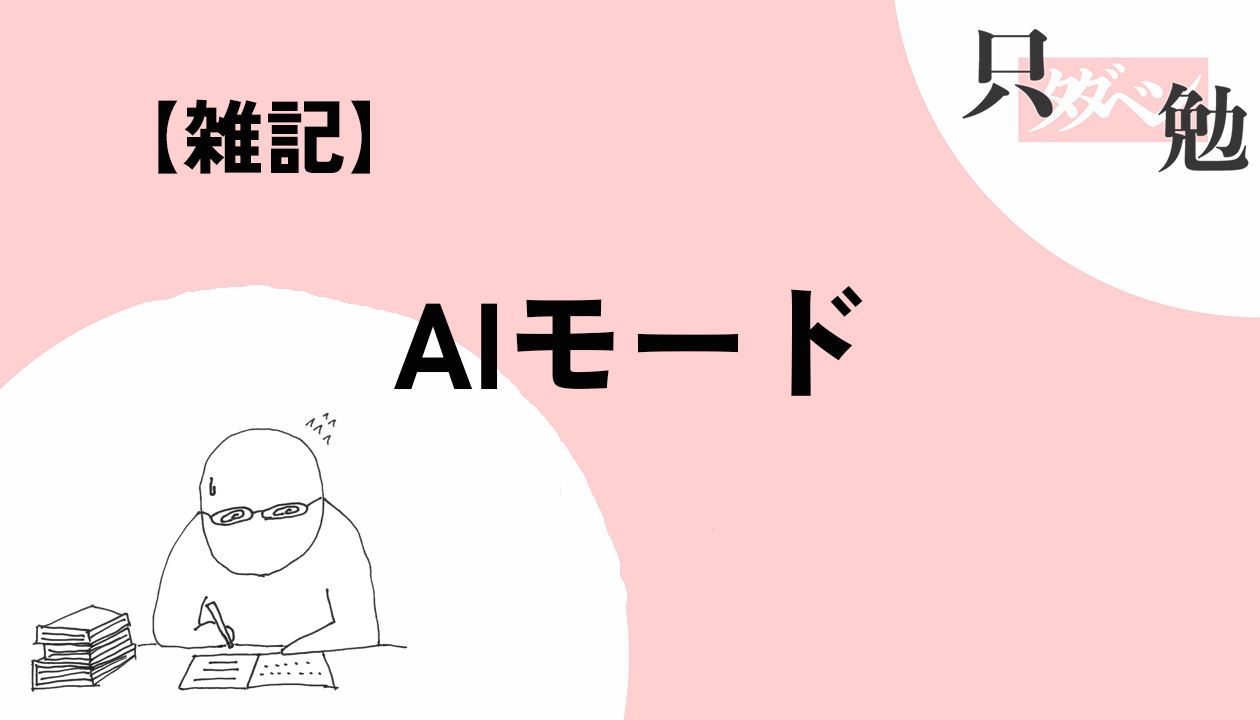
今後のWEB関連の流れがどのようになるのかと思い、Google I/O 2025関連のページをざっくりと洗っていたところ。
目に止まったのが「AIモード」という言葉です。
インターネット検索を始め、マップやスプレッドシートにカレンダー、コンタクト。
クラウドにApps Scriptなど。
Googleの提供するWEBサービスは、様々なところに入り込んでいます。
AIに関してはTransformerを開発したものの、少し遅れを取っていた感がありましたがー。
Geminiがリリースされてからは、生成AIという意味だと個人的にはかなり使いやすいなぁと思っています。
そんなGoogleの基盤は検索なので。
そこにAIを活用するというのが、「AIモード」らしいです。
今のところアメリカだけでの利用みたいなので、情報をまとめるという意味で書いていきます。
AIモード
「AIモード」はチャット形式でAIと対話しながら、複雑な内容を検索し行動につなげるもので、AIを使った検索体験の総称として使われるそうです。
ざっくりと概要を見てみても、今後のインターネット上での情報収集を劇的に変えるものにはなりそうです。
まず、今までの検索とは違い、チャット形式でAIと対話をしながら、インターネット上の情報を検索していくようです。
生成AIとのやり取りの用な感じで、情報を集め、深めていくというようなイメージ。
インターネット上の情報を利用してソースを示しながら、必要な情報の核心にまで迫るようような感じでしょうか。
ある意味では、専門家に質問を投げかけるようなイメージかもしれませんね。
で、驚いたのが「AIモード」ではGoogleが提供する他のサービスやリソースにある情報も利用できるということです。
WEBページや画像、マップといったものは、今は切り替えないと完全に検索することはできませんが。
それが一つのチャットの流れの中で確認することができるようになっています。
他に気を散らされることなく、検索することにより集中しやすくなる感じですかね。
また、AIと外部ツールを連携させるMCPなどの技術も話題ですが。
そのような外部ツールとの連携によるエージェント機能もあるようで。
例えば、お店を検索した後にそのまま予約してくれるとか。
靴を探していてそのまま購入してくれるとか。
キャッシュレス化により便利になった決済操作を、AIが代わりにやってくれるみたいですね。
ここらへんは幅広いサービスを提供しているGoogleだからこそ、連携しやすい部分なのかもしれません。
AIが変える検索体験
現時点でも、「AI Overview」という機能がGoogle検索には実装されています。
検索ワードから該当する記事群の要約を、検索のトップに表示してくれる機能ですが。
これが実装されてから、かなり便利になったと思います。
知りたい情報の概要を知ったうえで、ソースとなる記事を読むことになるので。
結果表示されているWEBサイトが、本当に知りたい情報を扱っているのかを判断することもできますし。
要約を知ることで、ソースとなる記事の内容も理解しやすくなるように感じています。
AIの情報処理能力が検索に生かされたことでの体験と言えますが、それをさらに自由にするのが「AIモード」というものだと自分は捉えています。
その答えのようなものが、私達が検索で使うワードの変化にあると思います。
あんまり意識していなかったことではあるんですが、以前に比べると話し言葉のようなクエリを入力していることが多くなりました。
以前は「近く ハンバーグ 美味しい」というような、単語を区切ったもので。
最近は「この近くのハンバーグの美味しい店」のように、話し言葉のようなクエリを使うことが増えたなぁと。
これはThink with Googleの記事でも(すこしニュアンスが違う気がしなくもないですが)扱われていたことで、検索に使用する語句が長くなっているという事実があります。
ある意味では、生成AIのお陰で検索ボックスのような入力フォームに、話し言葉でプロンプトを入力する機会が増え。
同じようなインターフェースを見ると、自然に話し言葉で入力するようになったのかなと思います。
また、Google検索にAIが利用されていて、その言語処理能力が上がったことで、曖昧な表現を含む話し言葉でも検索結果の表示の正確さが上がったことも関係あるかもしれません。
生成AIを使用していなくても、周りの知り合いがそのように検索しているとか。
音声入力で検索することが多いとか。
他の理由でも、話し言葉で情報を探すことに、私達が慣れてきているという可能性はありますね。
このように、Googleの研究の努力はもちろん、その技術を反映させたAIの利用によって、私達の検索体験は知らず知らずの内に変わって来ています。
それをもう一段階変えてくれるのが、「AIモード」であると言えます。
つまり、「AIモード」はAIの力を通じて、より検索が便利になるものであると考えられます。
「研究が現実に」
冒頭のGoogle I/O 2025のページの見出しの一つが、この見出しです。
Googleが取り組んできたAI開発のいくつかが紹介され、その最後の方に「AIモード」が紹介されています。
研究結果を盛り込んで「検索を再構築」することができたということでしょう。
そもそも、曖昧な表現での検索ができないわけではなかったものの、利用するにはかなりの負荷があったのは事実です。
検索を試行錯誤して、なんとなく耳に残っていた曲を探していた若い頃が懐かしい・・・
もちろん途中で検索することを諦めたこともあります。
それが、今回の「AIモード」の導入でなくなる可能性が高いですね。
またGemini以降で感じていたことではありますが。
AIのモデルが、情報を扱う精度が急激に高まったという印象も受けています。
生成AIの問題としてハルシネーションが挙げられ、今だに利用する場合には気をつけなければならない問題ですが。
少し前までは、AIが学習していないであろう情報については、解答の精度が怪しいことが多かった印象です。
・・・自分のプロンプトの能力も関係してそうですけどねw
ですが、WEB上の情報を扱うようになることで、学習に使われていないデータの利用(解析ですかね?)の精度も上がったような気がしています。
その結果がAI Overviewの便利さだと思います。
そして、ソースを与えさえすれば、ハルシネーションの少ない正確な情報によるやり取りが行えるという実感を与えてくれた、notebookLMの存在も大きいと思います。
生成AIの能力向上により、可能な検索の再構築なんだろうと。
そこに、Googleが持つ膨大なユーザーデータ(パーソナルコンテキストの方が良いんですかね?)も投入するということなので。
これはもう、AIエージェントの入口と言っても良いような気がします。
日本語で使えるときが待ち遠しいですねぇ。
AIがより身近に
「AIモード」で提唱されている内容を見た時に、一番最初に思い浮かべたのは。
SF映画でAIと喋りながらやり取りしている主人公の場面です。
日常生活の中に普通にAIが存在し、パートナーとなっている状態。
そんな世界が近いのかなとか思いました。
そのためにはまだまだ課題が多いとは思いますけどね。
だからこそ、人間がやるべきクリエイティブと、AIに任せる領域を把握しておく必要もありますし。
それを実際に体験しておかないと、AIが単なる恐怖になってしまうものです。
・・・というのを、最近みたなにかのCMで思いました。
AIが作業を豊かにするだけではなく、生活を豊かにする時が近いのかもしれません。
ワクワクします。
参考:
Google I/O 2025
検索におけるAI:情報を越えた知性へ
AIが拡張する「ググる」体験 Google検索トップに聞く「AIモード検索」‐株式会社インプレス
Googleは検索を”捨てていない”「AIモード」投入、狙いは過去資産の徹底活用‐(西田宗千佳)ITmedia
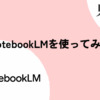
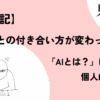
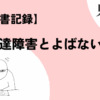

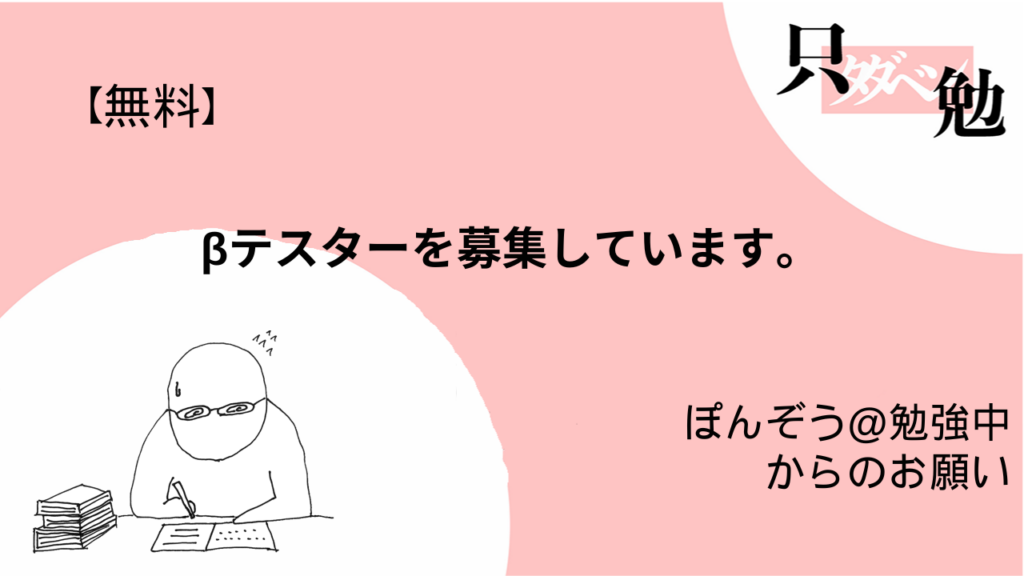
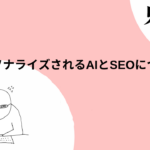
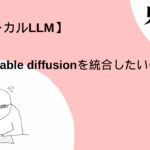
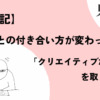
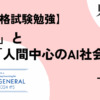


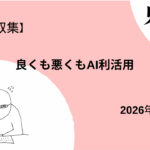
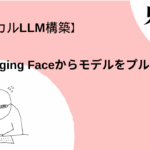
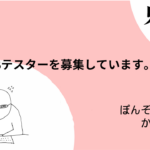
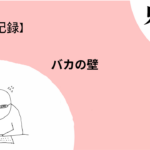
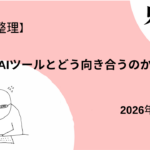
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません