【読書記録】ドーパミン中毒(著者:アンナ・レンブケ 訳者:恩蔵絢子)|「正直」から始まる「今」の人生
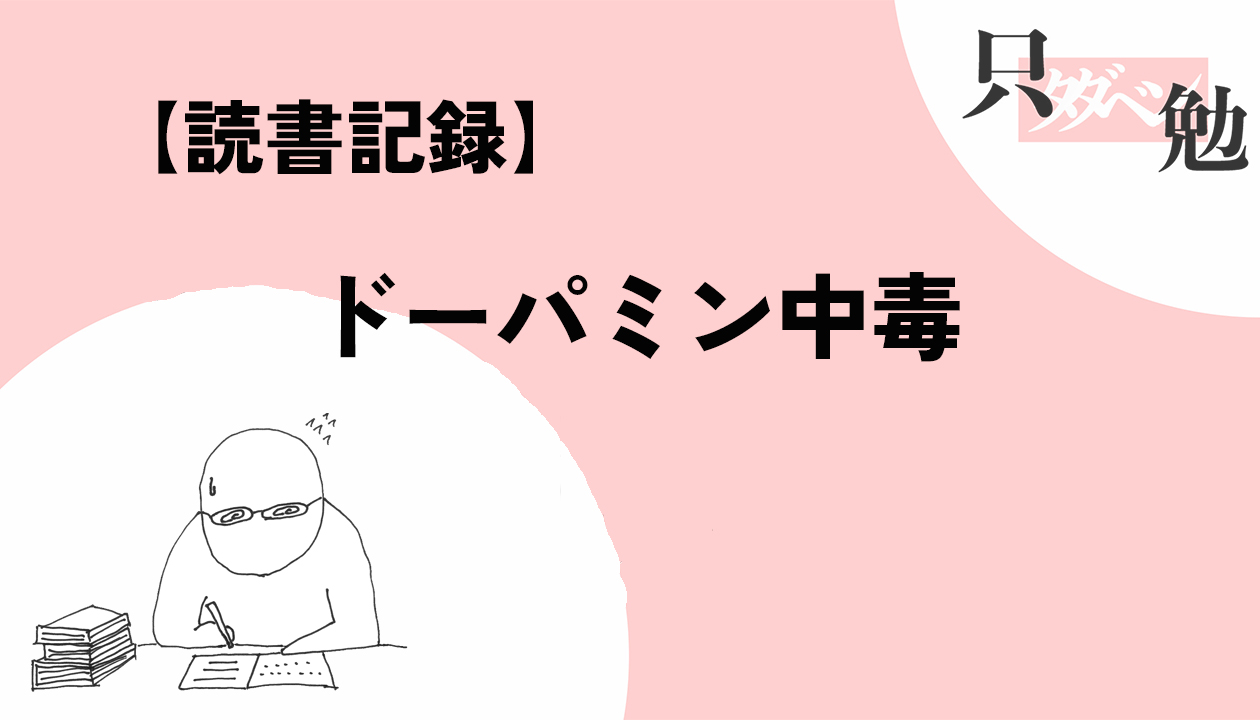
いやー。なんども下書きをやり直すことになってしまった、今回の本「ドーパミン中毒」です。
書き直し続けた結果、2行の下書きで投稿を一つ作ってみることにしました。
個人的には学びが多すぎて、どうにもこうにも長くなってしまう気がするので。
一番考えさせられた、「徹底的な正直さ」についてだけ感想を書いていくことにしました。
ドーパミンとは?
著者のアンナ・レンブケさんは、精神科医で依存症医学の第一人者だそうです。
著者自身が行った患者とのカウンセリングの内容を元に。
依存症に関係の深い脳内神経伝達物質である、ドーパミンの働きと問題につながる理由を解説しています。
本書によると、ドーパミンとは。
ドーパミンは報酬が得られたことの快楽というより、報酬を得ようとする動機の方に重要な役割があると思われる。「好き」というより「欲しい」に関係しているのである。
<中略>
ドーパミンが放出されればされるほど、また放出が早ければ早いほど、そのドラッグは依存性が高いと考えられる。
第3章 快楽と苦痛のシーソー P.74~7
本書では、依存性のあるものすべてを「ドラッグ」と表現しているため、スマホやSNSなどのデジタルなものも含まれています。
「欲しい」という欲求が働かなければ、食べ物を取ることさえままならないという、重要な神経物質がドーパミンです。
そして、「欲しい」という欲求が刺激され、その対象を手に入れたり利用することで快楽を感じます。
しかし、そのように手に入れた快楽は、心地よかったりするので。
もっと欲しいとか、続きを見たいといった、苦痛に変わります。
ドーパミンの発見に加えて、神経科学者は快楽と苦痛を処理する脳部位が重複していることを確認した。苦痛と快楽は相反過程のメカニズムで処理される。言い換えれば、快楽と苦痛はシーソーのように働くのである。
第3章 快楽と苦痛のシーソー P.75〜76
このような働きの元が、ドーパミンによって引き起こされるとのことで。
本書ではドーパミンを「苦痛と快楽を支配するメカニズム」として説明しています。
苦痛を避けるために快楽を追求します。
今はモノや情報が溢れているため、快楽になるものは人それぞれで多岐にわたりますが。
共通するのが、追求を続けることで、実生活に悪影響を与える依存症になってしまうということです。
その流れについての解説もとても興味深く、学びが多いんですがー。
この記事では取り上げないことにしました。
ただ、現在の状況で覚えておかないと行けないのは、他の本でもよく見かけるこの主張でしょう。
人間は究極の探求者となり、快楽を追求し、苦痛を避けるという課題にあまりにも一生懸命になりすぎた。その結果、私たちは世界をもののない場所から、凄まじくものが溢れる場所へと変えてきてしまった。
私たちの脳はこういった豊かな世界で生きるようには進化していない。<中略>
私達は今や快楽を感じるのにより多くの報酬を必要とし、小さな傷でより多くの苦痛を感じるようになってしまった。
第3章 快楽と苦痛のシーソー P.93~94
モノが溢れることで、次から次へと快楽の元が提供されます。
(あ、一応感じたことではありますが、快適というものも含めて快楽という強い表現にしていると思います。快適を超えて不必要な楽になると快楽だと思いますし。)
なので、一つの快楽を追求し始めると、終わりがなくなるという状況です。
しかし、脳はそれに対処するように進化していないので、狩猟時代とほぼ変わらぬ状況判断をするわけです。
ある意味では、欲求に従うことが、結果的に依存症につながっていると言えるかもしれません。
読み進めながら思ったことは、時間の使い方が関係してくるのではないか?ということでした。
消費に追われることで過剰摂取する
モノや情報があふれることで、消費することに全力を注ぐようになっているのが現実だと思います。
一時期、倍速で動画や映画を視聴するということが話題になったことがありましたが。
それぐらいしないと、消費できないくらい、コンテンツが溢れていると言えます。
つまり、起きている間、時間があれば、自分の欲求を満たすモノに触れていないといけない。
そう思ってしまいやすい状態です。
消費することによって、その対象に対する依存が生まれ。
それが継続することで、脳の仕組みが変わり、その対象がないと正常な機能を果たせなくなり、依存症につながっていく。
その結果、本来使うべきことに時間を割く事ができず、「小さな傷」に耐えられなくなっている。
このように読み進めていて思いました。
じゃあ何に時間を使えば避けられるのかというと。
様々な方が、瞑想や読書、ノートなど様々な方法を提唱していますが。
本書の内容を引用すると、「自分に正直になる」ということです。
徹底的な正直さー大きなことでも小さなことでも真実を言う、特に自分の悪癖が顕わとなり、深刻な結果を伴う時にこそ真実を言うことーは依存症から回復するためだけではなく、この報酬の溢れる生態系の中でどうやってバランスを保って生きていけば良いか探っているすべての人たちに不可欠なものだ。
第8章 徹底的な正直さ P.238
嘘をつくことによって、どのような反応が起こり、依存症につながるかを説明している部分ですが。
これは、相手に対して嘘をつくのではなく、自分に対して嘘をつくことに対しても適用されています。
そして、この嘘は「今」の自分に対してついていることになります。
インターネットの発達によって見えてしまったもの
本書の流れとしては、自分に正直になることで依存症からの脱却や、居心地の良さを感じるコミュニティが見つかる、というとても前向きな流れが描かれています。
しかし、最後の結論の冒頭の文章をなかなか理解できずにいました。
私達は皆、世界からー自分自身や他者に設けた実現不可能な基準からー解放されたいと望んでいる。自分自身の容赦なき反省会から一時的にでも解放されたいと思うのは自然なことだ。
結論ーシーソーの教訓 P.309
なぜ最後の始まりがこの文なのか?
読み進めると、快楽ではなく自分に没頭し、「世界」を見る方向を変えて直視することが大切であるように書いてあります。
結論に至る前の文脈を考えると、様々な方法や代替手段は考えられるが、自分自身に徹底的に正直になることが何よりも重要なように感じます。
となると、快楽は世界から解放されるために手を出す手段ということになりますが、それは解放に至る正しい手段ではないということはここまでで分かります。
ということは、「世界」の見方を変えるしかないということになり、ここに正直さが必要ということになります。
ここまでの、筆者と面談を重ねた患者のことや、扱われている内容というものから考えてみました。
そこから導いたのは、この「世界」とは、自分自身の理想や期待という尺度であるということです。
つまり、起こるかどうか分からない「未来」だと考えると腑に落ちました。
今はSNSの発達により、個人間のコミュニケーションが取りやすくなり。
有意義な関係性を築きやすくなっていますが。
自分自身の理想とするものや、期待する状態というものが見えてしまいます。
それは、自分が「未来」にありたい姿が、身近に感じる存在から見えてしまうということです。
その「未来」に期待する姿と、現実である「今」の自分を比較し、そこに達していないことに苦痛を感じるわけです。
すこし話はそれますが、「今」はモノが溢れ豊かであるために、「未来」に対する不安が強くなるとも考えられます。
不安の対象が「未来」であるために、「今」を正しく認識しようとしない、または認識させないようにしてくる状況があるとも考えられます。
これが、先進諸国で全般性不安障害の人が増えているという、冒頭で扱われた内容にも納得したところ。
すごく身近なところとして、相手に期待する反応というのは、自分が「今」起こした行動に対する相手の「未来」の行動とも言えます。
このように、「実現不可能な基準」である「未来」と自分の置かれている「今」を比較してしまうというのが、問題なのであろうと。
どうなるか分からない「未来」に対して、「今」の自分がダメだと思っても、どうしようもありません。
「今」の自分は「過去」の積み重ねであり、「未来」は「今」の積み重ねでしかないのです。
つまり、悩みや苦痛に感じる対象の時間軸がズレているから、どうしようもない、なんとなくの不安を抱え苦痛に至るということです。
だから、この時間軸を「今」にする。
つまり、「今」の自分に対して「徹底的に正直」になり、できる自分・できない自分を受け入れることが始まりなんだろうなと。
そして、ドーパミンの働きを「今」の自分のために向け、「自分に没頭」し。
それを継続して、周りを気にせず「前へ進んでいく意思」をもつことで。
この瞬間には何の影響もないように見える今日の自分の行動が、実際にはいい方向へ向かって積み上がっており、それがいつかわからない時に明らかになるーという信念を持てばいいのだ。
結論ーシーソーの教訓 P.312~313
という、「今」に集中すること。「今」を大事にすることが、現代を生きやすくする術なのだと。
すごくじっくりと教えてもらうことができた。
楽に流れるのは簡単だ
これは自分自身を戒めていることでもありますが、人間はほっておくと楽な方に流れると思っています。
そして、自分の事を見つめ直したり、欠点を知ることはとても苦しいことです。
もちろん個人差がありますが、それが結局落ち込む原因にもなりかねません。
しかし、そんな自分を受け入れ。
その背後にどんな想いがあったのかを正確に理解する。
本書にも書かれている、「マインドフルネス」の実践が、重要なのかもしれませんね。
ドーパミンを刺激する快楽が溢れるのは、ある意味パーソナライズが進む世界ではしょうがないのかもしれません。
そんな中で、「今」を大事に過ごすことの大切さを知ったという。
ちょっと思ったのと違いますが、学びも楽しみも多い本でした。


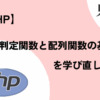
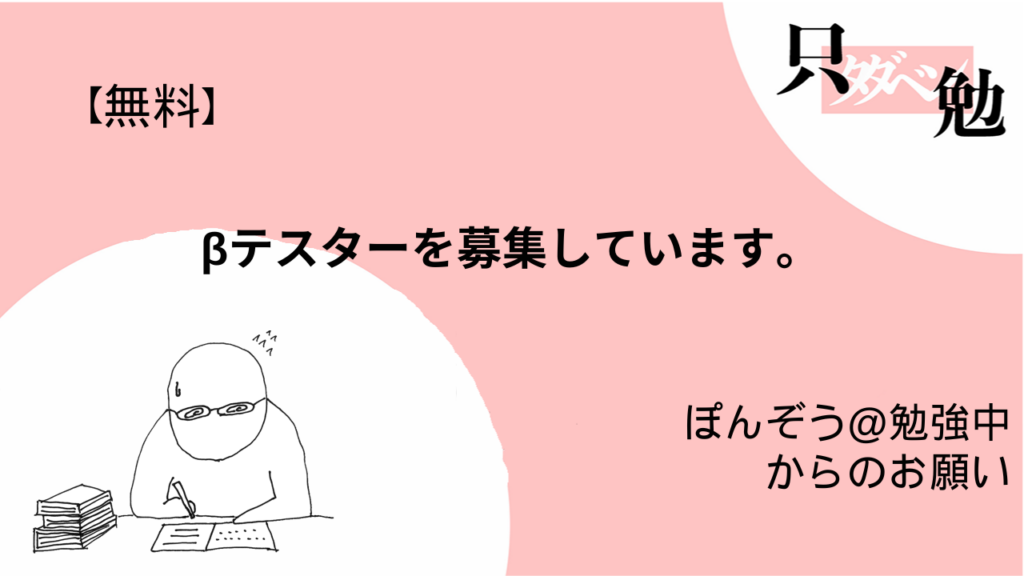
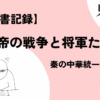
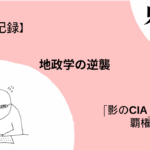
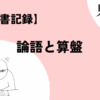
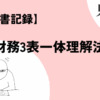


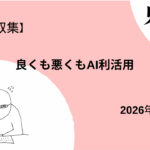
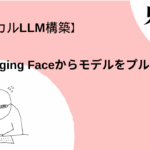
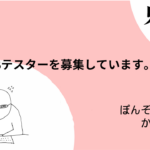
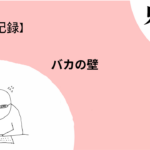
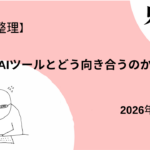
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません