ブランディング戦略から考える「ブランド」
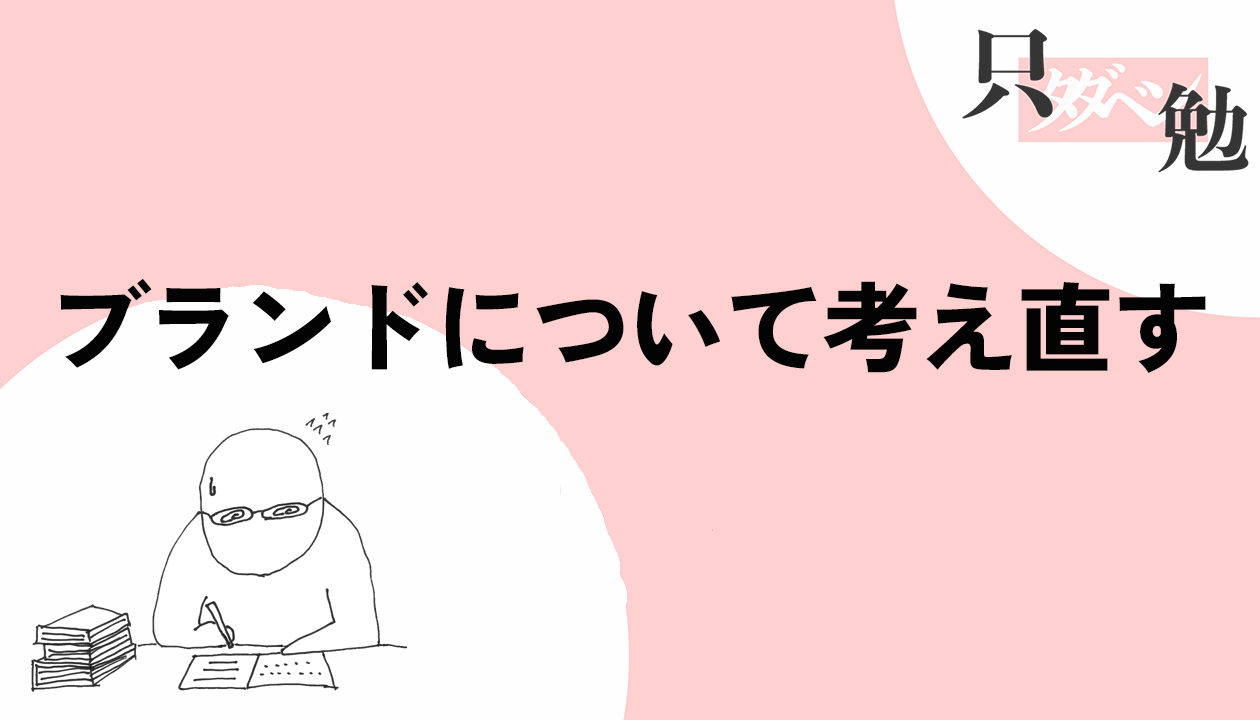
AI生成コンテンツが猛威を振るっています。
AIは便利なので私も使っていますがー。
SEO関連の情報を漁っていると、自分の体感よりも多くのAI生成コンテンツが出回っているんだなと思います。
あ、このブログで適当に書いているものは、自分の考えをツラツラ書いてるだけです。
・・・AIの方が高品質かも知れませんがw
で、コンテンツがWEB上に溢れている中で、見直されているのがブランディング戦略なのかなと。
住さんの「Googleは「ブランド優遇」SEOの成功の鍵はブランディング」という記事を読んだことが、考える切っ掛けとなりました。
自分も普段の仕事の中で、ブランディングについては考えてやることを決めてはいるものの。
少し「ブランド」の捉え方を変える必要があるんじゃないか?
と記事を読みながら考えることになり。
その考えたことを適当に書いていこうかなと思う次第です。
「ブランド」について
仕事でブランディング戦略について扱った事は何度かあるので、少しその考えに固執していたところがあるかなと、反省しているのが今です。
ブランディング戦略は「ブランド」をブランド化するための戦略です。
ブランドを言葉だけの意味で調べると、「信頼」という言葉になります。
では、信頼とは何かというと、「信じて頼ること」または「頼りにできると信じること」という意味の言葉です。
つまり、「なにかを信じてその効果に頼る」のか、「その効果が得られると頼って、なにかを信じられる」という二方向の意味合いがあるということになります。
ここにいれた「なにか」がブランドで、信頼の元になるものですね。
企業名やメーカー名、製品名や商品名といったブランドを表すものです。
ざっくりと、すでにある製品やサービスの効果を信じて頼るのが前者の意味合いで、製品やサービスの提供者や関連製品の効果を信じて別のものを頼るのが後者の意味合いになってきますかね。
この両方向からの信頼を得られれば、提供者としても提供しているもの自体も信頼されている、理想的な状態だとも捉えられます。
こう言葉にするのは簡単ですが、信頼を得るまでの過程を考えると、気が遠くなりますし。
継続的な信頼形成のための一貫した努力が必要であることも分かります。
ブランディング戦略は、この努力を効率的・効果的に推し進めるためのマーケティング手法で、それによりファン化した顧客を獲得するためのものですが。
そもそもブランドが確立されていないと、この戦略を取ることはできません。
なんとなく形にして、なにがなんだか分からないブランドを信頼するのは無理でしょう。
なので、ブランドをどのように作るのかを考えていきます。
ブランドの構成要素
ブランドの構成要素というとなんだか堅苦しいですが。
5W1H のような形で考えるとしっくり来るかもしれません。
「誰が【Who】、どんな立場(ポジション)で【Where】、どんなことを言い(または、作り)【What】、どれくらいの人に【How many】、信頼されているか?」
・・・ちょっと無理矢理感はありますが。
この長い一文を考えると、ブランドがどのように構成されているかが分かります。
ブランドというと、メーカー名や製品名などが浮かぶと思いますが。
その浮かんだメーカー名や製品名を、何らかの理由で信頼しているから、「ブランド」というものになります。
品質や価格など様々な要素で同じような物があるにもかかわらず、そのブランドを選ぶわけです。
それはなぜかというと、品質や価値を信頼しているからということになりますが。
その品質や価値を表すものが、その製品やメーカーの存在する市場の中で、際立つ個性となっているからです。
その個性により特徴を持ち、他の類似品とは区別されているわけです。
しかし、際立つ個性があるからと言って、それだけではブランドにはなりません。
というのも、際立っていても、使っている人や効果を実感している人がいなければ、その製品やメーカーを信頼することができないからです。
用意したサービスや製品を利用してもらうために、広告やマーケティングを実施し、手に取ってもらう必要があります。
つまり、ブランドを用意するのは提供者ですが、ブランドにするには顧客の力も必要なのです。
市場調査や自社の強みなどで、製品やサービスに対して、「独自性」を提供者が作り出し。
知ってもらう努力をしながら顧客に知ってもらい覚えてもらうことで、「認知性」を高め。
興味を引きながら、使ってもらい売り込んだ内容通りの効果を実感してもらうことで「信頼性」を高め。
そのように信頼をもった顧客が他のまだブランドを認知していない人に進めることで、「評判」を呼び。
ブランドに対するファンを増やし広く知られることによって、ブランドとして認識されるようになります。
なので、ブランドを作ること自体が、時間のかかる作業であることが分かります。
しかし、一度提供した「独自性」を「認知」してもらい「信頼」してもらい、「評判」を獲得できれば、ブランドを一緒に作り上げたという感覚がファンにも生まれ、硬い信頼関係を築くことができます。
実際に、住さんのブログの中の「ユーザー行動」のでもアメリカでの調査結果が掲載されていますが、知らないブランドよりも知っているブランドのものが選ばれるという報告もあります。
このようにブランド化することの効果が高いことは分かりますが。
どうしても時間がかかりますし、市場の状況によっては思った通りの成果にならない場合もあります。
そのために考えたいのが、「範囲」です。
誰に・どこに向けてブランドをうたうのか
信頼の言葉の意味で、「頼りにできると信じること」というのを取り上げましたが。
すでに何らかの製品・サービスで、ある市場に対してブランドとして認知されているのであれば、同じ市場でブランド価値を持つことはできます。
しかし、別の市場に対して行う場合には、その効果は期待できないかもしれません。
市場規模や、所属する市場が他の市場に与えている影響度、または市場を超えた認知度があるかによっても変わるので、もちろん一概には言えません。
しかし、そのような規模を大きく戦略を打つにはコストがかかりすぎます。
なので、まず考えるのは「どこの誰に向けてブランドの存在を知らせるのか?」ということです。
つまり、マーケティングでいうターゲット設定やペルソナ設定です。
これらの設定を行うことで、用意したブランドの独自性を認識し、好んでくれる層に向けてマーケティングを効果的に実施することができます。
そして、ターゲット設定をすることで、「範囲」も決まって来ます。
この「範囲」というのは、年齢や性別と言った個人に関わるものだけでなく、サービスや商品の流通方法による地域の範囲も決めることができます。
つまり、認知してもらうための範囲が決まることで、どのような個性を際立たせた方が良いのかわかりやすくなり。
製品やサービスで得られる効果をターゲットに合わせて具体的にすることができます。
また、顧客との関係性構築の活動も一定の範囲に絞ることができ、マーケティングも効率的になります。
ブランド化はじっくりと
「範囲」を絞ったとしても、その中で取り組むことは変わりませんし、手を抜くこともできません。
信頼できる独自性というものは、ただ製品やサービスを作るだけでなく。
製品やサービスに込めた思いやビジョンを提示し、共感してもらうことも大切です。
そうなると、提供元自体がその思いやビジョンに反した言動を取るわけにはいきません。
つまり、活動全体・取組全体で、顧客や社会との関係性を考えなければならないのです。
何でもそうですが、取り組むと効果をすぐに求めたくなりますが。
少しずつ認知を広げていくイメージで、確実にブランド化する方向で考えるのが良いかもしれません。
もちろん、かけられる予算にも寄りますが。
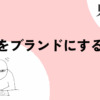
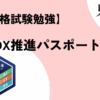

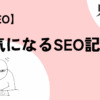
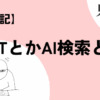
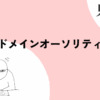




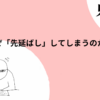

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません