【読書記録】始皇帝の戦争と将軍たち 秦の中華統一を支えた近臣集団(著者:鶴間 和幸)|漫画「キングダム」のお供に持っておきたい
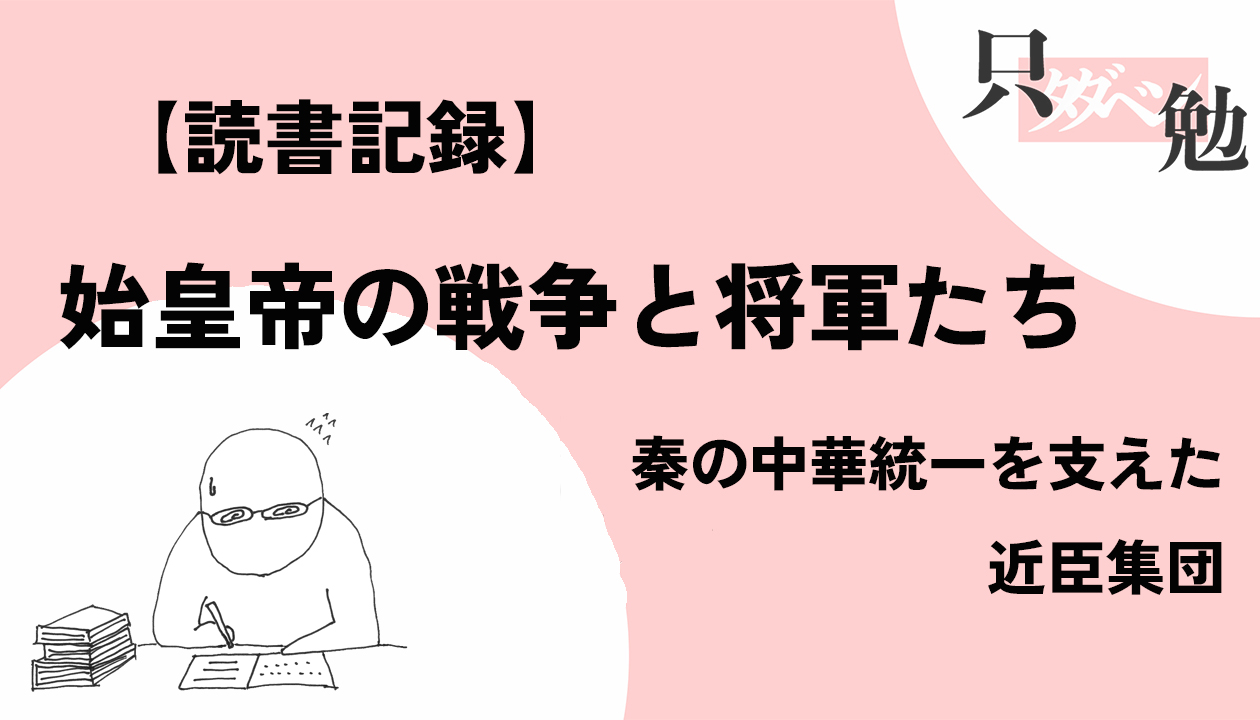
書店に並んでいたのが、実写映画「キングダム 大将軍の帰還」が公開されてから少し後(初版を見ると、2週間後みたいです)だったので、タイトルに興味を惹かれつつ。
帯にも「『キングダム』原泰久先生 推薦!!」の文字があり。
悩みに悩んだ末、読むことにしたのが、今回の本「始皇帝の戦争と将軍たち」です。
「キングダム」は好きで、漫画もアニメも実写映画も見ております。
ゲームもキングダム関連のしか、気がついたらやってないですねw
キングダムゲームの攻略?ブログも書いたりしてます。
連載しているヤングジャンプに掲載された、原先生のインタビューなどから、史実を元に物語を作られているのは知っていましたがー。
なんとなく、史実に近いものにはあまり触れないようにして過ごしてきたのが私です。
もうサービス終了してしまいましたが、「キングダムセブンフラッグス」というスマホゲームでのこ゚縁があった、ぴーよしさんのYoutubeチャンネルをたまに見るくらいですかね。
なんでしょう。
ネタバレになるからとか、そういうのではないんですが。(そもそもそんなに記憶力は良くないので、読んでもたぶん忘れますw)
「キングダム」で描かれている武将達のキャラクターが好きなので、史実による実際の雰囲気を想像できるようになるのは、なんか嫌だなぁと。
実写映画になったら、感じるような違和感に似たようなものを感じたくない・・・(あ、キングダムの映画はそういうの抜きで楽しみましたw)
というので、読むかなやんでいたのです。
が。結果的には読んだことで、よりこの先の「キングダム」の展開が気になることになりましたw
「人間」始皇帝をとりまく人間模様
正直、中国史は学生の頃の歴史の授業の知識程度で、大学生の頃に読んだ「蒼天航路」で三国志を補填したような人間です。
なので、始皇帝のイメージは授業でやった「初の中華統一」はもちろん、「焚書坑儒」や「万里の長城建設」というものしかありません。
で暴君として説明されることが多く、今回の本の中にもそのように書かれていますがー。
まぁ、初の統一王朝で、文化や思想が違う人達をまとめ上げるには・・・とか、巨大になった領土を脅威から効率的に護るには・・・とか、そんな感じであんまり暴君というイメージはもともとありませんでした。
かといって、「キングダム」で描かれる嬴政のような、賢くて勇気のあるイメージもなかったんですけどね。
今回の本「始皇帝の戦争と将軍たち」の著者である鶴間和幸先生は、秦漢史を研究されている歴史家のです。
始皇帝がどのような人間であったのかを研究し続けていらっしゃるとのことで。
始皇帝が中華を統一する模様を、単なる史実からどのようなことが伺えるかということではなく。
史実に登場する始皇帝の近臣や、敵国の英傑たちとの関係をもとに、当時の情勢なども踏まえ紐解かれています。
本の約4割が始皇帝や秦と関係の深い人達のあらすじとなっていて、人間模様を重視しているというのが伝わりますし。
目次を読んで、これなら読もうかなと思えた理由でもあります。
歴史はロマン
・・・というと、少しありきたりな感じですが。
「始皇帝の戦争と将軍たち」の本を読み終わった後に思ったことなんですよね。
本編となる中華統一までの歴史的なことについては、自分は何も言えないんですが。
始皇帝と近臣の絆は、他の中国史と比べても特異なものだったようです。
兵馬俑のような墳墓が作られるのはよっぽどのようで。
たくさんはなくても、似たような墓の形があるのかと勝手に思っていた分、ここからも絆の強さを感じることができたというのに驚きました。
「始皇帝の戦争と将軍たち」の中でも繰り返し述べられていますが、始皇帝の死によって朝廷内の統率が取れなくなり、秦が滅ぶことにつながったと。
「おわりに」の中で、鶴間先生はこのように書いています。
始皇帝と近臣集団の関係は、始皇帝の死によって次代に受け継がれるものでなかった。二世皇帝胡亥は、また新たに近臣集団を築く必要があった。しかしながらその暇もなく、秦という国家は崩壊してしまったのである。
おわりに P.242
本文の内容とこの部分まで読み進めて思ったのが、始皇帝に対する忠誠以上の関係が近臣集団と築けていたんだろうなと。
それが、強固過ぎたことが、秦崩壊のきっかけになったのかもしれないなと。
なんとなくその気持がわかるというか。
秦という国に仕えるという意識よりも、始皇帝に仕える。始皇帝の描くビジョンを実現するために命をかけても惜しくない。
・・・という、まさに「キングダム」で描かれているような、熱い関係性だったのではないかと思いました。
でも、その熱意というか思いというのは、向けている対象がいなくなると変わってしまうというかなんというか。
仕事でも、この人の元でなら・・・と思っていた人がいなくなると、転職などの別の道を探すこともあるもんなぁと。
そうならないように、そういった慕ってくれている人たちが残るように立ち回るものだとも思いますが。
それができなかった原因は、巡業中の病という始皇帝の死因だったのでしょうね。
「引き継ぎ」の難しさを考え込んでしまいましたw
このような人間模様が見えてきたのも、「人間始皇帝」の研究をされてきている鶴間先生の著書だからだと思います。
そんな「歴史家」という職業について、鶴間先生はこう書いています。
私たち歴史家は史実だけを追い求めているようであるが、実は違う。史料を読み、史実を並べただけでは歴史学にはならない。いくつかの史実の間を結びつける何かを見出す作業は、フィクションを生み出すことではないが、史料には書かれていない歴史の真実を発見するものである。
おわりに P.243
「歴史家」という職業の面白みとも言えるかもしれませんが。
「キングダム」の作者である原先生も、インタビューの中で春秋戦国時代は史実の空白が多いから、面白みがある・・・というようなことを言っていた気もします。
史料を並べ、その間にあるつながりを考え、発見し、思いを馳せるような。
そんな仕事なのかなぁと。
その成果として、学校の授業で教わるのとはちがう、始皇帝の姿を見せてもらえたんだと。
そんなふうに思います。
すこし読まず嫌いをしているところもある、歴史本に対する見方が少し変わった一文でした。
解釈や捉え方の違いを楽しみ、どのようなことを歴史から学び取るのか。
そういう読み方をしてみたいなとも。
「キングダム」を読む時のお供に
「始皇帝の戦争と将軍たち」は、嬴政が秦王に即位する少し前から、中華統一を果たすまでの流れを地図を使って説明してくれています。
「キングダム」の連載もこの記事を書いてる段階で、韓への侵攻がはじまったところなので。
地図を見ているだけでも興奮しますねw
「キングダム」の合従軍編のときに、李牧が「この中華が詰みかけた」という理由も知ることができます。
そんな合従軍編は、「キングダム」の中でも登場人物が一気に増え、読み応えのあるところですが。
史実だと、それがいつ起きてもおかしくなかったというのに驚きです。
秦の戦争の後ろにあった、「合従と連衝」というつながりの戦いのためのようです。
合従が縦のつながり(趙・魏・韓・楚)というイメージで。
連衝がその縦のつながりを断ち切るための、横のつながりというイメージ。
この戦いの変遷が、この本で統一戦争の解説に使われている、秦の国境の変遷を表した一連の地図ですね。
秦に危機をもたらした合従軍は、領土的にもまさに縦のつながりで。
統一を目指す秦の戦略は、東方進出でその縦のつながりを分断するように侵攻していることが見て分かります。
しかし、そのように侵攻している間は、いつでも合従軍がおこってもおかしくは無かったはずで。
戦場で戦っていた将軍たち意外にも、遊説の士と言われている人たちも使って阻止し。
思想でも軍略でも全てを使う、まさに総力戦だということも分かります。
この縦と横の関係というのは、世界の歴史を表しているような感じがしたというところでも、面白みを感じました。
このような背景の中で、昌平君が総司令として軍略を考え、昌文君や李斯たち文官がそれを支え、信たち武将が戦場実行する・・・・という。
「キングダム」で描かれる世界がより深みをましたような気がします。
で、「キングダム」と史実での人物の描かれかたが違うことも面白かったですねぇ。
李斯がこんなに活躍しているとは思いませんでしたし、趙高って太后の側近の趙高かな?とか。
より「キングダム」のキャラクターの事を考えるようになりました。
逆を言えば、信自身も「謎の多い武将李信」と言われることが史実だとあるみたいなので。
空白の多い人物を、原先生の力で物語の中心にすえ、世界観を作っているのかなとか。
「キングダム」に対する読み方も変わったような気がします。
これから描かれる戦いや出来事の背景、人物などに思いをはせながら読める。
「キングダム」を読む時に横に置いておきたい本です。
興味があることだけど
「キングダム」という好きなコンテンツをきっかけに読むことにした、「始皇帝の戦争と将軍たち」ですが。
結果的に、より「キングダム」の内容を面白く感じる事になり、歴史を知ること自体も楽しくなりました。
ためになる本だけでなく、こういった興味につながる本も読んでいきたいですねぇ。


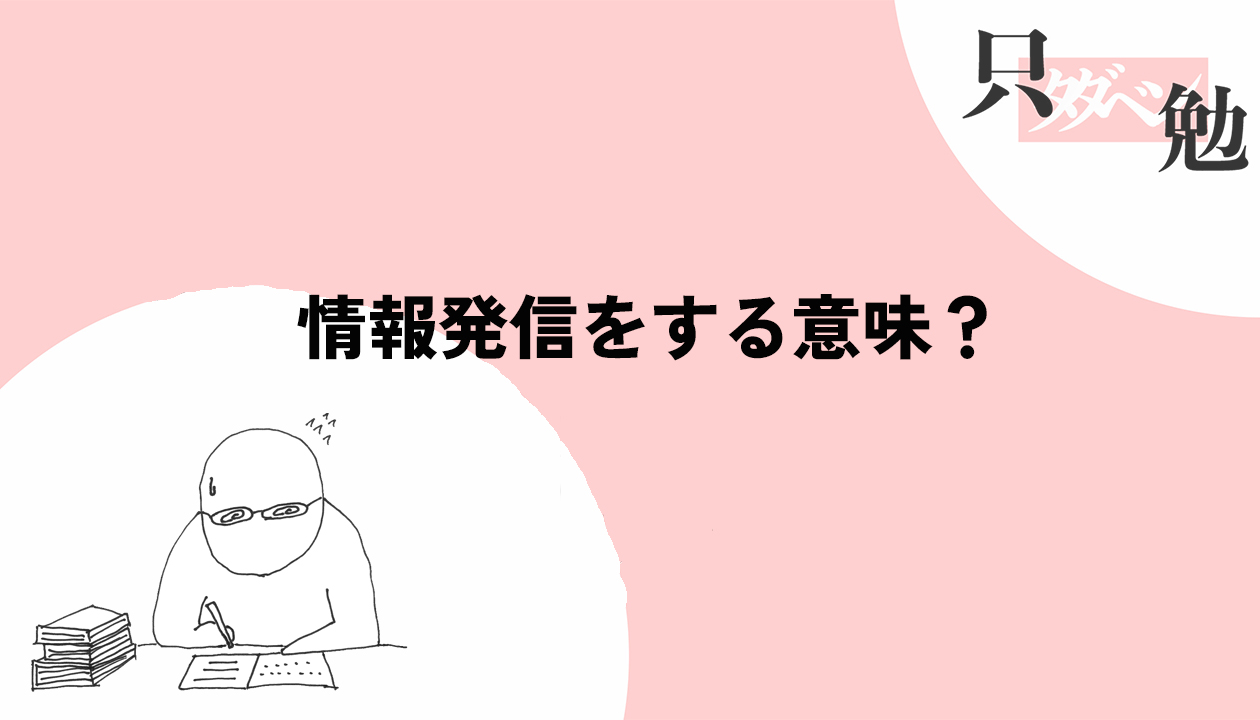
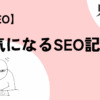
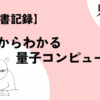
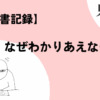
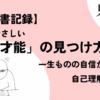
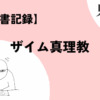
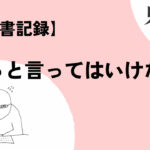




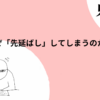

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません