勉強と記憶のメカニズム
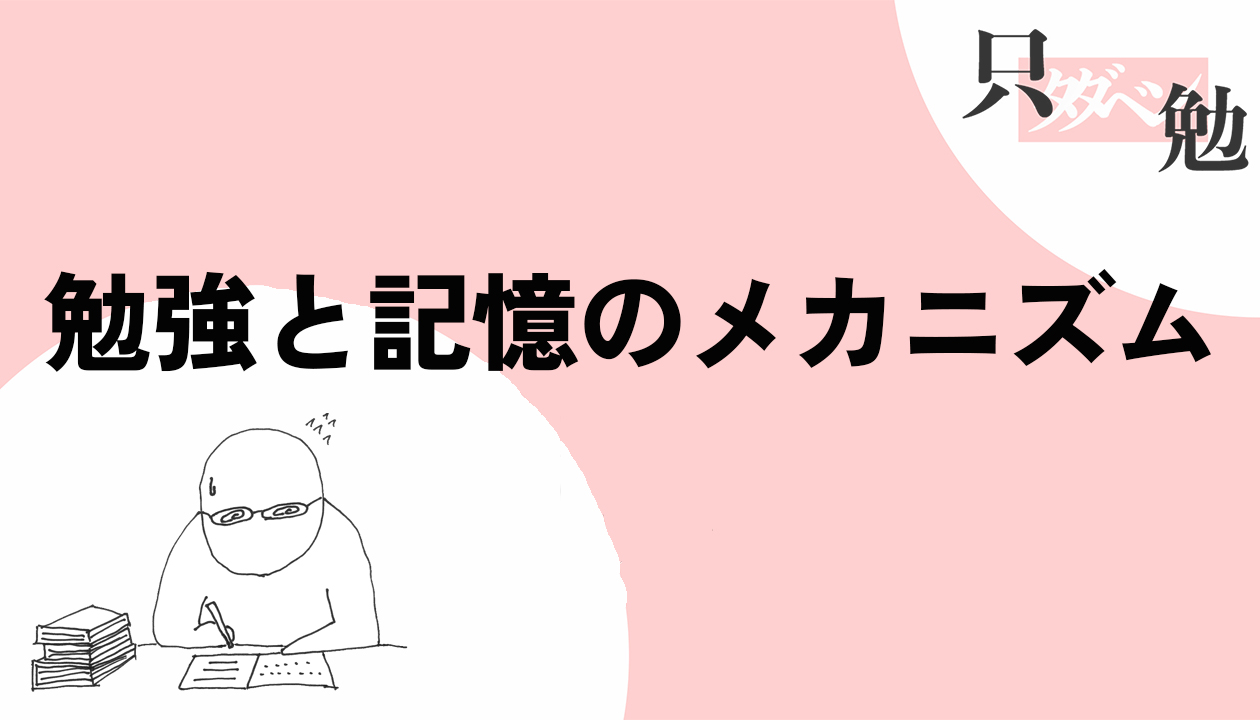
一応、資格勉強関連の記事をいくつか投稿している当ブログです。
自分の理解を深めるために投稿しているものや、体験を投稿しているものなど。
それでも、繰り返し学習しないと覚えるところまでは行かないですね。
勉強方法について発信している方々も繰り返し学習することを伝えていて。
徐々に復讐の期間を空けていくという感じだったかと思います。
人間の記憶は忘れるようにできていて、ガーッと一時期に詰め込むだけでは定着には結びつきません。
なので、「思い出す」ということが必要です。
そんな記憶のメカニズムについてまとめ、今後の学習に活かせたらなと。
・・・忘れないと良いですがw
記憶といえば「脳」
記憶がどこにあるかといえば、脳です。
まずは生理的なメカニズムについて、ざっくりと。
大脳辺縁系に記憶に関する部位が集まっていて、主に海馬と扁桃体があります。
記憶といえば海馬ですが、記憶に関する閉鎖回路で文脈としてつながった記憶(エピソード記憶)が形成されます。
主に睡眠中に記憶の再生・統合が行われ、大脳皮質で保持されているようですね。
私達が当たり前のようにしている身体の動きは、大脳基底核や小脳で保持され。
考えなくても自転車に乗ったり、物を動かしたりできます。
扁桃体では外側核において、感情に関わる記憶の形成がなされます。
主に恐れに関係する記憶の形成に関わるとのことですが、海馬とは別で記憶されるほど重要な記憶であると考えられます。
恐れなど生死に関わる記憶なので、回避するために備えられた記憶回路なのでしょう。
これらの記憶を強化する仕組みは神経伝達物質のアセチルコリンが担っています。
詳しくは「自律神経の科学」の本をお読み頂ければと思いますが、脳血流の調整を行う物質です。
アセチルコリンは海馬や大脳皮質といった記憶に関する部位で分泌され。
血流が増強されることで、活動が活性化され神経結合を強化します。
勉強に関わる記憶の部位でいうと、海馬や・・・感情を動かしながら学べば扁桃体もですね。
これらも脳の機能のとして働いてくれるわけです。
そのため、アセチルコリンの分泌を妨げるとされる、睡眠不足やストレスを割けることも記憶の定着には重要です。
勉強していると気がついたら時間が経っていることも多かったり。
区切りが悪くて決めた時間をすぎてしまうこともありますが。
睡眠時間を確保して、生活リズムを安定させ。
学んでいることに感情を働かせることが、正しく記憶する方法の一つであるといえます。
記憶の処理
脳の機能としてはあくまで記憶を受け取り、保存するというものです。
その機能を正常に保つために、規則正しい生活を送ることが大事だというわけですが。
実際に脳に記憶を送り込むメカニズムを心理学から見てみます。
獲得した情報の扱いとしては、記銘化(コード化)➾保持➾想起、という流れの中で残る記憶として処理されていきます。
外部情報を感覚器官が得る
↓
感覚記憶(重要度や好感度を測るフィルター)
↓
注意を向けられた情報が「記銘」される
↓
短期記憶
↓
長期記憶
↓
想起
という流れで処理されます。これを「多機能貯蔵モデル」といいます。
記銘化された情報は、リハーサルによって繰り返し処理され記憶となります。
短期間記憶を保持する処理が「短期記憶」で、維持リハーサルが行われます。
英単語や漢字の暗記のように、繰り返し同じ事を繰り返す処理です。
みなさんも体験があるかもしれませんが。
テスト前に一生懸命繰り返しおぼえたのに、終わったら忘れてしまうという記憶。
この忘れやすい記憶が短期記憶のものです。
そのため、「長期記憶」に情報を移すことが大事ですが、その時に行うのが精緻化リハーサルです。
精緻化とは、意味・関連を考え深い処理を行うことで。
これにより記憶の定着が良くなる効果を「処理水準効果」といいます。
リハーサルというぐらいなので、これらを繰り返し処理することが記憶の定着につながり。
思い出す「想起」の段階で利用できるようになります。
脳や心理学のメカニズムを見ると、人間という動物が自然界で生き残るために必要な機能なんだなと改めて思いますね。
瞬発力が必要であろう、強烈な体験や運動に関わる記憶は、脳の別の機能で保持されていたり。
多少の危険をさけ、快適に生きるために、繰り返し体験・学習し休息を取ることで定着・習慣化できるんだなと。
記憶を強くするために
ただ生きるだけなら、これまでのメカニズムで十分かもしれませんが。
勉強など記憶を強化し、確実に再生できるようにすることが、私達の求めることです。
心理学のメカニズムで書いたとおり、長期記憶に情報を移すことが記憶の定着に欠かせないわけで。
長期記憶に至るためには、意味と関連付けを行う「精緻化リハーサル」を行います。
これは、「自分の言葉で説明する」「図にまとめる」など、理解を深めるようなことにより。
短期記憶で覚えた言葉に対し、一般的な知識や意味といった内容の「意味記憶」に変えることができます。
それよりも強力なのが、「エピソード記憶」です。
関連付けに関わる記憶方法となりますが、人生でのある時、ある場所での経験や出来事として思い出される記憶です。
「自分の言葉で説明する」場合、その説明した状況やモノに触れることで、その時の状況や説明した内容を思い出しやすくなります。
これは「状態依存効果」や「符号化特定性原理」と言われるもので、模擬試験などはこれに当たります。
「状態依存効果」は気分によっても思い出され、明るい気分の時の出来事は同じく明るい気分の時に思い出しやすいという記憶の特徴もあります。
これらの記憶の中心にあるのは、紛れもなく自分の経験です。
つまり、自分自身に関わることとして処理される記憶は長期記憶に移りやすいとも言えます。
これは「自己関連づけ効果」と言われ、処理水準が自然に高まるのも当然ですかね。
良くも悪くも自分の事を一番に考えるのが人間ですから。
長期記憶に移った記憶を保持するのに有効なのが、思い出すことです。
勉強でも「復習が大事」と言われるように、繰り返し思い出すことが定着につながります。
反復学習として効果が高いのが「分散学習」です。
一定の間隔を空けて復習する学習法ですが、72時間後とかいろんなことが言われていると思います。
単純に書けば、数学をずっと勉強し続けるより、数学・英語・国語・数学・・・というように分けて勉強するイメージです。
教科の単元毎でも当てはまるかもしれません。
また、どこで聞いたかは忘れてしまいましたが、外国の有名大学で推薦される学習法に「小テスト」が入っていたのが印象的でした。
これに近いのは資格試験勉強の基本とされる、過去問の繰り返しです。
「テスト効果」という、前にテストされた項目の成績が優れるというものもあります。
テストは記憶を頼りも解答するものです。
なので、一生懸命答え自体を思い出したり、解法を思い出して欄を埋めるわけです。
このように、「思い出す」という記憶の「再生」が、「長期記憶」の定着には欠かせないわけです。
定着することで、その記憶は強くなるんですね。
記憶を活かす勉強法
記憶のメカニズムについては理解しても、いざ実践するとなるとひたすら繰り返すだけになったり。
深く考えたけど・・・ということになるかもしれません。
なので、それらをどう活かすかです。
まずは、自分を信じましょう!・・・という精神論からですがw
結局は思い出す「復習」が一番の勉強になるわけです。
そのためには、勉強を続ける気持ちが必要なわけです。
勉強によって、知識を知恵に変え、応用させることで、自分の能力を伸ばすことができます。
「自分は能力を伸ばすことができる!」と信じることが、まず一歩でしょう。
それを実感できるのが、小テストや過去問などの客観的に評価してくれる仕組みです。
間違った項目を復習するのはもちろん、正解した項目も、正解した理由まで答えられるかを考えたり。
自分の理解度を客観的に把握し、勉強の計画を調整しましょう。
これは自然と分散学習へとつながり、思い出すための仕組みへと変わって行きます。
そして、他の事柄への応用に気づくことも大事です。
例えば、数学の難問と言われるものを解けない理由について言われていることですね。
問題文を理解する国語力が必要であるとか。
様々な視点から物事を見るために、多様な考え方を聴くことが必要であるとか。
そんなことが言われています。
ビジネスモデルなども、「この分野にも応用できるのでは?」というところから発展していきますし。
個人的に最近思ったのは、脳の神経回路の研究が情報ネットワークになって、ディープラーニングになったのかなとか。
このように、一つの知識が他の分野での知恵になるのです。
なので、学んだこと自体を復習するとともに、その学んだことの構造も理解するように学習すると。
復習の場が自然と増え、応用が聴く柔軟な記憶を定着させることにつながります。
「思い出す」を習慣にする
勉強というと、覚えることに注意が集中しがちですが。
覚えるということは、記憶するということです。
この記事で書いた通り、記憶することは、思い出すことです。
よく聞く資格試験の勉強法の入口は、
・過去問を眺めてどんなことが問われるかを把握する
・テキストをざっと一周して扱われる内容を把握する
というもので、これが記憶のきっかけになるわけです。
自分はこれからどういうことを勉強するかという、自分事として理解を始めます。
その中で、テストをして復習を繰り返したり、誰かに説明したりブログやSNSで発信したり。
自分の行動として、復習した知識を関連付け。
試験本番でも思い出し、合格後も得た知識を思い出し発展させて、高度な内容に取り組むわけです。
まさに「習うより慣れろ」ですね。
何回も教わるよりは、何回も復習して慣れてしまう方が、記憶の定着になるわけです。
・・・ことわざの使い方が違うかもしれませんが。
人間の脳は生きるために忘れる仕組みとなっています。
なので、忘れないために、思い出す習慣を見に付けて行きましょう。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか、問い合わせフォームよりご連絡ください。
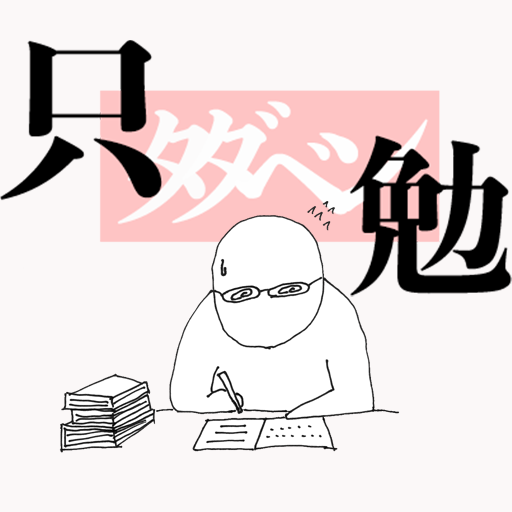
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!

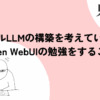
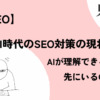
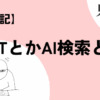
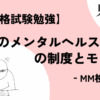
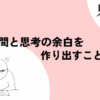
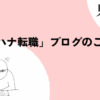
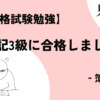

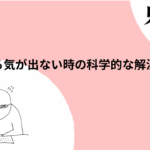
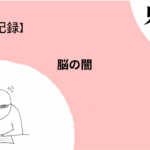
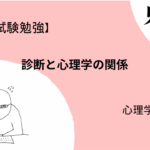
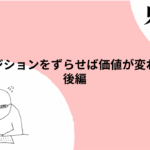
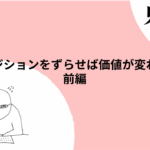
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません