職場のメンタルヘルス対策の制度とモデル|メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)
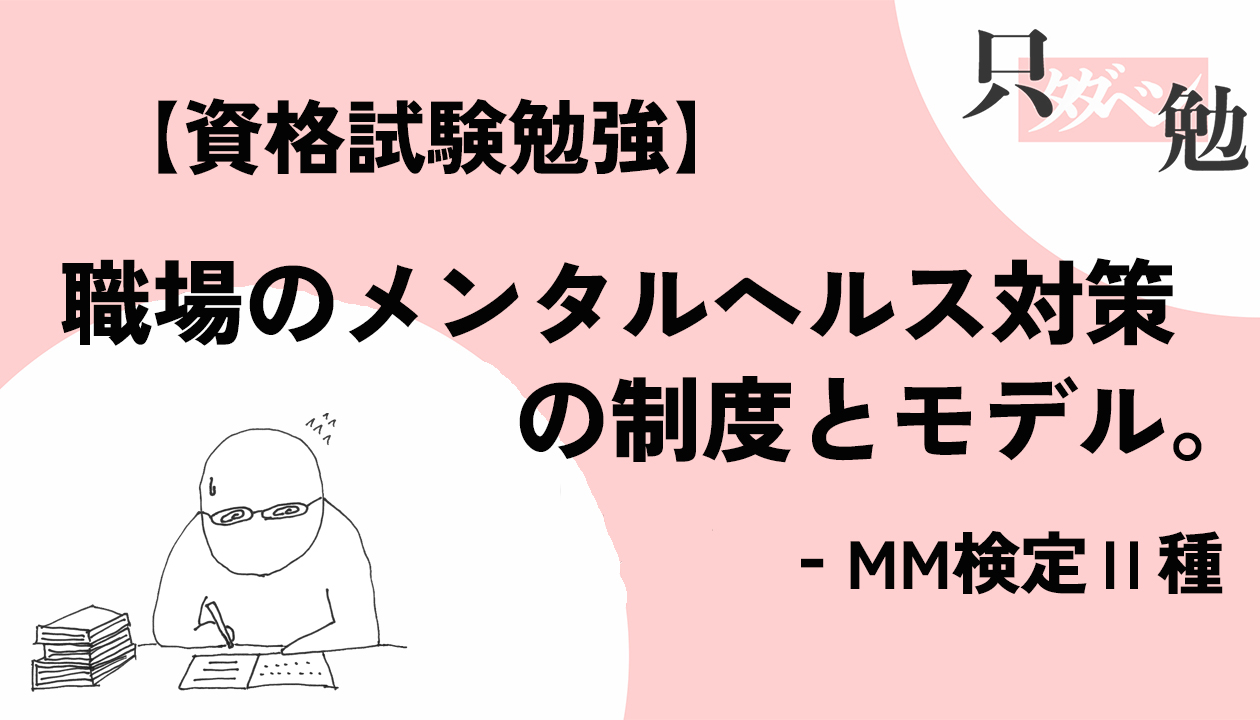
前回は職場でのメンタルヘルス対策において、管理監督者の視点と把握したい問題について書きました。
次に職場で活用できるメンタルヘルス対策の制度やモデルといった考え方について書いていきます。
メンタルヘルスケアは、個人的な要因だけでなく職場環境なども踏まえた対策を取ることが大切です。
部下のパフォーマンスなどで状態を把握しやすい立場にいる管理監督者が、利用できる制度やツールを把握することで適切な対応ができるようにもなります。
また、専門家である産業医などの産業保健スタッフとの連携もスムーズになります。
今回も基本的には「メンタルヘルス・マネジメント検定試験Ⅱ種(ラインケアコース)」の内容に基づいていますので、参考になればと思います。
土台となる法制度と理論モデル
労働者のストレス状態を把握するために、法律で実施が決められている「ストレスチェック制度」があります。
また、職場環境と個人的要因からストレス状態を把握するし、職場環境を整えるきっかけとなる理論モデルなども利用し、従業支援につなげることができます。
ストレスチェック制度
2014年の労働衛生法改正により、常時50人以上の労働者を使用する事業所に年1回の実施を義務付けられているのが、ストレスチェック制度です。
50人未満の事業所は努力義務となっており、派遣労働者に対しては派遣元の事業所に実施義務があります。
目的
ストレスチェック制度は。
・労働者のストレスの程度を把握
・労働者自身のストレスの気付きを促す
・職場改善につなげ、働きやすい職場作りを進める
以上による一次予防(労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止する)が目的です。
そのため、結果の評価時には、受検者のストレスの程度、高ストレス者に該当するかどうか、面接指導が必要かどうかについて評価を行い。
該当する労働者への対策や、専門家の支援を得ながら。
労働者の健康状態の改善や、職場環境の改善に活かしていきます。
調査票
医師や保健師等の資格を有する人が実施者となり、調査票を利用し点数化して評価しますが。
以下の3つの領域に関する項目が含まれている調査表を利用する必要があります。
①ストレス要因:職場における、当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
②ストレス反応:心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
③周囲のサポート:職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
これらが含まれていれば、事業者の判断で選ぶ事ができるとされていますが、「職業性ストレス簡易調査票」の使用が推奨されています。
また、事業者は結果の評価方法や基準を決めることもできますが。
基本的には、実施者の助言や提案のもと、衛生委員会の調査審議を経て決定することになります。
実施体制
実施者は調査票のところでも書いた通り、ストレスチェック制度のほとんどにかかわることになりますが。
衛生委員会は、事業所における実施規定や実施計画、実施方法についてストレスチェック指針や実施マニュアルの内容に基づき調査審議を行い、事業者の決定を助けます。
また、実施する際には実施事務従事者という実施者の補助をする人たちも、円滑なストレスチェックの実施のために必要です。
実施者と異なり、受検する労働者に直接、解雇・昇進・異動の権限を持つ監督的地位にある人以外という条件以外に特別な資格は必要ありません。
そして、受検から結果に至るまで係るとともに、事業所の全労働者がストレスチェックを受けるように勧奨することも大切な役割です。
結果の通知
結果は実施者が受検者に直接通知します。
ストレスチェックの結果を事業者が、本人の同意なく知ることはできません(労働安全衛生法第66条10の2項)。
評価によって、受験した労働者のストレスの程度、高ストレス者に該当するかどうか、そして、面接指導が必要かどうかを判断することになります。
面接指導の判断も通知されるので、申し出る場合の窓口や申し出の方法についても結果に記載されます。
面接指導
面接指導が必要という結果を通知され、労働者がおおむね1ヶ月以内に申し出た場合。
事業者は申し出を受理してから1ヶ月以内に、原則労働者の就業時間内を使って、医師による面接指導を実施します。
ただし、申し出を行うことで、結果を事業者に提供することに同意したとみなされることは、受検者も覚えて置いた方が、トラブルは少ないでしょう。
医師は面接指導の実施した結果から、就業上の措置に関する意見や職場環境の改善に関する意見をまとめ、事業者に書面により通知します。
事業者はその内容から必要があると認められる場合、面接指導を受けた労働者に対する対策を実施します。
・就業場所の変更
・作業の転換
・労働時間の短縮
・深夜業の回数の減少など
実施する対策について、衛生委員会や労働時間等設定改善委員会へ報告し、他に適切な措置が必要であればそれも講じます。
事業者は他にも、面接指導の記録の作成と5年間の保存義務があり。
実施者や実施事務従事者は、申し出を行わない労働者に対して、勧奨を行うことも勧められています。
職場環境の改善への活用
ストレスチェックは職場全体で行うため、職場環境の改善に活かすことができます。
とはいえ、事業者はストレスチェックの結果を知ることができないので。
集計や分析を実施者に依頼します。
10人以上の集団を対象に依頼し、事業場ではなく職場単位でのストレス状況の把握に務めます。
実施者は、その結果を事業者に通知し。
その結果の調査審議を経て、改善への取り組みを行います。
注意事項
労働者の健康情報という機微な個人情報が、ストレスチェックの実施により明らかになるため。
関係者は守秘義務を守らなければならず、実施者や実施事務従業者には義務と罰則が法律で規定されています。
医師・歯科医師➾刑法
保健師・看護師➾保健師助産師看護師法
精神保健福祉士➾精神保健福祉士法
公認心理師➾心理師法
実施事務従事者➾労働安全衛生法
こんな感じです。
そして、事業者は面接指導の申出を行った労働者に対し、それを理由とした不利益な取扱いをしてはならないと安全衛生法第66条10項の3で規定されています。
罰則のない規定もありますが、安全配慮義務違反となる場合もありますし。
実施状況の労働基準監督署への報告や、記録の保存、守秘義務に違反した場合は罰則があります。
面接指導の申出を行った労働者を扱う立場にいる管理監督者は。
・面接指導を受けることを妨げないこと
・医師の意見を尊重し、就業上の措置を講じること
・結果を知った場合には、取扱いに注意する
・その労働者に対し不利益な取扱いをしない
・就業上の措置の変更は、産業医等の意見を聞き、変化に応じて対応する
といったことへの注意が必要です。
面接指導の申出により、結果を知る可能性がありますが、管理監督者は知ることを拒否することはできます。
・・・と、労働者のストレスを把握するものなので、実施手順については細かく規定されています。
職業性ストレスモデル
米国立労働安全衛生研究所(NIOSH)が提唱する、包括的なモデルです。
研究報告に基づく仮説ですが、職業性のストレスと疾病の発生の関係を総合的に理解し、職場のメンタルヘルス対策を勧めていく上での参考になるものです。
職場のストレッサー、ストレス反応、病気への進展を横軸で示し。
それに個人的要因や仕事以外の要因、ストレスを緩和する緩衝要因の作用が表されています。
・職場のストレッサーが非常に強い
・複数のストレッサーが重なる
・それが長期に渡って持続する
・個人のストレス耐性を超える
・健康障害の発生
このような変遷を見ることができます。
仕事の要求度‐資源モデル
職業性ストレスモデルを発展させたものとして、「仕事の要求度‐資源モデル」があります。
仕事の要求度とは、仕事における以下のようなストレス要因を指します。
・量的負担
・質的負担
・身体的負担
・対人葛藤
・役割の曖昧さ
資源は仕事の資源と個人の資源に分けられ、それぞれの持つ強みを表します。
仕事の資源:意義、組織との信頼関係などの職場が有する強み
個人の資源:自己効力感、レジリエンスといって個人が有する強み
この3つの要素を起点とし、「動機づけプロセス」と「健康障害プロセス」から構成されるモデルです。
・動機づけプロセス
仕事の資源/個人の資源➾ワーク・エンゲイジメント➾健康・組織アウトカム
・健康障害プロセス
仕事の要求度➾バーンアウト(ストレス反応)➾健康・組織アウトカム
従来は健康障害プロセスに注目し、バーンアウトを低減すること専念していましたが。
ワーク・エンゲイジメントの概念から、仕事の要求度を低減させ、資源を向上させることを目指しています。
それにより、バーンアウトの低減にもつながるので、職場環境の整備と従業員の支援に重要であるとするモデルです。
これらの考え方によってストレスと労働者の関係を把握するとともに。
ストレスチェック制度を利用して、ストレスによる健康障害発生の把握と、組織としての適切な対策を行うことができます。
組織の持続的成長を支えるアプローチ
職場環境を改善したとしても、継続されなければ本当の改善とはいえません。
また、テレワークの普及で体験した方も多いと思いますが。
社会が変わるとともに、ストレス要因も変化していきます。
事業者が持続的に改善を続けることができる仕組みや考え方を利用しましょう。
健康職場モデルと健康経営
従業員の健康が害されると、本人の生産性が低下するだけではなく、そのフォローなどで組織としての生産性も低下してしまいます。
そのため、従業員の健康保持・増進の取り組みが将来的に収益性を高める投資であるという考えのもと、従業員の健康管理を経営的視点から戦略的に実施することを、健康経営といいます。
実際に健康経営の考えに基づく取り組みを行った企業が、実際に業績をあげていることもあり。
投資対象として信用に値する企業と判断し、経済産業省と東京証券取引所は「健康経営銘柄」として選定し公表しています。
また、非上場企業や医療法人が健康経営の取り組みを行うと、経済産業省と日本健康会議が顕彰している「健康経営優良法人認定制度」を利用することもできます。
あくまで目的は従業員の健康保持と増進です。
しかし、このような制度を利用することで、健康経営の取り組みが広がり。
授業員の活力向上や、組織の活性化や生産性の向上につながり。
医療費の抑制にもつながることが期待されています。
自社の取り組みを評価してもらえる制度として活用したいところですが、企業がメンタルヘルスケア対策に取り組む意義として参考にできるものに、「健康職場モデル」があります。
こちらもNIOSHが提唱しているもので、従業員の健康や満足感と組織の生産性は両立することが可能で、相互作用があり互いに強化することができるとする考え方です。
企業がメンタルヘルスケアに取り組むことでマイナスからプラスの状態にできるとします。
マイナスの状態:従業員の不健康・不満足、組織全体の不活性化
↓
ゼロの状態
↓
プラスの状態:授業員の健康・満足、組織全体の活性化
このように健康で活力のある組織を目指すことを、管理監督者として意識することができる考え方です。
ワーク・エンゲイジメント
新ストレス簡易調査票で測定可能な、ポジティブ心理学に基づく概念です。
仕事に対する熱意の低下しているバーンアウトの対極にあり、以下の3つが揃った状態としています。
・熱意(Dedication):仕事に誇りややりがいを感じている
・没頭(Absorption):仕事に熱心に取り組んでいる
・活力(Vigor):仕事から活力を得て活き活きしている
ワーク・エンゲイジメントが高い状態の従業員は、心身ともに健康で、仕事や組織に積極的に関わり、良好なパフォーマンスを行う傾向があります。
先程の「仕事の要求度‐資源モデル」の鍵概念となるのが、このワーク・エンゲイジメントです。
部下の状態をワーク・エンゲイジメントの高い状態を保ち、チームや組織として生産性の高い状態を維持することを、管理監督者として心がけたいものです。
ツールや評価方法
ストレスチェック制度のパートで触れましたが。
調査結果を集団分析することで、職場環境の改善に活かすことができます。
そのため、職場環境の状況を知るために、ストレスチェックで利用する調査票を活用することができます。
また、従業員が当事者として職場環境の改善に携わるためのツールや、改善の施策の評価方法を知ることで。
継続的な改善活動の実施が可能となります。
職業性ストレス簡易調査票・仕事のストレス判定図
ストレスチェックでの利用が推奨されている「職業性ストレス簡易調査票」は。
ストレス反応や、職場におけるストレス要因と修飾要因(ストレス要因からストレス反応が生じる際に影響する要因)を評価することができます。
仕事のストレス要因に関する項目が17項目、ストレス反応についての項目が29項目、修飾要因について11項目で質問が構成されていて、業種にかかわらず使用することができます。
すべての項目を受検者自身が4段階で評価する方法となっており、受検の負担も少なめです。
これに仕事から得られる心理社会的資源についての評価を加えた、「新職業性ストレス簡易調査票」もこうかいされています。
・作業レベル:仕事の意義や成長の機会が与えられているか?
・部署レベル:上司のリーダーシップや公正な態度は?
・事業場レベル:キャリア形成の機会が提供されているか?
といった質問を通し、ワーク・エンゲイジメントや職場の一体感の測定が可能です。
新旧のどちらが良いというわけではなく、特徴を捉えて利用することが大切です。
旧の特徴:ネガティブな側面の評価➾仕事のストレスへの悪影響の改善・予防に役立てる
新の特徴:ポジティブな側面の評価➾良い点、強みを更に伸ばすことに役立てる
そして、調査票を利用して作成できる図が「仕事のストレス判定図」です。
「仕事の要求度‐コントロール‐サポートモデル」に基づき。
①仕事の量的負担
②仕事のコントロール
③上司の支援
④同僚の支援
という4つの要因を取り上げ、集団の平均点を算出することで、職場環境を評価します。
「量‐コントロール判定図」と「職場の支援判定図」の2つで構成され。
健康問題リスクの標準集団の平均を100として表している斜め線との位置関係を見ることができます。
そして、総合健康リスクを算出し、従業員への健康への悪影響がどの程度かを把握します。
4つの要因とこの数値により、職場環境の改善に役立つ情報をえることができます。
メンタルヘルスアクションチェックリストとトータル・ヘルス・プロモーションプラン
従業員が自発的に職場環境の改善にかかわる場合に活用できるものとして、「メンタルヘルスアクションチェックリスト(職場環境改善のためのヒント集)があります。
日本全国から集めた職場環境等の改善事例を収集し、専門家・実務家・研究者の討議を経て、現場で利用しやすい6つの領域30項目に集約整理して作成されたものです。
①自分たちの職場の経験をもとにグループ討議を始め
②改善が必要な点への気付きと改善のためのヒントを得て
③優先して改善すべきポイントを明確にし
④すでに実施されている良い活動事例を発見・収集し
⑤職場を多面的に捉えることで、ストレスとなる職場環境に関心を持つ
という効果が見込めます。
問題点の把握や点数化による職場のランク付けや、職場環境を抜け落ちなく点検することが利用の目的ではなく。
あくまで、グループ討議で利用するためのものです。
このような小グループによる改善活動に持ち込めることが、チェックリストを利用するメリットです。
なぜなら、日本は生産性の向上や品質改善といったもんだいに、小グループによる改善活動を行ってきた経験があるからです。
このように、労働者自身も積極的に職場環境の改善への参加を促すためのツールが用意されています。
また、職場としても労働者の健康予防に積極的にかかわるものとして、「トータル・ヘルス・プロモーションプラン(THP)」という事業もあります。
これは、健康保持推進事業として。
・生活習慣病に対する保健指導、栄養指導、運動指導
・メンタルヘルスケアとしてストレスに対する気付きの援助
・リラクセーションの指導
・良好な職場の雰囲気作り
を推進していくために、予防に積極的に介入することを意味しています。
どちらかというと、健康問題を抱える個人に向けたハイリスクアプローチと呼ばれる関わり方でしたが。
集団に対して講演等で働きかけ、組織全体として健康の保持増進に取り組む意識を高めるポピュレーションアプローチを強化していくことに変わっています。
労働者の自助努力を支援すると同時に、職場の健康障害要因に予防的・積極的に介入していくことに利用できます。
3つの評価視点
持続的に職場環境の改善を続けるには、PDCAサイクルに当てはめ検証と計画を繰り返すことが必要です。
その検証のために施策の評価は欠かせません。
計画に対する取り組みを評価する手法が「プロセスの評価」。
取り組みによって、休職率の低下や生産性の向上といった、成果をもとに評価する手法を「アウトカムの評価」といいます。
これらの評価方法を使い、対策の効果性を検証しすることで、職場環境の改善に一歩ずつ近づいていきます。
また、「労働安全衛生マネジメント・システム」を利用した場合。
ストレスチェックの結果の評価をリスクアセスメントに位置づけることで、監査のステップで検証することもできます。
ISO45001などの国際規格もあるので、ぜひ利用したいものです。
まずは理解することから
制度やツール、考え方について解説してきましたが。
管理監督者は、まず職場環境を保ち、部下の健康を守る立場にいるという意識を持つことが必要です。
そして、ツールや考え方もそれぞれあるので、すべてを覚えるのは難しいと思います。
なので、まずは理解することから始め、メンタルヘルス対策の意識を高めることが大切です。
対策や施策を考える時に、この記事で紹介したツールやモデルを活用し。
職場環境の改善に活かしていきましょう。
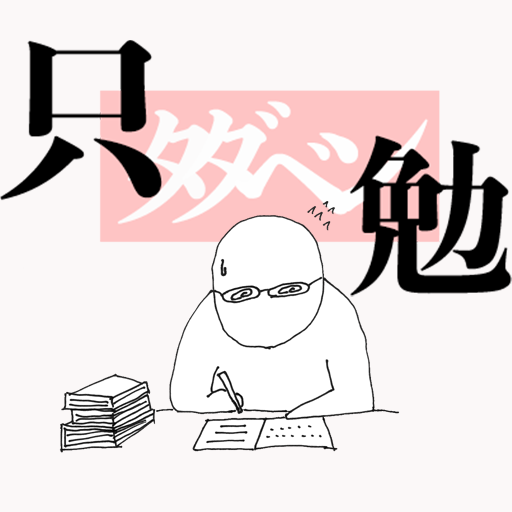
はじめまして、「ぽんぞう@勉強中」です。
小企業に一人情報部員として働いている40代のおじさんです。IT技術での課題解決を仕事にしていますが、それだけでは解決できない問題にも直面。テクノロジーと心の両面から寄り添えるブログでありたいと、日々運営しています。詳しくはプロフィールページへ!
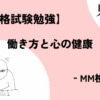

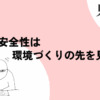
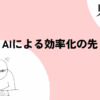
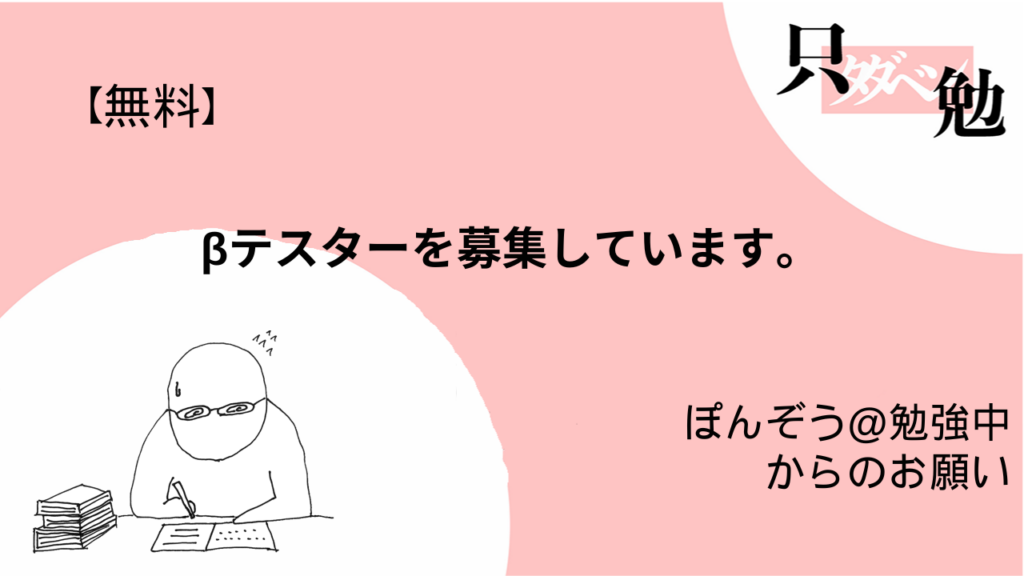
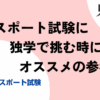
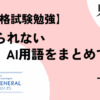

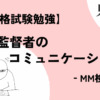


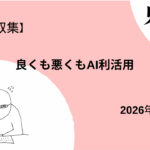
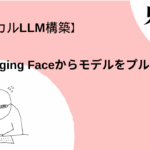
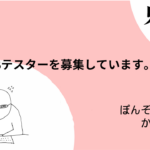
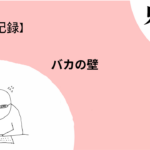
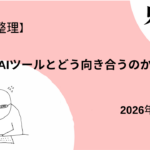
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません