【ポエム】読書に生成AIを活用する記事を書いたことについて
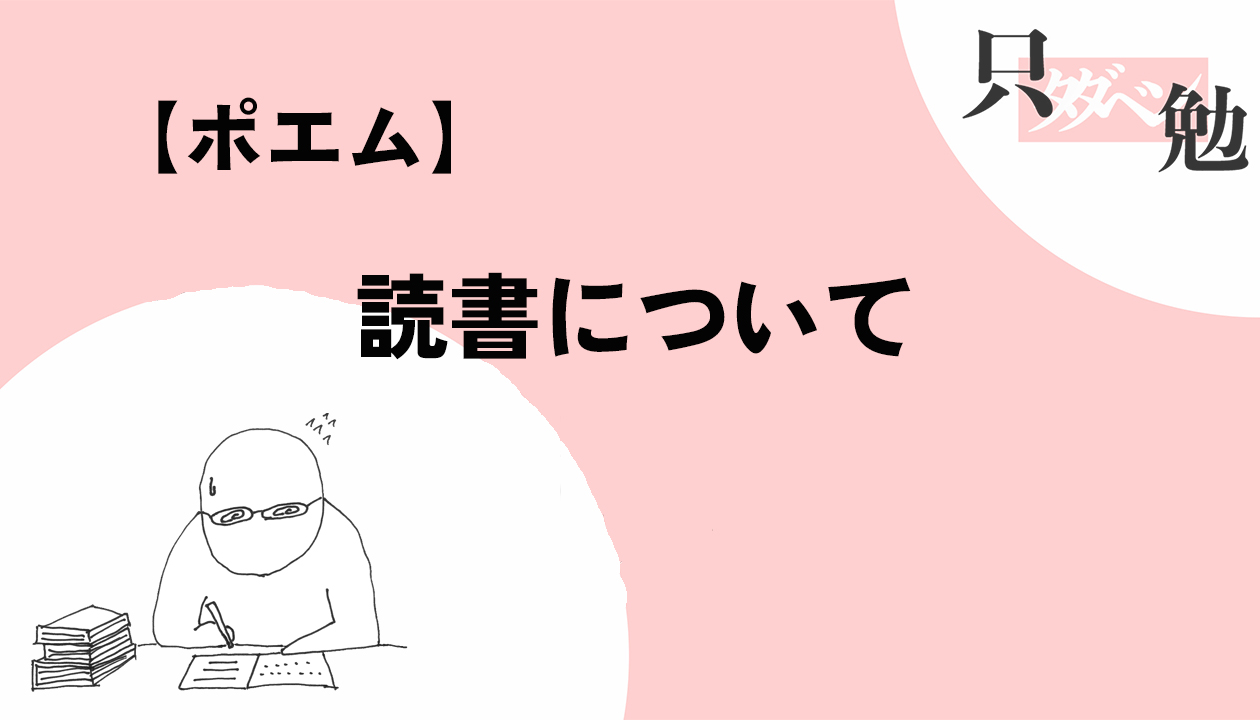
読書に生成AIを活用することについての記事を4件ほど記事を書きました。
この記事を書く動機となったのは、1記事目に書いた通りライフハッカージャパンさんの記事ですが。
それ以前から、「月◯冊読んでます!」とか「◯日間で読みました!」とか。
読む冊数で興味を引くようなSNSなどの投稿に少し疑問を覚えていました。
速読という技術もあるので、一概には言えませんし。
過去になにかのテレビで見た、パラパラと読むだけで全て記憶できるような能力があれば別ですけども。
数字の影響力は大きいので、説得力はありますがー。
本についてはどうなのかなぁと思います。
他の番組でも自己啓発書を大量に読んでも、身につけられていない方がいるのを見た記憶があります。
自分もどちらかというと、冊数にこだわると読むだけになってしまう側の人間なので。
生成AIを使いながら読書をし、その体験として記事を書くことにしたわけです。
読書の価値はどこにあるのか?
書いていこうかなと思います。
他者との比較は関係ない
読書の価値というものは人それぞれで。
他者と比べるようなものではありません。
・・・なので、大量に読んだことを証明するために冊数を目標にするのも人それぞれです。
が、影響を受けるのではなく、自分の読書の目標を意識することが重要です。
他者と自分を比較してしまう傾向を心理学では「社会的比較理論」というもので説明します。
読書において分かりやすく「すごい」と思われる方法は・・・まぁ冊数ですかね。
短期間で大量の読書をできることは、特殊能力のようにも感じられますし。
タイム・マネジメントの旨さも感じるかもしれません。
読書量に関する投稿を見ると、無意識に自分が劣っていると感じてしまい。
「もっと読まなきゃ!」と思ってしまうわけです。
まぁ・・・分かりますね。
自分が見習いたいと思う人達も、本の引用が会話の随所に出てくることもあり。
量を読む必要性を感じてしまいます。
しかし、見習って量を読むことに徹すると、周りの人から「すごい」と言われることが目的という「外発的な動機」となってしまうので。
もしかしたら、読書そのものが苦痛になってしまうかもしれません。
実際、読書というものは個人的なものです。
オススメや必読書という形で推薦されたものを読むこともあると思いますが。
読むか読まないかを決めるのは自分です。
読書自体が楽しかったり、新しい知識を得ることが面白いという、「内発的な動機」で本来行うものです。
・・・まぁ、仕事の場合もありますが。
そもそも好きじゃなければ、レビュアーやライターといった職業にはつかないでしょうし。
と。
読書は自分の内側から湧き出る好奇心に従って行うもので、他者との比較によって行うものではないということです。
・・・という前提をおいて起きます。
それでも身についた気がしない
ここまで書いたような心理学的な側面があったとしても。
自分の行動が変わったような気がしない事はあります。
自己啓発書では特にそうかもしれません。
冊数に関する投稿をする人たちは、実際に行動に変えているように見えて(実際そうだとは思います)。
だから、「自分も冊数をこなさなければ!」と思ってしまうのかなと。
しかし、冊数をこなしたとしても、多分変わらないと思います。
なぜかというと、あくまで本に書いてあるのは著者の方の考えや方法論で。
読むだけでは、他人の考えを知ったにすぎないとも言えます。
自分が興味のある内容なだけまだマシですが、会社の方針について棒読みしている上司の言葉を聞いているのとあんまり変わりはないと思います。
なので、知ったことを自分の考えや価値観にするために、考える時間を取ることが大切です。
が。
消費に追われやすい現代では、この考える時間を取ることが難しいものです。
次々と情報が出てくるため、本以外にも読んだり見たりするものはたくさんありますしね。
考える時間を効率的にするには
そこで活用したいツールが、生成AIです。
という意味で、4件連続で記事を投稿しました。
詳しくは記事を読んでいただけたら嬉しいですが。
本の要約や重要なポイントの抽出といった、本の全体像を把握する助けにすることや。
自分の読書メモを利用して、受けた印象や持った感想を整理する助けになります。
これにより、本の内容を普段の生活にどのように反映させるのか、取り入れるのかを考えやすくしてくれます。
AIは「人間の脳の拡張」であると捉えれば、もう一つの脳に整理を手伝ってもらい。
決断や実行は自分の脳で行えば良いのです。
重く捉えすぎないようにする
自分も良く陥る罠でもあるのですがー。
「本の内容すべてを学びにする必要はない」というふうに考えるのも大切かと。
一冊1,000円以上のコストをかけるので、知らず知らずのうちに「元を取らなきゃ!」と考えてしまいがちなのが、私です。
それを変えてくれた一言が、「一冊の本から一つの学びがあれば十分」と言われたことです。
・・・誰に言われたかは忘れましたw
良く考えてみると、本にかかれている「一つの学び」を得るための他の方法を考えると。
本を買う以上のコストを払う必要がある場合もあります。
学校に通ったり、その学びを直接教えてもらうために足繁く通ったり。
お金や時間といったコストを大量に払って、ようやく「一つの学び」を得られるかもしれません。
それが本であれば、本の代金と読む時間だけで済みます。
深く知りたくなってから、さらにコストを払えば良いわけです。
タイパもコスパも読書は良いと思います。
また、この「一つの学び」というものは、読んだ人それぞれで構いません。
レビューサイトを見ると色々な意見がある通りで。
学びになる部分は人それぞれです。
自分自身が感じる扱われる内容の本質と思われる「一つの学び」を掴み、それを使って自分の考えや行動をどう変えるのか。
そのようにして、自分の内面に変化をもたらすことができれば、あなたの読書は成功だったと言えるでしょう。
なので、「読むんだから、全部覚えなきゃ!」と重く考えるのではなく。
「どこが今の自分の役に立つかな?」と気軽な気持ちで楽しみながら読書をしましょう。
読書はだれかと比較するものでも、誰かに何かを言われるようなものではありません。
まとめ
本を読み切ると満足感があるため、どうしてもそこで終わってしまう場合もあります。
また、物語などは満足感に浸れれば良いかもしれません。
しかし、どんな形でも著者の方の考え方や主張というものは織り込まれています。
そこから自分がどのような影響を受け、取り入れ、活かしていくのか。
そのように考える時間を取れれば、より有意義な時間を過ごせると思います。
時間を取ることが難しければ、生成AIというツールを使って、理解を深めましょう。
で、書いているうちに、本を選ぶということについても少し書いてみたくなったので。
次回はそれについて書こうと思います。
このブログや記事の内容について、疑問に思っている事はありますか?
もしあれば、どんなことでも構いませんので、コメントを残していただくか問い合わせフォームよりご連絡ください。
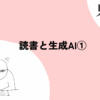
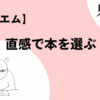
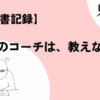
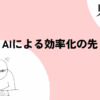
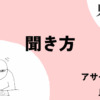
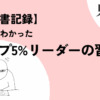
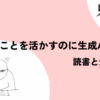

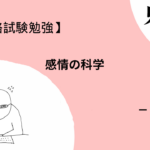
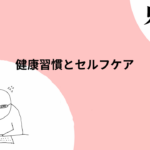
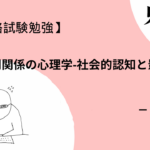


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません