生成AIにアウトプットを利用して読書を「行動」に変える
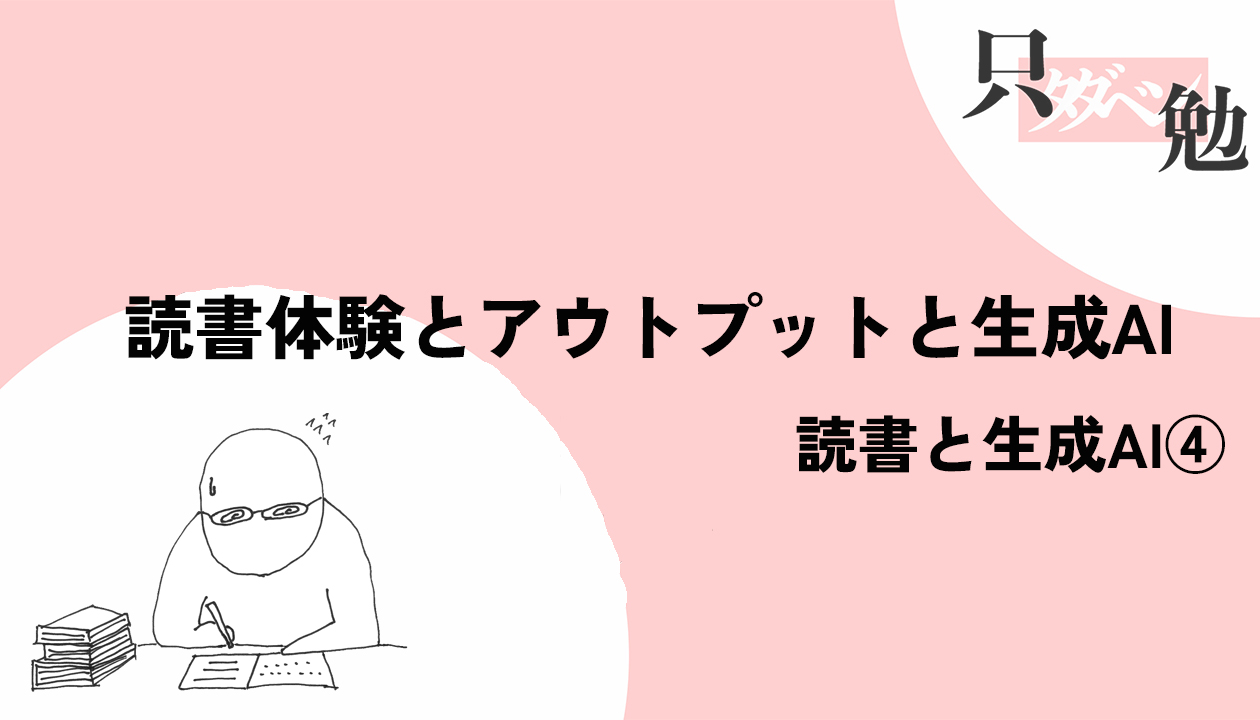
前回までの記事で。
読んだ本の内容を活かすことや、読書のパートナーにして理解を読書中から深めるという内容でもサラッと「行動」に変える方法について触れてきましたが。
少し考えを深めて見ようかと思います。
アウトプットが大切
読書は知識を得る行為であることがほとんどなので、知識を身につけることを効率化することが、生成AIの利用によって可能になることを提示してきたつもりです。
なので、実際に見に付けた知識を活かし「行動」に移すにはどのように利用すれば良いのか?
知識が身についた状態というのは、「行動」自体が変わることもそうですが、その知識を自分の言葉で説明できる状態になることも身についた状態となります。
自分の言葉でしかも他の人に分かりやすく説明できることで、知識が自分に馴染み「行動」が変わって行くことに繋がります。
なので、学んだことをアウトプットすることは、「行動」を変えるためにも重要です。
本で知ることができた良い事をアウトプットし、そのために自分の中でも整理することで、より「行動」に変換しやすくなります。
読書にかかわらず、「アウトプット型学習」の有効性はいろいろな分野でも取り入れられていますし。
私がこのブログに学んだことや読んだ本について書いているのも、学んだことで「行動」や「意識」を変えたいからです。
・・・思ったことだけガリガリと書いてるので、読みやすいかどうかは微妙なところかもしれませんがw
そして、本で学んだ知識の整理というのは、まさに生成AIにぴったりなタスクと言えます。
本の内容やメモの整理から自分専用のワークブックを作成
これは、2記事目でも扱った内容なので、さらっと書いていきます。
2記事目で書いたのは、読書で学んだことを自分に活かすために、自分専用のワークブックを作り。
そのワークブックを実践して、知識の定着や行動指針に使うという内容で書きました。
この「自分専用」というところがポイントで。
本は読んだ人によって、感銘を受けるポイントや活かしたいと思うポイントは違います。
自分にとって有益だと感じた内容を知らずに悩んでいる方がいるかもしれません。
その悩みを解決する方法を、この本から学ぶことができるということを伝えることができれば、自分自身も伝わった人にもプラスになるのではないでしょうか。
ある意味、自分自身の行動の方向を知らせることにもなるので、決意表明のようにもなりますし。
自分の経験によって、コーチングビジネスを始めることもできるかもしれませんがー。
それはまた別の話ですね。
アウトプットのために言語化する
ワークブックでも、感想文でも良いですが。
他の人に伝えるためには、自分の受けた感覚を言語化しないと伝わりません。
情報が溢れている現代だからこそ、情報の受け手に類推したり、推測するといった、負荷がかかる情報の発信はマイナスです。
私も気をつけないとなんですが。
とはいえ言語で書かれている本だから、その部分を引用すれば良いじゃないかと思われるかもしれませんが。
その文を読んで受ける印象は人それぞれですし、解釈も人それぞれです。
さらに、そこに著者の意図が含まれている場合もあります。
なので、他の人に伝えるためには、自分が受けた印象や読んだ感想を分かりやすく言語化する必要があります。
で、実際に説明しようとすると。
ブログを書いていると良く分かるんですがー。
書いてあることに対するもう一歩踏み込んだ理解や、関連する他の知識もないと言語化しにくい場合良くあります。
「〇〇を説明するためには、△△も説明しないとわかりにくい」とか、「この言葉の意味が難しすぎるから、言い換えるには・・・」とか。
そんな時に、3つ目の記事で書いた生成AIをパートナーにした読書がおすすめです。
読んだ時点で疑問に思ったことをすぐ解決できますし、周辺知識についても生成AIに背景を尋ねることで得ることができます。
このように、自分自身の理解にもつながると共に、アウトプットの準備を進めることができます。
もちろん、読んだ後に活用するのも、アウトプットに繋がります。
本の内容に対する自分自身のポジションを固めた後に生成AIを利用すれば、違う視点や新たな視点にふれることもでき。
アウトプットの幅を広げることにも繋がります。
実際にアウトプットする時に
ここまでは、どちらかというとアウトプットの準備のようなものです。
本から得た知識を整理し、自分の理解にするのに、どのように生成AIを活用できるかで。
詳しくは、各所に貼った前回記事をご覧いただければと思います。
では、実際にアウトプットする時にどのように生成AIを利用するかですが。
生成AIに本の内容を要約させ、感想文を生成させるという方法もありますがー。
あんまり意味ないですよね。
電子書籍ならまだしも、紙の本の場合は全部手入力するの?という労力もありますし。
著作権からも微妙です。
この前にも書いたように、読書メモを要約して感想文を生成するというのも一つの方法ではありますが。
自分の考えをまとめるという過程が抜けてしまうので、自分の言葉にはしにくいです。
なので、生成AIを感想を言い合う相手と見立て、アウトプットの流れを作ってもらうのが一つの使い方です。
本のメモなどを伝えた後に、「あなたは本の理解を深めるナビゲーターです」などで役割を与え。
本の内容について質問をしてもらい、それに回答しながら考えたことや感情が動いた事をまとめていけば、自分の言葉による感想文が出来上がります。
そして、それを他の人が読みやすいように、生成AIに整形してもらいましょう。
ブログであれば、「ブログ記事の流れを作って」とか「ブログ記事を書くための骨組みを作って」などのプロンプトでも十分です。
・・・良くやりますw
文章でも口頭で使う台本でも、時間を使うのは構成を作ることです。
構成を作ることは伝わりやすさに影響はしますが、ある程度の型があります。
それよりも本から得た知識や体験を言語化する方がメッセージを伝えるためには重要です。
なので、大まかな枠組みを生成AIに作ってもらえば、あとは自分受けた印象や感情が動いたことなど、人間にしかできない表現を組み込んでいくことで。
アウトプットを楽しむことができるでしょう。
新しい読書体験へ
読書はどちらかというと個人的な体験で、自分自身の教養を深めたり、専門知識を得るために行うことです。
しかし、読書により受けた影響や感想を他の人と分かち合いたいというのも、私達におこる自然な感情です。
これまでは文章を書くことや説明することが苦手で、避けていた方もいるかもしれません。
生成AIを活用すれば、苦手意識を持っていたことを飛び越え、自分の読書から得た体験を他の人と共有しやすくなります。
そこから、新たな視点を得たり、同じ視点の人と繋がることにも繋がります。
生成AIを読書に活用することで、自分の知識の蓄積や深化、思考の深化を効率的に行い。
それを共有するためのアウトプットも楽しむことができます。
地味にここらへんの機能が揃っているのが、notebookLMなので。
色々な使い方ができるなぁ。notebookLM。
生成AIを使って理解を深めるために、行っている準備やプロンプトがあれば、コメントで教えて下さい!
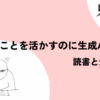

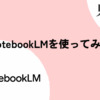
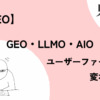
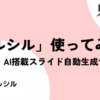
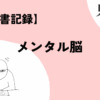
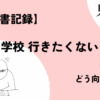

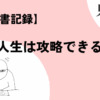
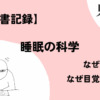




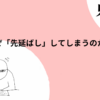

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません