読み込んでしまったThink with GoogleのAI活用記事
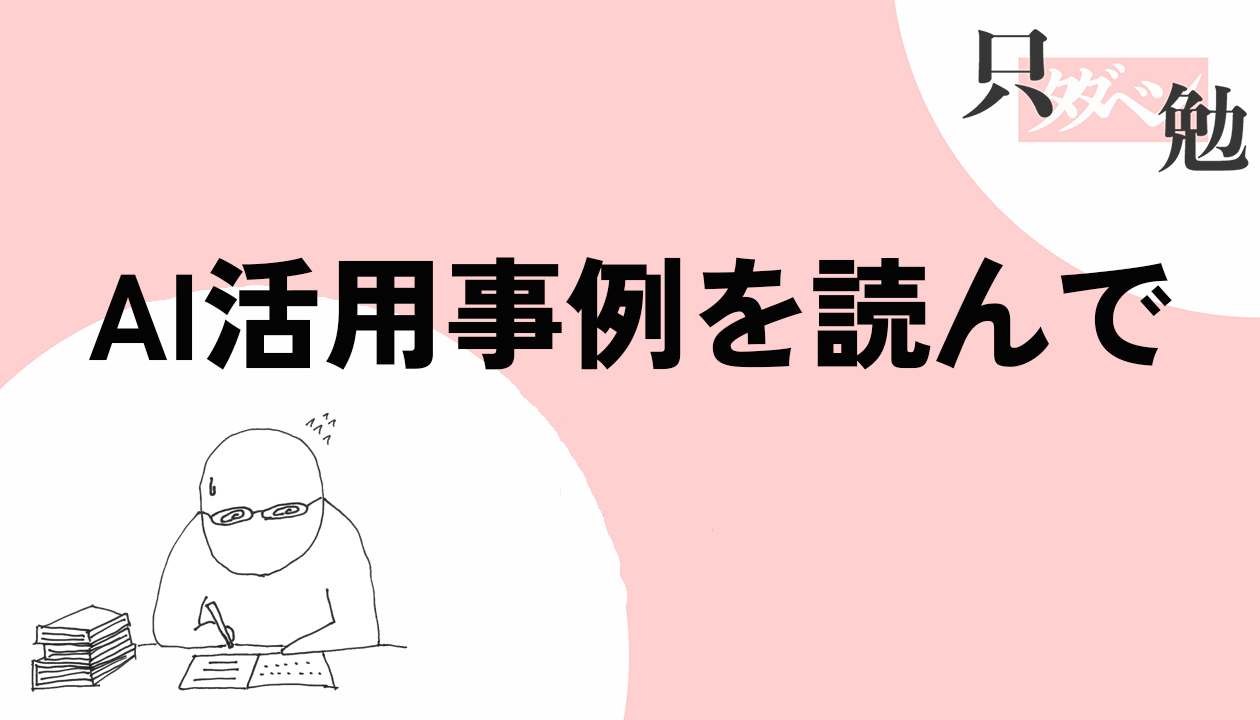
「わずか6週間で新製品のプロモーションをやりきった米国事例、GeminiやImagenなどを活用」という記事が、Think with Googleに投稿されていました。
原文の英語記事自体は、2025年の4月に公開されていたみたいで、日本語に翻訳・編集されたものが公開されています。
Google翻訳でなんとなく読んだ記憶はあるんですがー。
あんまり覚えていなかったので、せっかくの日本語訳ですし、じっくりと読んでみました。
今では様々なAIツールが登場していて、少し前でもAIモデル毎の得意に合わせて使い分けることが語られることもありました。
そんな多種多様になっているAIを、業務のどの領域に当てはめていくのか?
の参考になる記事だと思います。
プロジェクトへのAI導入
私が生成AIとの向き合い方を変えたことについて、数記事書いたことがありますが。
その中で「クリエイティブ」について触れた記事があります。
Stable Diffusionあたりを触って遊んでいた頃ではありましたが、当時はまだテキスト生成AIを念頭に記事を書いていた気がします。
それからDALL-E3の登場で、Copilotを使いつつ画像を生成できるようになったり。
X上でも生成できるようになったりと、視覚イメージも生成AIが「提案」しやすい状態になっています。
また、エージェントモデルなど、より個人に近いAIの開発も進み。
コーディングにおいては、ほぼノーコードと同じような感覚となってきているなとか思っています。
ますます私達がAIに「何を頼むか?」を考えることが大事になっているという実感です。
そんなことを思っている時に、プロジェクトでAIを活用した事例の日本語訳記事が投下されれば読むしかないでしょうと。
読み始めはそんな感じでした。
内容はというと、新規市場への商品投入のためのプロモーション戦略の立案とビジュアル作成にAIを活用したというものです。
短時間のうちに、
・プロモーションのアイデア出し
・広告クリエイティブの作成
・新商品の発表
・新規客と既存客へのリーチ本記事より参照
を行わなければならず、GoogleのAIを活用して各項目に対応させるための、
・顧客インサイトの検討
・アイデアの作成
・ワークフローの高速化
・クリエイティブ制作の効率化本記事より参照
を実現することを目指したとのことです。
と、元記事の内容をなぞってもしょうがないので、各項目で思ったことを書いていきます。
提案のAIと決定の人間
結論から書いてしまうと、プロジェクトの流れを決めるのは人間で、その意思決定に関わる内容についてAIに提案させる、というAIとの協働という形だったんだろうなと思いました。
まずは、プロモーションの核となる「顧客インサイトの検討」ですが。
ここでは提供する商品の「ミッション」をGoogleのAIであるGeminiにインプットし、ペルソナを作成したとのことです。
プロンプトの精度を高めるのにも、前情報や役割を与えるということがありますが。
テーマやミッションといった込める思いを軸に考えさせるというのは、たしかになと。
このペルソナの想定は生成AIの得意分野だと思います。
「ミッション」に合うペルソナとその背景を設定させれば、人間は顧客の事を想定し、訴求する方向性を考えておくことに舵を切ることができます。
興味深いのは、それぞれ違う特徴を持つであろうペルソナが設定されたにもかかわらず、その共通点を見出し、キャンペーンの決定につながったということです。
各ペルソナに向けたプロモーションではなく、同じプロモーションを実施することで、商品の訴求やブランドとしての一貫性を示すことにも繋がるなと。
練り上げていく中で、コンセプトを見出し、それを視覚化することでキャンペーンの内容が決まり。
判断材料に活用したそうです。
テキストイメージだけではなく、Imagenを利用して視覚イメージ化し。
プロジェクトのコンセプトに基づく、「キャンペーン」を決定することができたようです。
ペルソナの興味・関心に沿った視覚イメージの選定です。
それにより、さらに「キャンペーン」の内容を決定しつつも、考慮すべき情報を落とし込み意思決定を重ねたとのこと。
内容や情報を分析し、それを文字で論理的に、イメージで直感的に理解するためのツールとして活用されたということですね。
ペルソナの背景を考えるのは大切なことですが、時間と労力がかかりますし。
コンセプトを視覚的に表現するイメージ作成も、クリエイターの力が必要です。
それらを得意とするそれぞれのAIに提案させることで、意思決定が迅速になり。
わずか1週間で、プロジェクトの骨組みを作れたことが伺えます。
一つ一つをチームメンバーが行うと考えると・・・悪いことではないですが、膨大な時間がかかるだろうなぁというのは簡単に予想がつきます。
これらの作業をやったうえで意思決定を行うとすると、また別のミーティングや能力が必要になりますしね。
AIに「提案」させることで、論理的にも、視覚的にも、納得感のある意思決定に集中できたということでしょう。
スケジュールが66%短縮されたというのは、この「提案」部分がAIによって効率化されたことが大きいと思うのです。
イメージを形作るクオリティ
画像生成AIは、本物と見間違えるほどのクオリティがあることは、体験済みだとは思いますが。
そのように生成されたものを、そのまま「広告クリエイティブ」に活用することで、制作時間を90%短縮したそうです。
動画生成AIも含まれてるような気はしますが。
広告などのプロモーションを作成する場合に、使用するイメージ数は膨大になると思いますが。
それらのイメージをクリエイターに伝えることで、制作につながります。
つまり、言葉で正確に伝えることが大切ですが、AIを利用する場合にもこれは変わりません。
プロンプトとしてAIに指示を出すために、生成して欲しいイメージを正確に言語化しなければ、思ったようなものは出てきませんからね。
そのため、ミッションを元にAIが提案したことに基づいて決定したコンセプトを、文章としてもイメージとしても共有することで、ビジョンも共有され。
同じAIを並列で利用することで、生成されるものも一貫性を確保できるようになると。
生成されたものを、調整することで、より魅力的なものに変える。
効率ということで考えれば、これは魅力的な流れだなと。
差し戻しや検査がAIとのプロンプトのやり取りでほぼ完結するので。
最終的には人間の手を加えてより魅力的にしたり、媒体に変換するということは必要ですが。
共有しにくいイメージというものを、共有しやすくなるというのはかなりの利点ですね。
AIを円滑化の材料に
と、今回の活用事例を追ってみると。
AIの主な役割は「提案」であると考えられます。
AIが得意とするアイデア出しをメインに、内容の調査・分析・要約・統合を繰り返し。
人間は生成物が提供されるたびに、確認・判断・指示を行い、決定する。
そして、その決定したものをチームの共通認識として、コンセプトとして論理的・直感的に共有するのに使用し。
そこからプロモーションに使うものを生成しつつ、より魅力的になるように人間のもつ技術で仕上げる。
という感じだと読み取りました。
チームの意思を統一するというのがやはり難しいところだと思います。
そこを、早い段階で説得力のある形により提示できるというのは、生成AIを使う利点だなと。
また、今回の例のように期間が限られている場合、手を抜くわけではないとしても間に合わせるために妥協する部分もあるかもしれませんが。
本来集中力を傾ける場面にかける時間を増やすことにも繋がるのがAI活用なので。
よりクオリティを上げるための時間に使うことができるというのも利点です。
よって、作業内容だけでなく、実はチーム内の業務連携の円滑化にもつながっていたのではないかと思うのです。
生成AIも様々な事ができるようになり、一つのモデルでも完結するようになってきて。
ここで書いたような事を考えずとも、最初から最後まで作り上げることもできつつありますが。
それでも、人間が起点であることに変わりはありません。
なので、AIにできることを把握し、人間がやるべきことを決める。
そんなAIとの連携を目指して行きたいものですね。
SF映画などをみても、AIは自律的になったとしても、基本は情報提供と提案という補佐の役割ですし。
業務内容を分解しておく
・・・ということを、読みながら思っていたら、ChatGPTを個人レベルで楽しんでいる人が増えているというニュースを見かけました。
スマホなどの身近な端末から利用できるからか。
否定してこないという利点も含めて、友達と会話するような感覚で利用しているとのことです。
なので、それなりにAI活用が広がってきているのかと思っていたんですがー。
業務利用はまだ4割弱というニュースも出てきました。
面白がって使うことはできるものの、ある意味では流れが決まっているようなところでは導入しにくいのかなと。
アンケートの内容をざっくりまとめてみると、「使ってはみたいけど、どう使えばよいのか分からない」という感じっぽいです。
AIの導入となるとコンプライアンスの問題もあるので、一概には言えませんがー。
どこに導入すれば良いのか分からないのであれば、自分が行っている業務を分解し。
部下や周囲の人などに投げているものが、AIで代替できるのか?を考えると良いでしょう。
例えば、定形の時候の挨拶のメール文面などから始めてみて、AIとの連携の成功体験を重ねるのも良いかもですね。
マニュアルがあれば、その内容で人間じゃないとできないことと、AIに任せられることを分類してみるのも良いでしょう。
小さなことから使ってみる
ということで、AI活用事例と見かけたニュースについて思ったことでした。
AI利活用はDXやその前のデジタル化などよりも、強力な変化をもたらすものです。
紙をPDFで電子化するとか、保存箇所をクラウドにして業務効率をあげるとか。
そういったポイントではなく、私達がおこなう業務の内容から変えてしまうものです。
しかし、もし自分が仕事ができて会社に貢献できていると思うのであれば、同じクオリティで仕事をデキる人が増えれば、さらに会社はよくなるのではないでしょうか?
そういった可能性がAIにはあって、開発が進むことでその可能性がさらに高まるのです。
「使わなくても、べつに困らないし」ではなくて、小さなことから導入してみると良いですよ。
私は、「面倒だなぁ」と思ったらいったんAIに相談してますw
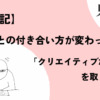
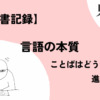
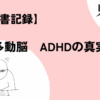
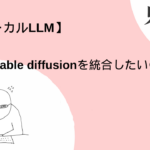
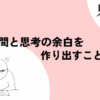
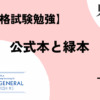



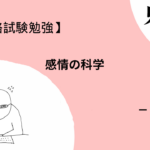
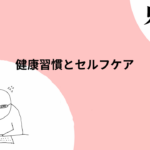
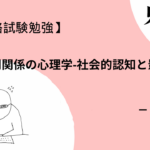

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません