自分の扱うものに自信を持つ施策と「PLSEO」を捉えてみる
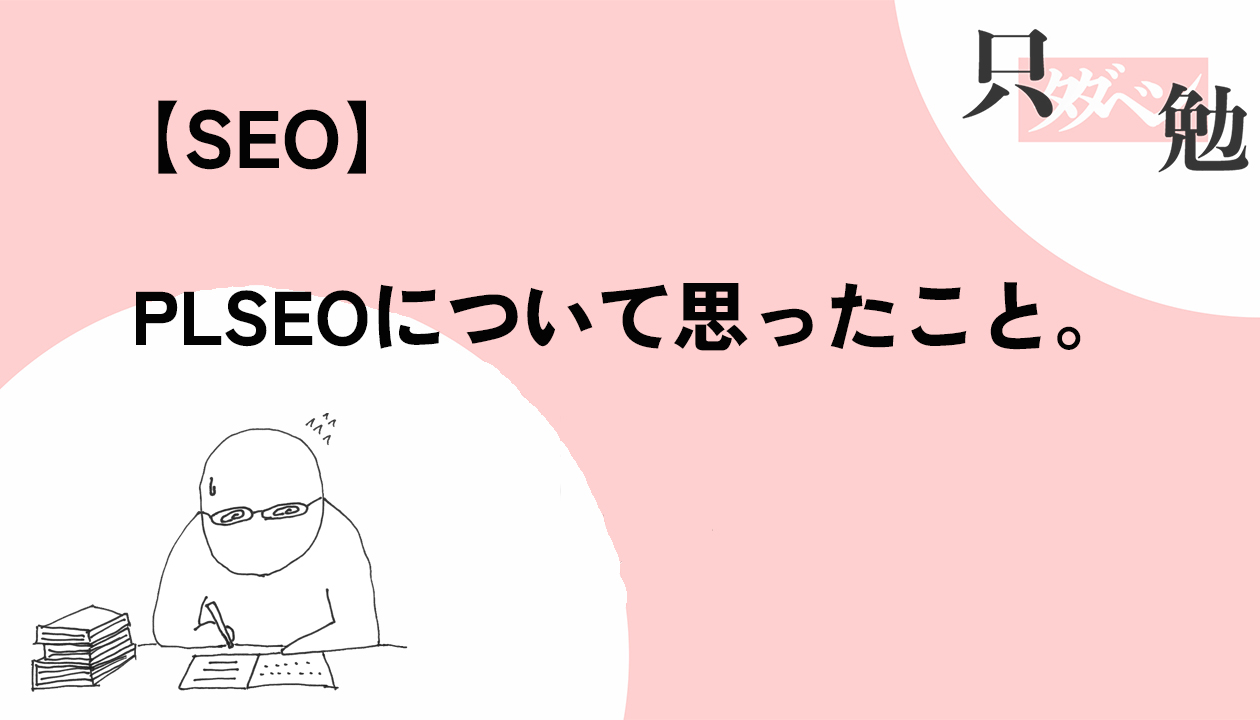
海外&国内SEO情報ウォッチをみてて、今回気になったのは「PLSEO」というものです。
なんだかいろんな言葉が生まれてくるなぁと思いながら、気になったのでチェックしてみたところ。
SEOの範疇で考えるのはもったいない、前提としての態度なのではないかなと。
そんなことを思いました。
PLSEOとは?
PLSEOとは、Product-Led SEOの頭文字を取ったもので、プロダクト主導型SEOと訳されます。
SEOという言葉がついている通り、検索エンジンに対して行う戦略ですが。
通常、SEOというと、検索エンジンに評価されるサイト設計やコンテンツの作成を行うことを考えます。
PLSEOでは、それらの設計や作成はプロダクト(製品やサービス)そのものが作り出すと考えます。
それには、製品やサービスを利用したユーザーが作り出す場合コンテンツ(UGC)である場合もあれば、プロダクトが持つデータ自体によって作り出される場合もあります。
UGCも多岐にわたり、よく見かける様になったユーザーが作成するコミュニティであったり、サービスを利用して作成したテンプレートであったりします。
言われてみると、GoogleでWEBサービスを検索すると、「〇〇のテンプレート」というものがヒットしたり、レビューが書かれたSNS投稿がヒットしたりしますね。
プロダクト自体が持つデータも、商品検索をした時に、各オンラインショップのカルーセルが表示されたり。
その商品ページが検索結果として表示されることは、もう当たり前です。
このように、プロダクトの制作やマーケター側が、必要なコンテンツの作成以外にSEO効果を高める手段として、プロダクトそのものが生み出してくれるコンテンツをSEOとして利用しましょう。
という戦略が、PLSEOであると、理解しています。
SNSもそうですし、様々なところでコミュニティが形成されていますが、その中心には大体なにかしらのプロダクトがあると思います。
そこから、情報の発信が行われている現状を考えると。
確かに効果的なアプローチであると感じます。
プロダクトに集中する
SEOと聞いて思い浮かぶのは、やはりキーワードやクエリから、ユーザーが必要と感じる情報を提供するためのコンテンツの作成です。
そのための調査や手間が非常にかかるもので、設計し必要なコンテンツを作り込むのに、ある程度の期間を見込まなければなりません。
しかも、ある程度の見込みはあるものの、その取り組みが正しいかどうかというものは、すぐには分かりません。
プロダクトに関係の深いものから、関係のありそうなもの・興味を引きそうなものまで、幅広いコンテンツの制作も効果が見込めるのであれば、取り組む価値はあります。
しかし、プロダクトを提供する側が本来取り組むべきことはそこなのか?という疑問はやはり残ります。
そういう事があるから、社内で広報の部署があったり、アフィリエイトと言う形で外部に委託したり。
分業でマーケティングを行っていく形ができたのかなと。
もちろん、プロダクトの紹介や使い方、FAQといった必要なコンテンツの作成は必要です。
しかし、集客目的のコンテンツ作成については、直接必要ではない部分においても作成が必要となる場合もあります。
そのような集客目的のコンテンツを、プロダクト自体やユーザーが生み出してくれると考えると。
そこにかけていたコストを、プロダクトに使えることになります。
プロダクトを改善し新たな価値や体験を提供したり、新しいプロダクトの開発に当てることもできます。
用意するもの
とはいえ、プロダクトを提供するだけで何も無ければ、プロダクト発のコンテンツは生まれにくいでしょう。
なので、3つのものを用意すれば良いのかなと思います。
プロダクトを用意することは当然なので割愛しますが。
プロダクトを伝えるもの
まずは、プロダクトを知ってもらわなければなりませんがー。
PLSEOの場合は、どちらかというとブランディングに近いもののような気がしています。
プロダクトに込めた信念を伝え、どのような使い方、楽しみ方ができるのかという基本的な事を伝えるものです。
これは、制作者側にしか作れないものです。
ただ単に「使って下さい」で使ってくれるほど、今はモノやツールや情報が不足しているわけではありません。
使う理由の後押しを、ホームページやランディングページで行う必要はあるでしょう。
プロダクトからコンテンツが生まれるとは言え、WEB表示のためのフォーマットは必要です。
自作するか、既存のサービスを使うかという違いは出ますが。
「場」の提供
プロダクトに合わせた「場」を用意することも大事でしょう。
そのプロダクトを利用するユーザーが作成したテンプレートを、共有できるサービスが増えていますが。
そういった共有の「場」を用意するのは、プロダクトの制作者が行う方が利用するユーザーの安心感に繋がります。
また、ユーザー同士の交流の「場」というのも、プロダクトによっては必要かもしれません。
これはコミュニティの形成やファンミーティングなど、公式・非公式を問わず行われていますが。
やはり、その制作者が関係しているかどうかで、安心感や信頼度に違いは出るでしょう。
ユーザーの声を集める「場」にもなり、プロダクトの改善や開発の方向性の参考にもなるでしょう。
コミュニケーション手段
場の用意にもつながるところがありますが、やはりユーザーとの接点をしっかりと用意しておくことが大事だと思います。
プロダクトがコンテンツを作り出すとは言え、そのプロダクト自体に問題があれば、コンテンツは生み出されないですし。
そもそも、プロダクトを利用してもらうことがPLSEOの出発地点だと思いますし、改善しユーザーが興味・関心を持ち続けなければ、ユーザーの拡大には至らないでしょう。
ユーザーが拡大されなければ、SEOの仕様から言っても検索結果にも上がらないでしょうし。
なので、ユーザー主導のコミュニティとは別に、プロダクトの制作者とコミュニケーションが取れる手段を用意しておくことが、より重要になるのではないかと思います。
継続の誓いのようなもの
途中で書きましたが、自分は内容を読んでいて、ブランディング戦略に近いなと思ったところがあります。
というのも、プロダクトを使ってくれるユーザーと一緒にプロダクト(ブランド)を育てる感覚を受けたからです。
そうなると、大切なのはそのプロダクトの開発や改善を継続する事だとも思います。
うまくいかないものを無理に継続する必要はありませんが。
PLSEOを実行しているであろうプロダクトの事を考えると、コアなユーザーと制作・開発者との信頼関係のよなものがあり、その熱量で他の興味のあるユーザーを呼んできている。
そんな流れを感じるわけです。
そのためには、すぐに終わってしまうようなプロダクトではユーザーの期待に答えることはできないでしょうし。
継続を誓うことが重要なんだろうなとも思います。
そもそも良いと思えなければ
というか、そもそも何かを提供する場合、自分自身がそれを良いと思えなければ、使ってもらえたり売れるはずもないでしょう。
プロダクトを出す時に誰しもそうでしょうが、すぐに止めるつもりもないとも思います。
であれば、継続の方法を考えておくのが良いですが、それが前述した「用意するもの」だと思います。
ある意味、自分の好きや得意であるプロダクトに集中し、検索エンジンに拡散や提供を代行してもらう手段が、PLSEOであると言えるかもしれません。
なので、自分が何に集中すべきかを明確にする考え方につながるものだとも思うのです。
検索という行動もユーザー体験の一貫なので、それも踏まえた設計を行うのにも自分自身が良いと思っていなければ難しいでしょうし。
考え方として持っておきたい施策
正直、情報をさらっているときには「何を今更?」と思いました。
しかし、SNSなどを起点としたユーザーコミュニティが強い力を持つ今だからこそ、考えておく方が良いことでもあるなと気付きました。
つまり、プロダクトを提供する側は、必要最低限の情報を用意してインターネット上に放り込み。
ユーザーに面白がってもらったり、利便性を感じたりしてもらい。
それに応じてプロダクトの価値を検索エンジン自体に広めてもらう。
ということなんだろうなと。
参考にしたページの中では、プロダクトの中でも向くものと向かないものという分類がなされていましたが。
PLSEOの背景にある考え方は、どんなものにでも当てはまるもので、初心に還るという意味でも覚えておきたいものだと感じました。
参考:
3 examples of product-led SEO – by Kevin Indig
SEOのためにコンテンツを作る…新発想「PLSEO」とは? | SEOコンサルタント.com
SaaS SEOに製品主導のコンテンツ戦略が必要な理由 – Vizologi
プラットフォーマー企業の定義:アグリゲーション理論|SaaSインサイト🚀「日本にもっとSaaSを」
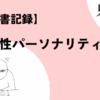
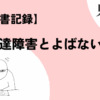

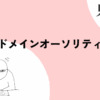
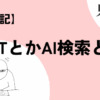
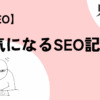





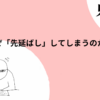

ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません